
視覚障害の友人 他のセンサーの有効利用
センサーと処理
人間は生物として、様々なセンサーを持っています。外界の状況をセンサーで捉えて脳で処理。
センサーの精度や働き方は、工業製品のように均一じゃありません。処理部分も同じ。
なので、同じものを見たり聴いたり触ったりしても、異なる捉え方と表現をする。
というのが人間。障害と呼ばれる症状の中では、このセンサー問題も大きい割合で存在します。
障害者とされる方々の一部は、このセンサーの分布の端っこの方にいる事があります。分布なので、どこに切れ目を入れて社会制度で呼称するか、はその時の取り決め次第になります。

このどこかに誰もが入ってます
なので、切れ目のないサービスを
そんな訳で自分は、障害者と健常者の区分けをしないサービスを考えたい訳です。
端っこの方で不便を感じてる方のために、少し便利になるサービスができたら、少し中心に近い方も便利になり、ど真ん中にいる人も便利に。
そんな感じのサービスになることが、ビジネスにもつながり、たとえ自分が手を引いても後続が現れることができる。これが理想です。
視覚障害者の友人のセンサー
いわゆる五感のうち、視覚のセンサーが働いてない状態。他は動いています。
普通に考えて、視覚情報が得られないと大変、と思ってしまいますが、彼はその状態で生活しています。
すると、他のセンサーが私より発達する訳です。
情報の欠けた部分がマイナスになりました、ではなく、他のセンサー情報で、私は利用してなかった物を、彼は生きるために利用するのです。
まずは音
一番使うのは音でした。自分と違いもある事がわかり、大変興味深い。

まずは発音体
周囲からの発生する音は、物体の姿となり、頭の中でマッピングされるとのこと。これは分かります。
次は反射
続いて、その音が反射する様子。レーザービームのように捉える人もいるようですが、周波数分布の違いを捉えることで、大きな構造物が分かるようです。
さらに、質感。硬い壁、木の壁、カーテン、など。
これらが3Dイメージで配置されるという感じの説明をしてもらいました。大きな柱がそこにあるでしょ、と初めて行った場所で言われ、驚いたことがあります。
中途失明だからこそ
全ての視覚障害者が同じではありません。彼は10代前半まではある程度の視力がありました。そのため、奥行きのある空間の再マッピングが可能なのです。
中途失明の彼は、法線、という物体の投影画像の輪郭をイメージすることもできます。
よりビジュアルイメージに置き換えやすい人です。
もちろん情報源として
音による情報は、このnoteでも扱ってる音声合成の発達や機器の発達で、相当使える状況になりました。
反面、点字を習得する人が減ることにも。
音声合成は、ある種のメディア革命に近いかも。
次に温度
これは私よりかなり敏感で、主に建物の部屋を移動する時に感じていたようです。
サッカーの試合に一緒に行った時も、屋外の広場、チケットゲートのテントの下、コンコース、座席、という変化が全て温度感でも表現してくれました。
歩く時は日の当たる方向などを検知するのにも便利とのこと。

ここから先は
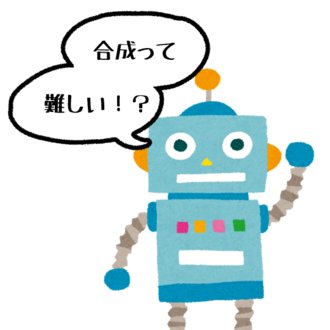
障害のある友人との交流日記
様々な障害を持つ友人がいて、一緒に活動するだけで、様々な知見が得られます。無力を感じることも。 でも、少しでも自分の気づきを世の中にシェ…
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
まだまだ色々と書きたい記事もあります。金銭的なサポートをいただけたら、全額自分の活動に使います!そしたら、もっと面白い記事を書く時間が増えます!全額自分のため!
