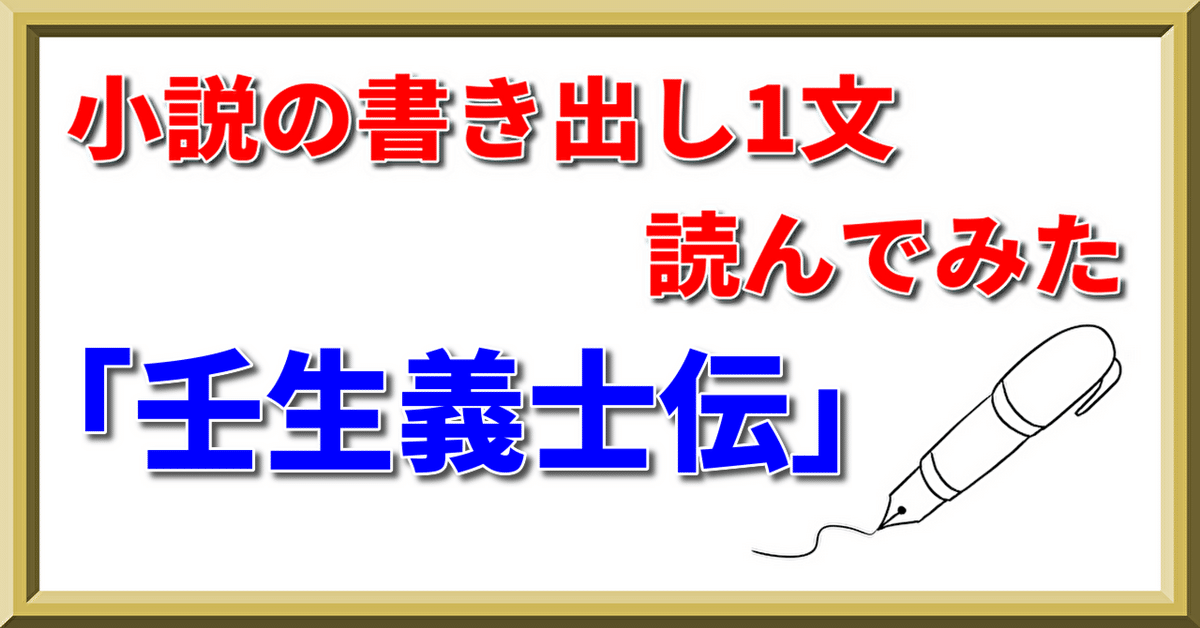
「壬生義士伝」の書き出し1文を読んでみた。
慶応四年旧暦一月七日の夜更け、大坂北浜過書町の盛岡南部藩蔵屋敷に、満身創痍の侍がただひとりたどり着いた。
好きな小説をあらためて読む。なぜこの1文から始まったのだろう。
日付と場所がはっきりと記された書き出し。
日本史、特に幕末・維新に詳しい人なら、慶応四年というだけで日本がどういった状況だったのかわかるだろう。
そして、夜更けに満身創痍の侍。
なんだか物々しい雰囲気だ。
この侍は、果たしてどんな信条を持って、どんな敵と戦い、どんな心情で屋敷にたどり着いたのだろうか。
侍に思いを寄せるために与えられた情報は多く、傷ついた経緯を知りたくなるような物語のスタートだと思う。
正直、私は年号だけでパッとどんな時代かわかるほど日本史に明るくない。
なのでおとなしく読み進めてみると、冒頭の時期はすでに薩長率いる新政府軍が旧幕府軍を圧倒している頃だとわかった。
そんな中、まだどちらの勢力に加担すべきかはっきりとしない盛岡南部藩に、脱藩したボロボロの侍が逃げ込むというシーンなのだそうである。
本作の主人公の吉村貫一郎は、剣の腕が立つ架空の新選組隊士だ。
貧しさから故郷を出て新選組に入隊し、妻子に仕送りを続けてきたのだった。
吉村は佐幕派の急先鋒である新選組隊士として、次第に名を上げるようになる。
しかし時代は移り変わり、新選組はほぼ壊滅状態となる。
そんな状況で吉村が大けがをして帰ってきたというのは、日和見を決め込む盛岡藩にとっては厄介ごとでしかない。主人公は全然ウェルカムじゃないのである。
さて、ここからどう物語が展開されるのか、と楽しめる。
歴史ものは日付である程度世界観が分かるのがミソだと思う。
たとえば1945年の日本なら、8月15日の前後で戦中戦後がはっきりする。
戦後世代としては推し量るのも難しいが、15日の前後で世の中の空気も全く違ったものだったのではないだろうか、と想像する。
時代劇や歴史ものを読むときに、特に年号や日付に詳しい人なら、何年何月という文字だけで察するものが多いことだろう。
本作の書き出しは、歴史的知識を絡めて、世界の趨勢とか空気を感じ取れるように書かれていると思う。
≪前回取り上げた小説≫
