
「モチモチの木」のナゾ(4) 資料編(設定について)
● 版の変遷
「モチモチの木」にとって,細かい表記の違いはあっても,物語の進行上,日付けの設定は重要である。また,場面の区切りを意識するためにも小見出しの有無でも版の違いを分けると,大きく6つの版がある。(教科書版については別に論じる)

日付の設定について考察しておきたい。
最初の設定では「ミソカ(三十日)」だったのが,なぜ「ミッカ(三日)」になったのか? これについて書かれている文章はどこにも見つからなかった。おそらく,斎藤氏の原稿では「ミッカ」と書いてあったものを『日教組教育新聞』に掲載する際に誤って「ミソカ」で載せてしまったと考える。
そう考えるのも「モチモチの木」は1963年12月3日の『日教組教育新聞』に掲載されたからだ。当時の『日教組教育新聞』は毎週火曜日の発刊であった。その頃は当然手書きの原稿だっただろう。寄せられた原稿を見て,期日的に近い霜月ミソカ(三十日)の設定だと編集部が勘違いした可能性がある。だから,その後,『ベロ出しチョンマ』に収録する際には作者が校正をして,「ミッカ(三日)」として刊行されたのである。
また,絵本化においては場面ごとの小見出しがなくなった。絵本の場合はページの区切りがそのまま場面の違いとなるため,小見出しが削除されたのかもしれない。そして,滝平二郎のさし絵では三日月が添えられた。
その後,1977年には〈ミッカでは夜半過ぎに三日月は昇らない〉という指摘を受けて,日付けが「二十日」に変わることになる。
私の所蔵している本では第61刷(1979年9月)の『ベロ出しチョンマ』ではすでに「二十日」で本文が変えられている。ただし,さし絵は三日月のままで刊行されている。
さし絵が古いまま本文を新しくするのならばわかる。不思議なのは1986年に刊行された『モチモチの木ものがたり』(理論社)である。この本は本文が古いまま,さし絵だけを新しくしている。つまり,本文中は「ミッカ」のままでありながら,さし絵を三日月から変更している。また,小見出しはなく,「1・2・3・・・」と数字で場面の区切りを付けている。
この本には「本書は理論社名作の愛蔵版『ベロ出しチョンマ』を底本とし,読みやすく編集しました」と説明してある。しかし,本文とさし絵の整合性がとれておらず,少し中途半端な編集に感じる。
● 教科書の扱いについて
「モチモチの木」は絵本化された翌年(1972年)に青少年読書感想文課題図書に選ばれる。もちろん,ミッカ(三日)の設定で滝平氏のさし絵も三日月のままである。
教科書で初めて採用されたのは,1977(昭和52)年に日本書籍と光村図書で採用された。この時になり,〈三日月は夜半過ぎに登らない〉と現場の教師から指摘される。
日本書籍では次の教科書改訂となる1980(昭和55)年以降は「二十日」にして収録している。
光村図書は1980年の教科書改訂では「モチモチの木」を採用しなかった。次に採用するのは1992(平成4)年になってからである。以後,光村図書では継続して教材として扱われている。
令和2年に小学校国語教科書を発行した4社ではどの会社もこの話を採用をしている。
しかし,豆太の描写では,「女ゴみたいに色ばっかりナマッ白くて」の部分を削除して利用するようになった。
1977(昭和52)年以降,国語教科書を発行した会社で「モチモチの木」をどのように扱ったのかを表にする。記号の意味は次のようになる。
4年…4年で採用
3年…3年で採用
※…不採用
空白は教科書を発行していない時期である。
原作…原作通りに「おなごみたいに色ばっかり白くて」と記述。
部分…一部削除して「色ばっかり白くて」から記述。
削除…「おなごみたいに色ばっかり白くて」の部分は削除。

教科書の掲載にあたり小見出しをつける会社が多い。しかし,教育出版では小見出しをつけずに,1・2・3・・・と数字で場面分けをしている。
さし絵は滝平氏のさし絵を採用する会社が多い中,学校図書では2005(平成17)年,2011(平成23)年と諸橋精光(もろはし せいこう 1954.1.1~?。鈴木出版より紙芝居「モチモチの木」を2001年に出版している。)にさし絵を担当させた。2015(平27)年から滝平氏のさし絵となる。
滝平氏のさし絵では二十日の月の形が正確でない。諸橋氏がそのことに気づいて正確に描いてくれれば良かったのだが,ほぼ満月の形で描かれており,もっと悪い。
「モチモチの木」は研究授業として選ばれやすい教材である。教材研究の本が単行本として刊行されている。(『教材別・単元別の可能性に挑戦する2 「モチモチの木」の授業」藤田慶三,東和男(編),東洋館,2011
『白石範孝集大成の授業「モチモチの木」全時間・全板書』白石範孝(著),東洋館出版,2016)また,教科書会社の指導書を見ても,焦点は〈豆太の優しさと勇気〉にあてられている。ほぼ日本中の教師がこの方針で指導して,ほぼ日本中の子どもがこの方針で学習している。

● 数えと満年齢
教科書会社の指導書や教材研究の単行本でも豆太のことを「5歳」として扱っている。数えと満年齢の違いは常識ではないのかもしれない。
現在では満年齢を利用している。生まれたばかりの子は0歳である。翌年の誕生日で1歳,さらに翌年の誕生日で2歳と言うように誕生日を迎えて歳を一つ増やす。図に書けば下のようになる。

しかし,昔は生まれたらすぐに「一つ」と数えた。新しい年を迎えて「二つ」となる。誕生日を迎えなくてもお正月には全員が一つ歳をとる。並べて書くと次のようになる。

数を数える時は,「1・2・3・・」と数える。だから,「一つ」から始まるのも合理的な理由がある。
でも,12月生まれの子は,生まれて1ヶ月もたたないうちに,「二つ」と呼ばれてしまう。だから,豆太が「五つ」と言うことは現在の3歳〜4歳の子をイメージしなくてはならない。保育園で言えばまだ年少組です。昼間のオムツが取れても夜はオムツをして寝ていてもおかしくない。
● 二十日の月の形
物語では「霜月」と旧暦の呼び方をしているので,1872(明治五)年の改暦以前の設定と考える。
当時は,月の動きを元にしており,毎月一日は新月となる。月は見えない。〈新しく月が始まるよ〉という意味で「月立ち」と呼ぶ。「つきたち」を「ついたち」と言うようになり,「一日」という漢字でも「ついたち」と言うようになった。
三日月は文字通り,毎月三日に見える月の形である。次のような形の月が夕方,西の空に出る。
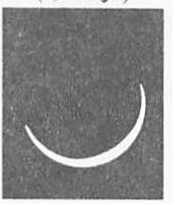
下のような半月は新月から1週間後,だいたい七日か八日ぐらいになる。夕方,南の高いところに出てくる。

「十五夜の月」は満月となる。毎月十五日には満月となる。夕方,東の空に出てくる。
さて,二十日の月となると,下のような月となる。

夕方に見ることはできない。夜の10時ぐらいに出てくる。真南に来るのが6時間後の午前4時頃になる。「うしみつ=午前2時から2時30分ぐらい」ならば,真南よりも少し東側に出ていることになる。だから,朝になり太陽が出てきても,西の空をさがすと見つかる。
● 霜月の月の高度
霜月が〈11月の昔の呼び方〉だと知っても,「霜月二十日」は「現在の11月20日」にはならない。昔の暦から現在の暦に切り替える時に約1ヶ月のズレが生まれたからである。だから,現在で言えば「12 月の終わり頃」になる。現在の冬至の頃の月になる。(必ず冬至と言うわけでない)
〈冬至の頃の太陽は一年でもっとも低く,太陽が高く昇るのは夏至の頃〉と言うことは知っている大人も多い。では,月の場合はどうなるか?
月の高さは太陽と逆だと思ってよい。〈冬至の頃の満月は一年でもっとも高く昇り,夏至のころの満月は低い〉となる。
● 初雪の設定から地域を考える
少し古いが『理科年表 平成24年』(丸善出版,2011)の「雪(降雪)の初日・終日の平年値と最早・最晩」を見ると(統計期間:1980~2010の平均値)各地で初雪が降るのは次のようになる。
10/22 稚内
10/23 旭川
10/24
10/25
10/26
10/27
10/28 札幌
10/29
10/30
10/31 網走
11/1
11/2
11/3 函館
11/4
11/5
11/6 青森
11/7 帯広
11/8 盛岡
11/9
11/10 釧路
11/11
11/12
11/13 秋田
11/14
11/15
11/16
11/17
11/18 山形
11/19
11/20
11/21 長野
11/22
11/23
11/24 仙台・新潟
11/25
11/26 福島
11/27
11/28
11/29 金沢
11/30
12/1
12/2 富山・福井
12/3
12/4
12/5 鳥取・松江
12/6
12/7
12/8
12/9
12/10
12/11 広島
12/12 下関
12/13 彦根
12/14 岐阜
12/15 前橋・京都・福岡
12/16
12/17
12/18 宇都宮・岡山
12/19 奈良・和歌山・長崎
12/20 名古屋・神戸・佐賀
12/21 徳島・松山・大分
12/22 津・大阪
12/23 高松・熊本
12/24 甲府
12/25
12/26
12/27
12/28
12/29 熊谷
12/30 高知
12/31 水戸
1/1
1/2 鹿児島
1/3 東京
1/4
1/5
1/6
1/7 横浜
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12 静岡
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17 銚子
1/18
1/19
1/20
1/21 宮崎
北海道は10月に初雪を迎え,斎藤氏が疎開していた秋田を始めとする東北の各地が11月になる。11月下旬から12月の上旬にかけて日本海側の各地が初雪を迎え,全国的には12月中旬以降に初雪となる地域が多い。太平洋側の地域が12月下旬以降の雪となる。
物語では「霜月二十日=12月の終わり頃」に「この冬はじめての雪だ」とある。単純に1ヶ月をずらして12月20日頃をイメージするならかなりの地域が該当する。また,霜月ミッカ=3日では12月3日頃となり,日本海側の地域となろう。
● 丑三つについて
暦の会(編)『暦の百科事典』(新人物往来社,1986)から橋本万平「季節によって変わった時刻法と暦の知識」から図を引用する。

昔は正確な時計がないために,季節によって変わってしまうものである。上の表もおおよその目安で見てほしい。表にすると次のようになる。
子の刻 午後11時〜午前1時
丑の刻 午前1時〜午前3時
寅の刻 午前3時〜午前5時
卯の刻 午前5時〜午前7時
辰の刻 午前7時〜午前9時
巳の刻 午前9時〜午前11時
午の刻 午前11時〜午後1時(正午というのは午前12時=午後0時)
未の刻 午後1時〜午後3時
申の刻 午後3時〜午後5時
酉の刻 午後5時〜午後7時
戌の刻 午後7時〜午後9時
亥の刻 午後9時〜午後11時
丑の刻は現在の時刻でおおよそ午前1時から3時となる。さらに細かく区分するために,この2時間を4つに分けて,丑一つ・丑二つ・丑三つ・丑四つと読んでいた。つまり,次のようになる。
丑一つ・・・午前1時〜1時30分
丑二つ・・・午前1時30分〜2時
丑三つ・・・午前2時〜2時30分
丑四つ・・・午前2時30分〜3時
4つの分けて,30分刻みにするのは他の時刻でも同様に考えて良い。
しかし,同書では次のように注意している。
ここで注意しておきたいことは,計算のうえでは詳しい対応時刻は出てくるが,何しろ不定時法は時計のない人々が大雑把に使っている時刻法であるから,たとえば丑の刻といっても,正確に現在で考えるような時刻であったかどうか疑わしい。したがって古い時刻の表現をあまり神経質に考えても無意味である。ただ日の出(卯)の時刻以前はまだ暗く,日の入り(酉)後は闇の時間であるということだけは忘れてはならない。不定時法と定時法とは混同しているあめに,つじつまの合わない解釈や説明をしている歴史家や国文学者も少なくないのである。
結局,あんまり正確に考えずに「丑三つ」は「真夜中」程度の意味で十分だと思う。
