
夫婦別姓にNO!働くお母さんの座談会 お父さんとお母さんの苗字が別々になったら…「家族バラバラは嫌だ」涙ぐむ子供たち
櫻乃ミキさん
笠原結佳さん
桑野ゆきさん
中村まりさん
長崎大学准教授の池谷和子先生は、「(別姓の議論に)子供からの視点が全くないのは、とても残念である。なぜなら「夫婦別姓」は必ず「親子別姓」、時には「兄弟別姓にもなってしまうからである。」「『婚姻している夫婦か』『実の親子か』『実の兄弟か』ということが、姓によっては識別不可能となり、学校、地域活動等、全てにわたって、実は家族ですという証明をしなければならず、様々な場面で、トラブルを誘発しやすくなる。」「姓は単なる個人の称号ではない。家族(時には家系も含む)チーム名なのである。」等と指摘しています。(「日本の息吹」令和6年11月号)
そこで、今回、全国の働きながら子育て中のお母さんの協力を得て、子供に「別姓」についてどう思うかアンケートを行い、その声に基づいて座談会を行って頂きました。もうひとつの当事者である子供たちの声に耳を傾けてみると―

子育て中の働く女性が「選択的夫婦別姓制度」に抱く強い違和感
櫻乃 経団連提言や自民党総裁選で話題に上がった選択的夫婦別姓制度について、声を届けたいと子育て中の働く女性が集まりました。
選択的夫婦別姓は、必然的親子別姓を意味し、強制的に家族の苗字(名字)がバラバラになってしまいますね。それぞれのお立場より、是非ご意見をお聞かせください。
笠原 私は夫と幼稚園に通う娘との3人家族です。フルタイムで仕事をしています。社会への影響を考える前は「うちは別姓にはしないから…。問題があったら誰かやってくれるだろう」とどこか他人任せのところがありました。しかし、次第に子供が育つ世の中について考えるようになりました。この問題は「他人事として考えてはいけないんじゃないか」と思うようになりました。
桑野 私は夫と小学生の息子と幼稚園の娘の4人家族です。フルタイムで仕事をしています。私が学生の頃は、まだ旧姓が広まっていない時代で、選択的夫婦別姓は困っている人のための論議だと思っていました。その頃は、確かに仕事上中々旧姓が使いづらいと聞いたことがありました。しかし今は、随分便利になって、私の職場でも普通に旧姓を使っている人もいて何の不便も無いようです。それでも別姓制度導入を殊更に言う人たちの本当の理由が知りたいと思うようになりました。
中村 私は夫と高校生の娘と小学生の息子との4人家族です。仕事はフルタイムで保育士をしています。実は私が高校生の時、夫婦別姓の議論が始まった時期で、学校では「選択的夫婦別姓」をテーマに小論文の授業がありました。「夫婦2人なら別姓は自由で構わないが、子供がいる場合は家族バラバラになるから反対」と書いた記憶があります。
最近になり、別姓を推進する人の言葉に「結婚で姓が変わることで、女性が自信をなくす」「キャリアが崩れる」という言い方をする人がいますが、違和感を抱きます。全女性代表の意見のように発信するのはやめてほしいと思います。私の職場は女性が多いのですが旧姓の通称使用をする人も多く、私自身も通称使用をしていますが、不便を感じたことは殆どありません。
櫻乃 確かに、旧姓使用は身の回りに広がっているという実感がありますね。
親子別姓で「バラバラは嫌だ」と涙ぐむ子供達
櫻乃 選択的夫婦別姓制度の議論には「子供の視点」が欠けていると思います。私たちは、幼児期から思春期の子供たちの声を集めました。今日お集りの皆さんに子供たちの声から感じられたことをお聞かせいただけますか。
笠原 子供に話を聞いてから、ことある毎に苗字の話をしてきます。よほど心に残っているのでしょう。大人が思っている以上に子供は繊細に感じ取っていると思いました。
うちの子は「お母さんが一番大好き」とよく言いますが、だからと言って「お母さんの苗字になる」とは言いません。「お父さんとお母さんとみんな一緒がいい」と号泣してしまうほどでした。娘の様子を見ながら、万が一夫婦別姓になった時、親の別姓を受け入れ、順応しながら大きくなる子供たちの心の有り様、親に従わなければならない子供の将来が心配になりました。他人事ではないと切実に思いました。
桑野 小学生の息子は、「お父さんとお母さんが別々の苗字になったら」と聞くと、「どうして?」とびっくりして飛びついてきました。多分、親に何かが起きたのかという気持ちが瞬間的に生まれたのでしょう。「絶対いやだ!」と言いながらずっとウルウルしていました。
「どっちがいい?」と聞かれて、小さな子は選択できません。大きくなって気付いた時には別姓という環境がある。「こんな大事なことを親が決めていいのか?決める権利が親にあるのか」と子供の様子を見ながら強く思いました。子供たちに悲しい思いをさせたくない。出来る限り安心感を与えたいと改めて思いました。やっぱり「家族はワンチーム」でそのシンボルが苗字だと。
中村 長女は高校生で、別姓の話題も知っているので、落ち着いて答えていましたが、質問が「兄弟が別々の苗字になったらどう?」と聞いた時に表情が変わりました。とても心が揺らいでいるのが分かりました。年の離れた弟が心配になったのだと思います。「それは絶対いやだ!」と。長女にとって弟は守らなければならない存在で、それがバラバラになると本能的に思ったのでしょう。小学生の息子はずっと涙ぐんでいました。この頃の子供は特に敏感だと思いました。
「よく話せば子供はわかってくれる」と選択的夫婦別姓を要望する人は言うけれど、子供に無理をさせているのではと思ってしまいます。子供達に「どちらを選ぶか」と聞くことは「選択という暴力」であると感じます。
櫻乃 皆さんからのお話を伺って、選択的夫婦別姓制度は子供達にとって過酷なものであると感じます。アンケートに答えてくれた子供達の回答を読みましたが、切実な子供達の声に胸が締め付けられる思いがしました。
その中で、一人のお母さんから次のような回答がありました。「お父さんとお母さんの苗字が違ったら、あなたはどっちの苗字になりたい?」という質問に小学1年生の息子は、「みんな一緒に変えるなら(お母さんの名前でも)いいよ、みんな一緒なら(苗字を)日替わりにしてもいいよ」と必死に考えているんです。最後には「みんな一緒!」と言いながら3人の子供たちがお母さんに抱きついてきました。このお母さんの文章を読んで涙が出ました。
別姓制度導入を要望する人は「改姓が辛い」と言いますが、「家族バラバラになるのは嫌だ」と涙する子供の声は比較にならないほど重たいと感じます。
また、NHK放送文化研究所の中高生を対象とした意識調査(2022年)では、9割を超える中高生が、将来結婚したら同じ苗字にしたいと回答しています。
令和5年4月には「こども基本法」が施行されました。「…こどもの最善の利益を常に第一に考え、こどもに関する取組・政策を社会のまんなかに据えていく『こどもまんなか社会』の実現を目指すという大きな価値転換をした」という文言が、こども家庭庁の子供の育ちにかかる基本的ビジョンにも掲げられています。
大人は子供を保護する立場であり、子供の心を考えないまま、大人の利便性を優先させることで、弱い立場の子供を精神的孤立に追いやってはなりません。
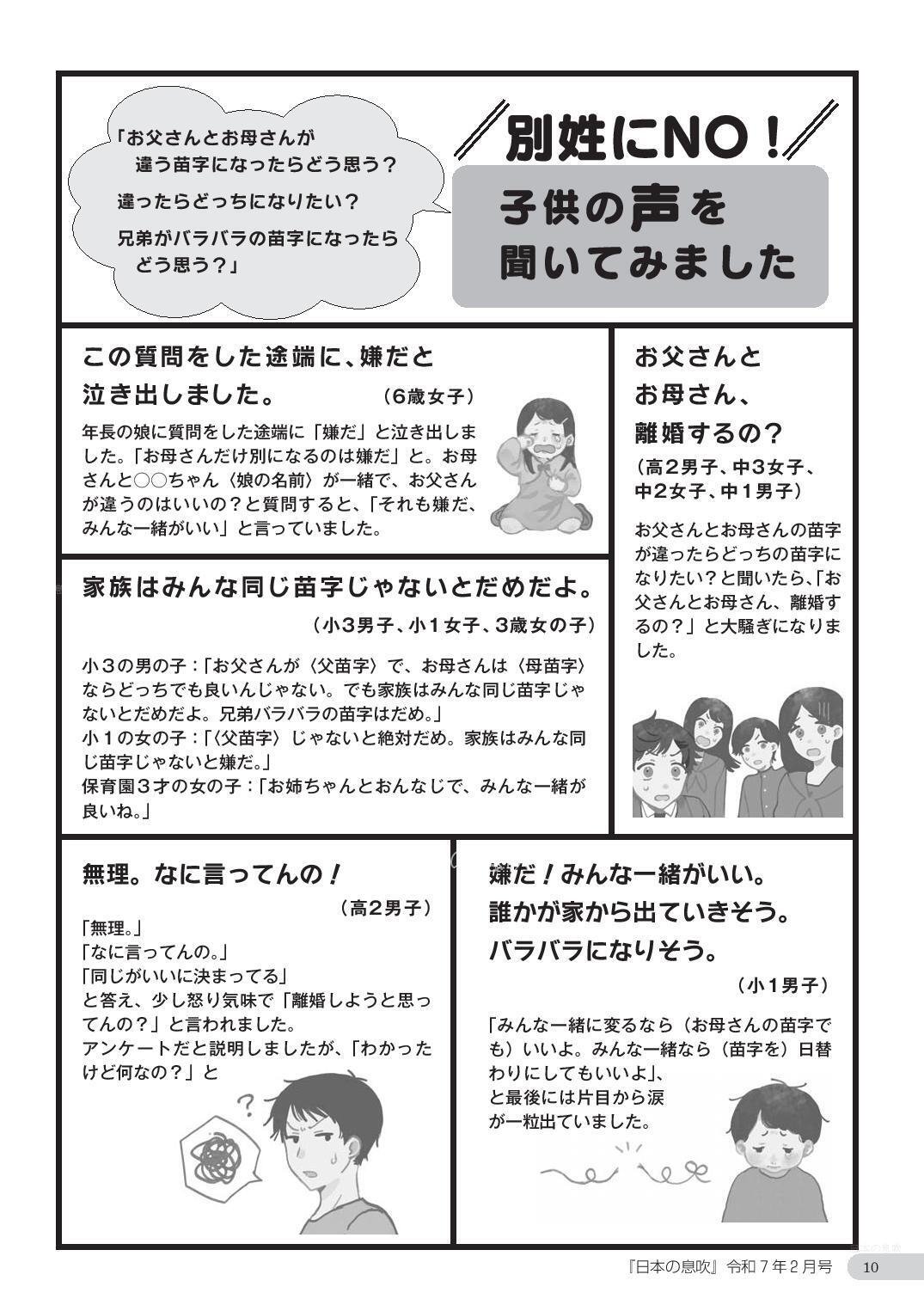

「やりたい人だけ」では済まない「強制的親子別姓」による社会全体への重大な悪影響
櫻乃 「やりたい人だけ別姓にすればいい」というキャッチフレーズがありますが、世の中全体への影響について考えてみたいと思います。
選択的夫婦別姓制度も一旦導入すると、一つの家族名であるファミリーネームが消えてしまい、個人の名札のようなバラバラな性質に変化してしまいます。また、この制度が導入されると、既婚者の家族に対しても「姓の選び直し」が適応される移行期間を設けるとのことで、小さな子供達がいる家族も含め、日本の全既婚者が対象になります。皆さんはどうお考えですか。
笠原 「選び直し」には恐ろしさを感じます。家庭は子供をはぐくむ場であり、安心を与える場です。「選び直し」出来るとなると、よく考えずに「やってみようか」と軽い気持ちで判断する人もいるのではないかと思います。「やりたい人だけ」という耳に心地良い言葉で社会に混乱を起こすのではと心配です。
桑野 私もそう思います。軽はずみに乗じる人が出てくると、子供達に不要な不安を与えます。
私は会社で人事やそれに関する事務の仕事をしています。「選び直し」で、別姓に変更する人が増えると、末端の現場の事務手続きは煩雑になり大変な混乱になります。行政システムの混乱も予想され、その事務手続きにどれくらいの税金が使われるのか心配です。
櫻乃 社会全体に様々な混乱が予想され、「選び直し」の期間には、アンケート回答のような子供達の悲痛な声が全国に溢れるのかと思うと、この制度導入は重大な悪影響があります。
また、別姓制度では、子供の姓を決める話し合いがスムーズに進まなければ家庭裁判所が決めるという案があります。これを聞き、子供の姓をめぐって、夫婦のみならず、祖父母や親族にまで対立を生じさせることになってしまうと懸念しています。
親子別姓―保育や教育現場にも負担がかかる
櫻乃 欧州では別姓夫婦が、子供と姓が違う場合、親子と証明するために様々な書類を提出せねばならない状況になっています。
保育の現場でお仕事をしている観点から、中村さんはどうお考えですか。
中村 保育や教育の現場では親と子の確認を慎重にせねばならず、特に入園入学時などは混乱が予想されます。なぜなら親子の苗字が違う場合、別姓の親子なのか、事実婚の親子なのか、中々判別が難しく、そのような親子関係確認の負担は必ず増えるでしょうし、余裕がなくなれば、保育や教育現場にしわ寄せがくると考えられます。
事実婚の場合は、母親が親権者で、母親と同姓になります。しかし、夫婦別姓の夫婦の子は、片親と親子別姓となり、その親は法律上の親権者として認められはするでしょうが、親子で名前が違うので、子供の受け渡しなど、保育所や医療機関、国際線の空港などでは、親子を証明する書類や親権者証明を常に携帯して提示することが義務付けられる可能性もあります。
また、数は多くないかもしれませんが、DVや虐待などで子供の命に関わる事例が発生した場合、子供を預かる機関は親子別姓の場合、区役所や児相(*1)とのやりとりの中で確認事項が増え、本当に子供を引き渡して良いのかなど、混乱が生じやすいでしょう。万が一の間違いがないかと想像すると、かなりリスクを感じます。お預かりしている子供の命にかかわることですので、ことは簡単ではありません。
※1 児童相談所
櫻乃 別姓制度が導入されると、連れ去りなどの犯罪から子供達をどう守るのかも課題になるということですね。
「改姓」は男女平等―「苗字」を分かち合える喜び
櫻乃 令和6年10月に国連女子差別撤廃委員会の勧告で選択的夫婦別姓が言及されました。その中に、日本における改姓の割合が女性95パーセントであったことが「女性差別だ」と国連は言っているのですが、これについてどうお考えでしょうか。
また、皆さんが結婚して家族で苗字を一つとしたことについて感じていることをご紹介ください。
笠原 令和6年に行われた世論調査(*2)で、夫婦同姓の支持が約70%となっています。もし改姓に差別を感じている女性が大勢いるならば、このパーセンテージは有り得ないですね。あと仕事で旧姓を使いたい人は使うという、とても柔軟な考え方の人が多くなっています。結婚のときに改姓で面倒だったことは思い出せません。銀行の通帳名義を変えたくらいです。友人たちからも「困ったね」なんて聞いたことがありません。それよりも、大切な人と同じものを分かち合える喜びを感じました。また、苗字を同じくすることで、今まで他人だった人たちが、親戚になり温かく受け入れてもらいました。
桑野 婚姻時に改姓するのは法的に全くの男女平等です。つまり自由が原則なので、この点を忘れてはいけません。
結婚して感じたのは、結婚前までは親は2人だったのが4人になったこと、そして私たちの幸せを4人の親が祈ってくれているという心強さです。ご先祖様とつながる柱が1本から2本になったことを感じます。
中村 女性の改姓が多いことは差別とは思いません。制度として男女平等であり、男性が改姓している例は身近に幾つもあります。
結婚して姓が変わることは嫌だということは全くなく、むしろ一体感が感じられて嬉しく感じました。
櫻乃 「男女がお互いを尊重し、助け合い補い合う関係性」が根底にあれば、「改姓」は嫌なことではなく、寧ろ夫婦一緒に家庭を築く喜びや、親戚が増えて心の支えが増える喜びが大きいのですね。このように苗字を一つにして嬉しいと感じている女性が多いという事実があるにもかかわらず、改姓率が半々でないから差別と決めつけるのは明らかに間違いですね。また、家庭の運営上で夫婦話し合って決めることは沢山あり、改姓だけ取り上げて力関係を論じるのはおかしなことです。
※2 令和6年7月7日JNN「同じ名字を維持すべき」21%、「同姓を維持して通称を法制化」47%、「別姓を導入すべき」26%。「同姓維持」は68%となる。
日本独自の価値ある制度を大切に
櫻乃 別姓を要望する人が、夫婦同姓である日本の法律が遅れているかのような発言をすることがありますが、どのように考えますか。
笠原 家族のあり方はその国で育んできた形でもあるので、独自であることは遅れていることとではなく、寧ろ大事にして良いことだと感じます。
桑野 「子供の視点を大事にする家族のあり方」は価値あるものですので、日本は今の制度を大事にしてほしいと思います。
中村 世界中に多様な家族のあり方がある中で、何を基準に遅れているというのか疑問を感じます。守るべきものは見極めて守ることが大事と考えます。
櫻乃 確かに、日本にしかない独自の良さがあって世界から評価されているものは沢山ありますね。苗字は昔から「苗字」とも書き、先人は苗字に命を育む苗床の働きを直感的に感じていたのではないでしょうか。苗字からは、ご先祖様とのつながりを感じ、子供達もご先祖様に思いを致す文化だと思います。
櫻乃 この座談会を通して、選択的別姓制度導入は、未来を担う沢山の子供達に負の影響を与え、長期的に深いダメージをもたらす社会的リスクがあることを、多くの方々に気づいていただきたいと強く感じました。
特に政治に携わる方々には、「不便だから、困っているから」という一部の大人の声だけで判断せず、本質を見誤らないでいただきたいと願います。「家族の一体感」を守る方向での施策が必要です。
子育て中でお仕事をしている女性の皆さんの大変貴重なご意見を伺いました。本当にありがとうございました。
(令和6年12月15日座談会)
関連記事を次の特集ページにまとめています。合わせてご覧ください。
