
【華秘メシ裏大奥】大江戸怪談~立夏編~
このお話は、【華秘メシ裏大奥】の番外編、
立夏目線のお話になります。
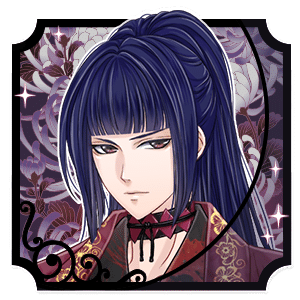
「大江戸怪談~立夏編~」1、
それは蒸し暑い8月の午後のこと。
謁見の間ではいつもように、勤め役たちが上様に大奥・裏大奥での最近の出来事を報告していた。そして、私はいつものように下座に控え、聞くともなしにそれを聞いている。今日は特段大きな報告事項はなく、どちらかといえばダラダラとした四方山話に近い。そのせいか、家光も妹君の膝に頭を乗せ、耳掃除をされながら眠そうにダラダラと聞いてる。

「……というわけなのでございます」
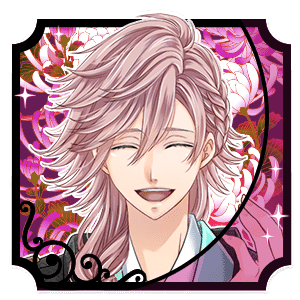
「へー、なるほどねえ。それは困ったねえ」
大奥全体の警護を務める服部半蔵正重が説明を終えても、家光は聞いていたのか聞いていないのか分からないような様子だ。
「上様、明らかに興味ないでしょうが、大奥内のことですよ」
「大奥の警備は正重に一任してるわけだし、しっかり頼むよ。妖怪の一匹や二匹、忍術で召し取って」
「さすがにそれは専門外ですよ。それに、女大奥の内側の問題にはいくら警備担当でも口をはさみにくいです」
「お前、ふだんははさみまくってるというか、入れまくってるでしょ?」
「いや、それとこれとは」
世に聞こえし伊賀忍をまとめる頭領、服部半蔵の名を受け継ぎし男でも家光が相手では顔色が青くなったり赤くなったりするらしい。
「そもそも大奥には妖怪より恐ろしい魑魅魍魎が跋扈しているじゃないの。今更そんなものでねえ」
この家光の言葉には、同意する。
先日も、大奥で松の木をはらっていた植木職人の若い男が行方不明になったと思ったら、全裸の上、錯乱した状態で見つかり、大騒ぎになった。何があったのか問い詰めても、「女は怖い、女は怖い」しか言わず、何があったのか想像できるだけに恐ろしい。
「でも、お兄様、夜、お鈴廊下に怪異が出るなんて恐ろしいです」
部屋に鈴の音のような声が響く。家光の妹君、香也姫だ。香也姫の声音には妙に不思議な力がある。か細く清らかであるのに、甘く鼓膜を嬲っていくような。
「香也は怖がりだからねえ」
妹には甘い家光の表情が急に優しくなる。
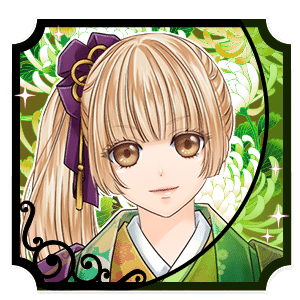
「そうですよ、姫だけじゃありません、大奥中の女が怯えきっておりますよ」
そこにすかさず口をはさんできたのが、香也姫の御付き侍女である、お縫。
もとは貧乏旗本の娘で、半ば口減らしのように大奥へやってきた田舎者であったが、知恵が回って口も達者、負けん気も強く、いつのまにやらドクダミのごとく繁殖してきた。特に春日局に目をかけられ、香也姫の御付きとなってからは、権力と食欲が増している。
「上様、しかも、夜中に現れては菓子部屋で、思う存分貪り食っていくだなんてもしや二口女の仕業ではありませんか」
「二口女? なんだい、それは。立夏、知ってる?」
なぜか家光は私に振ってきた。ある事件以降、彼はどうやら私が妖怪に詳しいと誤解しているのだ。
「申し上げます、上様。二口女とは、姿は普通の若い女なのですが、後頭部に大きな口が隠れていて、なんでも食べてしまう妖怪のことですよ」
いけない、うっかり答えてしまった。
「へえ。そりゃ怖い。もっとも、女は誰でも二枚の舌があるけど。そして、お縫、いつから大奥には菓子部屋なんてものができたの?」
「最近、大奥では痩せて美しくなることが流行りなんです。だから、中臈たちが持っていた菓子を菓子部屋に集めて封印し、むやみに菓子を食べないようにしているんですよ」
「へえ、面白いことが流行るねえ。正重、菓子部屋に現れるなら話は早い。そこに罠を張って、早急に解決して」
「しかし、その菓子部屋はお鈴廊下の先、女大奥の中にあります。男の自分は入れません。あそこは男子禁制なので」
「お前、そんなことを言って、しょっちゅう入っているのでは?」
「上様、自分は確かに身持ちが堅いとは言いませんが、最低限の決まりは守っています」
半蔵は苦い顔で返す。まあ、確かにこの男、下女には節操なく手を出しているが、将軍の御手付きとなる可能性がある中臈以上には決して手は出さない。
「立夏、正重は本当のことを言っていると思うかい?」
なぜ、いちいち私に振るのだ。
「確かに、半蔵殿は下働きの女をよく蔵やら庭やらに呼び出しているようですから、女大奥に立ち入ってはいないでしょう」
私の言葉に半蔵は決まりの悪そうな半笑いを浮かべる。そこへお縫がサッと手をあげた。
「上様、私がその妖怪を退治します!」
「え? お前が?」
「あの菓子部屋には私の菓子もたくさん、たくさん保管されているのです。それを勝手に食われるだなんて、絶対に許せません」
「お縫、お前は本当に食い物に執着するね」
その通り。こいつとお品の食欲ときたら、冬眠前のクマと同じだ。
「んー、こう言ったらなんだけど、痩せるために菓子を封印しているんだよね? だったら、妖怪に喰わせてしまった方がいいんじゃない?」
その通り。不本意ながら、家光に同意だ。他の男性陣も同じ意見だったらしく、なんとなくこのまま流してしまおうとした時、鈴の音のような細い声がした。
「あの、お兄様」
出た、香也姫。
余計なことを言うなよ、絶対言うなよ。
「ですが、お兄様、そんな妖怪が出るのは恐ろしいことです。一時的に正重殿が入れるようにして、警備してはいかがでしょうか」
「自分ですか?」
半蔵が微妙な顔になる。確かに女大奥の菓子を守る仕事など、あとで中臈たちにどんな難癖をつけられるか分からない。どんな勇猛果敢な男でも、および腰にもなるだろう。
「いえ、上様、ぜひ私にお任せを! このお縫、どんな危険があろうとも必ずや妖怪を仕留めてみせます」
「いや、お前が絡むと余計に面倒くさいことになる予感がしてるんだよ。あ~、もう、お縫を制御できて、女大奥に入っても中臈たちにボロカスに言われ無さそうな男といえば……そうだ!」
家光は私のほうへ持っていた団扇を向けた。
「将軍が命じる。この事件、立夏が解決しておくれ」
「私がですか?」
「大奥内のことに詳しいし、適任じゃん」
「はい、お兄様、お耳の掃除が終わりました」
「香也、ありがとう。次は手を揉んでくれる? じゃ、そういうことでいいね、立夏」
「……かしこまりました、上様」
なぜ、なぜ、なぜ、なぜ、こんなことに!
時々、家光は私の正体を知っていて、じわじわと低次元な嫌がらせをして楽しんでいるのではないかと思う。まさか、いや……とりあえず、徳川家光、絶対に許さぬ!!
2、
その後、私はお縫に半ば拉致されるような形で、いや、完全に拉致され、香也姫の部屋へ連れてこられた。
「で、お夏、どのような手段で二口女をつかまえるのですか?」
この女が張り切った時、それは必ず暴力的な結末が待っている。仕方なく、私は当たり障りない回答をした。
「夜中、お鈴廊下で張り番をしようと思っています」
「立夏ひとりでですか? それは危なくありませんか?」
香也姫が不安そうに言う。しかし、私にはもう結末が半分見えていた。
「たぶん、大丈夫だと思うんですよね……」
男には挑まねばならぬ時がある。たとえ、破滅が待っていると知っていたとしても。
「お夏、実は私、すでに三晩ほど張り番をしたのです。ちなみに昨夜も」
察するという行為を一切しようとしないお縫が指を3本突き立てる。
「したのですか?」
「ええ。ですが、まったく出てきませんでした。あいつは見張りをしていると出ないんじゃないでしょうかね。だとしたら、相当賢いヤツです」
「それはまあ、そうかもしれませんね……」
敵は賢い上に、恐ろしく頑丈な妖怪だ。どうしたら、穏便に倒すことができるだろうか? 私は思案した。
「あの、立夏?」
「……そうだ。もう日が落ちてきましたし、少しお酒でも飲みません?」
「お酒ですか? でも、立夏は今日はお役目を言いつけられていますよね?」
お鈴廊下でもし妖怪と遭遇した時に酔っぱらっていては、困るに違いない……と、香也姫は思ったのだろう。お優しいことだが、お前は余計なことを言うな。一切言うな。家光とお縫を増長させている元凶は絶対にお前だぞ。
「ほんの少しだけ景気付けですよ。お縫殿はいける口でしょう?」
「え~私は今、痩せようと思って、控えてるんだけどお~」
黙れ、このウワバミが!
「では、つまみを食べずにお酒だけ召し上がってください。お酒は水みたいなものですから、飲んでも太りません。飲むと太ると言われているのは、つまみを食べているからです」
これはもちろん、ウソだ。酒の原料は米なのだから。
「私もそう思うけど、香也姫があまりお酒を好きではありませんし~~」
くそ、また香也姫か。私は表情筋をしっかりと笑顔の形に作って、姫の方を見た。
「姫は妖怪が怖いんでしょう?」
「はい。あんな話を聞いてしまっては、今夜は寝付けない気がします」
「では、お酒を召し上がったほうがいいです。そうすると、グッスリ眠れますから」
「そ、そうでしょうか」
「では、さっそく酒を準備させます」
3、
それから、私は気が進まなそうな姫を無視して、お縫の盃にどんどん酒を注いだ。すると、もともと酒好きな彼女は、途中から自分でどんどん杯を重ねていった。わざと空腹に飲ませたことが功を奏し、さすがのウワバミもじきに酔い始める。
「お夏う~、もしかして、お夏も妖怪が怖いんじゃありませんかー?」
「怖いですね。非常に怖いです。大奥一、獰猛な相手なんで」
きっぱりとそう答える。
「でしょー!? そう思ったー」
そう言って、お縫は畳にごろりと寝転がった。その様子に姫が驚いて彼女を揺する。
「お縫? 大丈夫ですか? お縫?」
「ああ、姫、そのまま寝かしておいてあげてください。昨夜も張り番をしたそうですから、眠かったのでしょう」
「はあ」
姫は不安そうにしながらも、お縫の体の上に薄物をかけてやる。
「あの立夏、ところで、私、その二口女というものをよく知らないのですけど……」
姫が人一倍怖がりで、神経が細いことは知っていたので、ここはしっかりダメ押しすることにした。
「教えてさしあげましょうか」
「はい」
「でも、その前に、今持っている盃を開けて頂かないと」
「でも、私、お酒に弱くて、すぐ酔ってしまうんです」
「酔ってもいいじゃありませんか。私がおそばにいるんですよ?」
「でも……」
「さ、どうぞ、飲んで」
彼女の手首を支え、半ば強引に盃を口元に持っていく。香也姫は人魚の生まれ、もともとあまり自我のある性格ではない。誰かに強く勧められたら、断れない。
「ふふふ、イイコです。ちゃんと飲めましたね」
「……私、本当にお酒は……」
酒に弱い姫はほんのわずかな量で、顔を赤くしてフラフラし始める。
「では、私が支えてさしあげます」
後ろから彼女を支え、もうあと一押しで盃を舐めさせる。
「あの、もう結構です……」
「酔ってきましたか?」
「はい……」
「二口女というのは、継子いじめをして、その継子を餓死させてしまった女なんですよ。継子の死霊が後頭部の傷に乗り移り、いつしかその傷が口になり、髪が手になり……。本人が気づかないうちに食べ物をガツガツと餓鬼のように食べるようになった」
「こ、怖い……」
「ふふふ、あなたは本当に怖がりですね」
その怖がり方があまりにもそそるものだったので、後ろから彼女を抱きながら、耳元で囁く。
「同じように二面女というのも居て、みんなが見ている顔はとても美しいのだけど、髪に隠れたもうひとつの顔はとても醜く、貪欲で、美しい見かけに引き寄せられて近づいてきた男を、がっつりと食べてしまうのです」
「立夏、やめて。もう怖い」
耐えられなくなった姫が逃げ出そうとするのを、あえて乱暴に引き戻す。
「あなたは食べるほうですか? それとも食べられるほう?」
「やめて……ううっ……」
とうとう姫は耳を両手でふさぎ、涙を流し始めた。ああ、家光の大事な妹(お人形さん)を虐めるのはなんと楽しいことだろう。できるならもっと虐げて辱めて、グチャグチャに号泣させてやりたいが、今夜は別に仕事がある。このへんにしておこう。
「ふふ、すみません。あなたが怖がる様子があまりに可愛らしいものですから、つい虐めてしまいました。香也姫、今、侍女に布団を敷かせますから、お縫殿といっしょに寝てください」
4、
真夜中のお鈴廊下。私は妖怪が現れるのを、じっと待っていた。どこまでも損な役目だが、一応は捕らえなければならない。
と、またもや余計なものが現れた。
「誰か……誰かいませんか?」
香也姫だ。この女はどうしていつもいつも、最悪な間でやってくるんだ!
「立夏……立夏どこ……」
怯えすぎているために、まるで生まれたての小鹿のような歩き方になっている彼女の背後に回り、口をふさぐ。
「しー。静かに」
「立夏……」
「どうして来たのですか?」
「目が覚めたら、ひとりでしたので、不安になってしまって」
「はあ……お酒が足りませんでしたか」
「立夏は私やお縫を眠らせるためにお酒を飲ませたのでしょう?」
くそ、アホのくせに妙に勘がいい。これは兄と同じか。
「はい。あのままほっておくと、ふたりとも私といっしょにお鈴廊下で張り番をすると言い出しかねない空気だったので……ごめんなさい」
「でも、本当に立夏ひとりで張り番しているのですか? 危ないのではありませんか?」
「平気ですよ。でも、あなたはここから動いてはいけません」
そう言って、背後から彼女の腕の上から、ぎゅっと締め上げる。部屋で寝ていればよかったのに、ガクガク震えながら、どうして私のところへ来るんだ? 本当に腹が立つ女だ!
「立夏、く、苦しいです」
「そうですか?」
腹立ちまぎれに腕の力をさらに強くしてやる。
「立夏……痛い……」
「動くからですよ。動いてはいけないと言いました」
「り、立夏は私のことが嫌いなのですか?」
「どうして、そう思うのです?」
「だって、意地悪ばかりします」
「意地悪ではありません、正確に言うと、虐めているのです」
「えっ」
「おや、来ましたねえ。妖怪が」
お鈴廊下を女らしき人影が歩いてくる。そして、廊下を横切り、お菓子部屋へと入っていった。
「姫、ここにいてくださいね」
「は、はい」
私は背後からコッソリと忍び寄り、女の腕を掴んだ。
「はい、捕まえた!」
これで事件解決──
そう思った瞬間、私の体は宙に浮き、床にたたきつけられていた。
「……っ!!」
「キャーッ! 立夏ーー!! 誰か、誰か来てください!!」
姫が大きな悲鳴をあげる。すると、廊下の板戸を蹴破って、半蔵が飛びこんできた。
「姫! 何事ですか!?」
「立夏が、立夏がやられてしまいました!!」
「えっ?」
半蔵が急いで部屋の行灯に火をつけた。そこには、投げ飛ばされた上に腕をとられ、女のお縫に十字固めされているという、天草でもここまでの辱めを受けたことが無かったほどの、無様な私の姿があった──
5、
「このたびのこと、まったくもって申し訳なく……」
お縫が私に向かって土下座をして詫びる。黙れ、土下座くらいで許すと思うな。時が来たら、お前は家光の次に必ず殺す。
「たぶん、あなたはお腹がすいて寝ぼけたまま、お菓子を食べに行っていたのでしょうね」
二口女の正体はお縫だと、私はとっくに察しがついていた。だが、やはり相手が女性だったため、捕まえる時に遠慮をしてしまった。それがいけなかった。本当にいけなかった。この女はクマだったのに。
「いや~~そういえば、朝起きると、口の周りに甘い粉がついていました。最近、痩せるために夕食を抜いていたので、空腹に耐えきれなかったのかなと」
何が、いや~~だ。絶対許さない、許さない、許さない。
「これに懲りたら、夕食はちゃんと召し上がってください」
これは主が私に与えた試練だ。どんな辱めにも、笑って耐えよ……そうおっしゃっているのだ。そう心の中で繰り返し、私は無理矢理に口角を上げ、そう言った。
「ハイ……すみません……。それで、あのう、上様には黙っていてもらえませんか?」
この女、どこまでも厚かましいな!
「黙るの何も、上様はあなたがお菓子を食べていた犯人だと知っていますよ」
「え、どうして」
どうしたもこうしたもあるか。あいつはすべてを知った上で、私にこのような屈辱を味あわせるため、画策したに違いない。絶対そうに違いない。
「話の流れからして、おおかたの予測はつきます。だから、あのように苦慮しておられたのでしょう」
「うわーん! 恥ずかしい!!」
「お縫、大丈夫です。お兄様は寛大な方ですから」
香也姫、お前は黙ってろ。
「というより、バカバカしくて咎める気も起きなかったのでは?」
おっといけない、本音が出た。
「り、立夏、やっぱり怒ってます?」
当たり前だ。
「二口女とは、妖怪ではなく、口では『痩せたい』と言って食事は抜くくせに、菓子はもぐもぐ食べている女のことを言うんです。お縫殿、お分かりか?」
「ううう。面目ない」
「そして、一言申し上げてよろしいですか?」
「なんなりと」
「痩せたければ、運動しろ! 食っちゃ寝するな!」
「うわーん! 正論すぎて言い返せない!」
お縫は畳につっぷし、全身で土下座をした。
「しかし、見事な巴投げでしたよ、お縫。立夏は殺されてしまったと思いました」
香也姫、だから、お前は余計なことを言うな!
「寝ぼけながらもあそこで男の姿を見ると思わなかったので、賊かと勘違いして、とっさに投げてしまったんですよ。ごめんなさい」
「とっさに巴投げって……私はお世辞にも小柄とは言えないんですけどね!」
このクマが!
「しかし、これで妖怪騒ぎも収まるだろう」
廊下で笑いをかみ殺していた半蔵がそう言いながら、私の方へ打ち身用の軟膏を投げてよこす。
「それは甘いんじゃないですかね?」
「いやいや、さすがに」
「賭けますか?」
「いいとも。秘蔵の大吟醸を賭けよう」
私の推測は当たり、その後もお鈴廊下とお菓子部屋に現れる二口女は増え続け、とうとう大奥には「食事制限禁止令」が出た。そして、私は半蔵の大吟醸酒を奪い取り、少しだけ留飲を下げたのだった。
「大江戸怪談~立夏編~」END
いいなと思ったら応援しよう!

