
ピラミンクス中級解法 ao100 sub-6への道
こんにちは。ピラミンクス好きのキューバーNiceYoです。初めての記事ですが、ピラミンクスのLBLの中級解法について書こうと思います。
パズルの紹介など
ピラミンクスの紹介
ピラミンクスは、3x3x3の通常のルービックキューブよりも覚える手順の数も手順数も少なく、回転パズル初心者の方にはもってこいなパズルだと思います。それでありながら、単発世界記録は0.73秒と1秒未満であり、トップ層の中では競争が激しい種目でもあります。ピラミンクスの強みは少ない手順でも速くなることができることだと思います。今回紹介する解法の覚える手順数は5個しかありませんが、速くなれば日本ランク平均100位以内も十分狙える解法となっています。
使ってるキューブについて

使ってるキューブはMoYu Weilong M Pyraminxです。現在、トップソルバーも使っている評判の良いピラミンクスは2つあります。僕が使ってるウェイロンと、YuXinが販売しているLittle Magic M Pyraminxです。日本記録を含め記録の樹立に使われたキューブには後者のリトルマジック(以下リトマジ)が多い印象があります。しかし、初中級者にはウェイロンの方が良いと感じます。1つ目の理由は、磁石の強さです。磁石があまり強くないリトマジに比べ、ウェイロンは回転が軽い代わりに磁石が強いです。回転に慣れてない自分自身を含めた初中級者には、磁石が強い方が使いやすいと思います。2つ目の理由は、調整の難易度です。元々メインキューブとしてリトマジを使っていましたが、使いやすいキューブにするためにはネジの調整やワッシャーの除去、潤滑剤を差すなど沢山の調整が必要です。それに比べウェイロンはほとんど調整をしなくても最初から十分使いやすい性能をしています。僕は頂点を軽くするために、リトマジから取り除いたワッシャーを入れ潤滑剤を差しましたが、何もしなくても十分使いやすいキューブです。
中級解法の解説
解法について
ここからはピラミンクスの初級解法と回転記号、パーツの名前が分かる方向けの内容です。今回紹介する解法は初心者向けのLBL(説明書などに書かれてる解法)に手順をいくつか追加したものになります。LBLは、Layer by Layerの略であり、頂点を揃える→センターを1つの面に持ってくる→完全1面を作る→2段目を揃える(LL)の手順から成り立っています。それではやっていきましょう。
インスペクション〜センター合わせ
インスペクションにおいて重要なのは、いかに完全1面が作りやすい形でセンターを合わせるかです。このためには、ペア(ピースが繋がっているところ)を探してペアを崩さないようにセンターを合わせる必要があります。ここからは写真を用いて説明します。
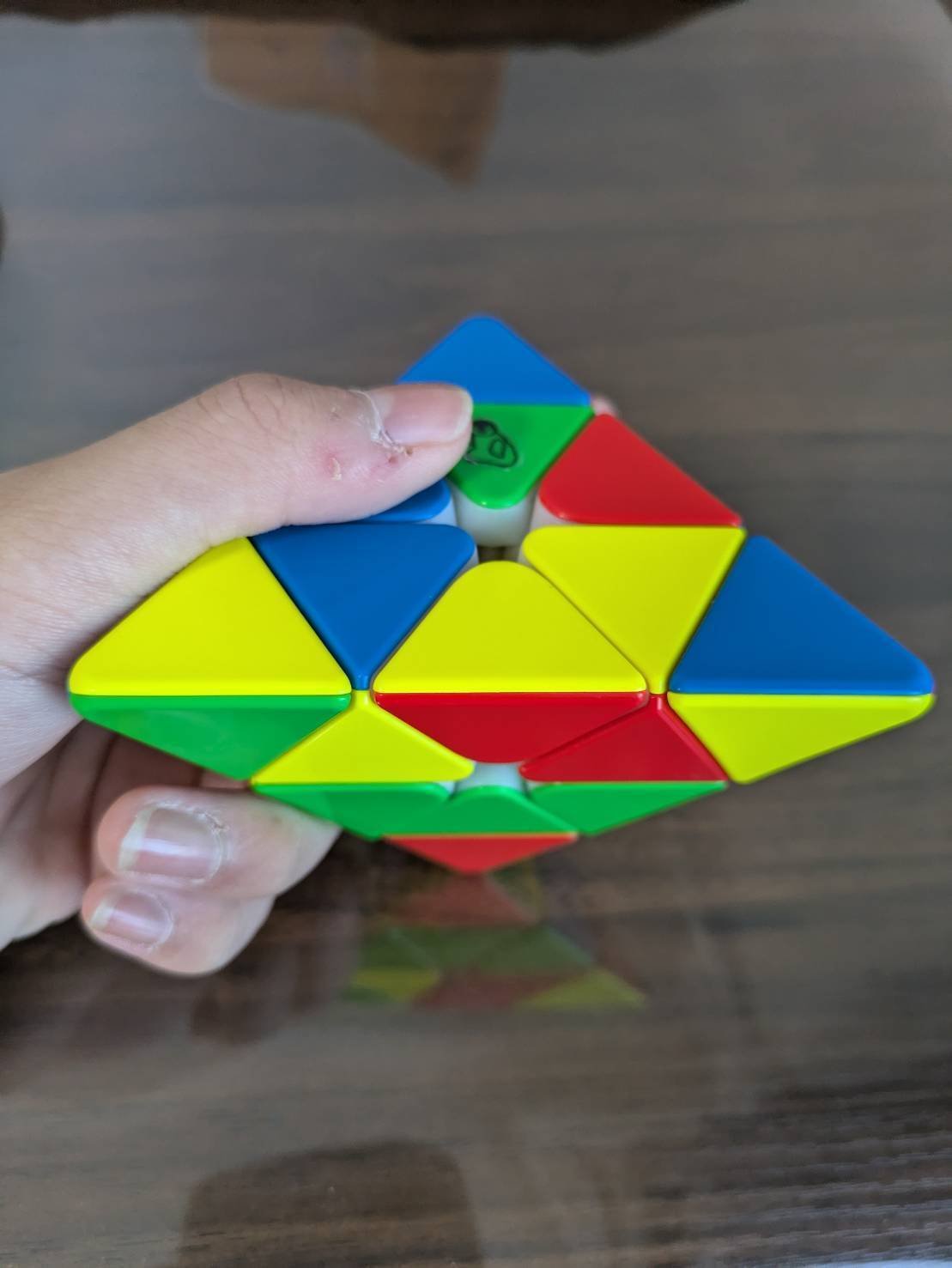

皆さんはお手元のピラミンクスで写真と同じスクランブルを作っていただくと分かりやすいと思います。スクランブルはL' U R L U B L R' r' u b'です。まず、ペアを探します。今回は赤黄色のペアがあるので(図2)黄色の完全一面にしますが、ペアを見つけたら何色の面でも完全1面を作るようにしましょう。ペアを見つけて完全1面を作る面を決めたら、センターを同じ面に持ってくるまでの手順を考えます。この時、ペアを壊さないようにセンターを合わせるのが重要になります。今回の場合は、ペアができているセンターとその右(図3)にある黄色のセンターをD面に持っていく必要があります。図3の面をF面とした時、先にL'をしてペアがあるセンターを移動してしまうと、右側のセンターを移動した時にペアが崩れてしまいます。それを防ぐために右側のセンターをR'でD面に持っていってからL'をします。多少手順数が増えても完全1面の手順数を減らすためにペアは崩さないようにし、インスペクションの時には頭の中でシュミレーションをしながらペアを崩さないセンターの合わせ方を考えましょう。センター合わせのインスペクションが終わったら頂点を読み、下の写真(図4)ように1発で揃えられるようにしましょう。

頂点を読んだら、持ち替えを減らすために完全1面を作る面を下にしてソルブを始めます。
完全1面
センターが全て1つの面にまとまったら、次は完全1面です。完全1面の挿入する時のパターンは7パターンあります(今回は黄色の完全1面)。また、完全1面だけでなく全体に言えることですが、Uを回す時に親指で面を押すようにしましょう。今回は黄色のエッジピースだけに注目してください。


このケースはご存じの方も多いと思いますが、挿入したいエッジピースがF面にある、かつ完全1面の色がこちらを向いてる状態です。この場合はスレッジハンマー(以下スレッジ)またはヘッジスラマー(以下ヘッジ)で揃えることができます。スレッジの手順はR' L R L'で、ヘッジはその逆、すなわちL R' L' Rです。入れたいピースが右にある場合(図5)はスレッジ、左にある場合(図6)はヘッジを使いましょう。


図7、図8は最初のケースに似ていますが、完全1面の色がこちらを向いていません。この場合、ピースが左にある時(図7)はR U' R'、左にある時(図8)はL' U Lで挿入することができます。ピースがない方を上げ、ピースを入れる形です。


図9、図10は入れたいピースが後ろにあります。やることは1つ前と同じで、上げて入れて戻す手順です。完全1面の色が右を向いてる場合(図9)はR U R'、左を向いてる場合(図10)はL' U' Lをします。

最後(図11)は、エッジが入れたい所に反転して入っている場合です。この場合は、一度出してから入れることができれば好きな手順を使っていただいて構いません。僕は、一度ヘッジで出して図8の状態にして、L' U Lで入れる手順を使います。
LL(2段目)
続いては最後の手順です。LLのパターン数は5つあります。LLを回す時に回す面を変えたい場合は持ち変えるのではなく、Uを動かして回すのがポイントです。あとちょっとです!頑張りましょう。


図12、図13は一見同じに見えますが、センターとエッジの位置関係が違います。図12は揃えるのにセンターを右にずらす必要があるのに対し、図13は左です。図12の場合は、L' U L U L' U Lで揃えることができ、図13の場合はその反対、すなわちR U' R' U' R U' R'で揃えることができます。図12の場合は左手、図13の場合は右手でLまたはRを動かし、もう片方の手の人差し指でUを動かします。手の場所に応じて、人差し指でUをトリガーするか面を押すかを決めます。


図14、図15も両方似ていますが、左右が違います。ここで注意点ですが、両方とも写真の向きで回さないと揃いません。図14の場合はL U R U' R' L'、図15の場合はR' U' L' U L Rで揃えることができます。指使いに関しては、自分が1番回しやすいやり方を探していただいて構いませんが、持ち替えないようにしてください。

最後のケースは2つのピースが反転している場合です(図16)。この場合は、反転している2つのピースがある面を前にして、R U' R' Uをしてからスレッジ(R' L R L')をすることで揃えることができます。
まとめ
これで中級解法の解説は終了です。お疲れ様でした!タイトルにもあるように、この解法だけでも平均6秒切りを目指すことができます。ですが、この解法に慣れてもっと速くなりたいと思ったら、今主流の上級解法「V First」の手順を覚えるのも良いと思います。V Firstは根本的なやり方はLBLと変わりませんが、最後まで完全1面を作らずにVを作った状態から全てを解く解法です。この解法を極めれば、平均3秒切りやインスペクションの時点で最後まで手順を予測する「完読み」が可能になります。最後までお読みいただきありがとうございました。次の記事でまたお会いしましょう。
