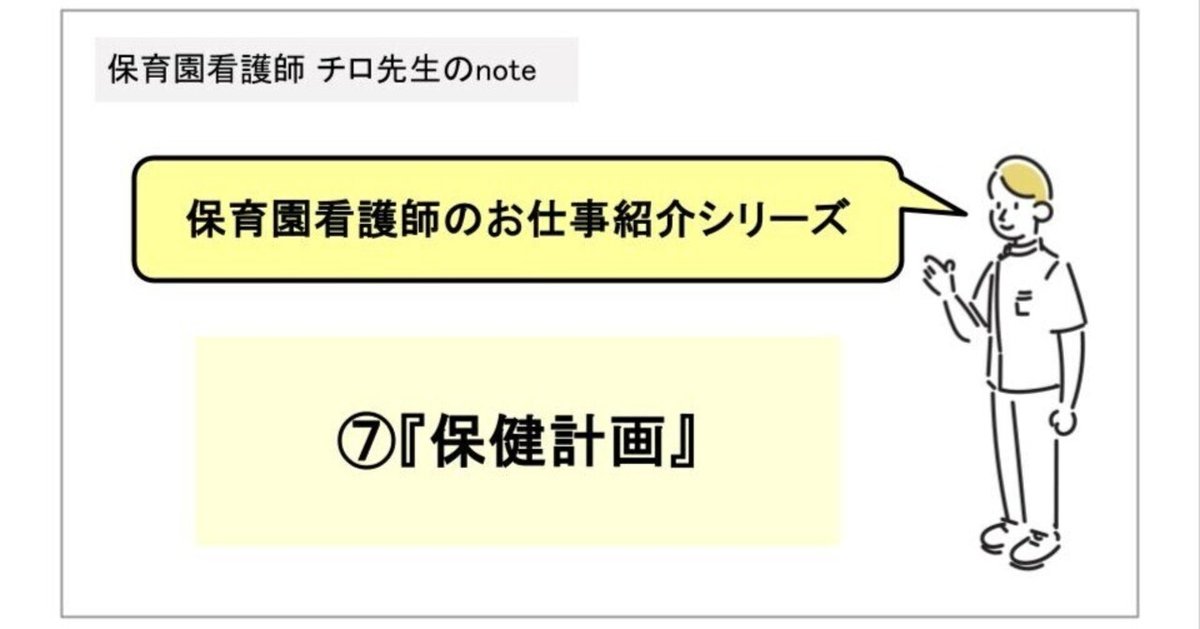
保育園看護師のお仕事紹介シリーズ ⑦保健計画
こんにちは!現役保育園看護師のチロです。
保育園看護師の仕事の楽しさや専門性を発信していく『保育園看護師のお仕事紹介シリーズ』!
第7弾は、「保健計画」について解説していきます。
保育園には、全体的な計画という園の保育目標を達成するための総合的・包括的な計画を中心に、指導計画(各クラスの年間計画、月案、週案、日案など)・食育計画・保健計画などたくさんの計画があります。
今回は、計画の中でも保育園看護師としてメインに携わることになる「保健計画」の目的や内容についてまとめてみました。
これまでのお仕事紹介シリーズも合わせて、是非ご参考いただけたら嬉しいです!
「保健計画」の目的と概要
保育園における保健活動は「保健計画」を元に取り組まれています。保健活動には、園内の衛生管理、感染症対策、健康教育、職員講習、園児や職員の健康管理等が含まれます。
「保健計画」は、看護師等が配置されている園ではその専門性を生かして作成すべきとされていますので、看護師等が担っているケースが多いと思います。もちろん、看護師等が配置されていない園もあります。看護師不在の園では、保健衛生に関するリーダー的な先生や主任等が作成している場合もあるかと思います。
保育所保育指針から読み解く「保健計画」の目的
「保健計画」は、保育所保育指針にて明確に作成することを義務付けられている記録のうちの一つです。保育所保育指針、第3章「健康及び安全」にて下記のように記載されています。
(2) 健康増進
ア 子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと。
イ 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにすること。
つまり、「保健計画」を立案する目的は子どもたちの健康の保持及び増進のためです。全体的な計画に基づいて、子どもの健康について園全体として意識していきたいこと、活動したいこと、気を付けたいポイント等を計画に落とし込んでいきます。
この計画を全職員で共有し、共通認識をもつことで、一人一人の子どもたちの健康の保持及び増進に努めていくことが求められているのです。
「保健計画」の内容
「保健計画」に所定の書式は特にありません。記載する内容としては、以下の項目を参考にして下さい!(ちなみに、監査の際に下記内容で指摘を受けたことはありません。むしろよく書けていると評価いただいたこともあります。「保健計画」としてベストかどうかはわかりませんが、合格ラインにはあるようです。)
年間目標
年間目標
年間目標に対するねらい(年間計画)
期毎に目標、ねらい、活動予定、配慮事項(環境整備他)等
保護者支援
職員講習計画
研修計画
日頃の保健衛生/看護業務に関すること
期毎に振り返りと反省
さらに、これらの項目について3歳未満児と3歳以上児のそれぞれで計画を立てることがベストです。もっと言えば、乳児(1歳未満)用も分けて計画できるとさらに良いと思います。(ちなみに自分は、「乳児(0~2歳児)グループ用」「幼児(3~5歳児)グループ用」の2つに分けて作成しています。)
1.年間目標
保育における「健康」という領域・視点から、園としてどういった子どもたちを育てることが目的なのかを言語化して目標にします。
または、保育所保育指針の第3章の内容から目標を組み立ててもよいかもしれません。「子どもたちの健やかな成長と発達を支える」、「心身ともに健康な身体をつくる」などといったざっくりとした表現になることが多いと思います。
2.年間目標に対するねらい(年間計画)
年間目標が決まったら、目標を達成するためのねらい(年間計画)を記載しておくとよいでしょう。例えば、下記のような文章になります。
「遊びの中で園児が安全に身体を動かし、健康な身体作りができるよう健康管理と環境整備を行う。」
「ほけんだよりの発行や保護者会への参加等を通じて、保護者と密にコミュニケーションを取り、園児の健康管理に生かしたり、園内の保健衛生や感染症対策に関する理解と協力を促す。」
ねらいについては特段記載していない園も多いと思います。イメージとしては年間目標の解像度を上げることで、より具体的な計画に落とし込む作業です。
ねらいを記載することで、より職員との共通認識を持ちやすくなるなどのメリットがあると思っています。また、ねらいが明確にあることで、保健活動を推進していく看護師自身にとっても意識的に活動するための指針になるように思います。
3.期毎に目標、ねらい、活動予定、配慮事項(環境整備他)等
この項目が「保健計画」のメインの部分になります。ポイントは期毎に記載することです。
保育園では、1年間をⅠ~Ⅳ期の4シーズンに区切って行事や計画を組み立てることがよくあります。なぜ4シーズンに分けるのかというと、期毎に子どもたちの姿や様子が異なっていたり、季節や行事等によって配慮すべきポイントが変わるからです。
「保健計画」においても同様で、季節ごとに健康管理や感染症対策のポイントは変わります。
例えば、夏場は熱中症対策のために室内の湿度が上がりすぎないような工夫(空調調整等)が必要ですが、冬場は感染症対策のために湿度を一定レベルまで上げる工夫(加湿等)が必要になります。どちらもやっていることは湿度管理ですが、より具体的に表記することで職員との共通認識も持ちやすくなります。
また、保健行事(健診・検査・健康教育等)についても記載しておきます。健康教育の予定については別紙でまとめてもよいかもしれません。保育の計画と連動して健康教育を実施していくためにも、保健計画としてあらかじめ設定しておくことが大切です。
期毎のねらい(計画)では、箇条書きで注意ポイントを列挙していきます。具体的にやるべきことのチェックリストを作成するイメージです。環境整備等の配慮事項も同様に記載します。
4.保護者支援
「保健計画」を立案する上で忘れてはいけないことが「保護者支援」の視点を持つことです。保健活動を円滑かつ効果的に推進していくためには、家庭でも意識して活動してもらうこと、すなわち保護者にも職員と同じように意識してもらうことが必要不可欠です。
保護者支援となる保健活動として、ほけんだよりの作成、保護者会への参加、予防接種の更新、身体測定や健診結果の共有等があげられます。特に監査では、どのように保護者と情報共有しているかを問われることがよくあります。アプリを通してなのか、専用のノートを介してなのか、各園のやり方に合わせて計画しましょう。
5.職員講習計画
近年は特に保育中の事故が増えているため、保育園を運営する上で緊急時の対応について適切に訓練しているかどうかが重要視される傾向にあります。そのため、保健活動の一環として、心肺蘇生法、窒息解除、食物アレルギーの対応等の講習と練習を計画、実施していくことが必要不可欠です。
また、全職員が園内の衛生管理や感染症対策を励行していくために、必要な知識や技術を伝えていくことも大切です。手洗い指導や嘔吐処理等の講習なども計画的に実施していきたいところです。
これらの職員講習については、園によっては外部講師を呼んで実施することもあります。しかし、職員の講習時間やシフトの調整が難しいため、代わりに保育園看護師が講師となって職員講習を担っているケースが多いと思います。(「職員講習」については、また後日ノートにまとめたいと思っています!)
6.研修計画
医療も保育も日進月歩で、日々進化しています。しかし、保育現場で働いていると最新情報に触れる機会が少なく、意識的に情報収集していないとエビデンスの更新についていけないということがよくあります。
情報のブラッシュアップという意味でも、専門性の向上や職業人としての研鑽という意味でも、外部研修を受けることは勉強になります。研修で学んだことを日常の保育に落とし込んでいくことで、保育の質向上や園全体のレベルアップにもつなげていけると思います。
認可保育所であれば、各園に対して職員の研修計画を組むように指導している自治体もあるかと思います。キャリアアップ研修や自治体が主催している研修などへの参加について、主任等と相談しながら計画できるとよりよいですね。
また、看護師は医療従事者としての知識・技術の更新も重要です。医療現場とは異なり、保育現場では医療的なスキルを実践する機会が少ないため、特に緊急時の対応(CPRスキルなど)は定期的に訓練したいところです。医療的ケア児への対応なども同様です。
職員講習を担う看護師が外部研修を受けることは、職員講習の質向上のためにも有意義だと考えています。
7.日頃の保健衛生/看護業務に関すること
通年実施する看護業務や保健活動についても記載しておくと便利です。実際に書面に起こしてみると、かなり細かく色々と活動していることが分かります。
もちろん、すべてを記載する必要はありません。しかし、日常の保健・看護業務を職員間でしっかりと共有しておくことで、看護師不在時や急なお休みの際も保健・看護業務を円滑に回すことができると思います。
8.期毎に振り返りと反省
「保健計画」通りに活動することは理想的ではありますが、必ずしもベストだとは限りません。その時々で必要になる保健衛生に関する課題も変わりますし、子どもたちの様子によって健康教育を再設定することも多々あります。
大切なのは、これらの計画や活動の変更も記録に残しておくことです。そして、期毎に活動の反省・振り返りを行うことで、次の活動に生かしていくことが重要です。
保育業界が抱える課題の一つとして、記録が「記録をすること」で終わってしまうという課題があります。本来記録をするということは、PDCAサイクルを回して保育実践の質を向上させていくためであり、職員間で情報を適切に共有するために必要な業務です。
計画倒れにならないよう、適切に振り返っていきましょう。変更事項や追加事項は赤いペンで直接書き込んで大丈夫です。監査の際に、担当の方が教えてくれたのですが、「計画はどんどん汚していい」「むしろどんどん汚していってほしい」とのことです。せっかく立てた計画を活用するという意識をもっと持ってほしいのだと思います。
まとめ
「保健計画」は、正直なことを言うと毎年大きく変更することはないと思います。年間目標やねらい(年間計画)は、ある意味恒久的なものですし、期毎に気を付けたいことも基本的には毎年同じです。
しかし、細かく業務を振り返っていくと毎年ブラッシュアップしていること、うまくいった活動とうまくいかなかった活動が必ずあります。その反省を次年度に生かしていくという姿勢が、保育の質向上のために大切なのだと思っています。
そして、保育園看護師だからこそ出来ること、専門性を生かして取り組めることもたくさんあると思っています。保育園における保健活動は、子どもたちの健やかな育ちにつながるための活動です。ぜひ、みんなで一緒に考えて、意識して、取り組んでいきたいですね。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
