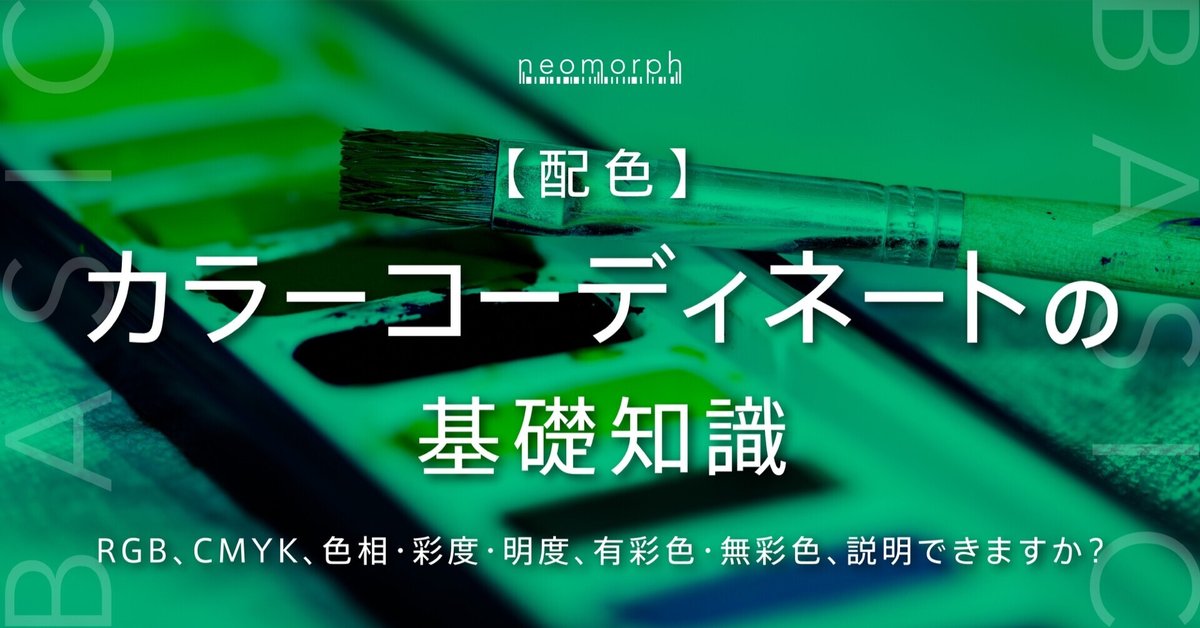
#6 [配色] カラーコーディネートの基礎知識 【ベーシックコース】 ネオモルフ デザインアカデミー
こんにちは、アートディレクターの松元駿です!
色の基礎について学び、それをしっかり覚えているでしょうか?
「配色の知識はなんとなくあるよ?」という方も多いと思いますが、今一度『色の基礎知識』を振り返ってみましょう。
たしかにある程度の色の知識はセンスでカバーできるのですが、目的に応じたデザインを“色の知識”を用いて作成できればより制作物の精度が上がりますし、「どんな色にしよう?」と必要以上に考える時間も省くことができます。
今後のベーシックコースでは配色の知識やテクニックにも触れていきますので、そのベースとなるカラーコーディネートの基礎知識をしっかりおさらいしておきましょう!
このnoteを読めば「なんとなく知ってる」ではなく、『三原色』、『色相・彩度・明度』や『有彩色と無彩色』、『効果的なモノトーンの使い方』を語れるようになりますよ!

noteだけでなくインスタグラムやYouTubeでもデザインの知識を投稿中!
色彩検定は必要ない
まず前提として、デザイナーが必要とする配色の知識はそんなに深くないと考えています。
デザイナーが必要とする知識は今回お話しする基礎の部分や色相環の使い方、色やその組み合わせが持つ印象や相性のいい組み合わせなどなど。
基礎の部分以外は知識というより、『実制作で培う経験』で養われていく部分です。
それを踏まえた上で、僕のところにたまに来る質問にここでもお答えしておきましょう。
Q.「デザイナーになるには色彩検定を受けておいた方がいいですか?」
僕の答えは、
A.「興味があるなら受けたらいい程度で、必須ではないですよ!」
僕は色彩検定を受けたことがないし、仕事で必要と感じたこともないです。
持っているからといって広告代理店やデザイン事務所でのお給料が良くなるということもないです。
もちろん知識があるに越したことはないですが、色彩検定の勉強を仕事のためにするなら、その時間を使って他のデザインの勉強をしたりポートフォリオを充実させることを優先させましょう!
実戦で必要な配色の知識はnote、インスタ、YouTubeを通して僕が全てお教えします!

色の三原則
さて、いきなり脱線しましたが、ここからはデザイナーとして活動する上で切っても切り離せない『色』の基礎知識を解説していきます。
ここから先は
¥ 330
定期購読マガジンでデザインが誰でもできるようになる知識を毎週投稿しています。内容の濃いnoteを執筆していきますのでフォローやシェア、サポートを宜しくお願いします!インスタグラム(@neomorph.jp)でも無料の知識を公開しているのでチェックしてみてください!
