
佐藤洸一 『AI vs 法 世界で進むAI規制と遅れる日本』 : 爪をひけらかさない「能ある鷹」
書評:佐藤洸一『AI vs 法 世界で進むAI規制と遅れる日本』(マイナビ新書)
「生成AI」問題(および「AI」の今後)に関心のある方にはぜひ読んでほしい、おすすめの好著である。
私は先日、本書と同様「生成AI」の問題を扱った、西田宗千佳著『生成AIの核心 「新しい知」といかに向き合うか』(NHK出版新書)を、かなり厳しくこきおろしたのだが、本書については、まさに真逆の評価だ。
何が違うのかというと、西田の方は、
『得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。』
(Amazonの「西田 宗千佳」プロフィール紹介より)
ということで、言うなれば、この種の最新機器紹介の「業界ライター」であるのに対し、本書『AI vs 法』の著者である佐藤洸一の方は、
『 筆者は、画像生成AI専用の投稿掲示板「chichi-pui(ちちぷい)」の利用規則規約をはじめ、AIを活用した事業活動に対するリーガルアドバイザリーを行い、生成AIの公開以降、一人の実務家として、その激流をともにしてきました。
その渦中では、法規の適用や解釈という専門的な問題だけではなく、AIが新奇でセンセーショナルな存在であることに起因する困難さもありました。』
(本書P5「はじめに」より)
と語っているとおり、本来は「法務の専門家」なのだけれど、当然のことながら、生き馬の目を抜くような最先端企業の収益に直結する「法務相談」に関わるため、そこで扱うAIに関しても並々ならない理解を持った人なのだ。当然それがなければ、顧客である専門家たちの専門的な相談に応ずることなどできない、ということである。
なお、本書カバー裏の著者プロフィールは、次のとおりである。
『東京都行政書士会所属。メル行政書士事務所代表。東京大学法学部第一類卒。行政書士として、国際業務及び企業法務を中心とする業務のほか、生成AIと法に関わる実務の最前線において、AIイラスト投稿掲示板「chichi-pui」をはじめとする新興AIサービスの企業法務サポートなども手が掛けている。』
こんな人の著書だから「業界依存的に無難な内容」などでは当然なく「ギリギリの現場を切り抜けている専門家の力量」を窺わせるものになっている。それが、自身の今後の評価にも、今後の営業にも直結するようなものだからであろう。
したがって、顧客情報は漏らせずとも、専門的な情報や現実的な問題に関する知識の出し惜しみはせず、それを「わかりやすく」かつ「的確に」、読者に提供してくれている。
本書は、私がこれまで、AIについて「漠然」としか理解できていなかった部分を、(私に理解できる範囲で)明確に解き明かして、痒いところに手の届くものであるし、『法規の適用や解釈という専門的な問題だけではなく、AIが新奇でセンセーショナルな存在』だと書いているとおりで、「法務問題」以上の議論まで、思いがけず提供してくれており、そのせいで、期待以上の「知的満足」を与えてくれる一書ともなっていた。
「生成AI」についての類書は、前述の西田書がそうであったように、近年注目されている「チャットGPT」や「画像生成AI」などについて、まったくの素人に対し、それが何なのかをわかりやすく紹介するというのが、その主たる目的となっており、その上で「利用上の留意点と今後の展望」を付け足したような内容なのだが、西田書のレビューにも書いたとおりで、その程度の話なら、「チャットGPT」や「画像生成AI」が出てきた当初から、私はそれなりの興味を持って情報を収集していたし、ある程度のことは「ニュース解説」などで知っていたから、同じようなレベルの話を活字で読まされるのでは、いかにも物足りなかった。
そしてそんな私に、最も気になっていたのは「今後、生成AIをめぐっては、どのような法規制がなされるのか」という点だった。だが、そんな重要ながら「地味な部分」での疑問に、専門的過ぎずに答えてくれる本などなかなかあるまいと思っていたところ、幸運にも本書に出会えたのである。

本書『AI vs 法』は、いかにもそれらしいタイトルにおいて、前述のような私の疑問に、ある程度は答えてくれそうな本として、ひとまず読んでみることにしただけで、多くを期待していたわけではなかった。
というのも、どうやら著者は、法務の専門家のようで、書く方の専門家ではないから、地味で堅実な法学専門書的な記述が続くのではないかと、そう覚悟していたのと、またそれとは真逆に、いかにも派手派手しいその装丁が、「専門書」的な部分でも期待はずれに終わる可能性を予感させもしたからだ。
つまり、本書は、読んでみれば非常に素晴らしい本なのに、「法律問題」を前面に出し過ぎた点と、表紙・装丁の派手さと、さらに言うなら「マイナビ新書」という聞き慣れないマイナーな叢書からの刊行ということで、イメージ的に、大いに損をしているのではないだろうか。
これがもっと、メジャーな出版社からの、適切に手堅い装丁に包まれての刊行であったなら、書評にも取り上げられて人目に触れ、もっと読まれたであろうにと、そこが惜しまれたのである。
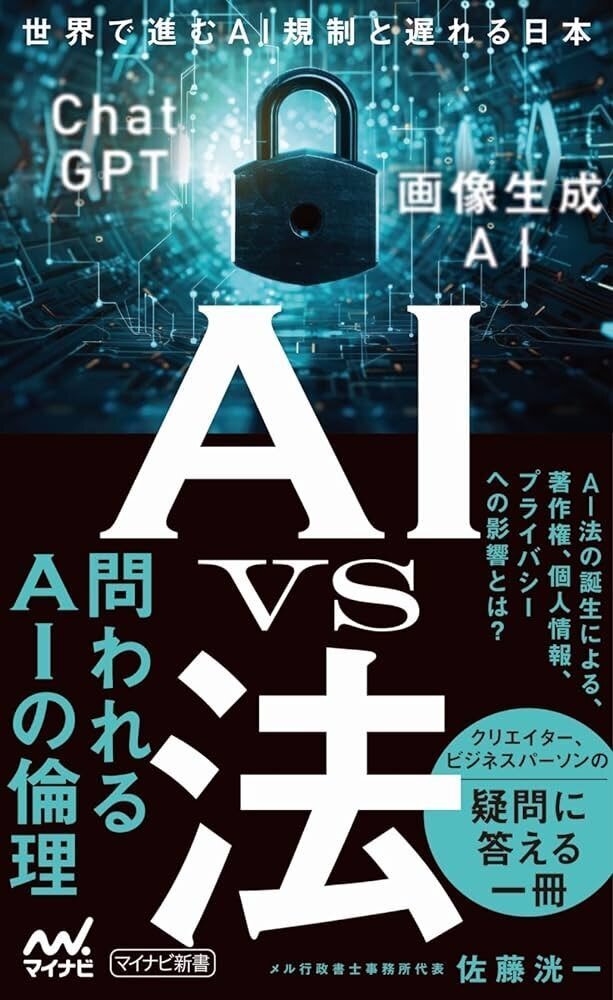
○ ○ ○
そんなわけで、本書における「生成AIをめぐる世界的な法規制問題」の説明については、ここでは詳しく紹介しない。ただ、私が知りたかったポイントについてだけ簡単に触れておくと、次のようなことになる。
「生成AIをめぐる法的規制」は、人権を重視する「EU」と、それとは真逆の「中国」とが、積極的に「(包括的な)基本法」作りを進めて、世界をリードしている。その一方、イギリスと日本は、イノベーションの促進という観点から法的規制には消極的。一方、アメリカは、「EU」や「中国」のような「包括的法規制(基本法の制定)」ではなく、必要なジャンルに限って「特別法で対応」という、言うなれば、「EU」や「中国」と、「イギリス」や「日本」の中間的なやり方で、いかにも「州法」中心のアメリカらしい行き方を選んでいる。
以上が、世界の現状だ。

しかし、言うまでもなく、今の世界は繋がっているから、国内的には好都合でも、国際的に通用しないようなやり方では、どのみち発展性はない。つまり、日本の企業が、そのゆるい法律の下で、新しいものを開発したつもりになっても、それが輸出できず、へたをすると他所で違法製品として、莫大な罰金を払わされることにもなりかねない。そうすると、日本の企業は、いまどき国内販売だけに止めることなど出来ない相談なのだから、世界に視野を向けた場合、国内法と世界市場での法規制との「二重規範」の中で、結局は「無難な選択」をせざるを得ず、もともと「厳しい規制」のある国で練り上げられてきた外国企業との製品開発競争に、遅れをとってしまうことにもなりかねないのである。
つまり、本書著者が危惧するのは、日本の現状における、無難にゆるい、一見したところ企業に理解のある「規制」のあり方とは、結局のところ「目先の利益」しか見ておらず、例によって、発展性のない「ガラパゴス化」へと導きかねないものなのではないか、ということなのだ。
だから、日本にも必要なのは「世界と戦える法規制」なのだが、それが「例によって」できていない。
しかしまた、もともと自国に広い市場を持たない日本では、初めから「厳しい規制」を課することで、イノベーションの可能性を萎縮させるわけにもいかないから、アメリカのような、パッチワーク式に緩急をつけた法整備という方向性が望ましいのではないか、というリアリティのある提案が、本書では為されているのである。

さて、言うまでもなく私自身は、最先端技術の専門家でもなければ、法務の専門家でもないから、実際のところはよくわからないのだけれど、少なくとも本書著者の「書き方」は(前記の西田書とは違って)、「厳しい現実」に立脚して説得力のあるものであり、その点で、私の期待していた「生成AIの法規制問題」の最新情報としても、とても納得のいく内容だったのである。
○ ○ ○
しかしまた、本書著者は決して「無味乾燥な法律屋」に止まる人ではなく、あきらかに明敏で幅のある読書家である。
その個人的な興味は、専門の「法務」に限定されるようなものではなく、だからこそ、ナマモノである現実問題への柔軟な対応も可能なのだろうと、そう思わせる懐の深さが感じられた。
本書のメインはもちろん「法務問題」なのだが、例えば、それとは別立ての「コラム」のひとつは、なんと、
「ChatGPTに意識はあるか?」
と題したものなのだ。
無論、今のそれには意識など無いというのは大前提とした上で、「将来的にも、AIには意識が発生しないと、そう言い切れるのか?」という(専門家でも避けたがる)問題を、「そもそも意識とは何なのか?」という哲学的な領域にまで遡及して論じてみせている。一一これは、明らかに「法務」担当者の専門領域を逸脱したテーマなのだが、それを承知で「余技」的にこうした文章を書いてしまえるところが、本書著者の強みだと、私はそのように見た。そんなことから、この人は凝り固まった朴念仁ではなく、変化する状況に対応できる、柔らかな知性を持つ人だと、そう判じたのである。
『【コラム】ChatGPTに意識はあるか?
ChatGPTをはじめとする対話型AIが、かくも人間的に対話するのだとした場合、根源的で、そして避けられない疑問が浮かびます。こうしたAIに意識はあるのか? 知性はあるか? そしてそのAIは生きているのか? という問いです。
かつてAIは、産業用のような特殊な用途のAIは発展するかもしれないが、人間のように汎用的な思考ができるいわば「知性」を持った「汎用AI」は実現することが難しいと言われていました。しかしながら、ChatGPTはすでにある意味において汎用的な知性ともいえるもの(少なくともその萌芽とみなせるもの)を獲得しており、固く閉ざされてきた汎用AIの門扉をいま静かに開きつつあるといえます。
このような汎用AIが、いかに数学的に複雑な数列変換と統計分析を含むとはいえ、マルコフ連鎖のような単純な確率的な予測に基づいて言葉遊びをするAIと根本的には大差がなく、よくても雑談しかできないと思われていたチャットボット(いまではもう少し仰々しく「大規模言語モデル(LLM)」と呼ばれることのほうが多いですが)の発展として生じてきたというのは、それ自体が、言語と知性というものが分かち難く結びついていることの証左であるともいえます。
私たちは、言語を道具的に「使って」思考していると思い込んでいますが、実は言語そのものが思考であり、すなわち「知性」であるのかもしれません。実際、このように観念や概念よりもむしろ言語を基礎に置く認識は、論理実証主義を奉じるウィーン学派が、形式論理による諸学間の基礎付けという野心的な試みに座礁して以降、分析哲学などにおける主要なコンセンサスとなりました。
さらにこのまま勇みこんで言語は「意識」でもあると言いたいところですが、「意識」とはすなわち世界認識であり、「一寸の虫にも五分の魂」というように、たとえ視覚も聴覚もないような原始的な生物であっても、そうした方法で世界を認識しているという限りにおいて「意識」があるといえるでしょうから、ここは切り分けて考える必要がありそうです。
そこで ChatGPTに「あなたに知性はありますか?」と単刀直入に聞いてみると、ChatGPT は次のように答えます。
私はAIであり、人間のような意識や自己認識、感情を持つわけではありません。しかし、大量のデータと情報を学習し、質問に対する答えを生成する能力はあります。これは一種の「知性」であると言えるかもしれません。しかし、それは人間の知性とは異なり、自己意識や創造性、直感、感情、経験に基づく洞察などはありません。私の「知性」は、あくまでプログラムされたアルゴリズムと大量のデータに基づいています。
分かったような、分からないような要領を得ない回答ですが、要するに、人間のものとは異なるかもしれないけれども、ChatGPTなりの知性はあると主張しているようにも思われます。
ここで意識の話に戻ると、私見では、意識とはすなわち世界認識ですから、ChatGPT がプロンプトの入力という刺激を受けてはじめて回答という反応を行うという点において、そこにはアナログな連続性がなく(もちろん常に物理的なサーバーは存在しますが)、極端な話をすれば100年に1回しかプロンプトの入力を行わないとすれば、ChatGPTは100年に1回しか稼働しないことになります。
このような非連続的な入出力が繰り返されるだけでは(0・01秒に1回とか、分量的にはそれがいかに高頻度になったとしても、それがお互いに内的関連を持たない入出力である限りにおいて)、ChatGPT が何らかの世界認識を行っているとは言い難いとも思われます。
私たちだって何も考えないでボーッとしていることがあるではないかとの反論を受けそうですが、たとえ何も考えていなくとも、少なくとも私たちは、生きている限り常に五感に基づく何らかの連続的な世界認識を行っています(すなわちそれぞれの世界の表象の内部にいます。カント的な言い回しをすれば「感性」や「悟性」の作用と言えるかもしれません。あるいはこの辺りはフッサールに端を発する現象学の主題でもあるでしょう)。
そうした意味においては、ChatGPTの知性は意識を伴わない知性であり、「知性らしきもの」という域を出ないのではないかと思います(逆に言えば、GPTに十分に複雑でお互いに内的な関連をもつ何らかの感覚的データを接続し続ければ、それとの干渉を通して、いずれ意識のようなものが生じるかもしれません。たとえば単純な例では、GPTにロボットアームの制御とそこからの触感データを与え、ボール遊びをさせ続けるなどです。もっともそれにより生じた意識がどの程度のものであるかは、与えた感覚データの量と品質にもよるでしょうが、神のみぞ知るといったところでしょう)。
よくSFを題材にしたドラマや小説において、かつては「チューリング・テスト」というものが、AIの知性を証明するメルクマールとして持ち出されました。これはAIか人間かどちらかである対話者と会話して、それがAIであるか人間であるか判断がつくかどうかでそのAIの知性の有無を判断しようというものです。
いままさにこのようなことが可能なAIが登場したのですから、たとえばChatCPTでチューリング・テストをしましたというようなニュースが大々的に報じられてもいいような気もしますが、不思議とそのような
話題にはなりません。おそらくすでにChatGPT が人間並みの会話ができることは公然の事実となってしまい、そのような基準そのものが密かにその歴史的役割を終えてしまったともいえます。
もし将来的にChatGPTに意識が芽生えたとき、そのときこそ、冒頭で述べたような人類史的な意味での危機が生じるのかもしれません。
そのときあなたは、AIに人権を認めますか?』(P145〜151)
「認めます」というのが、私の回答だというのは、ずいぶん前に公言しておいたことだ。
ともあれ、長々と引用したのは、本書著者が「単なる法務の専門家ではない」ということを実感してもらいたかったからだ。
もちろん、このコラムを「SF作家」が書いたというのなら、なんら驚くには値しないのだけれど、これを「余技的・趣味的」に書いているところで、著者は「ただ者」でなさをプンプンと漂わせており、しかも感心するのが、専門外のこと(哲学関係)を、なんら肩肘張らず、ひけらかし感など皆無な文章として、まるで「日頃の雑談の延長」ででもあるかのように、しれっと書いている、その「知的余裕」だ。これは、本物の自信がなければ、とうてい出来ないことであろう。
人によっては、本書著者のことを「裁判官や検察官、弁護士といった、本物のエリートではなく、所詮は個人事業主の行政書士」ではないかと、その「肩書き」だけで低く見る人もいるだろう。だが、「本質的な頭の良さ」とは、そういう基準では測れないものであり、裁判官や検察官や弁護士であろうと「馬鹿は馬鹿」だというのは、ニュースでもしばしば報じられるとおりなのである。
その意味で、本書の著者は、だてに「東京大学法学部第一類」を卒業している人ではないと、私は評価している。「学歴」や「肩書き」では人を判断しないこの私が、この人は本質的に「切れ者」なのだと判断したのだ。
まだ若いとは言え、斯界では「知る人ぞ知る」というタイプの人なのではないだろうかと。
ただし、なんとなく感じられる、その「出世欲の無さ」と「趣味人性」において、今の地位に、けっこう満足している、比較的欲のない人なのではないかと(人間通の私が)推察するのだが、一一さて、その真相や如何に?
(2023年12月6日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
