
中井英夫 『月蝕領映画館』「中井英夫全集12」 : 反世界からの映画批評
書評:『中井英夫全集[12]月蝕領映画館』(創元ライブラリ・2006年)
『月蝕領映画館』は、1984年に大和書房から初版単行本が刊行されたものの、その後、再刊や文庫化もなく、中井英夫の主だった作品(著書)を収めた第二次「中井英夫作品集」(三一書房・全10巻+別巻1)にも収録されないままだったのが、「創元ライブラリ」版「中井英夫全集」において初めて収録され、いわば「文庫化」も成った著作である(なお、三一書房は、1969年に1巻本の『中井英夫作品集』を刊行しているので、こちらが「第一次」ということになる)。
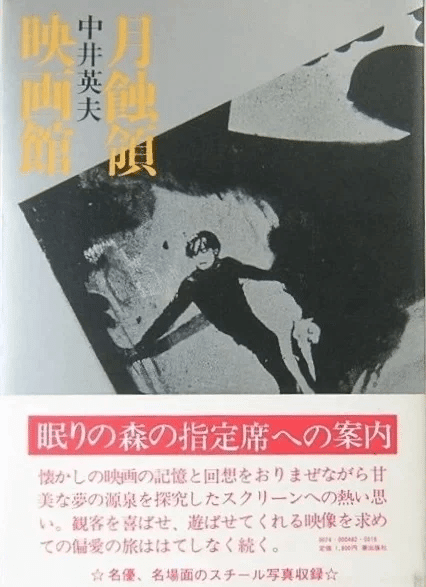
さて、先日、年来の悲願であった、と言うと大袈裟にすぎるが、長らく気になっていた映画、ロベルト・ヴィーネ監督の『カリガリ博士』(1920年・ドイツ映画)を視ることが叶った。
そのレビューにも書いたことなのだが、この『中井英夫[12]月蝕領映画館』には、付録の月報エッセイとして、「眠り男の迷宮・迷宮の夢」と題した拙稿(田中幸一名義)が収録されており、本書は直接的な縁のある、私には特別な一書である。
だが、にもかかわらず私は、この『月蝕領映画館』を、今日に至るまで読んではいなかった。今回、読んでみて「やっぱり、読んでいなかった」と確認する、体たらくだったのだ。
無論、全集の月報に文書を書かせてもらうほどのファンなのだから、早くから中井英夫の著書はすべて所蔵していたのだが、すべて読んでいたわけではなかった。あくまでも私は、小説家としての中井英夫のファンだったし、自分なりの中井英夫論を確立するまでは、小説作品の裏面を語る資料となる「日記」の類いはあまり読みたくないという意識があって、避けてきた部分が確かにあったのだ。
ただ、本書『月蝕領映画館』については、単純に、当時の私が映画ファンではなく、本書で語られている映画の多くを観ていなかったため、それであまり興味を持てなかったというのが大きかったと思う。
ちなみに、私は「眠り男の迷宮・迷宮の夢」を『月蝕領映画館』の巻に収録されるものとわかっていて書いたわけではない。結果とした、この巻に収められただけで、そうだとわかっていれば、さすがに私だって、その当時に読んだのではないかと思う。たぶん、ではあるけれども。
ともあれ、一昨年に退職して以来、映画を趣味的に見るようになり、それまで観たこともなかったフランス映画や古典的な名作映画まで観るようになったというのと、たまたま今回、本書『中井英夫[12]月蝕領映画館』を古本で再入手したので、この機会に読むことにしたという次第であった。
○ ○ ○
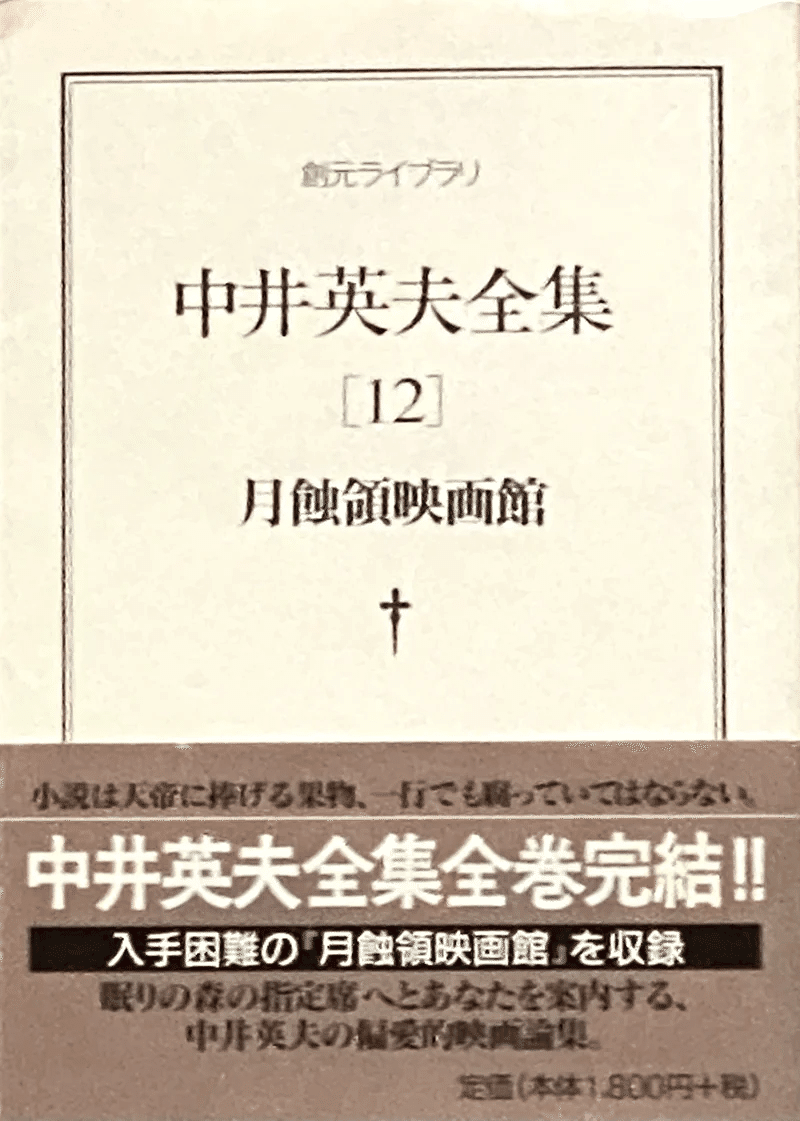
本書カバーの背面や、本書の版元である東京創元社のウェブページなどには、本巻についての次のような内容紹介文が掲載されている。
『影だけが妖しく壁を伝い、眠りだけがすべてを宰領する月蝕領映画館。「街があり映画館があり、中に映画があり銀幕がありスタアがいるという“往き”の手続き、あるいはその逆という“還り”の手続きなしに映画だけの話をするつもりはない」――昔語り、批評、苦言、ぼやき、小言、悪態……そして褒詞が少々。独断と偏見、記憶と回想に彩られた、月蝕領領主の偏愛的映画論集。解説=松山巖』
斯くあるとおりで、本書の特徴は、肝心の「映画分析」など無いに等しく、むしろ「昔語り、苦言、ぼやき、小言、悪態」といったことの方が多い、という点にあろう。「解説」の松山巖も、次のように指摘している。
『 読みはじめるとわかるが、『月蝕領映画館』には小言が多い。映画そのもの以前に、映画館の椅子が硬かったり、汚れていれば怒る。予告をだらだらと観せられれば腹を立てる。案内係の不親切さや観客の心ない振る舞いには傷つき、音響装置があまりに粗末であれば不満を漏らす。そういったことは映画鑑賞の愉しみを奪うからである。
映画そのものも同様で、ユニークな発想でワクワクさせてくれれば手放しで誉めるし、たとえ評価が高い作品であっても、彼の審美眼に合わなければ辛辣に叩く。』(P213)
私の場合も、本書を読み始めて最初の感想は、映画そのものに対するよりも、「映画館」に対するこだわりの方が強い、というようなことだった。だから本書を、前記の内容紹介文のように『映画論』と評するのは、あまり正確とは言えないなとも思った。松山巖も、
『話題は自在に展開していく。思いつくままの気楽なエッセーである。しかしそれだけに彼のこだわりや好みが文章の端々から顔を出し、作家中井英夫の人となりを語る上では見逃すことはできない。』(P212)
と書いているとおりで、本書については、常識的には「映画エッセイ集」と呼ぶのが適切であろう。
ただし、松山の言う『気楽なエッセー』という評価は、あくまでも形式上の話であって、中身のことではない。
中井英夫は、本書で「映画作品そのもの」をほとんど論じなかったかわりに、別のことを論じており、そっちの方がよほど「重い」というか「気鬱」なものだというのは、この「映画をめぐるエッセイ集」に「昔語り、苦言、ぼやき、小言、悪態」が多く、要は「(当時の)今」に対する「批判」が多いということだと、そう解するべきだろう。
つまり、中井英夫は、「映画好き」ではあっても「映画オタク」ではないので、「映画」と「この世界・この時代」を切り離して、「映画だけ」を論じているわけではない、ということなのだ。
だから、本書を「映画論」だと思い込んで読むならば、実際には「映画作品そのもの」についての突っ込んだ議論をしていないのだから、物足りないということにもなろう。前述のとおり、本書における「映画評」には、「分析」などという「評論らしい属性」は、皆無に等しいのである。
だが、重要なのはそこではない。中井は「映画」を通して「この世界・この時代」を語っているのだと考えれば間違いないし、中井英夫にとっては、「映画」もまた、そういうものだということなのである。「昔語り、苦言、ぼやき、小言、悪態」は、「脱線」などではなく、「批評」の「構成要素」そのものと見るべきなのだ。
言い換えればそれは、「映画批評という既成のレール」に、易々とは乗ってしまわない、それは、「反世界」に所在する「月蝕領」の領主たる者の「非凡さの証し」なのだとも言えよう。
したがって、読み終えてもまだ本書を、世間並みの「映画評論」としか見ていなかったのだとしたら、その読者は、本書を全く読めていなかったということになる。
本書には「昔語り、苦言、ぼやき、小言、悪態」が多い。なぜかと言えば、「今(現状)」が嘆かわしいものと感じられるからであり、そうした評価は、すでに通常の「映画評論」の枠になど収まらないものだからである。
しかしながら、中井英夫の場合、それは何も「映画」に限った話ではない。
中井の著作に『ケンタウロスの嘆き』という文芸論集があって、これは盟友・三島由紀夫を論じた同書収録エッセイを表題作としたものなのだが、要は、三島もまた「半人半獣」の人だったという話ではなかったかと記憶する。つまり、そんな人だったからこそ、三島は、「この世界・この時代」に馴染みきることのできなかった、つねに違和感を抱えていた「異形」であったと、そういう話だ。
一一要は、「文学者論」にしてからが、そうしたものだったのだ。
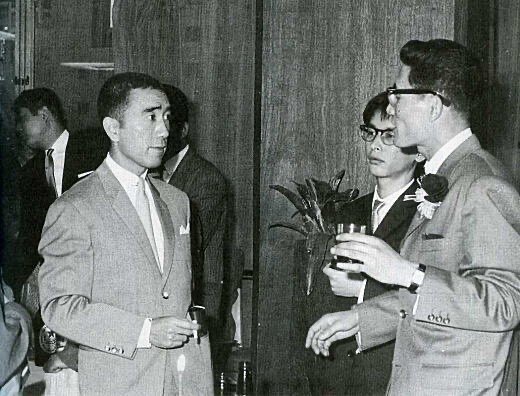
それはまた、中井英夫自身のことであったというのも、論を待つまい。
むしろ、三島由紀夫を評する言葉として、仮に適切性を欠いていたとしても、中井自身を語る言葉としてなら、完全に適切だったと言えるだろう。少なくとも、中井本人は、そのように感じていたのは、間違いないことなのだ。
では、そんな「異形」だの「異星人」だのが、地球人のものたる「この世界・この時代」を論じて嘆くことに「何の意味があろう。我々はこれで満足しているのだから、余計な差し出ぐちは無用だ」というのは、正しい考え方なのだろうか?
無論、そんなことはない。
中井英夫とは縁もゆかりもない、およそ対極的とも思えるタイプのノーム・チョムスキーが、しばしば「仮に、宇宙人が人類を観察した場合、その目に、人類の行いはどのように映るだろうか?」と問うていることからも分かるように、「当事者がいちばんよく承知している」などということは、金輪際ないのだ。
むしろ宇宙人から見れば、人類というのは「なんと愚かな生物なのだ」となるのは、容易に想像できるところなのである。
だから、「半人半獣」つまり「人外」である中井英夫が、その立場から「この世界・この時代」を論じることは、決して「部外者による、余計な差し出ぐち」などではなく、むしろ貴重な「客観的助言」だと捉えるべきなのだ。
「当事者」性に埋没してしまわない「人外」なればこそ見えるものがあるはずだし、当事者ではないからこそ、平然と「映画批評という既成のレール」を疑い、そこから外れることも辞さなかったのである。

当然、中井英夫の場合、「昔語り」が多いからといって、「昔は良かった」式のことを言いたいわけではない。
それは、次のような「批判」にも表れている。
『 「ダカーポ」という情報誌で「映画芸術」が八一年のベストテンとともにワーストテンを選んでいることを知った。のぞいてみるとこれがなかなかきびしく、日本映画のワースト順位は、「駅・連合艦隊・白日夢・ええじゃないか・悪霊島・マノン・謀殺下山事件・なんとなくクリスタル・ラブレター・蔵の中」と続く。評判の「泥の河」も「遠雷」も二十位以内に入り、しかもその拒否理由がそれぞれすさまじい。現在の映画状況のなかで、いわば犯罪的にダメな作品(山根貞男)とか、いまこの時、存在すること自体が許せない作品群(伊丹皓二)とかの言葉が飛び交い、四方田犬彦は、「泥の河・長江・駅」の三本に対し、必然性を欠いた生真面目において・傲慢において・冗長な感傷趣味において、と理由づけた上で、真に悪質と弾効する。そんなにも苛立つほどの状況とは何か、この回答からもう少し具体的に浮かびあがるといいのだが。
結局このワーストの点数を差し引いた結果のベストテンは、「陽炎座・嗚呼!おんなたち 猥歌・遠雷・泥の河・スローなブギにしてくれ・狂った果実・ガキ帝国・炎のごとく・セーラー服と機関銃・の・ようなもの」となるが、こうした催しでいささか気がかりなのは、試写もまだそこそこの映画をあげる人もいることで、あくまでも一般封切後に限らなければ意味はなく、さらにまだ見ていない作品には特定の印をつけるといった配慮も欲しい。批評の先行と観客とのズレは、いつどんな裂に育つか知れないのだから。
映画の観客数は一昨年よりさらに落ち込んで一億五千万人を割ったというが、一方では日本映画の豊作が讃えられている。それももっぱら新人監督の擡頭によるということで、読売新聞では石井聰亙から後藤俊夫までの十人を'82シネマ・ニューウェーブとして紹介した。小栗康平が入っていないので訊くと、いろいろ賞はもらっているが「泥の河」はもう古い映画なんですという返事だった。たった一本を撮っただけで古株扱いされるのでは、「陽炎座」をワーストワンにあげ、墓場の陰からしつこく顔を出す清順にはうんざりした(福島市男)などと、およそ見当違いな気焔をあげる手合が現われるのも当然であろう。』(P98〜99)
つまり、平たく言えば「若くて将来有望な皆さんは、好きに批判してもいいですよ」といった甘やかされた状況にある時には、まるで自分がそうした特権的な立場(一般公開前に、ご招待で作品を観ることができるような、特別待遇的立場)にあるのが当然のことででもあるかのように偉そうな態度で、ろくな根拠提示もせず、作品を頭ごなしに貶してイキがる、そんな低脳な輩の「毒舌」とは、「批評」でもなければ「批判」でもなく、「毒の抜けた毒舌もどきの(むしろ)冗舌」に過ぎない、ということだ。
こんなことが許されたのは、映画業界がまだ大繁盛して、余裕のあった当時だからでしかなく、中井が正しく危惧したように、
『映画の観客数は一昨年よりさらに落ち込んで一億五千万人を割った』
という事実の先にある、今日のような映画産業の不振(一部の娯楽作品だけが、馬鹿みたいにヒットして、作品の多様性がほとんど失われている)状況になると、こういう「お座敷芸として毒舌」を売りにしているような輩は、みんなそそくさと「幇間(太鼓持ち)」へと転職してしまうか、良くて沈黙したまま消えてしまうといったことにもなろう。そうなるしかないのだ。
したがって、たしかに昔は「今よりは、映画批評が生きていた」とは言えるだろうが、それは「9割のクズ」に紛れて「映画批評」と呼ぶに値するものもあったという話であって、「昔は良かった」という話ではない。
たしかに「ゴミ評論家」でも「食えた」時代を「昔は良かった」と評することができるのなら、それはそういう手合いには良かったのかもしれないが、そんなものがどれだけ映画のためになったのかは極めて疑わしいし、総じて言えば、昔も今も「9割はクズ」であり、映画が危機的な状況にあるという点に、本質的な違いはない。
映画に限らず、小説でも絵画でも何でもそうだが、およそ芸術というものは、いつだって危機的な状況にあるのであって、そのことを知らせる「炭鉱のカナリア」が、映画界にあっては、映画批評家であるべきだったのである。
つまり、中井英夫の「映画に関する批評」とは、そうした異次元のものであり、その意味で、当時の「業界にどっぷり浸かった」映画オタクたちとは、一線を画するものだったのだ。
そして、中井英夫のこうした「狷介」さは、言うまでもなく、その強すぎるまでの「愛」から出たものである。無論、この場合だと「映画愛」だ。
解説者の松山巖は、中井の「たのしい映画」を求める、わけ隔てない「映画愛」を、次のように語っている。
『『彼方より』のこの記述は、中井の希みをよく表わしている。「芸術に必要なものは、それが生々としてたのしいことだ」。誰にでもわかる、この映画の観方はほぼ四十年後に書かれた『月蝕領映画館』でも変ることはない。それどころか、「生々としてたのしいこと」への餓えは四十年前より強まっている。つまりはなかなか「生々としてたのしい」映画に出遇えず、中井は過去の映画をしばしば思い出す。
片岡千恵蔵の第一作トーキー『旅は青空』を思い出しては、ノーテンキな主題歌を口ずさむ。アニメ映画や魔術映画も動物映画も観に出かけるのだが、結局はアニメ映画といえば、ディズニーの『白雪姫』や『ファンタジア』、魔術映画なら『魔術の女王』や『世紀は笑う』と戦前の映画に言及せざるを得ない。それにしても中井英夫は「たのしいこと」にはじつに貪欲である。』(P216)
つまり、中井英夫自身、むかし観たものの方が楽しく感じられることを承知の上で、しかし、「新作」を頭から馬鹿にしたり、ジャンルで作品を差別したりはしない。
結果として、悪口を並べることになったとしても、それは何らかの期待を持って観に行ったからに他ならないのだ。
中井が最も好きなのは、若い頃に観た「フランス映画」のようだが、しかし、そんな中井が、CG映画の嚆矢である『トロン』を楽しんだり、『宇宙戦艦ヤマト』以来の「松本零士アニメ」ブームに乗って作られ大ヒットした劇場用アニメ『1000年女王』(1982年・明比正行監督)を観に行ったり、体調不良で観に行けなかった、招待状の届いた作品の一つとして『六神合体ゴッドマーズ』(1982年の劇場版・今沢哲男監督)の名まで挙げている律儀さは、敬服に値するものだ。

もちろん、『1000年女王』を「松本零士の作品」として(否定的に)評価しているところなどは、アニメファンの私に言わせれば「わかってないなあ」という感じではある。
アニメだって、肝心なのは「監督」を中心にしたアニメの制作スタッフなのであって、ほとんど「原作者」の問題ではないからだ。
しかし、そうした「無知」や「弱点」は、誰にだってある。だが、それを隠して「得意ジャンル」ばかりを訳知り顔で語りたがるのが、ほとんどの映画評論家の現実だろう。
例えば、「フランス映画」を得意とする映画評論家で、アニメをきちんと論じられるものなどいないに等しいのだが、中井は「専門家・マニア」ぶりたいがために、無難に得意ジャンルのことしか語らないし、触れようともしないなどという、保身的な態度は採らない。
知らないことは知らないなりに、可能な範囲でそれを理解しようとして、その時点での理解を隠すことなく語るのである。
こうした、中井英夫の「正直さ」というのは、例えば、イングリッド・バーグマンの評価にもよく表れている。
『カサブランカ』(1942年)、『誰が為に鐘は鳴る』(1943年)、『ガス燈』(1944年)、『汚名』(1946年)などの作品で知られる、もはや伝説的な美人女優で、中井の好きな女優の一人なのだが、それでも中井は、バーグマンが「大女優」かというと、そう呼ぶには「人間的すぎる」というような注文をつけている。
つまり、「大女優」と呼ぶに値するのは、グレタ・ガルボやマリーネ・ディートリッヒのような、いっしゅ近寄りがたいオーラを放つ、人間離れした存在にこそ相応しく、それに比べると、バーグマンは「人間的」な部分を残しており、親しみやすさはあっても「大女優」とは呼び難いと、そう言うのだ。

もちろん、これは「大女優」というものの定義によりけりの話だから、バーグマンを「大女優」だと評価する人がいるのは当然で、それは中井英夫だって否定しはしないだろう。だが、中井がここで語りたかったのは「スターの存在価値」とは何なのかということであり、それは「観る者を、日常空間から攫って、天高く飛翔するような存在だ」といった、中井の「スター観」を語るためなのだ。
映画オタクによくある「こっちが凄いとか、あっちが上だ」などという幼稚素朴な「好み」の話とは、そもそも次元の違う議論なのである。
で、それでも中井英夫の「正直さ」であり「かわいらしさ」は、そのような「スター観」を語り、「バーグマンは、大スターとは呼び難い」などと客観的評価を語りながらも、しかし個人的にバーグマンに惹かれるのは「きっと、彼女に、母性的なものを感じるからだろう」と、そんなふうに正直に書いてしまうところだ。
中井英夫ファンなら周知の事実だが、中井は大変な母親っ子、お姉さんっ子だったのである。
だから、バーグマンの訃報に接した際には、半分冗談めかしながらも、彼女を「大女優ではない」と語ったことについての後悔を語っているし、テレビでの追悼特集だけではなく、映画館でもそれをやらないのかと注文をつけている。
そしてここで、アニメファンの私が面白いと思ったのは、テレビの追悼特集でバーグマンの代表作が放映される際、当然のことながら「吹き替え」版の放送となったのだが、その声を当てたのが、声優の池田昌子であり、そのことに触れて中井は「池田昌子の吹き替えは、まあ良いとして」、吹き替えではなく本人の声でやる(字幕でやる)ことくらいできなかったのか、と注文をつけている点である。
ひとまず、もっともな注文ではあれ、いちいち注文をつけるところは、いかにも中井英夫らしいのだが、私が注目したのはそこではなく、「池田昌子による吹き替え」自体には注文をつけなかった点だ。
というのも、たぶん中井自身はハッキリとは意識していなかったのであろうが、池田昌子の声とは、凛としていながらも、「母性」のある、お姉さん・お母さん声なのだ。そしてその典型的な例が、『銀河鉄道999』の「メーテル」役である。
「メーテル」とは、言うまでもなく「マザー」のドイツ語読みであり、メーテルは、主人公・星野鉄郎の母親「生まれ変わり」だという「隠し設定」のあるキャラクターなのだ。つまりメーテルとは、永遠の命の象徴たる「機械の体」を求めて旅する少年・鉄郎を、見守る「母性」の象徴なのである。だから、鉄郎が、機械の体などいらないと気づき、一人の男へと成長した暁には、彼の恋愛対象となることはできず、別れなければならなかったのだ。

ともあれ、声優・池田昌子の声とは、そういう特性を持っていた。それを中井英夫は、きっと無意識のうちに正しく感じ取っていたから、「吹き替え」は好ましくないと思いながらも、「まあ、池田昌子のによる吹き替えはかまわないか」という、いっしゅ曖昧な態度を採ったのだ。
中井は「吹き替え反対派」的な「イデオロギー」として、一貫した態度に固執するのではなく、自分の「実感」に沿って、正直に語る人だったからこそ、こうしたことも意図せず、自然に可能だったのである。
そんなわけで、『月蝕領映画館』という「映画エッセイ集」を、「エッセイ集」だからという理由で、声高に「映画監督論」や「作品論」を謳ったような「評論書」と比較して、軽く見たり低く見たりするのは、言うまでもなく間違いである。
そんなふうに考える者とは、そもそも「文章」そのものが読めないからこそ、「看板」頼りの分類評価しかできないのだ。ものの「本質」を見ることができないのである。
例えば松山巖は、中井が、戦後の「ソ連映画」について「日記」に記していたことに正しく注目して、次のように指摘している。
『 試みに、中井の戦時中および戦後の日記『彼方より』から、若い中井が当時の映画や芝居、演奏会をどのように観ていたのか、引いてみよう。
「幕間(11の後)で環女史あらはれ、挨拶をのべていはく、私は昔ロンドンに行つて歌劇をやりチョイと圧倒してきた、それからアメリカでまたみんなのしてきた。かういふ勝つて帰つた先例があるんですから、皆さん私のやうに年とらずしつかりおやんなさいだの、アンナ・パヴロワとシャリアピンと私と三人はちょつと変つてゐるといはれたものだ、それは私が心に大和魂を持つてゐますからだの、鼓の音に涙を流した日本礼讃をやる口調は、外人が日本を賞めるのを聞くやうな、みえすいた浅薄さだ。」(一九四三年十月十二日)
「『ヨイコ』といふ軍国主義時代の言葉が未だ用ひられてゐる。これ位おしつけがましい、欺瞞性のあふれた言葉は珍しいだらう。(略)曾て私はそのヨイコたちが、学校を軍隊式に『自治』してゐる映画を見せられた。即ち彼らは銃の代りに棒切れか何かを持つて門前に衛兵を設け、先生と見るや「敬礼』と叫んで立上るのである。歩哨も出てゐて、その交代も棒切れを「担へ銃』して『歩哨交代ニ来マシタ』といふ、そんな文化映画(!)だつた。」(一九四五年十一月二十六日)
「ソ連映画『スポーツパレード』を吾郎と観た。東京中央劇場。若い世代、たとへば私にしてからがさうだが、『全線』や『静かなるドン』などの名に憧れはしながら、ソビエト映画といって先日封切られた『陽気な連中』とこれで二本目だ。(略)それにしてもこの美は、まつたく整列し、集団化され、機械化され、調和された美であつた。だがそれこそナチス独逸の精鋭が、軍国日本の皇兵がもつとも得意とするものではなかつたか。今ここにソビエトが、何のゆえあってその統制とその人形化と、一言にいへば非人間的な集団美を誇るのか。」(一九四六年十一月八日)
「昨日、地球座で「旅路の果」をみた。兵隊にゆく前、どうか封切つてはくれないだらうか、あれを観てから兵隊にゆきたいと、さう願つてゐた作品だが、やはり失望した。一寸デュヴィヴィエと思へぬくらゐ、ぎくしやく人間の動きがつまつて、そのぎこちなさが流れる情感をはばんでゐる。」(一九四八年四月二十七日)
戦時下では映画を自由に観る機会は少ない。映画鑑賞の記述がないので、三浦環の独唱会の感想を引用したが、浅薄なナショナリズムに対する反撥を虚飾なく記している。この反感は、戦争が終った後も一貫している。戦後、ソ連の国家体制は日本ではいわゆる民主主義陣営から、支持された。しかし中井は一本のソ連映画を観ただけで、当時は未だ多くの人が気づかなかったスターリニズムの匂いを感じとり、ナチズムや日本の軍国主義と結局は同じではないかと断じている。彼が見つめ、怖れたのは、映画であれ、芝居であれ、音楽であれ、文化が政治の道具となり、変質し、矮小化されることであった。』(P214〜215)
戦後、日本の知識人の多くは、「アメリカ帝国主義(米帝)」に反発し、その反対物としての「ソビエト共産主義」の「理想」に共感して、これを支持したのだが、彼らには、その「ソビエト共産主義」の隠された実態たる「スターリニズム」が全く見えておらず、のちに、その惨状が伝えられるようになって、やっと、おのれの浅薄さと、その「偏見(色眼鏡)」を恥じなければならなかったのだが、中井英夫は「ナチスドイツによる人間のロボット化は悪だが、ソ連式の集団主義的調和は素晴らしいなどという、日本の知識人の小理屈など、所詮は愚かな、イデオロギー的自己欺瞞でしかない」と、映画一本観ただけで看破していたという話である。

そして、これは「吹き替えは好ましくないが、池田昌子の声は悪くはない」といった、一見したところ「矛盾」に見えて、実は矛盾でも何でもない、中井英夫の「非イデオロギー」的な「曇りなき目」の証明ともなっているのだ。
そしてまた、こうした問題は、何も「戦中」や「戦後」に限った話ではない。
「大東亜共栄圏」だの「八紘一宇」だのといった「綺麗事のプロパガンダ」を真に受けるのと、「商業主義的な大宣伝」によって、あっさり洗脳されてしまう、今どきの「私の(批評)眼=個人としての主体的な眼」の無さは、結局のところ同じことなのだ。
「大本営発表」を真に受けるのと、「観客動員数」だの「興行収益ランキング」だのを「傑作」であることを示すものだと思い込んでしまうような幼稚な「数字信仰」も、本質は同じ。いずれも、「私(の眼)」の無さの証明でしかないのである。
つまり、中井英夫が本書で語っているのは、昔の話ではなく、まさに私たちの「今」の問題であり、「今の映画」の話なのだ。
こうした批評は、近年の「新自由主義市場経済」的な「ヒットしたもの勝ち」の「あさましさ」にどっぷりと浸かっているような、映画制作者や映画評論家や映画ファンには、語りようもないことである。
だからこそ、本書『月蝕領映画館』は、今こそ読まれるべき「映画書」であるし、私も、書くのであれば、中井英夫的な「映画評論」を書きたいと思う。
その意味で、私もまた「人外」である。
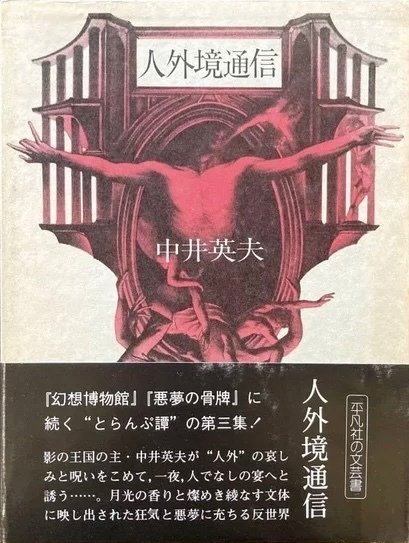
(2024年2月14日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
