
モバイルバッテリーについてのお話
SNSを眺めていると、モバイルバッテリーについて、mAh?W?Wh?定格3.7V?5V?とよく分からないままに何となく使ってる人が多々見受けられます。
誤った認識でモバイルバッテリーを論評しないように簡単な説明をしていきます。
そんなに難しい話ではありません。
ちゃんと詳しく理解したい人は物理で電気の勉強してください。
このnoteではガジェット関連のバッテリーに関わる仕様の表記や意味についての解説します。
筆者は第2種電気工事士の免状を受けていますが、そもそも小学生でも合格可能なレベルの資格であること、日常での作業がDIYの範疇にとどまるため、必要最低限の知識技術しか持ち合わせていません。素人というわけではありませんが専門家でもありません。
ご容赦ください。
用語の定義と意味
定格電圧と定格電流
安全に動作するための最大の電圧と電流の値のこと
リチウムイオンバッテリーは通常、定格電圧3.7Vである。
家庭用コンセントは100Vないし、200V
実際には定格電圧で固定されているわけではなく、
リチウムイオンバッテリーの場合はその充電量によって3.7±0.5Vで動作し、家庭用コンセントは100±5V, 200±10Vで供給されている。
定格電圧5V/定格電流4Aというのは5Vで最大4Aまで安全に電流を供給できるという意味。
自動車で言うならギア比と回転数かな。
定格容量
定格電圧と定格電流によって安全に扱えるエネルギーのこと
例えば家庭用コンセントは定格電圧100V、定格電流15Aで定格容量1500Wと表記される。(=供給可能電力)
リチウムイオンバッテリーの場合、定格電圧3.7V定格容量10000mAhなどと表記される。(=蓄電可能電力量)
これは3.7Vの電圧を持ち,10A(10000mA)の電流を1時間流せる容量であることを意味する。
この定格容量のことを一般的にバッテリー容量と呼んでいる。
自動車で言うなら燃料(航続可能時間)に相当する。
電力
機器が単位時間あたりに消費or供給できるエネルギーのこと。
ワット(W)。
電力=電圧×電流である。
120Wの神ジューデンは20V, 6Aである。
自動車で言うなら速度に相当する。
電力量
一定時間に消費した電力の総量のこと。
電力量=電力×時間
Whで表す。1500Wのドライヤーを1時間使ったら1.5kWhとなる
電力会社の明細にある電気の使用量がこれ。
自動車で言うなら走った距離に相当する。
では、実際のバッテリーの仕様を見ながらその意味や表記を確認していきます。(解説中の計算に関してはすべて理論値であり、電力ロスや発熱を考慮していない)
Xiaomi 165W 10000mAhの仕様をチェック

バッテリータイプ
リチウムイオンバッテリーが使用されていると記載。定格電圧3.7V?→電力量が36Whであることから定格電圧3.6Vのリチウムイオンバッテリーが使われていそう
定格電圧3.6Vのリチウムイオンバッテリーは高エネルギーよりも長寿命や高耐久が要求されるものに使用されているようです
バッテリー電力
これがこのモバイルバッテリーの持つエネルギー総量となる
一般的には電力量と呼ぶ。
36Whは36Wの電力を1時間取り出すことが出来る電力量である。(電力ロスや発熱があるのですべてが取り出せるわけではない)
このバッテリーセルは4個並列で定格電圧3.7Vであるので
バッテリーの持つ電力量は
3.7V×2500mAh*4=37000mWh=37Whと計算できる。
(電力量から逆算すると定格電圧が3.6Vとなるのでバッテリー電圧を下げている可能性が高い)
このバッテリーで9V3A(=27W)の充電(出力)をする場合、
36Wh÷27W=1.33h(時間)の充電が可能である。
10000mAh(3.7V)を基準として考えてしまうとこのバッテリーを90W(20V4.5A)で給電(入力)したとき、どのくらいの時間がかかるのかや、5V2Aで動作する機器をどのくらいの時間使えるのかなど、計算するのが難しくなる。
90W給電で0→100までの時間は36Wh÷90W=0.4h(=24分)、
5V2Aの機器は36Wh÷(5V×2A)=3.6h(時間)使用できる。
あくまでも10000mAhというのはリチウムイオンバッテリーの持つ定格電圧3.7Vの時の値であることに注意をする
つまり、バッテリーがリチウムイオン以外の場合や直列で接続されている場合はバッテリーの持つ電圧が異なることがあり、〇〇mAhでは比較できない。
ポータブル電源では使用電圧3.2Vのリン酸鉄リチウムイオンが使われ、4個直列接続されているので電源電圧は12.8Vとなっていることが多い。(なので〇〇Whと表記されているはず)
リチウムイオンバッテリーは3.7Vが基準となっているので製品名では3.7Vは省略され、〇〇mAhと表記されていることが多いが、あくまでも製品名。
また、製品によっては定格電圧5Vの定格容量を表記しているものもある。
(9600mAhなのに10000mAhと名をつけた製品もあったりする。)
バッテリーに蓄えられるエネルギー量を比較したいのであれば電力量で比較したり、計算するのが望ましい。
13T Proを充電できる回数を計算してみる
モバイルバッテリーのセルは3.7Vである一方、出力時は5V-20Vに昇圧するので電力ロスが発生し、定格電圧3.7Vのときの定格容量よりも減少する。
このモバイルバッテリーの定格容量は5500mAh(5V)と判明しているため、出力時の電力量は
5V×5500mAh=27500mWh である。
13T Proのバッテリー容量は5000mAh(3.89V)であるため、0から満充電に必要な電力量は
3.89V×5000mAh=19450mWh である。
よって、充電できる回数は
27.5Wh÷19.5Wh=1.41≒1.4回 と計算できる。
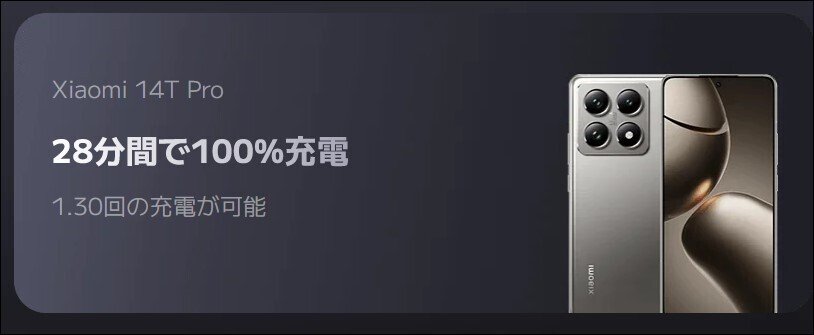
同じく5000mAh(3.89V)を持つ14T Proを1.3回充電できると説明されているので概ね正しそうですね。
補足
先述の通り、モバイルバッテリー(リチウムイオンバッテリー)の電圧が3.7Vであるのに対してスマートフォンへの給電時の出力電圧は5-20Vである。
出力時はモバイルバッテリー内で昇圧してスマートフォンに電力供給をしている。また、スマートフォン供給された電力は3.7Vへ降圧されバッテリーに蓄電される。
それぞれ昇圧降圧時に電力ロスが発生するため、モバイルバッテリーの容量すべてがスマートフォンに給電されることはない。
一般的にロスは全体の15-25%とされている。36Whであれば実際に給電出来る電力量は32.4Whと考えたほうがよい。仕様に5500mAh(5V)と記載あり
以上で簡単なバッテリー容量についての説明でした。
厳密には異なる説明や省略した部分もありますが、あくまで一般教養として提供するものであり、物理学の知識として提供するものではないことに注意してください。
説明が不十分な箇所や明らかに間違った説明があれば指摘をお願い致します。
今回取り上げたモバイルバッテリーはこちらで紹介されています。
また、Xiaomi 33W Power Bank 20000mAhのバッテリー電力量の公称値は74Whですが、実測では90Wh超えています…
普通は公称値よりも少なくなるのが当たり前ですが、何故か超えてきます。定格容量は12000mAh(5V)となってるので出力時は60Whほどに落ち着くってことでしょうか?
そのうち出力も測ってみようと思います。

