
「なぜ、いまソリッドベンチャーに注目するのか」〜スタートアップ・エコシステムの変遷により、ソリッドベンチャーとM&Aに焦点が当たり始めた背景〜
エンジェルラウンド株式会社(以下、エンジェルラウンド)と、株式会社ファイナンス・プロデュース(以下、ファイナンス・プロデュース)は、先日、ソリッドベンチャーの成長支援強化に向けた業務提携開始を発表しました。
なぜ、このタイミングで2社がソリッドベンチャーの育成に向けての提携で合意を行ったのでしょうか。エンジェルラウンド代表の大越氏とファイナンス・プロデュースの入江が対談を行いました。
VC大量組成から約10年、一巡したスタートアップ支援

エンジェルラウンド大越氏(以下、大越):
大越です。よろしくお願いします。2023年5月に設立し、デジタル領域で挑戦する起業家に投資するファンドを運営しています。
ファイナンス・プロデュース入江(以下、入江):
入江です。ファイナンス・プロデュースで、主にスタートアップやソリッドベンチャーを対象に、資金調達やM&A売却の助言、伴走を行っています。
大越:
私自身、いわゆるVUCA時代に突入した今、これからの日本経済をドリブンしていく主役の一人に起業家がいると考え、彼ら・彼女らを支援しようと自社を立ち上げています。支援をご一緒できて嬉しいです。
入江:
我々も様々な規模のクライアントをご支援してきておりますが、実は注力中のテーマとして、ソリッドベンチャーM&Aなどもございます。
大越さんはソリッドベンチャーの生みの親として、日々SNSでも提唱されていますね。
◾️ソリッドベンチャーとは
ソリッドベンチャーとは?Jカーブビジネスのスタートアップとは創業時の売上の考え方が全く違う会社のこと
大越:
そうですね。どの形態を特別に推しているというわけでもないのですが、この10年くらいのスタートアップ・エコシステムの変遷を見てきた中で、ソリッドベンチャーという成長の仕方もありだなと思う様になり、このワードを提唱しようとしていっています。
入江:
改めてその流れについて伺えますでしょうか。
大越:
はい。釈迦に説法ですが、日本でスタートアップブームが起こり、2010年代には多くのベンチャーキャピタルファンドが設立されました。LPと呼ばれるファンドへの資金の出し手は多様なプレイヤーがいますが、巨額の出資となってくると金融機関からの支援が必要になる中で、金融機関におけるリスクマネーの取り方には一定のルールがあることから、多くのファンドで、償還10年というキャップがついています。
最初はそこを気にする必要はなく、当時のキャピタリストたちは、自分たちの推しを投資委員会にかけることを進めてきましたが、時間が経つとやはり、ファンド成績を意識せざるを得ないフェーズに入ってきます。
ただ闇雲に出資をすればよいというわけではなく、ポートフォリオのうちどれくらいの社数がどれくらいの評価額で、どうEXITをする必要があるのか、ということに本腰を入れて向き合っていくタイミングになってきました。
入江:
スタートアップとして起業するならばIPOを目指そうという考え方の創業者や投資家は10年前はもっと多かったでしょうね。実際今でも、表向きにはM&Aでも構わないと意見表明されているVCであっても、IPOを原則目指してくださいという圧力は感じます。
例えば1号ファンドを運用するVCは、IPOを期待していた投資先が、M&Aを選択するケースなどにおいて、VCの意見と起業家の意見が異なり、利害調整が難航して弊社に相談がきたケースもありました。
10年前はよりIPOを目指す風潮はありましたか。
大越:
そうですね。一方で、米国不景気や新型コロナウイルスの流行、国内株式市場の乱高下など、「谷のシーン」がやってきて、多くの企業がその影響を受けました。ビジネスモデルを直撃したスタートアップもありますし、ファンド側も、投資時に想定していた成績からブレが出てきたでしょう。
一方で、証券取引所側も、上場基準を大幅に緩くするというわけにもいきませんから、経営者や投資家としては、売上・純利益を上げるよう事業を成長させたり、追加調達やM&Aによって経営を継続させる必要が出てきます。
入江:
IPOシナリオを想定して創業し、PMFが見えづらい状況下であっても外部資本を入れ続けてきてしまったスタートアップが、想定通りの成長やファイナンスが難しいと感じる局面は、増えてきていると感じます。
ファイナンス・プロデュースでも様々な支援を行っていますが、例えばM&Aにおいては「ロールアップ(水平型M&A)」や「ボルトオン(補完型M&A)」「バーティカル(垂直統合型M&A)」といった言葉が浸透したり、「スイングバイIPO」の事例が出てくるなど、事業成長の手法は随分と多様化をしてきている印象です。
大越:
そうなんです。特にベンチャーキャピタルからの出資を受けてスタートアップモデルの経営を始めると、償還期間や評価額のプレッシャーから、EXITをめざしての経営を考えがちですが、本当に大切なのは事業を成長させ続けること。法人や調達の形態というのはその手段の一つですからね。
そんな背景の中で、様々な会社を見ていて、実は、しっかりと成長をしている企業の特徴の一つとして、結局は「きちんと純利益を出している会社」という、とても基礎的なポイントに注目するようになりました。

入江:
それがソリッドベンチャー提唱につながるんですね。営業利益、純利益がしっかりと出せている会社であれば、キャッシュフローも健全であることも多く、そもそも外部資本に頼った資金調達をしなても良いですよね。銀行調達はまだ難しい状況でも、売上債権の流動化、RBFやベンチャーデットなど、デット調達ができる場合もあります。
M&Aにおいては、そもそも赤字企業は入り口の段階でNGという買い手が多いです。買い手企業が、のれん負けを回避するための条件として、EBITDAマルチプルのX倍以下を買収価格とする、というように、売り手企業が黒字であることを前提とする典型的な社内基準を設けている会社も多いです。
スタートアップとは、従来の事業と異なり、革新的で未浸透であるからこそ、最初はPMF(プロダクト・マーケット・フィット)するまで時間がかかり、まず赤字を掘ってから一気に拡大するJカーブモデルを描くと言われますが、そもそもJカーブで成長しなくても良さそうなビジネスモデルも沢山存在しますよね。
堅実に成長させつつ途中にJカーブモデルで事業展開するような戦い方や、1社目の起業におけるソリッドベンチャー・モデルの事業は事業売却やM&A売却し、2社目に連続起業家としてJカーブモデルの事業に挑む戦い方も増えているような印象もあります。もちろん、1社目でいきなりDeeptech領域に挑まれていて、社会への影響力も大きい分野で戦っている起業家の友達もおり、それはそれで非常に尊敬しています。
大越:
そうですね。たとえば、技術から社会実装型プロトタイプを作るまでに時間がかかるDeeptechの領域のように、ハイパーグロースながらもある程度Jカーブ型を描かざるをえない業態もあると思いますが、一概にそうとも言えず、できるだけ純利益が上がっているに越したことはない、と考える様になりました。
毎年100社ほどの会社がIPOされていて、2023年をみてみると新興市場のグロース市場に上場しているのが68。社年。そのうち、うち約70%の48社が黒字上場、約30%の20社が赤字上場なんです。スタートアップ界隈にいるとIPOしている会社の多くがJカーブモデルの赤字上場だという感覚になってしまうんですが、実はそれほど多くない。では、どんな会社なのかというと、創業から毎年きちんと売上と利益を着実に積み上げていって上場をしてるようなケースです。
これを堅実な(ソリッド)ベンチャーという意味の造語で、ソリッドベンチャーと呼ぶことにしました。
入江:
我々のクライアントにも、スタートアップ型とソリッドベンチャー型が混在しています。
実際にM&Aのご支援をする際は、売上・利益を積み上げている会社の方が、買い手企業の候補が多くて選択肢が多いことを前提とした”磨き上げ”をしやすいです。(”磨き上げ”とは、対象会社の特徴をより魅力的に投資家に伝えるために、事業計画・資本政策・エクイティストーリーの整合性などを対象会社と協議し、複数のシナリオをシミュレーションするプロセス)
大越:
ソーシャルインパクトのために大きな夢を描くこと自体は大切ですが、最初から売れない前提で赤字の事業計画を引くのは、起業家にとっても投資家にとっても精神的にあまり良い影響をもたらしません。特に市況がよくないと、あまりに博打なモデルにはどのみち資金は集まりませんので、事業は継続できない状況に徐々に追い込まれていきます。
入江:
赤字前提ではなく、売上が立つ前提で事業をしていくという心構えは事業成長に大前提で必須ですよね。
磨き込むFAと、優良銘柄をエンジェル投資する投資家が連携する時代へ
入江:
ファイナンスにおけるスタートアップ支援という言葉において、現時点で、一番最初に名前が上がる外部パートナーといえばキャピタリストかなと思います。ただ、あくまでキャピタリストは勝つ投資先を選定し、投資を実行することが仕事のポジションであると考えています。
他方、スタートアップ・ソリッドベンチャーFAという立場は、ディール(=試合)を勝たせるところまで汗をかいて動く、磨き込む、投資家と議論・交渉する、クライアント先の着金日まで責任を持つ仕事のポジションだと考えています。
こんな状況下になれば、クライアントも、弊社も死活問題ですし笑
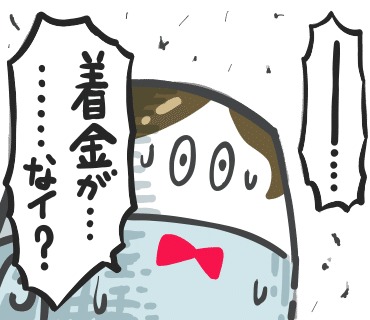
大越:
はい、そう思います。デジタルマーケティングやPRは、エージェンシーに依頼するのが当然になってきているように、ファイナンスもきちんと専門家に預けて、事業が成長していく文化を構築したい。そのためにも、資金調達にもM&Aにも、きちんとFAが入るようにしたくて、今回、ファイナンス・プロデュースさんとの提携を決めました。
特にシードアーリーの発行体にはCFOがいないことがほとんどですし、トップクラスのキャピタリストについてもらえるかどうかという属人的な博打でなく、外部に委託すれば一定のクオリティで経営ができるという環境が望ましいと思うんです。
実際、FAが磨き込みまでしてきてくれてからスタートアップにきてもらう方が動きやすいので、Win-Winな構造なんじゃないかと思っています。
入江:
起業家の中には、自社の強みのなんたるかを言語化できていない人もそれなりにいるので、それを投資家にわかりやすく噛み砕いてあげるのもFAの役割かなと。投資家側も、多くの案件を見ていて日々相談が多い中で、つい「先日も見た類似事業だな」「あの案件でこんな懸念点がでたな」というような印象ができてしまうものだと考えています。
なので、対象会社が持つ事業の本質的な理解、財務とビジネスを紐付けるアプローチなど別の視点で補完できないか模索し、投資家が理解しやすいように対象会社と整理しています。
大越:
構造上、キャピタリストとしても高いバリュエーションを付け、できればIPOをする案件に入れた方が自身のキャリアの泊付けになりますから、そうなると投資委員会を通しやすい案件の方が打率は良い訳で、まだ顕在化していないが市場がある事業を掘り出すという力学とはちょっと違う物になりがちですよね。
直近で時価総額1,500億円超で上場したスタートアップがありますが、当初はファイナンスに苦戦したというのはこれに当たるかなと。
ソリッドベンチャーというのは、まさに、評価も認知もされにくいが、黒字になっている分、市場が確実にあってこれから跳ねるという企業たち。この人たちを伸ばしていきたいけれど、自分一人では限界があるので、ファイナンス・プロデュースと連携していきたいと思っています。
入江:
ソリッドベンチャーというものを皆様も薄々認知はしていたけれど、大越さんが名前を付けてくださったことで、改めてその存在を認識しやすくなったと思います。エンジェルラウンド自体が業界に欠けているピースとしてユニークであり、その分広報力も強くて凄いです。
ご一緒できて非常に嬉しいです!
引き続き連携よろしくお願いします!
関連記事
おすすめnote
ファイナンス・プロデュースではnoteで「M&Aマガジン」も配信中です。M&Aの基礎とトレンドが詰まった大人気コンテンツです。M&Aをご検討の方はぜひフォローください。
\人気のM&Aナレッジnote/
「スタートアップM&Aの規模化と質の向上を、事例から考察」は、特に人気の記事となっています。
