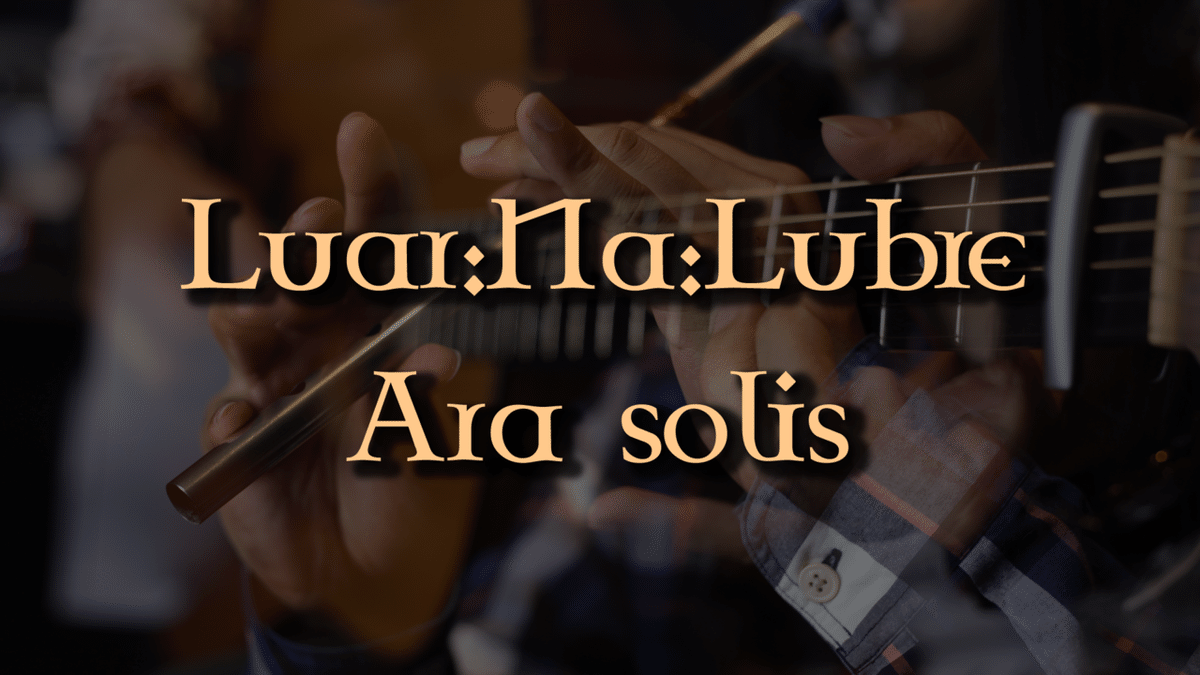#011 楽器を触ることの重要性・実践編
こんにちは。ノイジークローク藤岡です。
第7回の記事で言及した「楽器を触ることの重要性」の続編、というわけではないのですが、色々言っておいてその実践にあたる部分を示さずにおりましたので、今回はそれを実際にやってみることにしました。
今回は自分が所有している楽器を使って、私の大好きなガリシア音楽のバンド、Luar na lubreの"Ara solis"という曲をできる限り原曲を再現しカバーしてみようと思い、動画を制作しました。
その中で今回私は
アコースティック/エレキギター
エレキベース
アイリッシュブズーキ
アコーディオン
ティンホイッスル
ガイタ(ガリシアのバグパイプ)
シンセサイザー(実際には電子ピアノでソフトシンセを鳴らしたものです)
チェロ
ウドゥ、コンガ、シンバルなどのパーカッション
を自宅で収録・撮影しました。ちなみにこの中でアコーディオン、チェロ、パーカッション群についてはズブの素人です…。
ただヴァイオリンだけは聴けたものじゃないので、これまで何度か収録や演奏でご一緒して頂きました、酒井絵美さんをゲスト演奏家としてご参加頂きました。(酒井さんもnoteをご執筆ですのでぜひこちらへ。)
まずは動画をご覧頂ければと思います。
何分、こういう動画制作ははじめてなので、多々見苦しいところがあろうかと思いますが、何卒ご容赦下さい。
このAra solisという楽曲はLuar na lubreのフルート奏者、Xan Cerqueiro氏(シャン・セルケイロ)作曲のもので、私はLuar na lubreの楽曲の中でも大好きな曲です。"Espiral"というアルバムに収録されておりますので、気になった方はぜひ聴いてみてください。
何百回と聴いたこの曲も、いざそれぞれのパートを演奏するとなるとひとつひとつ注意深く聴くことになり、その結果、新しい発見もたくさんしました。例えばギター弾きの自分から見ても思いつかないようなエレキの使い方や、シーケンス的なブズーキのフレーズや、アコーディオンの音の抜き差しなど。
また、実際に楽器を触って録音してみることで、それぞれの楽器の大変さだったり、作曲時にパートを作っているだけではなかなか見えない細かい部分に気づいたり、またその楽器のプロとしてやっている演奏家さんたちのすごさに改めて気づかされたり、或いは音楽の楽しさそのものを再認識したり。
たったひとつの曲からこうして得られるものは本当に多く、今後の自分自身の制作にも、大きく意味のあるものになると確信しました。今回のように動画にするしないは別として、定期的にこういう実践をしていきたいと思います。こうしたことは都内に住んでいたり、防音設備がなかったりするとなかなかやりにくいものですが、何とか方法を見つけて環境を整えられれば、楽器の上手い下手、録り方の上手い下手関係なく、本当にたくさんの実のある発見ができると思います。
ということで、今回は記事としては短いのですが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた。