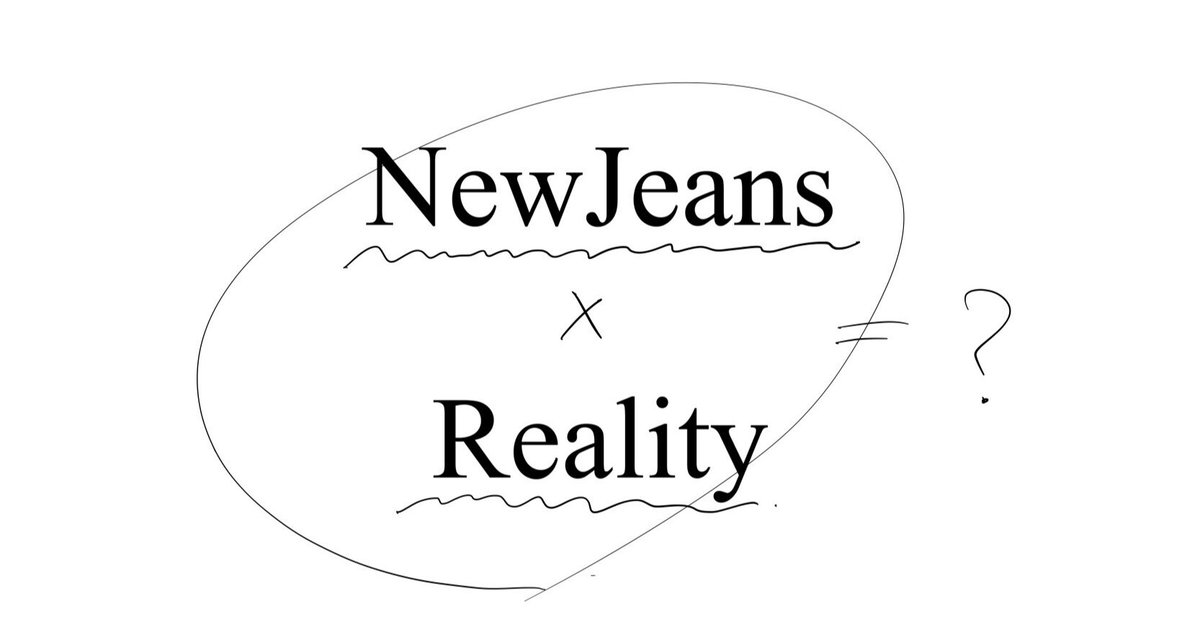
NewJeansが作り出すリアリティとその行方 #5
注意) できるだけ冷静に、そして客観的に、分析・考察を行いたいと考えていますが、どうしてもオタク心が抑えられないことがあります。ときどき文章が乱れますが大目に見てください。
4章 第4世代K-POPガールズグループが作り出すリアリティ(前編)
ここまで、NewJeansが作り出すリアリティについて、デビューアルバムのEPにまつわる様々なクリエイティブを分析することでその輪郭をあぶりだすことを試みてきた。
↓これまでの記事(長い)
思ったよりかなり、長くなってしまっている。。。
どうせなら、無限に章を作って終わりのない論考みたいになったら面白いかもしれない。
サグラダファミリア的な論考。なんかかっこいい。
戯言は置いといて、進めよう。
さて、上述のように輪郭をあぶりだしていると言っても、未だふわっとしていて、ともすれば消えてしまいそうな不安定なものに思える。
ここからは、その輪郭をより明瞭にするために、現在のK-POPシーン、とりわけ第4世代のK-POPガールズグループの潮流を概観してみたい。
第4世代という区切りはどこからか?と言う議論はここではあまり重要ではないので、ITZY以降にデビューしたグループを第4世代と仮に定義することにする。
尚、本章においては、最後に様々なグループとNewJeansを比較するという形式をとるが、決して優劣をつけるものではない。あくまで、それぞれのグループが持つリアリティを系の中にプロットすることで、相対的にNewJeansの位置する座標を想定するという試みである。
4章の概要
4.1
はじめに、2020年に中小事務所のHigh Upエンターテインメントからデビューを果たしたSTAYC、そして、HYBE LABEL傘下のSOURCE MUSICから2022年にデビューしたLE SSERAFIMについて取り上げる。彼女らが魅せるのはアイドルという人間のリアルである。
4.2
次に、第4世代ガールズグループの草分けともいえるITZYについて概観した後、NewJeansと同様に韓国の音楽チャートを席巻するIVEについて考える。ITZYは自己愛のアイコンとなり、今、まさに次のステップへと動き出す存在である。IVEはKPOPのアイドルグループの完成形ともいえるべきカリスマ性やクオリティを提示できる稀有なグループである。両グループは自己愛を皮切りに研ぎ澄まされた物語を作り上げる。
4.3
続いて、その突出したコンセプトと楽曲から圧倒的な存在感を放つaespaについて言及する。aespaはリアルな手触りとは対極にいる。新たな時代の身体性を持ったaespaは、他のグループのリアリティを相対化すると同時に、リアリティの可能性を拡張する。
4.4
そして、現在のKPOP業界を語る際に避けては通れない、オーディション番組の存在と、その系統の中で最も重要な転換点であったと思われるIZ*ONEについて考える。ファンがアイドルを選ぶことによって、支持すること(オタ活)自体のリアリティが強化される。さらには、そういった支持すべき人材が流動的に存在し続けることでKPOP業界全体のポテンシャルは成長しつづける。
4.5
最後に、NewJeansよりも後に登場したtripleSについて検討をすすめる。時代の空気感を乗りこなし、新たなアーティストとファンの関係性を提示するチームである。参加型のデザインスキームであり、ファンをアイドルの活動に積極的に巻き込む。
4.6
章の最後では、NewJeansも含めた各グループのリアリティをモデル化することを試みる。目に見える形でリアリティの根源を示すことで、今後のNewJeans、ひいては、K-POP業界におけるリアリティのあり方を考えていくためのベンチマークとしたい。
他にも魅力的なチームが多々存在することは言うまでもないが、分量の都合上泣く泣く割愛する。尚、各チームの基礎情報をここで確認するのはめんどくさい蛇足なので、説明はwikiに譲りたい。
全てのチームとその作品に敬意を払い、分析と考察を進める。
4.1 アイドルという人間のリアル
アイドルも人間である。至極当たり前なことだ。
しかし、隣にいる友達や家族、会社の同僚と同じ"人間"として彼らを見ることはできるのだろうか。
ある側面においては、一般人から距離のあるセレブリティとして神格化されることで、そのアイドルの価値が担保されることは間違いないだろう。
それがエスカレートすると弊害も生じる。
アイドルの人間としてのリアリティを感知できない人々は、心無い言葉を逡巡もなく発してしまう。
「最近太った」「愛想が悪い」「〇〇と××は不仲らしいよ」「△△最近人気落ちたよね」・・・etc.
そんな地獄のようなコメントが飛び交うインターネット砂漠の最中において、突出した人気を誇る二つのグループがある。
STAYC、そして、LE SSERAFIMだ。
両グループとも、楽曲やパフォーマンスのすばらしさはもちろんのこと、ファンからの支持や愛され方が尋常でないように思える。
彼女らを支持したくなるのはなぜなのだろうか?
その秘密を探っていきたい。
STAYC

High Upエンターテインメントを率い、STAYCの楽曲制作を主導するブラック・アイド・ピルスンは、K-POP業界においては言わずと知れた有名プロデューサーユニットである。
もはや、K-POPガールズグループ業界において生きる伝説となったTWICEである(異論は認めるが論破する自身あります)が、ブラック・アイド・ピルスンはその陰の立役者とも言うべき存在だ。
というのも、彼らは「Like OOH AHH」「CHEER UP」「TT」「LIKEY」といったTWICEを代表する楽曲群の作曲者でもあるのだ。
TWICEを通してK-POPという文化に出会った筆者からすると、彼らは神的な存在であり、アイドルのように偶像として崇拝したいぐらいである。言うなればブラック・アイドル・ピルスン、、、
そんな彼らが事務所を立ち上げ、初めに公開したプロジェクトがSTAYCである。
Youtubeで公開されているドキュメンタリー番組でSTAYCの練習生時代の様子を見ることができる。プロデューサーと練習生たちの対話や練習風景、月末評価の様子はもちろんのこと、練習生のリアルな生活の様子が事細かに描かれている。
また、"BEAUTIFUL MONSTER"のカムバック前には、STAYCのメンバーとプロデューサーの深い会話や次曲のコンセプトに関する議論がなされる様子をSTAYC’s next album is…というタイトルで映像公開している。
デビュー前の様子が描かれることや新曲の公開前にメンバー本人たちの思いが描かれることは稀だ。
そこでは、デビューに対する期待と不安、新曲への想いやアイドルとしての苦悩が赤裸々に語られている。
現在のK-POP業界では、ビハインド映像によって舞台の外でのメンバー達の素の姿を知ることができるというのは当然のこととなっている。
楽曲のMVが公開されたり、メディア露出があった後は、我々ファンは涎をたらしながらビハインド映像を待つ。パブロフの犬状態である。
しかし、この流れが常態化するに連れて、ビハインドという布地を纏った作品となってしまっているきらいがある。現実を美化した作為のある映像であり、虚構であり、ドキュメンタリーではない。
昨今、ドキュメンタリーはそのジャンル自体に大きな需要があるように思う。
Netflixのドキュメンタリー作品が人気を博していることからも、それは自明だ。
また、2022年の第3回JAPAN Podcast Awardsでは、テレビ東京の番組から派生した音声によるドキュメンタリー番組「ハイパーハードボイルド
グルメリポート no vision」が大賞を受賞している。音声メディアにおいても、ドキュメンタリーの存在感は圧倒的である。
STAYCはビハインドにも描かれない、さらにリアルに近い状況を迷いなくドキュメンタリーとして見せる。
本来なら取り除かれてしまうようなえぐみのある部分も摂取することで、ファンはメンバー達のパーソナリティや想いをより深く知ることができる。
しかし、これらは本当に実際の彼女たちの姿を映したものなのだろうか。
ドキュメンタリーから嘘を感じてしまうことはあるし、説教臭さから見るのが億劫になってしまうこともある。
とどのつまり、ドキュメンタリーは"実"を映すものなのだろうか。
ドキュメンタリーの第一線で映像を撮り続ける森達也氏は、以下のように語る。
ある程度はキャメラの存在に馴れたとしても、絶対にゼロにはならない。自分に照準を向けるレンズの威圧感は凄まじい。市井で普通に生きる人にとって、キャメラは永遠に異物のままだ。まずはその現実を撮る側が自覚するところからドキュメンタリーは始められなければならない。ありのままの事実など撮れない。キャメラのフレームに映りこむ世界は、キャメラという異物によって再構築される現実なのだ。
現実を撮っているようで、カメラを介するということ、編集によって再構築されることからすると、ドキュメンタリーもまた、"虚"であることは逃れられない。
STAYCの素を映そうと試みた、先述のドキュメンタリーも例に漏れないだろう。
しかし、いくら再構築の結果だとしても、その場で発せられた彼女らの言葉や行動には嘘や作為は無いのではないか?ファンとしてはそういった希望的観測がどうしても前面に出てしまう。
森氏の主張は、このような希望にも冷静に事実を突きつける。
この作為は撮る側だけの特権ではない。撮られる側は演じる。つまり嘘をつく。自覚的な嘘の場合もあれば、無自覚な場合もある。撮る側は時にはこの嘘を利用し、時には別の回路に誘いこむ。こうして撮る側の作為と撮られる側の嘘が経糸と横糸になって、ドキュメンタリーは紡がれる。
どんなに、彼女ら自身が自然体であると思っていても、カメラを向けられている時点で無自覚に演じてしまうことは避けられない。
我々ファンは、このことには自覚的になるべきだろう。
ドキュメンタリーとして描かれるアイドル達の姿は、アイドルとしての自覚を持って(あるいは無自覚に)演じられた姿であるのだ。
ただ、STAYCが見せるドキュメンタリーは比較的、実に近い虚であり、その試みは特筆すべきチャレンジであることは付け足さねばならない。
STAYCは、ビハインドというフィクションから一段階ノンフィクションに近い状態を見せる。これは、アイドルを含んだ製作陣にとってはリスクが大きいものであることは間違いない。
ファンの中には、ただただ作品を楽しみたいだけの人もいるだろうし、アイドルたちの過酷な状況への疑問から、素直に作品を享受できないというような人もいるだろう。
事実、筆者も業界の体質に対する疑問は少なからずある。
より持続的な文化として定着するためには、改善が必要な部分も少なくはないと思う。
ただ、そのリスクを背負ってでも、限りなくリアルに近い側面を描くことで、作品の礎になる文脈を受け手に理解させ、作品に深みを出すという姿勢は革新的だ。
製作陣やアイドルという立場でできる最大限のクリエイティブを発揮しようというプロの矜持がありありと感じられる。
ドキュメンタリーだろうがフィクションだろうが、私たちの真実を届けたいというSTAYCの姿勢に嘘はないだろう。
そのリアリティに私たちは感銘を受け、心動かされることは避けようのない事実だ。
LE SSERAFIM

ファッションショーのようにクールなショーケースでデビューを果たしたLE SSERAFIMは、デビュー前から今に至るまでそれぞれの物語を持っている。
作り上げたコンセプトの世界観を演じることに重きを置くことがメインストリームである昨今のK-POP業界において、パーソナリティの強さという特長は矛盾を孕みかねない。
作品とパーソナリティの乖離が大きければ大きいほど、作品のコンセプトを努力して演じているような雰囲気がどうしても見え隠れしてしまう。
これは、先述したような、ドキュメンタリーにおける無自覚な演技よりもたちが悪い。
なぜなら、自覚的な演技であり、かつ、自身の考えや人間性にも嘘をつく行為であるからだ。
しかし、LE SSERAFIMの楽曲やクリエイティブにはそのような雰囲気は微塵も感じられない。
というのも、メンバーへのヒアリングを重ねる中で抽出されたメンバーたちの考えや精神性をもとに、曲やクリエイティブのコンセプトが練り上げられていることが功を奏しているようだ。
創作でありながら、表現者の中のリアルをできるだけピュアに描き、それを時代の要請にうまく応えながら表現している印象がある。
日本でのアイドル経験を含めると三度目のデビューとなるサクラや、バレー界での華々しい経歴を持ちながらKPOPに飛び込んだカズハのように、彼女らのデビューまでの道のりにはすでに大きな物語がある。
IZ*ONE時代から一つ殻を破り新たな自分の魅力を発揮したいと宣言し実行し続けるチェウォン。グループ最年少ながら、デビュー間近のタイミングでプロジェクトに参加し、必死に食らいつくウンチェ。
それぞれのメンバーについて語るとそれだけで三篇ぐらいの記事になってしまうのでここでは省略するが、とりわけLE SSERAFIMのリアリティを色濃く表象する存在としてホ・ユンジンに注目したい。

ユンジンはPRODUCE 48に出演後、一度はKPOPアイドルとは別の道を目指したことを明言している。知る人ぞ知ることではあるが、デビューまでの道のりが険しいことで知られるK-POPアイドルの中でも、彼女は厳しい状況を潜り抜けてきた。
また、デビュー・トレーラー映像では「アイドル・シーンを変えたい」という台詞が注目を集めた。経験に基づいた確固たる主張だ。
以下に、デビュー時のインタビュー記事からユンジンの言葉を引用する。
あの映像で、「私は20歳です」、「アイドル・シーンを変えたいです」と言っていましたよね。
HUH YUNJIN:言いたいことがあるかと言われて、自然に言った言葉でした。音楽やステージで踊るのがとても幸せで好きなので、そして韓国で活動したかったので、アイドルを夢見るようになったんですが、練習生をして、K-POPを間接的に経験しながら感じたことがちょっとあったんです。
どういう部分を変えたいのですか。
HUH YUNJIN:アイドルについての厳格な基準に合わせるよりは、一つずつ打ち破りたいです。良い姿を見せるのは当然ですが、カメラの前で自分本来の姿を隠すよりは、もっと自由に自分を表現できる環境を作りたいです。なぜなら、私は私自身を誰よりもよく知っていますから。
インタビューを読んだ感想は、かっけえぇ、、、である。
語彙が枯れるほど、圧倒的にクールな内容だ。
グループとしての楽曲に、こういった彼女の考えやパーソナリティが色濃く表現されているのはもちろんのこと、セルフプロデュース曲という形で、ユンジンの宣言は実現へと漸近する。
彼女のセルプロデュース曲はこれまで(2023年4月18日現在)に3曲が公開されている。
これらの作品はチームとしてのLE SSERAFIMが表現する楽曲よりもさらに自身の内面や周りの状況をよりリアルな形で表現している。
最初に公開された"Raise y_our glass"は、自身のこれまでやグループへの想いについてかなり赤裸々にかつ詩的に表現された傑作で、ファンとしては感涙ものだ。まじ号泣。
とはいえ、特筆すべきは、2つめの楽曲である”I ≠ DOLL"だろう。
무시마 my voice
내 목소리 volume up
Idol doesn’t mean your doll to fuck with
私の声を無視しないでよ
私の声は大きくなっていく
アイドルはあなたが思い通りにできる人形じゃないの
(訳: 筆者)
デビュー前のイメージビデオでアイドル業界への一石を投じることを宣言していたように、ユンジンはアイドルという職業のリアルを惜しげもなく体現し表現に昇華している。
ジャンルは違えど、システムや不条理への怒りをエネルギーに変換するようなHIPHOP的な姿勢も垣間見える。
あるいは、Black Lives Matterで立ち上がったアーティストやセレブリティと同様に、自信の影響力に自覚的だからこそ生じる覚悟のようなものをひしひしと感じる。
ホ・ユンジンという大きな存在はこれからのアイドルにとっては希望の光であり、アイドルとファンの間をつなぐ頑強な架け橋となるだろう。
エンパシーの先にある感動
STAYCとLE SSERAFIMが描き出すのはアイドルという人間のリアルであった。
我々ファンのいる場所をノンフィクション、アイドルのいる場所をフィクションとするならば、アイドルを職業とする人は、常にフィクションとノンフィクションの間、虚と実の間を行き来することになる。
先の2グループからは、その虚実の間で引き裂かれそうになりながら、不安定な状態の中でもがく姿がありありと感じ取れる。
少しひりひりするような感覚。できればあんまり見たくないような、蓋をしておきたいようなものを見てしまったような感覚。
しかし、この痛みにも似た感覚こそはリアルであり、彼女たちへのエンパシーを可能にするきっかけとなる。
エンパシーという言葉は、ブレイディみかこ氏のエッセイやASIAN KUNG-FU GENERATIONの楽曲を通して日本でも市民権を得たように思うので、ここでは深くは掘り下げない。念のため、以下にそれらの作品を紹介する。
ここで主張したいのは、ドキュメンタリーとして彼女らの感覚に同期するための俎上が用意されていることで、我々ファンは自然とアイドルの想いを慮るためことができるということだ。
こういった行為を通して私たちは彼女らの作品をより深く理解し、自らの感覚としてもリアルに感動を享受することができるようになるのである。
さて、ここで述べてきたのは、アイドルの痛みや喜びに対するエンパシーを通し、文字通りに身体性を伴ったリアリティを感じる過程であった。
次節では、ITZYとIVEについて考える。
両グループはコンセプトという虚構に対して真摯に向き合い、作品そのものに確固たる説得力とリアリティを与える。
圧倒的な実力とカリスマ性がそれを可能にしているのは、ファンからしたら言及するまでもないことだろう。
そのコンセプトの上流に感じ取れる自己愛を発端とした物語に注目して、上記の側面とは別の角度から両グループがつくり出すリアリティの源泉を探りたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
