
日本人が英語を話せないのは学校教育のせい?
こんにちは。英語学習Webライター・兼・英語学習研究者のなっつるんです。
日本人が英語を苦手とするのは、学校教育の弊害によるものなのでしょうか。
その通りだと思います。考えれば考えるほど、学校教育の罪は大きいと感じるようになりました。
けれど……。
……というお話です。
学校教育の弊害①間違いを恐れる心が育つ
これは、よくいわれていることですよね。
「文法的に間違えるとテストで点数をマイナスされる」経験を数えきれないほど繰り返した結果、文法的誤りを極端に恐れるようになる、と。
でも、文法的誤りをいちいち気にしてたら、英会話は上達しない。
文法を学ぶこと自体が間違っているわけではないですが。
きちんとした英語コミュニケーションが必要になった時、文法知識は大事だと思います。
でも、順番が逆だと思うんですよね。
単語の羅列でコミュニケーションをとって、「通じた!」「楽しい!」という実感を経てからなら、文法を勉強したくなると思うんです。
文法だけを頭ごなしに教えるから、結果として英語嫌いの子、英語嫌いの大人を量産してるんですよね。
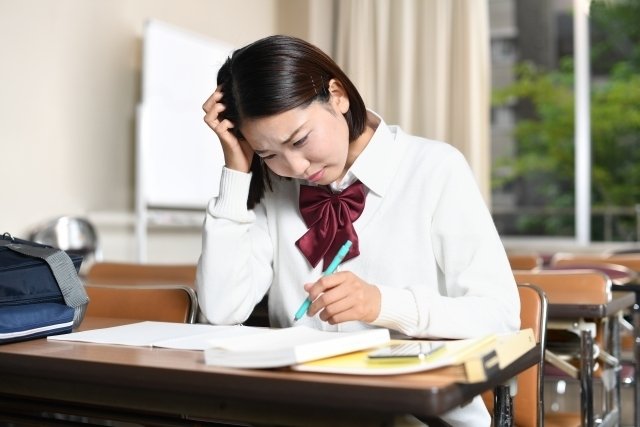
学校教育の弊害②英語脳が育たない
学校教育の弊害としてもうひとつ、よく挙げられるのが、和訳偏重の教育手法です。
英文をきれいな日本文に訳すには、ある程度「後ろから戻って」訳さないといけません。
でも、実際の英語コミュニケーションの時、「後ろから戻る」クセがついていては、英会話のテンポについていけなくなってしまいます。
英語を英語で考えることができなくなってしまうんですよね。
和訳学習自体が間違っているとはいいません。
例えば、英語に不慣れな時期に、和訳なしのオールイングリッシュで授業を行ったら、それはそれで、英語嫌いの子が育ちかねないと思います。
和訳の練習も、通訳を目指す上では必要不可欠ですしね。
ただ、学校英語では和訳「しか」させませんよね。
和訳するクセがしみついてしまうほど和訳させるのは、英語教育として好ましくないと思います。

学校教育の弊害その③意見が言えない大人に育つ
これは、英語の授業以前の話ですが、日本の学校では、ディベートやディスカッションをあまり行いませんよね。
欧米の子たちは、小さなころから「議論する」訓練を積んでいるというのに。
そもそも、和を重んじる日本では、「議論」=「ケンカ」ととらえ、自己主張より協調性が重視されてきました。
今までなら、「それはそれで日本文化の特色の1つ」と考えてよかったと思います。
でも、今は英語を使いこなし、世界的に活躍できる人材が求められているわけですよね。
「英語人材」というのは、単にTOEICでハイスコアをマークしてればいいんでしょうか。
そんなはずはありません。
「英語を使って、自分の意見を発信できる」能力までが、「英語力」だと思います。
日本の学校でも、学校でもっとディベートの手法を学ぶ機会を設け、どんどん生産的な議論の練習をすべきだと、私は思います。

けれど……
けれど……ふと、思ったのです。
「学校教育の弊害」を声高に叫ぶだけでいいのか、と。
具体的には、このセミナーに触れてからです。
「日本人が英語を話せないのは、学校教育のせい」
そういうと、現場の英語の先生を責めているようにも聞こえます。
でも、学校の英語の先生たちだって、必死で「英語を話せる子どもたち」を育てようとに対応してるんだと思います。
無責任に、声高に批判するだけでいいのか。
最近はそんなことを自問自答しています。
いいなと思ったら応援しよう!

