故安倍晋三元内閣総理大臣の功績と足跡を偲ぶ
大勲位菊花章頸飾を受章された故安倍晋三元内閣総理大臣(従一位)
彼の功績と足跡を学び、偲ぶ記事を書きたいと思いました。
SNS上では箇条書き的に「功績一覧」と書かれているものはあっても、その中身(成立時の状況、どのような障壁があったか、もともと存在していた問題にどう対応するものだったか、問題は解消できたのか、評価はどうなってるのかなど)に触れているものに出会う事は少ないです。
これはある意味当然で、国政というのは多数の専門分野から成り立っており、あらゆる国家活動に精通する専門家は居ないですし、ましてや専門家ではない者が半端に理解・論評・評価しきれるものではないからです。
しかし、重要概念の入門的な知識の理解や、「専門家らがどのように評価していたのか?」を知ることはできるはず。
そこで、私自身きちんと理解できているわけではないものについても、安倍氏の死去を受けて書かれた論稿を中心に、功績をまとめてみようと思った次第です。
もちろん、「安倍氏の功績と捉えるのは如何なものか」「安倍政権よりも前の政権時代からの流れがあった」「成立・実行したが不十分・弊害がある」といった指摘が可能なものもあるでしょうけど、「安倍氏の功績」という要素を抜きにしても重要な事実を取り上げる意義はあるだろうと思い選んだものも含まれます。
「これも功績だ」「この功績の説明にはこれが良いのではないか」というものがあればコメント欄等にお願いいたします。
※新聞の引用は紙面によるものが多いですが、リンクを貼っている場合にはWEB記事上のタイトルと異なる場合があるのでご了承ください。
※リンク先が変更されていた場合、政府機関であればWARPで検索すれば出て来るはずです。
※英文和訳は戦略用語などの専門用語に関する素養が無い者が行っているということを念頭に呼んでいただければ幸いです。
◆北朝鮮による拉致問題の認知・被害者取り戻し
「安倍政権」の功績ではありませんが、北朝鮮による拉致問題の認知・被害者取り戻しは、安倍晋三という政治家の存在抜きでは実現されなかっただろうと言えるほど、その貢献度は高いです。
産経新聞令和4年8月2日9面 日本性悪説と戦った安倍氏 西岡力
当時は拉致問題に関わるのは大きなタブーに挑戦することだった。
~省略~
タブーに負けず有本さんらの訴えを真面目に聴いてくれたのは安倍氏が秘書をしていた安倍晋太郎事務所だけだった。産経新聞以外のマスコミもこの重大な事件を疑わしいとしてほぼ無視していた。
~省略~
私は有本恵子さん拉致が表に出た平成3年、ある月刊誌に学者として初めて日本人が拉致されているという論文を書いた。そのとき政府関係者を含む専門家から「身の危険はないですか」と警告された。匿名の「殺す」という脅迫状も受け取った。
「拉致問題に関わるのは大きなタブーだった」
このことは2001年に増元照明 氏が当時の荒川区議斎藤裕子に宛てた手紙で、社民党の土井たかこ議員(当時)に拉致問題に協力をお願いするメールを出し、本人に直接会って返事をお願いしたが返事をもらえなかった、という事実などからもわかります。社民党は以下、反省の念を記しています。
北朝鮮・拉致事件について 社会民主党全国連合常任幹事会
党は、北朝鮮による拉致問題の真相解明のために、また真実の追及のために何をしてきたのかとの批判を受けてきた。しかし、1997年以後、社民党が参加した与党三党および全政党の国会議員による訪朝の場で強く質しても、「拉致の事実はない」と北朝鮮側は強く否定してきた。否定されてもなお、党が追及し続けたかという点は、率直に言って十分ではなかった。被害者ならびに被害者家族の皆さんには、たいへん申し訳なく、力不足を心より謝罪する。
平成9年(1997)には家族会=北朝鮮による拉致被害者家族連絡会が発足した直後に安倍氏は仲間を募って「北朝鮮拉致疑惑日本人救援議員連盟」(旧拉致議連)を立ち上げました。
その後の2002年10月、小泉純一郎政権下で官房副長官だった安倍氏が拉致被害者を北朝鮮の要求通り北朝鮮に出国させようとする外務省に反対して小泉総理に進言した結果、5人の被害者の帰国が実現しました。
2004年5月の日朝首脳会談後には蓮池氏・地村氏の子供が「帰国」、7月には曽我ひとみ氏の夫ジェンキンス氏とその子供が帰国しました。
小泉総理の判断力の結果・功績であることは間違いないのですが、安倍氏の貢献度は無視できません。

毎日新聞のコラムで元外務省の田中均氏が、安倍政権の外交政策について語っています。 このインタビューを読んで、私は11年前の官房副長官室での出来事を思い出しました。 拉致被害者5人を北朝鮮の要求通り返すのかどうか。 彼は被害者の皆さ...
Posted by 安倍 晋三 on Wednesday, June 12, 2013
その後、目立った進展が無いことはまことに残念ではありますが、日本政府として、安倍政権として何もしていなかったわけではありません。
とくに横田めぐみさんの遺骨がニセモノだと判明して以後は、死亡したという証拠を出しなさい、という交渉のしかたは、むしろ生存している被害者に危害が及ぶ危険性があると考えるようになった。いま、わが国が「『八人の被害者の生存』を前提として交渉する」という交渉姿勢を貫いているのは、そうした前提があるからである。
安倍晋三
認識誘導的な報道記事がたびたび出ていますが、注意すべきです。
※2023年7月7日追記:「救う会」=北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会の会長である西岡力 氏と産経の阿比留記者による「安倍晋三の歴史戦」においてこの辺りは詳しく書かれています。
第一次安倍政権時代の功績概要
第一次安倍政権時代の功績と言えるものを並べると
◆教育基本法改正
◆朝鮮総連の固定資産税免除減免措置の撤廃
◆拉致問題解決のための北朝鮮への短波放送開始
◆防衛省の設置(防衛庁からの格上げ)
◆海洋基本法成立
◆国家安全保障会議(日本版NSC)を創設
◆国民投票法成立施行
こういったものが思い浮かびます。
たった11カ月ですが、重要な項目が立ち並んでいます。
◆教育基本法の改正
教育基本法の全面改正についてはその理念的な記述について論じられることが多々ありました。
旧法前文一部抜粋
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
改正法 前文一部抜粋
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献すること
を願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
“教育の憲法”とも称されていた教育基本法は、占領中に成立した点や内容が「コスモポリタン的」等と批判されることがありましたが、安倍自身、旧法を評価していないわけではありませんでした。
第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第8号 平成18年6月2日
○安倍国務大臣 ~省略~ 現行の教育基本法、戦後の教育基本法の理念のもとで構築された教育諸制度は国民の教育水準を向上させ、我が国の社会発展の原動力となったのも事実であります。しかし、まさに戦後六十年を経て、制定から六十年を過ぎたわけでありまして、その中で、いろいろな社会情勢等々の大きな変化もある中において、我々は今回、この教育基本法を改正するという判断をしたわけであります。
この認識は「教育基本法改正法成立を受けての内閣総理大臣の談話」にも表れています。
それ以前の問題意識や安倍内閣で引き継がれた経緯については【残る学習指導要領の問題点と課題 追悼 安倍元首相 一般社団法人全国教育問題協議会】などが詳しい。
旧教育基本法は占領下で制定されたものゆえ、規程内容に直接間違ったことが規定されているわけではないが、日本の教育のためのものとしては、日本の伝統や文化を尊重し日本人として教育しなければならないという観点から見れば、それを明示する規定が表面上ないため、早くから批判にさらされていた。
改正反対派からは「愛国心の押し付けだ」のような反論が多く為されましたが、自虐史観が圧倒的であった当時の世相で教育基本法の理念部分の改正は非常に重要なものでした。
教育基本法改正についてはこうした理念的な主張の側面だけがクローズアップされることが多いですが、実務的な観点からも重要な条項があり(障碍者の教育の機会についての支援、国と地方公共団体の相互協力など)、決して抽象的な理念に拘泥したものではないということが言えます。以下、新設された条文のごく一部を引用します。
教育基本法5条 ~省略~
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
参考:教育基本法改正旺文社 教育情報センター 19 年 1 月
◆「在日特権」朝鮮総連の固定資産税免除減免措置の撤廃
あまり有名ではありませんが、安倍政権時代に朝鮮総連の固定資産税免除・減免措置の撤廃(=本来の法的要件判断を行うこと)に取り組んだということを菅義偉元総理が述懐しています。
厳密には菅義偉氏が総務副大臣・総務大臣時代の平成17年から平成19年の話なのですが、以下書かれています。
政治家の覚悟 文春新書 菅義偉
私が第三次小泉内閣において総務副大臣に就任した際には、懸案の朝鮮総連に対する固定資産税減免措置を見直す絶好の機会と考えていました。拉致問題で行動をともにしてきた安倍官房長官からもお墨付きをもらっていました。
◆北朝鮮への拉致被害者救出のための短波放送開始
北朝鮮への拉致被害者救出のための短波放送に関しても第一次安倍政権の功績は無視できません。
政治家の覚悟 文春新書 菅義偉
安倍内閣が発足して三日後、拉致問題対策本部の設置が閣議決定されました。
~省略~
拉致された可能性のある人たちの救出活動をしている特定失踪者問題調査会では、独自に短波放送をする「しおかぜ」を通じて、北朝鮮に向けてメッセージを流していました。国際放送をする周波数は、国際電気通信連合(ITU)から割り当てを受ける必要がありますが、当時の日本には残念なことに「しおかぜ」から放送するための電波がありませんでした。そのため、「しおかぜ」は英国のVTコミュニケーションズに委託して、香港や東南アジアから北朝鮮に向けて発信していました。
~省略~
こうして2007年3月、初めて日本国内(八俣送信所)から「しおかぜ」が、堂々と北朝鮮に向けて拉致被害者救出のための放送ができるようになったのです。
「しおかぜ」による国内からの短波放送が始まったのは第一次安倍政権発足後に拉致問題対策本部が設置されたことがきっかけというのが分かります。
政治家の覚悟 文春新書 菅義偉
日本から「しおかぜ」の放送をする方策に着手すると同時に、私はNHKの短波の国際放送から北朝鮮に向けて拉致問題を特に放送するように、総務大臣としてNHKに命令することを考えていました。
~省略~
官僚が指摘した通り、マスコミは報道への介入だとこぞって猛反対キャンペーンを組みました。
一方、官邸での拉致問題対策本部では、
「拉致問題は、わが国の国家主権と国民の生命・安全にかかわる重大な問題であるとの認識のもとで、政府一体となって全ての拉致被害者の生還を実現すべく、今後の対応方針を決定」
との方針も示されました。
中央公論令和4年9月号 菅義偉
官僚はマスコミの反応を気にして反対しましたし、私は「命令大臣」とも呼ばれました。だけど、安倍総理とはよく相談していましたし、わたくしのことを信頼して、いろんなことを任せてくれました
さらに、NHKから拉致問題を取り上げる番組を放送させる「命令放送」も実施されました。
※当時の放送法33条1項による。平成19年改正法によって「要請放送」となり(現行法65条)、以来、毎年度国際放送の実施を要請。
日弁連などが代替案を示さずに反対(改正後の声明を見ても個別具体的な事項に関する放送を繰り返させることが問題とする趣旨で、要請すら反対)していますが、そういう空気感をものともせずに実施したことの意義は大きいと言えます。他にどういう組織・団体がどういう主張をして反対していたのか、ネットで検索してみるといいでしょう。
◆防衛省の設置(防衛庁からの格上げ)
第一期安倍晋三総裁時代
これまで内閣府の外局として扱われてきた防衛庁を「省」に移行させるための防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の成立です。これにより、平成十九年一月九日、防衛庁設置法が防衛省設置法となり、防衛庁は昭和二十九年七月一日の発足以来、五十年余にして「防衛省」として新たなスタートを切りました。
それに伴って、防衛庁長官は「防衛大臣」となり、これまで在日米軍や自衛隊が使用する防衛施設の取得、建設、管理、その周辺対応を所管してきた防衛施設庁も統合・廃止されました。自衛隊法も改正され、自衛隊の国際平和協力活動が「付随的任務」から「本来任務」に格上げされました。
防衛省移行記念式典で安倍首相は「国防と安全保障の企画立案を担う政策官庁として位置付け、さらには、国防と国際社会の平和に取り組むわが国の姿勢を明確にすることができました。
防衛省の設置(防衛庁からの格上げ)については防衛庁設立時から議論がありましたが、具体的な検討項目として挙がってきたのは小泉政権時代の第164国会。ただし、改正法案は継続審議となりました。
その後、衆院選を経た第一次安倍政権時代の第165回国会において可決成立したという経緯になります。
小泉政権時代の流れを第一次安倍政権がしっかりと受け継いだと言えます。
◆海洋基本法成立
海洋白書2014 海 洋 政 策 研 究 財 団
「海洋の管理」原則のもとに、排他的経済水域(EEZ)制度や深海底制度、海洋環境の保護・保全の義務などをはじめ、およそ海洋法のすべての側面を規定する包括的な国連海洋法条約が1994年に発効したが、わが国のこれに対する対応は各国に比べて鈍かった。これを憂慮して、2002年に日本財団が「海洋と日本:21世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言」を世に問うたが、この時はまだ、「海洋政策?それは何ですか」という反応が一般的だった。しかし、海洋政策研究財団が、日本財団の提言を引き継いで発展させ、「21世紀の海洋政策への提言」を行った2005年になると、中国による東シナ海の石油・ガス田開発等が進んできたこともあってようやく世間の目が海洋に向いてきて、2006年にこの提言を受けて超党派の政治家・有識者による海洋基本法研究会が発足した。そして、海洋政策大綱および海洋基本法案の概要がとりまとめられ、これを基にして2007年に自民、公明、民主各党の議員が中心となって議員立法により海洋基本法が制定され、7月20日に施行された。
海洋基本法により、わが国の海洋政策の司令塔として内閣に総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部が設置され、2008年3月にはわが国初の海洋基本計画が閣議決定された。その下で、大陸棚限界委員会へのわが国の大陸棚の延長申請の提出、海賊処罰・対処法(注1)、低潮線保全法(注2)
等の海洋関係法律の制定などが行われ、わが国の海洋問題への取組みが動き出した。これらは、海洋基本法がなければこのようにスムーズに取り組むことが難しい問題ばかりであり、海洋基本法制定により、わが国の海洋に対する取組みが着実に進展してきたことは明らかであろう。
さらに言えば、海洋基本法制定により、海洋関係省庁が行っているさまざまな海洋に関する施策が海洋基本計画および総合海洋政策本部の傘の下に置かれ、海洋政策が内容、手続きの両面から総合的・計画的に推進される仕組みができ、ここに初めて相互に密接な関連を有する海洋の諸問題にわが国が適切に対応していく道が開けたのである。
その効果の一例を挙げれば、ソマリア沖等で猖獗を極める海賊に対処するための2009年の「海賊処罰・対処法」の制定である。海賊の問題は、海洋基本法が定める基本的施策の「海上の安全の確保」「海上輸送の確保」「国際的な連携の確保及び国際協力の推進」などに関係し、省庁も国土交通省・海上保安庁、外務省、防衛省、法務省など多くの省庁が関係している。海洋基本法の下で内閣に総合海洋政策本部が設置され、この問題に強力なリーダーシップを発揮して対応する仕組みが整備されていなければ、同法の成立は難しかったと思われる。
これを「安倍政権の功績」と呼んでよいのかはわかりませんが、事実経過からして安倍晋三氏の存在は無視できないでしょう。
笹川平和財団 海洋基本法の制定とその意義慶應義塾大学名誉教授、海洋基本法研究会共同座長◆栗林忠男
2006年2月に「日本財団」会長等から安倍内閣官房長官(当時)に提出され、政党によって受け止められるよう要望したことが直接のきっかけとなった。政界でも海洋政策に関する議論と関心が高まっていた状況があり、4月に自民・公明・民主各党による超党派の「海洋基本法研究会」(石破茂座長)が設置されることになった。研究会は、国会議員有志のほか学識経験者、産業界代表に加えてオブザーバーとして参加した関連官庁10省庁の局長・課長など、わが国の多数の海洋関係者を交えて10回の会合を重ね、2006年12月の最終会合において「海洋政策大綱」と「海洋基本法案の概要」につき合意を見た。通常の議員立法の場合とは異なり、準備段階において、政治家とともに広く官・産・学を巻き込んだ多数の海洋関係者の見解や取り組みの現状を検討し、その成果を国会議員による立法作業に繋げるという極めてユニークな過程であったといえる。
◆国家安全保障会議(日本版NSC)を創設
国家安全保障会議(日本版NSC)を創設したのも安倍政権下であり、安倍氏の主導によって行われました。
産経新聞令和4年7月15日 1面 日本の安保、根本から変えた エドワード・ルトワック
安倍氏は、日本の安全保障戦略や戦略策定の仕組みを根本から変えた。
以前であれば、例えば日米関係では外務省は国務省、防衛省は国防総省、海上自衛隊なら米海軍も個別に話し合って政策を調整して、日本側は省庁間で連携しなかった。それぞれが事実上の米国の出先機関と化し、日本国として複数の指があっても、一つの手として自律的に動くことのできない状態だったのだ。
特に外務省と国務省との間では、ライシャワー元駐日米大使(在任1961〜66年)にちなみ「ライシャワー・ライン」と呼ばれる人脈があり、日本の軽武装、専守防衛、自衛隊の海外派遣禁止にこだわり続けた。
安倍氏の下では、外交官と自衛隊関係者が意見を交わし、日本が自らの手で外交・安保政策を作り上げる体制ができた。安倍氏は、日本外交が独立性を増し、適切な責任を負うことで、日本が米国のより良き同盟国になることができると確信していたのだ。
その意味で、国家安全保障局の設立は、安倍氏の指導力なしでは実現し得なかった、外交・安保分野での最大の遺産といえる。
なお、2019年10月には経済班設置準備室が用意され、翌年4月に発足しています。
前国家安全保障局長の北村滋 氏が民主党政権期に厳しさを増した安全保障環境、中国・北朝鮮・ロシアの軍事プレゼンスの強化を踏まえて以下述懐しています。
これだけの脅威に囲まれた日本を守るには二つのことが重要です。
一つは、相手国に軍事行動を思いとどまらせるための抑止力の強化。二つ目は、相手国との緊張が高まらない環境を作り、関係を安定させる外交です。抑止力があるからこそ、外交もうまくいく。安倍総理はそのことをよくご存知でした。第2次安倍内閣の発足後から、この二つを官邸手動で取り仕切る司令塔・国家安全保障会議(NSC)の創設に取り組まれたのは、こういう背景があります。
前国家安全保障局長 北村滋
話の内容が前後しますが、以下で述べる第二次安倍政権時の評価とは切っても切れない内容を北村氏が話しているのでこの段階で紹介します。
21年1月、オブライエン補佐官が開示した「米国インド太平洋戦略構想」(United States Strategic Framework for the Indo-Pacific) の前文には、「この4年間の日米同盟の成長は、この地域における戦略的アプローチの整合性を高めたという意味で特筆すべきものである。トランプ大統領は、日本が最初に提唱した『自由で開かれたインド太平洋』というコンセプトの戦略性に強く共鳴した」との記述が見えます。
~省略~
外交安全保障の基盤になるのは、情報収集・分析(インテリジェンス)です。自国で情報を集めるだけでなく、同盟国や同志国と情報をやりとりすることも重要です。他国とやりとりした機密情報の保全を強化する特定秘密保護法を13年に成立させました。日本が漏えい防止を徹底したことで、やりとりは質量ともに格段に向上しました。
~省略~
今でこそ、広く知られるようになっている経済安全保障の重要性に気づいたのも、安倍総理でした。安全保障というと軍事をイメージしがちですが、人工知能(AI)や量子技術など軍事転用可能な先端技術が民間で育っている今日、そういった技術が他国に奪われないようにすることが大切です。そのために企業や大学、研究者を守るのが経済安全保障という考え方です。
~省略~
官邸で安倍総理に「これから経済班を設置します」と説明したところ、総理は「遅かったぐらいだ」と仰ってました。そういう問題意識をかねてお持ちだったということです。
前国家安全保障局長 北村滋
「前文」に書かれている内容の原文は以下。
This growing alignment of strategic approaches in the region is perhaps nowheremore noteworthy than in the growth of the U.S.-Japan alliance during the last four years.
本体については複数媒体で確認可能。
A statement on the recently declassified 🇺🇸 Strategic Framework for the #IndoPacific from National Security Advisor Robert C. O’Brien.
— U.S. Embassy Australia (@USEmbAustralia) January 13, 2021
Read the full declassified document here: https://t.co/gFw5Ny4xJJ pic.twitter.com/cvu5KjqlNK
◆国民投票法成立施行
日本国憲法第96条第1項では憲法改正の要件が定められていますが、その具体的な手続については国会法68条の2〜6で国会による改正の発議の方法が定められている以外には規定がありませんでした。
特に憲法改正発議後の国民投票に関しては具体的な手続を規定したものが何も存在してませんでした。
そこで成立したのが【日本国憲法の改正手続に関する法律 平成19年法律第51号】であり、本法が成立・施行することで憲法改正の道筋が付けられたことになります。
これ自体が国家運営を前進させた明確な事例であると言えます。
潰瘍性大腸炎の症状悪化による辞任、自民党の下野、そして再挑戦
その後の平成19年(2007年)9月12日、安倍氏は持病である潰瘍性大腸炎の症状悪化によって総理大臣辞任を余儀なくされ、9月25日に内閣総辞職。
安倍氏は麻生政権下の自民党の衆院選大敗を経験、民主党への政権交代に伴い下野するも、その後、新薬による寛解を経て自民党総裁に返り咲き、2012年12月に第二次安倍政権を発足させます。
この間発生した東日本大震災からの復興支援に対する安倍氏の取り組みについては第二次政権時代の行動と合わせて紹介することとします。
第二次安倍政権時代の功績概要
第二次政権時代の功績・政策実行の前提となる動きについては以下。
◆米国上院下院演説・オバマ大統領の広島訪問等、日米関係の醸成
◆河野談話以来の慰安婦問題に対する対外発信の軌道変更
◆FOIP=自由で開かれたインド太平洋構想の提唱(戦略)
◆QUADの構築
◆集団的自衛権の行使容認
◆特定秘密保護法成立・施行
◆テロ等準備罪成立・施行
◆TPP締結、CPTPP発効
◆経済政策=アベノミクス(第一の矢=金融政策を起点)
◆東日本大震災の復興への取り組み
◆新型コロナへの初期対応確立
ここで論じ切るにはあまりに重要かつ膨大な項目ですが、一つ一つ見ていきます。
◆米国上院下院演説・オバマ大統領の広島訪問等、日米関係の醸成
この話は現在の日米関係や日本国の先の大戦に関する認識に対する欧米諸国による評価・信頼関係に関連し、FOIPやQUADが受け入れられた土壌の一つとして論じられることも多いので最初に指摘します。
米国連邦議会上下両院合同会議における安倍総理大臣演説 平成27年4月30日
これは画期的な出来事であり、「英語演説で世界を沸かせた総理大臣は伊藤博文と安倍晋三だけ」と評されることもある異例の演説でした。
この演説単体での効果とは到底言えないでしょうけれども、日米関係の改善・進化にとって明らかに一つの象徴的な出来事でした。
その後、オバマ大統領(当時)が米国大統領として初めて広島市を訪問し…
外務省 オバマ米国大統領の広島訪問(概要と評価) 平成28年5月27日
次いで、安倍総理がハワイの真珠湾を訪問し、各種演説・ステートメントの発表が行われました。
こうした動きの積み重ねによって、日米関係や日本の国際関係が次のステージに進む礎となっていったと言えるでしょう。
同様に戦後70年談話によっても国際社会の信頼獲得の成果があったとする指摘もあります。
アメリカの老舗シンクタンクCFRではSheila A. Smithが「おそらくもっと注目に値するのは、トランプ政権への移行をナビゲートする安倍の能力だった」と評しており、米国民主党の大統領から共和党の大統領に変化するなかでもアジアの地政学について助言することを優先したことを指摘しています。
◆河野談話以来の慰安婦問題に対する対外発信の軌道変更
欧米諸国による信頼関係に関連するものとして無視できないのが慰安婦問題についての日本政府の姿勢の変更です。
産経新聞令和4年8月2日9面 日本性悪説と戦った安倍氏 西岡力(再掲)
当時、政治家が慰安婦問題について議論すること自体、大きなタブーだった。言論界では悲惨な体験を強いられた韓国女性の人権を侵害する「歴史修正主義者」「極右政治家」というレッテル貼りが横行していた。しかし、安倍氏らは慰安婦「性奴隷」派の意見も聞きながら事実は何かを明らかにしていった。
~省略~
平成24年12月、第二次安倍政権発足直前の党首討論会で安倍氏は朝日新聞記者の質問に「慰安婦問題は、あなたの朝日新聞が吉田清治という詐欺師の話を事実みたいに広めたからでしょう」と明言した。
平成28年1月には、前年12月の日韓慰安婦合意に関する国会答弁で「(慰安婦問題について)海外のプレスを含め、正しくない事実による誹謗中傷があるのは事実でございます。性奴隷あるいは20万人といった事実は無い。…政府としてはそれは事実ではないということはしっかりと示していきたいと思います」と歴史的答弁をした。
~省略~
政治家が慰安婦問題について議論すること自体、大きなタブーだった。
これは論を待たないでしょう。閣議決定ではない河野談話と記者会見の席上での河野洋平議員の発言が朝鮮半島にとって都合の良い形で伝播していき、小中高の教科書では「日本軍による強制連行」があったかのような記述がありました。
このような論調に迎合した学校教育や報道が「自虐史観」を生み、たとえば旧統一教会=家庭連合による贖罪意識への付け込みが行われる素地となる世論が形成されていたことは、ほとんどメディアに現れることはないが公然の事実でしょう。
第二次安倍政権発足直前の党首討論会は複数回行われていますが、同様の趣旨の発言は報道もされていました。
論説委員・石川水穂 問題談話の総点検が必要だ 2012.12.8 03:16 産経新聞
安倍氏は「朝日新聞の誤報による吉田清治という詐欺師のような男が書いた本がまるで事実かのように日本中に伝わった。人さらいのように(慰安婦を)連れてきたという事実は証明されていない。このことは閣議決定されている」とも指摘した。
これは11月30日の11党での党首討論会中の発言にみられます。
慰安婦問題・河野談話については10分35秒あたりから。
この発言の2年後、朝日新聞が吉田清治の証言記事の撤回を発表し、謝罪。
慰安婦問題の簡易的な年表は以下。
◆1983年~慰安婦問題:吉田清治証言という嘘を発端に1993年、金学順(キム・ハクスン)が女子挺身隊として強制連行されたと事実誤認の主張で慰安婦問題が加速
⇒2014年12月、朝日新聞が吉田証言記事の撤回を発表・謝罪
※ただし英語媒体では不審な動きが継続している
⇒2020年前後、金学順証言を報じた朝日新聞記事を書いた植村隆の記事に事実誤認があると裁判所も認定、2021年には最高裁で植村の「捏造」認定が確定
◆1993年:慰安婦問題に関する河野談話。日韓政府の合意のもと、道徳的責任の趣旨で慰安婦慰労金資金を拠出。「女性のためのアジア平和国民基金」を作り慰労金事業。しかし、韓国挺対協の反対で元慰安婦の基金受領を妨害。2002年、韓国内での慰労金支給を終結。
◆2015年慰安婦合意:安倍政権がアメリカを証人として「最終的且つ不可逆的に解決」
⇒日本が「和解・癒やし財団」に10億円を拠出するも韓国は日本との協議なしに解散を表明。韓国側の不履行状態
安倍政権下では議員の中でも河野談話以来の政府の姿勢を問いただす者が多く出て来るようになります。
そして、平成27年8月14日の戦後70年安倍談話が出されることとなります。
日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。しかし、それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合わなければなりません。謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります。
平成31年4月には外務省でも「性奴隷は事実に反する」など対外的な発信の仕方も大きく変わりました。
現時点でも、欧米における戦前の日本に対するナラティブが合理的なものとなるように払しょくされたと言えるか疑問ですが、現在はアメリカ人によって学術的な観点からも再検証が為されているなど、明らかに国際世論に変化が生じました。
◆FOIP=自由で開かれたインド太平洋構想(戦略)の提唱と浸透
FOIP=Free and Open Indo-Pacific=開かれたインド太平洋構想(当初は「戦略」)とそれに基づく国際協調の枠組み構築は、第二次安倍政権の功績として最も重要なものであり、日本国の歴史的に見ても戦略の転換を導いた大業として国内外から評価が高いものです。
FOIPはTICAD VI開会に当たって・安倍晋三日本国総理大臣基調演説(2016年8月27日(土曜日))(ケニア・ナイロビ,ケニヤッタ国際会議場)で示された日本政府の外交方針です。安倍氏は小泉政権時代からこの発想を持っていたようです。
もっとも、日本の大衆向けメディアでこの点がクローズアップされることは少なく、むしろ海外メディアにおいて率直な評価をしているものが見られます。
Statecraft was Abe’s natural instinct. He was miles ahead of his peers not just in the domestic political space but also fellow global leaders when he captured international imagination with strategic constructs like the Free and Open Indo-Pacific, which reverberates in today’s strategic lexicon. Likewise, it was Abe’s strategic foresight that put a premium on weaving a democratic “diamond,” which subsequently matured as the Quad, a formidable force amid the China-U.S. tensions. He crafted a grand strategy anchored on universal values of democracy, human rights, and rule of law.
国政術は安倍首相の天分であった。彼は、今日において響き渡る戦略用語である「自由で開かれたインド太平洋」のような戦略的構想で国際的な関心を集めたとき、国内の政治空間だけでなく、世界の指導者たちのはるか先を行っていたのである。同様に、安倍首相の戦略的先見性によって、民主的な「ダイヤモンド」の形成が重視され、その後、中米の緊張の中で強力な効果を発揮している「クアッド」として成熟していった。彼は、民主主義、人権、法の支配という普遍的な価値に根ざした大戦略を作り上げたのである。
FOIPの「最重要の当事国」と言えるインドのモディ首相からは「我が友、安倍さん」と題する以下等に採録されている追悼文が出されました。
Among his greatest gifts to us and his most enduring legacy, and one for which the world will always be indebted, is his foresight in recognizing the changing tides and gathering storm of our time and his leadership in responding to it. Long before others, he, in his seminal speech to the Indian parliament in 2007, laid the ground for the emergence of the Indo-Pacific region as a contemporary political, strategic and economic reality — a region that will also shape the world in this century.
私たちへの最大の贈り物であり、最も永続的な遺産であり、世界が常に恩恵にあずかっているのは、現代の潮流の変化と嵐の到来を認識した彼の先見性と、それに対応するリーダーシップであろう。2007年のインド議会での演説で、インド太平洋地域が現代の政治的、戦略的、経済的な現実 — 今世紀の世界を形成する地域 — として出現するための基盤を、他の人よりも遥か前に築いたのである。
And, he led from the front in building a framework and architecture for its stable and secure, peaceful and prosperous future, based on values that he deeply cherished — respect for sovereignty and territorial integrity, adherence to international law and rules, peaceful conduct of international relations in a spirit of equality and shared prosperity through deeper economic engagement.
そして、主権と領土の尊重、国際法・ルールの遵守、平等の精神に基づく国際関係の平和的な運営、より深い経済的関与による繁栄の共有など、彼が深く大切にしてきた価値観に基づいて、その安定と安全、平和と繁栄の未来のための枠組みとアーキテクチャの構築を正面から主導してきました。
“The Quad,” the ASEAN-led forums, the Indo-Pacific Oceans Initiative, the India-Japan Development Cooperation in the Indo-Pacific, including Africa and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, all benefited from his contributions. Quietly and without fanfare, and overcoming hesitation at home and skepticism abroad, he transformed Japan’s strategic engagement, including in defense, connectivity, infrastructure and sustainability, across the Indo-Pacific region. For that, the region is more optimistic about its destiny and the world more confident about its future.
「クアッド」、ASEAN主導フォーラム、インド太平洋イニシアティブ、アフリカを含むインド太平洋地域での日印開発協力、災害に強靭なインフラ整備の提携など、すべて彼の貢献によるものである。ファンファーレもなく静かに、国内での躊躇いや海外からの懐疑的な見方を乗り越え、彼はインド太平洋地域全体で防衛、接続性、インフラ、持続可能性を含む日本の戦略的関与を変革していった。そのおかげで、この地域はその運命に対してより楽観的になり、世界はその未来に対してより自信を持つことができるようになったのです。
産経新聞令和4年7月21日7面ではインド全土で異例の追悼が行われたことを受けて、森浩氏によってインドに対する安倍政権下の関わりが紹介されていました。
・新幹線方式の高速鉄道のインド導入
・インドへの原発輸出を可能にする原子力協定を締結
・外務防衛閣僚協議2+2を初開催
・航空自衛隊とインド空軍の戦闘機訓練で合意
・インド政府は21年、民間人に贈られる勲章で2番目に高位のパドマ・ビブシャン章を安倍氏に授与
さて、FOIPは安倍政権の国家戦略・外交戦略の根幹だったわけですが、外交戦略全体について慶応義塾大学の国際政治学者である細谷雄一教授が以下指摘しています。
アメリカのオバマ元大統領、トランプ前大統領、ロシアのプーチン大統領、インドのモディ首相、EU(欧州連合)のドナルド・トゥスク前欧州理事会常任議長など、政治体制も異なるさまざまな国や主要機関の指導者たちから安倍は信頼され、また友好関係を築いてきた。それは、首相として安倍が「国際協調主義に基づく積極的平和主義」を掲げて世界中の指導者たちと交流し、さまざまな国際協調枠組みのイニシアティブを発揮したこととも関連している。
~省略~
外交政策、安全保障政策、経済政策において安倍が進めた改革は「漸進的な革命」と呼べるものであって、従来の政策を根底から転換するようなものではなかった
~省略~
最も論争的であった集団的自衛権の行使容認についても、それは従来の内閣法制局の解釈を根底から覆すものではなく、「接ぎ木」をするように、それまでの方針を柔軟に時代に合わせて適応される解釈変更であった。
日本の主要メディアが「アベによる民主主義の破壊」などと言ってる傍から、以下の事実を提示しています。
むしろ、世界中で「民主主義の後退」が懸念され、ポピュリスト的な扇動的指導者や、権威主義的な指導者が溢れるなかで、国際的には安倍は、民主主義を擁護するリーダーと認識されてきた。
上掲のディプロマットやモディ首相の文章に現れた安倍氏の認識と一致しているのが分かります。
われわれは「吉田ドクトリン」に未練を抱き、その限定的な国際的責任という快適な場所に安住するのではなく、より厳しい世界の現実に直面する勇気を持たなければならない。おそらくはそれこそが、「安倍ドクトリン」としてわれわれが向き合うべき新しい外交路線であり、また安倍が強く希求していたものであったのではないか。
細谷教授は産経新聞でも以下指摘しており、端的な表現が分かりやすいためあわせて引用します。
国際政治学者として評価するなら、安倍氏の最大の功績は、日本の外交・安全保障政策を前後の「吉田路線」から「安倍路線」に転換させたことだ。
~省略~
安倍氏は「積極的平和主義」を掲げ、日本の主体性を回復し、国際社会で指導力を発揮した。その外交は明治以降で最も創造的といえる。
~省略~
第2次安倍政権の当初、中国の巨大経済構造「一帯一路」がほぼ唯一のアジア秩序構想で、多くの欧州・アジア諸国はこれに追従した。オバマ米政権も指導力を発揮できないでいた。だが、安倍氏は「インド太平洋」という新たな地域概念を創出し、日米に加え、民主主義国がアジアの地域秩序形成の中核を担うべきだと考えた。中国主導の潮流は一変した。
細谷教授は、それが可能となったのは「集団的自衛権の解釈変更」や「歴史認識70年談話」での国際社会の信頼獲得があったとみており、トランプ前大統領が2017年秋の訪日時に「安倍氏の力強いリーダーシップを支える」と言ったことを受けて「対米追従の関係を逆転させた」と評しています。
安倍氏が世界的な評価を得たのは、海外のメディアや世論に浸透するようなメッセージを発信してきたからでもある。戦略的なスピーチを自らの政治主導で、英語で作成した。だから相手に言葉が届く。安倍氏は海外メディアとのインタビューにも積極的に応じた。
海外からも同様の認識で語られている例としてクリストファー・ジョンストン氏へのインタビュー記事があります。
死去した安倍晋三元首相とオバマ元米大統領による被爆地・広島、米ハワイ・真珠湾の訪問は「過去を乗り越えよう」という安倍氏の構想と指導力により実現し、日本がインド太平洋で指導的地位を築く転機になったと語った。
~省略~
安倍氏が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」構想がトランプ政権下で取り入れられたのは、「米国がやろうとしていた自由と開放性の促進を簡潔に言い表してると感じた」ためとの見解を示した
~省略~
安倍氏が提案した日米豪印4ヶ国の「クアッド」については、バイデン政権が首脳間対話の枠組みに発展させたとし、「安倍氏からトランプ氏、バイデン氏へと1本の線のように継承された」と語った
岸田総理による故安倍元総理の功績についての言及でもFOIPが言及されたように、安倍政権の最も重要な政策であり、成果を生んだものだったと言えます。
FOIPに関する説明、経緯、その後の展開については調べればたくさん見つかりますが、一つの参考として以下を置いておきます。
他にも2013年7月にフィリピンやマレーシアを訪問しましたが、これらの国に総理大臣が訪問したのは第一次安倍政権時の2007年以来だったことについて安倍氏は危機感を持っていました。その後、ASEAN加盟諸国すべてに訪問しました。この意識は菅義偉政権にも受け継がれ、菅総理の最初の訪問先はベトナムとインドネシアでした。
◆セキュリティダイヤモンド構想からQUADへ
第二次安倍政権発足直後の平成24年(2012年)12月27日、"Asia's Democratic Security Diamond"=「アジアの民主主義セキュリティダイアモンド」と題する英語論文がプロジェクトシンジケート上で掲載されました。
オーストラリア、インド、アメリカ合衆国(ハワイ)と日本を四角形に結び、4つの海洋民主主義国家の間でインド洋と太平洋における貿易ルートと法の支配を守るために提唱されたものです。
その後、日米豪印戦略対話、または4か国戦略対話=Quadrilateral Security Dialogue=QUADとして捉えなおされ、インド太平洋構想の中核を形成しています。
QUADについてはFOIPに触れながら他の戦略・外交方針と並べて言及されることが多いですが、以下を挙げておきます。
https://www.hudson.org/research/18110-three-legacies-left-by-former-pm-abe-what-comes-next
ハドソン研究所の長尾賢 氏は、安倍首相が「強いインドは日本の最善の利益であり、強い日本はインドの最善の利益である」と宣言し、「強い日本」を作るために自衛隊の多くのメンバーを含む国家安全保障局(NSC)を設立したことや防衛省改革をして自衛隊の社会的地位を高めたと指摘。それとともに台湾の支援に力を注ぎ、安倍氏の2022年4月の論文「台湾をめぐる米国の戦略的曖昧さは終わらなければならない」では、台湾に対する明確な支持を主張したことを挙げ、そのビジョンと実践の遺産があると評しています。
This is why Abe was such an essential and valuable leader. His visions, like the Indo-Pacific, the QUAD, a strong Japan, and the support of Taiwan, have become ingrained in Japanese policy. The Indo-Pacific and QUAD concepts are now core parts of US strategy. Japan’s current prime minister, Fumio Kishida, will increase the defense budget and military capabilities over the next five years. He also seeks to amend the constitution to elevate the social status of the SDF further. There is strong support for Taiwan among the Japanese public. For example, when China banned pineapple imports from Taiwan, many Japanese tried to buy them. The visions Abe put into practice will survive.
これが、安倍が非常に重要で価値のあるリーダーであった理由だ。インド太平洋、QUAD、強い日本、台湾の支援などの彼のビジョンは、日本の政策に根付いている。インド太平洋とQUADの構想は、今や米国の戦略の中核をなしている。日本の現首相である岸田文雄は、今後5年間で防衛予算と軍事力を増強する予定だ。また、憲法を改正して自衛隊の社会的地位をさらに高めようとしている。日本社会には、台湾に対する強い支持がある。例えば、中国が台湾からのパイナップルの輸入を禁止したとき、多くの日本人がそれを買おうとした。安倍首相が実践したビジョンは生き残るだろう。
Satoru Nagao
安倍氏が総理退任後も一議員として台湾との協力関係を進展させようとしていたことは台湾パイナップルの件などからもうかがい知れるところです。
是非とも #台湾パイナップル をご堪能ください!五個で足りなければ、気軽にお知らせください。いつでもお送りします! https://t.co/GvSPkPubPY
— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 28, 2021
「安倍氏は中国からの脅威に対抗するために日本の台湾との関係を変えた」とする見方もあります。
なお、オーストラリアからはQUADが評価されて勲章が授与されています。
安倍総理はトニー・アボット元豪州首相について、総理大臣就任後の靖国神社参拝直後に面会して「日本はいわれなき非難を受けている」と声をかけられ、それ以来連携が進み現在のクアッドに繋がったことを伺わせる話をしていました。
◆集団的自衛権の行使容認する政府見解変更の閣議決定
集団的自衛権の行使容認する政府見解変更の閣議決定とは以下のことです。
国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について 平成26年7月1日 国家安全保障会議決定 閣議決定
我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態におい
ても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈
のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いか
なる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整
合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における
憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを
守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
政府見解上の表現としては「従来の政府見解の基本的な論理(閣議決定中でも明示されている)に基づく自衛のための措置」の見解変更であり、この基本的な論理について解釈を変えたわけではない、という立場です。
【問4】 解釈改憲は立憲主義の否定ではないのか?
【答】 今回の閣議決定は、合理的な解釈の限界をこえるいわゆる解釈改憲ではありません。これまでの政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果であり、立憲主義に反するものではありません。

外交防衛委員会調査室 沓脱 和人https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2015pdf/20151214031.pdf
それに合わせ、平成27年9月19日に成立した自衛隊の防衛出動に関する自衛隊法76条1項の改正を含む平和安全法制の整備が行われました。ここの細かい話は割愛します。
この法律案の審議の時期である2015年8月に大学教授が「もちろん暴力を使うわけにはいきませんが、安倍に言いたい。お前は人間じゃない!叩き斬ってやる!民主主義の仕組みを使って、叩き斬りましょう!」などと人格否定までして反対論を展開していたことはあまりにも有名です。
自衛の措置としての武力の行使の新三要件として
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
これらを挙げています。
もっとも、日本政府は国際法上の集団的自衛権をフルスペックで行使することは憲法が認めていないという立場であり、「密接な関係にある他国」や「存立危機事態」などの要件があることで、国際法上、主権国家に認められている集団的自衛権の行使要件よりも厳格なものになっています。
国際法上の集団的自衛権の行使要件には援助要請要件がありますが、これは自衛隊法88条2項に読み込まれて要求されるというのが政府見解です。
ただ、細谷教授も指摘するように安倍政権による解釈は「漸進的な革命」なんでしょう。一歩ずつ先に進むための橋頭保と捉えれば良いのではないでしょうか。
憲法改正すればこの範囲が広がるのかどうかは改正の仕方次第であり、きちんと意思を示すべきでしょう。

今思えば、新型コロナ禍が無ければ、持病の悪化が無ければ、東京五輪が開催される2020年に改憲発議が為されていたのかもしれない…と思わざるを得ません。
第一次安倍政権で国民投票法を成立させたことで憲法改正の道筋をつけたのですが、少なくとも自衛隊の法的正当性の論争を終わらせようという安倍氏の発言の趣旨に適う改正については、他国メディアも賛意を示すまでになっています。
The United States and other democracies should support the legitimation of a democratic Japan’s military capability. To be sure, many in Japan, mindful of militarism’s awful legacy, still recoil from the idea. South Koreans and Chinese have their own bitter memories of Japanese occupation. And no doubt support for an amendment is strongest in Japanese conservative nationalist circles, which Mr. Abe long represented.
Nevertheless, the proposed amendment would only legalize what is already reality — Japan has land, sea and air forces.
ワシントンポストが「米国や他の民主主義国は日本の軍事力の正当性を支持すべきであり、憲法改正案は既に現存する陸海空軍を合法化するだけだ」、という主張をし、日本国の憲法改正を支持するような論調を繰り出すまでになったのは衝撃的です。
◆特定秘密保護法成立・施行
【特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)】は、外交秘密・防衛秘密・テロ防止・スパイ(特定有害活動)防止の4分野について秘密情報を指定して情報管理を厳格化するための法制度。
これ以前からも国家公務員法などによる秘密情報という扱いはあったものの、扱いの厳格さはバラバラでした。
そこで、「秘密」の中でも「特定秘密」という扱いのものを設定し、適性評価をクリアした者のみが特定秘密の取扱いの業務を行うなどし、情報漏洩した公務員や一定の要件のもとで取得・知得した者へ刑事罰を設定するなど扱いを統一したものです。したがって、従来の「秘密」の範囲を拡大するものではありませんでした。
国内政策において政権に返り咲いた安倍総理にとって最初の試練でした。
◆安全保障環境が変化
⇒的確に情報収集、収集した情報を基に迅速・適切な判断を行うことが重要
⇒関係国からこれまで以上に質の高い情報を得ることが前提
⇒我が国の情報保全体制が関係国から信頼され、機微な情報の提供を受けられるようにし、情報交換の促進を図る必要
⇒また、国家安全保障会議(NSC)の審議をより効果的・効率的に行う必要
⇒秘密保護の共通ルールを整備し、安全保障上の秘密情報を統一的に取り扱うためのスキームを確立
⇒行政機関における秘密の取扱いに客観性と透明性が高まる
安倍氏の本法に関連する問題意識について、この動画で平将明議員の質問に答える形で語られています。
「日本は戦争をやめろ」「戦争が始まったら、女性の人権が破壊される」「映画が作れなくなる」「小説が書けなくなる」などと荒唐無稽な反対運動があったことなど動画内でも振り返られています。
◆テロ等準備罪成立・施行
特定秘密保護法が秘密情報全般の交換に関するものに対して、テロ等準備罪は犯罪者情報の交換に関するものと言え、TOC条約を締結するため、テロを含む組織犯罪を未然に防ぐために設けられたものです。
この話の対象となる法律案の正式名称は【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案】です。平成29年6月15日に成立しました。元の法律は【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)】
①組織的犯罪集団の団体の活動として、②特定の犯罪類型について、③二人以上での計画をし、④準備行為をした者、を処罰する内容です。
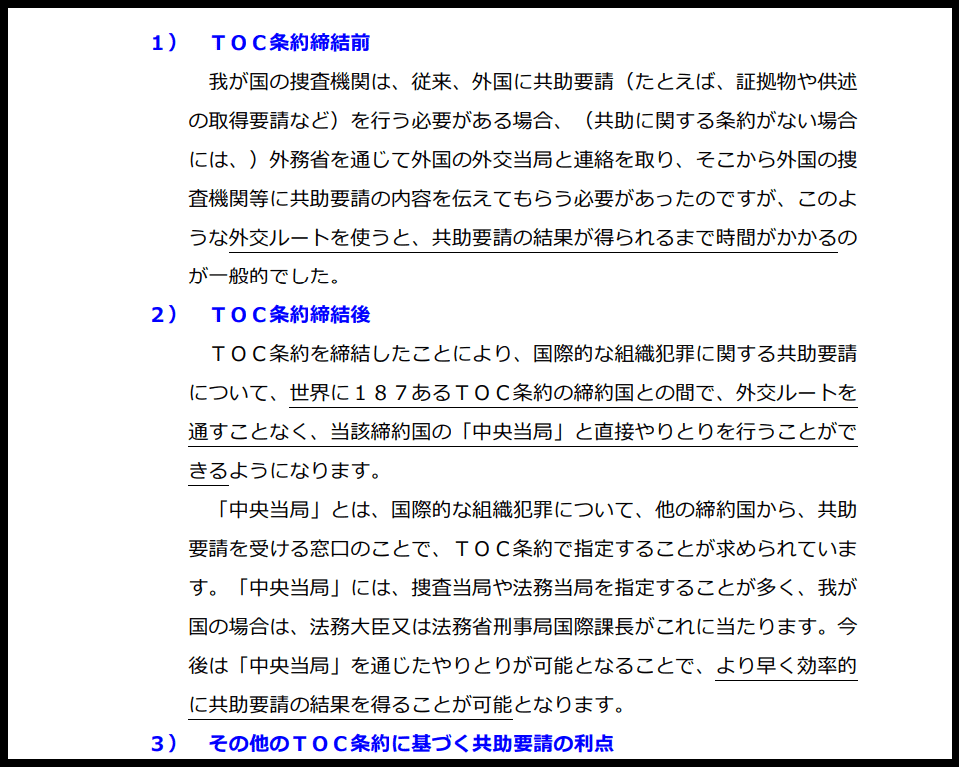
国家機関の情報共有ルートが短縮されたという効果があります。
テロ等準備罪成立によってTOC条約締結がされ、締結によって海外の犯罪者情報が簡単に手に入るようになった(検察官より)
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) December 2, 2017
具体例:❶日本の検察⇒法務省⇒外務省⇒❷外国の外務省⇒法務省⇒検察
締結前はこのやり取りがあったが現在は検察同士のやり取りで可能に。
これを妨害するのは犯罪的ですね。 https://t.co/NNhtuAX5KA
2017年当時、「共謀罪法に反対!」などとマスメディアでも日弁連でも盛んに叫ばれましたが(成立後も)、「準備行為」が求められる本法に対しては事実誤認もいいところでした。もともと刑法の適用時に「共謀」が認定されていたわけで(共謀しただけの者を処罰するには実行犯の実行行為の開始が必要)、共謀が存在した時点で犯罪が成立する他国の法制度との違いは明らかだったにもかかわらず。

「居酒屋で上司を殴りたいと会話しただけで逮捕?」などという、法律案の名称すら見ていない者の妄想をメディアが大真面目に取り上げていた始末。ワイドショーでも言いたい放題でした。
当時のメディアの認識誘導の手法は以下でまとめています。
◆TPP(環太平洋パートナーシップ)締結とTPP11(CPTPP)へ
元々は2006年に発行されたシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4か国EPA(P4協定)の拡大から始まりました。
日本のTPP締結には国内からも「対米追従!TPPで亡国!」などと言われることがありましたが(いわゆる右派も悪性評判をしていた)、平成25年3月15日安倍内閣総理大臣記者会見において交渉参加することを決定したことを表明し、甘利明議員の尽力もあり実現されました。
2016年に12カ国が参加するようになりましたが、2017年にアメリカが離脱した後にTPPの一部の規定の発効を停止した上で新たな貿易協定を交渉し再開された多国間経済連携協定がCPTTP(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定)=TPP11と言われます。
そしてもう一つの見落とされがちな、そして大きな意思決定がTPP(環太平洋パートナーシップ協定)であろう。トランプ大統領による米国の離脱をうけて、その成立が危ぶまれたTPPを18年の発効にまでこぎつけたことは、安倍氏の外交的なリーダーシップを示している。また、米国抜きであってもその成立を急いだ先見の明に驚かされる。
ロシアのウクライナ侵略以降、にわかに注目されることになった経済安全保障の確立において、中国に対抗する国際的な経済連携の強化の重要性は、あえて強調する必要はないだろう。ウクライナ戦争によって世界的な要請が高まる西側先進国の経済連携にとって、TPPはそのベースを提供することになる。今後はいかなる形で米国をTPPに(実質的に)復帰させるかが重要だろう。
「経済安全保障の確立」は、国家安全保障会議(NSC)の経済班設立の際にも意識されていました。
ただし、それは「日本国を守る」という観点だけにとどまるものではありません。CSISのマシュー・P・グッドマンは、その世界経済における役割について、より広く安倍氏の遺産であるとして紹介しています。
最初に、安倍首相は就任から 2 か月足らずの 2013 年 2 月にワシントンを訪れ、 CSISで「日本は帰ってきた」と宣言した印象的な演説を行い、当時進行中だった米国主導の環太平洋パートナーシップ(TPP)貿易交渉に日本が参加することに関心を示していることを明らかにした、と言及されています。

In addition to kickstarting TPP, Abe played an even more critical role in salvaging the agreement after Donald Trump, in one of his first acts as president, pulled the United States out of the agreement in early 2017. Against all odds, Abe rallied the 10 other TPP member countries and ultimately won their support for a Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) that largely kept the previous agreement intact and left the door open to an eventual U.S. return.
July 8, 2022
Matthew P. Goodman
Senior Vice President for Economics
やはりここでもアメリカ脱退後にアメリカが復帰するための扉を開いたままCPTPPを発足させたことを評価しています。グッドマン氏は2020年の別稿でも指摘したように、CPTPPに加えて"質の高いインフラ "を推進するキャンペーンも特筆すべきだとし、2015年に開始された安倍首相の「質の高いインフラのためのパートナーシップ」と、その後、2019年のG20大阪サミットにおいてチャイナの習近平国家主席を含む他の経済リーダーたちに、6つの「質の高いインフラ投資のための原則」を承認させたことを挙げています。
A third example of Abe’s impact in global economic rulemaking is in the critical area of data governance. The global economy is increasingly digitized, with massive amounts of data created every minute, yet there are no internationally agreed rules on the privacy, security, and flows of these data. Speaking at the World Economic Forum in Davos in January 2019, Abe proposed the concept of “data free flow with trust” (DFFT) as the organizing principle for global rulemaking in this area. Again, Abe won G20 endorsement of this concept, and the current Kishida administration is reportedly planning to make realization of DFFT rules and norms a priority for Japan’s G7 host year in 2023.
July 8, 2022
Matthew P. Goodman
Senior Vice President for Economics
また、データガバナンスについての国際合意が少ないなか、2019年1月にダボスで開催された世界経済フォーラムで講演した安倍首相は「信頼あるデータの自由な流れ」(DEFT)というコンセプトへの同意を取り付けたことも評価されています。
そして、グッドマン氏は「日本は国際経済において基本的にルールテイカーであり、国際貿易においてしばしば守りの姿勢をとり、新しいルールや規範を支持するためにリスクをとることはほとんどなかったが、安倍首相はこれらの取り組みにより状況を一変させた。米国が世界経済ルールの形成者としての伝統的役割から退いている中で、安倍首相のリーダーシップは極めて重要であった」、と締めくくっています。
なお、安倍元総理はチャイナがメンバーに入るRCEP(東アジア地域包括的経済連携)においても日本が主導的な役割を果たしていく決意でした。
両者の日本国にとっての位置づけが今後どうなっていくのか、FTAAP=アジア太平洋自由貿易圏構想の形成とのかかわりがどうなっていくのかはわからりませんが、以下の記事は参考になるかもしれません。
◆アベノミクスと「三本の矢」:金融政策・財政政策・成長戦略

第一の矢=大胆な金融政策
第二の矢=機動的な財政政策
第三の矢=民間投資を喚起する成長戦略
アベノミクスとは第二次安倍内閣の経済政策を指し、その説明概念として「三本の矢」という表現が用いられました。2013年6月14日発表の「日本再興戦略」で全体像が示されるようになりました。
のちに「アベノミクス」と呼ばれる政策が言及された施政方針演説は2013年2月28日ですが、起点をさらに前と捉える考え方も存在します。
飯田泰之 道半ばのアベノミクス 2022年8月22日 中央公論編集部
アベノミクスのスタートを12年11月14日と捉える論者は少なくない。同日の党首討論において、民主党の野田首相(当時)は安倍自民党総裁に対して「16日に解散をします。やりましょう」と衆議院解散を明言した。マーケットはその瞬間から大きく動き始める。同月上旬までは1ドル=70円台にまで上昇することがあった円ドル相場は現在まで、1ドル=80円を切ったことはない。また14日に始値(はじめね)8660円だった日経平均株価は16日には9000円を超え、15年央に2万円台を付けるまで上昇基調が継続する。
アベノミクスの第一の矢であり、現在も続く日本銀行の金融政策は、民間の将来「予想」を変化させることによって経済に影響を与えることを特徴としている。12年11月14日には、金融政策が近い将来に転換するという「予想」の影響力を証明した。この日、経済政策のレジームが変わったと言っても過言ではない。総選挙における自民党の地滑り的な勝利、その後の日銀人事において金融緩和派が正副総裁に就任したことによって、金融政策転換への予想はさらに強まっていくことになる。
第一の矢は功を奏してデフレマインドをある程度払拭したが、2度の消費増税があったことなどもあり第二の矢は不徹底、第三の矢もあまり…といったところが巷間の一般的評価のように見えます。
ただし、明治大学政治経済学部教授の飯田泰之氏によれば、以下の評価が可能とされています。
アベノミクスの第一の矢であり、現在も続く日本銀行の金融政策は、民間の将来「予想」を変化させることによって経済に影響を与えることを特徴としている。12年11月14日には、金融政策が近い将来に転換するという「予想」の影響力を証明した。この日、経済政策のレジームが変わったと言っても過言ではない。
アベノミクスは、巷間のイメージとは異なり、財政再建と金融緩和を並行して進めた政策であったと振り返ることができるだろう。
成長戦略については少々過小評価が過ぎるのではないだろうか。
筆者は16年から19年にかけて規制改革推進会議委員や同農林ワーキンググループの座長を務めた。規制改革を中心とする成長戦略は、財政・金融政策に比すると、その一つひとつは非常に地味な政策のため、進捗を広く国民が実感することは難しい。
しかし、そのなかで農協改革や森林経営管理法の策定、金融・商品を一元的に取り扱う総合取引所の創設、ドローンの利用に関する規制改革など、小さくはあるが着実な構造改革が実現されている。
では、アベノミクスによって日本経済に関する数値はどうなったか。
飯田泰之 道半ばのアベノミクス 2022年8月22日 中央公論編集部
円高の修正と急ピッチでの株価上昇については前出の通りであるが、第2次安倍政権発足当初、アベノミクスは為替・株価等の金融市場に影響を与えるのみで、実体経済への波及は見られないとの批判が散見された。しかし、13年後半には比較的動きが遅いと言われる雇用においてさえも、その改善は明確になっていく。求人数を求職者数で割った有効求人倍率は12年前半には0・7台だったが、13年後半には1を超える──つまりは求人の数が職を求める人の数を上回るようになってきたのだ(厚生労働省「一般職業紹介状況」)。
この雇用の改善をリーマン・ショックからの趨勢的な改善にすぎないと評する向きもあるが、誤りである。これを確認するために雇用者数の推移を見ていこう(図1)。10年から12年にかけて雇用者数は5500万人前後で横ばいが続いていた。これが13年央には上昇トレンドに転じ、19年には6000万人台に到達した。この傾向は自営業者や家族従業者を含む就業者ベースで見ても変わらない。
さらに、同時期には正規従業員数も顕著に増加している点も注目に値する。現在の基準による正規・非正規従業員の統計は13年以降の数字しか得られないが、13年に3300万人だった正規従業員数は、19年には3500万人に増加している。同時期の雇用拡大を、定年に達する団塊世代の継続雇用増大に求める言説もあるが、団塊の世代が60歳を迎え始めたのは07年であるため、このような継続的な雇用拡大の主因とは捉えづらい。
これらの成果は円高の是正や資産価格の上昇と無縁ではない。円高の是正は生産拠点の海外流出を防ぐことを通じて、国内雇用を維持することとなる。
また、大胆な金融政策は地価の下げ止まりにも資するところとなった。中小・中堅企業にとって、地価は財務状況を大きく左右する。保有資産の評価額が高ければ、金融機関からの借り入れが容易になるためだ。これら中小・中堅企業財務の改善を通じた雇用増加も、雇用情勢改善の要因である。
上武大学ビジネス情報学部の田中秀臣教授は2020年8月28日の安倍氏の辞任表明の前後に以下振り返っています。
もちろん景気下降の中で消費増税を昨年行った「失政」がある。またさかのぼれば、さらに経済失政は二点ある。14年の一回目の消費増税、そして18年前半にインフレ目標の到達寸前までいったにもかかわらず、財政政策も金融政策も事実上無策だったことだ。ただし、今日で2800日を迎える中で、新型コロナ危機以前の経済状況は、雇用を中心に大きく前進した。「長期デフレ不況」のうち「不況」の字がなくなり、「長期デフレ」だけが残っていたのが、昨年10月以前の経済状況だっただろう。
このことは経済に「ため=経済危機への防御帯」を構築したことでも明らかである。安倍政権の経済政策(アベノミクス)の防御帯は主に三点ある。1)雇用の改善、2)株価、不動産価格など資産価格の安定、3)為替レートが過度は円高に陥ることがないこと、である。これらのほぼすべてを事実上、アベノミクスの三本の矢のうち金融政策だけで実現している。急いで付け足せば、ここに積極財政の成果も加わればインフレ目標も早期に実現でき、経済はさらに安定化しただろう。
雇用の改善は、政権発足時の完全失業率が4.3%で、新型コロナ危機前には2.3%にまで低下していた。現状は2.8%と悪化しているが、あえていえばまだこのレベルなのは経済に「ため」があるからだ。有効求人倍率も0.83倍が、新型コロナ危機で直滑降的に悪化しているものの1.11倍で持ち堪えているのも同じ理由による。もちろん「ため」「防御帯」がいつまで持続するかは、今後の経済政策に大きく依存する。このような雇用の改善傾向が、若い世代の活躍の場を広げていき、また高齢者の再雇用、非正規雇用の人たちの待遇改善、無理のない最低賃金の切り上げなどを実現していった。
Economics Lovers Live 田中秀臣のブログ
日本のように財政政策のあり方だけが議論され、そこで緊縮財政と反緊縮財政の対立「だけ」に議論が尽きてしまうのは、海外からはガラパゴス化した政策論争に見えるだろう。この閉塞(へいそく)した日本の経済政策の世界に、安倍首相は新しい息吹を与えた。政策だけではない。日本経済は安倍政権のもとで息を吹き返した。長期停滞からの脱却である。
そのことは数字をみれば明瞭だ。生活実感のベースである名目国内総生産(GDP)は、安倍政権前(2012年度)と比較して19年度までで約60兆円増加した。「失われた20年」の間は、名目GDPの変化はほぼゼロだった。雇用面はさらに劇的に改善していく。政権発足時の完全失業率(季節調整値)は4・3%で、新型コロナ危機前には2・2%にまで低下していた。若年層、女性、高齢者の雇用環境は劇的に改善した。若い人たちの安倍政権への支持が厚いのは経済再生の恩恵を一番受けているからだ。
また、「非正規雇用が増えた」ことがまるで悪いことかのように言われることがありますが、そのような見方については多方面から突っ込みが入っています。一例として分析されているまとめとして以下紹介。
消費税増税は安倍氏の意思ではない、ということが飯田泰之氏など多数人が仄聞していることを指摘していますが、増税の流れについては以下でまとめています。
◆東日本大震災の復興への取り組み
平成23年(2011年)3月26日、当時野党議員だった安倍晋三氏は他の自民党員ともに福島に支援物資の供給等の活動を行っていました。世耕弘成 氏も同行していました。
安倍総理は、総理就任直後の平成24年12月29日にまず福島県を、その後の平成25年1月12日には宮城県を、平成25年2月9日には岩手県・宮城県を訪問しています。
第一次安倍政権前の2006年に刊行した「美しい国へ」を改訂し、あらためて2013年1月に発行された著書の増補となる最終章に、文藝春秋2013年1月号に掲載された文章が採録されています。
私はまず復興庁の意識を変えていく必要があるだろうと思います。復興庁の仕事の実態は、被災自治体が申請した復興交付金の使途を厳しく審査する「査定庁」となりつつあります。復興庁は復興交付金の使途を「最低限の生活再建」と限定しているため、各自治体の最初の申請のうち認可されたのは、六割未満にすぎません。
しかしながら、被災地からの要請を、東京の役所の卓上で審査するだけでは、東北復興などできようはずもない。復興庁の職員は、原則は現地に拠点を置き、現地の人たちの声を吸い上げながら、どうすれば彼らの要望を叶えて、東北の復興につなげていけるかと考えるべきでしょう。
安倍晋三
こうして2013年2月1日に福島復興再生総局が設置され、「5年で19兆円」という復興フレームを見直し、25兆円に増額しています。
国際オリンピック委員会総会において、福島の状況に関して「アンダーコントロール」と主張するなど、国際社会へのアピールも積極的に行っていきました。その後、東京オリンピックの一部競技(野球・ソフトボール)について福島県の競技場で試合が行われることが決定・実施されました。
総理大臣就任後、何度も代わり映えのしない「ジューシー」というセリフとともに福島県の食品をおいしそうに食べる姿をメディアに見せていました。
安倍さん、左翼が「原発近海モノの魚」を揶揄嘲笑していた頃から福島の魚介類を食べてくれてたね。
— HAYASHI Tomohiro (@KumawithSake) July 8, 2022
おにぎり頬張ったり、桃食べたり。
旨そうに食べるくせに語彙力なくて、感想は「ジューシー」ばっかりだったけど。
福島の桃の旬は目の前。
今年も、きっとジューシーだよ。
味わって、ほしかったな
安倍総理退任後ですが、2021年には米国FDAが処理水の海洋放出に「安全への影響はない」と科学評価、IAEAが海洋放出に技術協力を表明、菅政権時のALPS処理水の海洋放出決定や、米国が日本産の食品輸入規制を撤廃するなど、着実に正常化が進んでいます。
◆新型コロナへの初期対応確立
安倍政権が新型コロナウイルスへの初期対応を確立したことを「功績」と呼べるのかどうかは後世に委ねるべきでしょうが、政権の判断が無ければ成し得なかったことというのは指摘できます。
・入管法5条1項14号の解釈を駆使して外国人の外国からの入国規制を実施
【出入国管理及び難民認定法】=入管法の規定は以下となっています。
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
~省略~
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
新型コロナが日本で流行する前の2020年1月当時、無症状病原体保有者に対しても各種の規制ができるのか?という問題がありました。なぜなら、それまでの政府・厚労省の認識は、「症状が出てから人に感染し得る」というものだったからです。
さらに、感染しているかも不明な人物に対して、感染流行地域から出国したことを理由として「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれ」を認定することの懸念を伝える者もいました。
しかし、行政手続法上も外国人の出入国に関しては広範な裁量があるとされているため、特段の事情が無い限り感染流行地域から入国拒否する方針が2月1日から実施されました。
このタイミングが遅すぎた・対象地域が狭すぎる、という批判もありました。ただ、当時の微妙な空気感=感染症の日本への蔓延を避けたいが「外国人の人権!(出入国に関してはそんなものは無いが)特別永住権者はどうなるのか!」と悪し様に言いたい人たちの歯に物が詰まったような物言いがあったことは指摘しておきます。安倍政権でなければ、もっとタイミングが遅くなっていた可能性は高い。
現に、これは2020年12月の話ですが、以下のような印象操作報道があったくらいです。2020年以前から存在する情報パンデミックと常に対峙していた。
・3密⇒3Csとして世界の模範として広がった感染対策
日本政府は尾身茂 氏を感染対策のトップに据え、以来ずっと対応をまかせてきました。その人選自体が称賛されるべきです。日本の感染者数に対する死亡者数は、ずっと世界で最も低い水準でした。世界で断トツの高齢社会である日本で、高齢者に対して死亡率の高い感染症に対して、このこと自体は誇るべきです。国民の協力があったからと言えますが、政府の発信を信じようとする素地がありましたし、一部地方行政のように医学的根拠が怪しい手段に飛びつくということは一切しなかった。
【注意喚起】#新型コロナウイルス に関するお知らせです。集団発生のリスクを下げるために3つの「密」を避けて外出しましょう。
— 首相官邸(災害・危機管理情報) (@Kantei_Saigai) March 17, 2020
①換気の悪い密閉空間
②多数が集まる密集場所
③間近で会話や発声をする密接場面
詳細はこちらをご覧ください▼https://t.co/GTXEBrZuFc pic.twitter.com/3d0Rkf9omi
新型コロナウイルスの感染予防の対策として、3つの密(3密)として「密閉・密集・密接」の環境に注意すべきという標語が2020年3月に生まれました。
厚生労働省では、これを"Three Cs" として同年3月28日から英語での発信が確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html
以下のようなパンフレットもありました。

https://www.mhlw.go.jp/content/3CS.pdf
⇒ドキュメントプロパティで3月29日作成ということがわかる。
英語圏でも、このThree Cs・3Csと呼ばれる標語が使われるようになりますが、WHOの発信で確認できるのは同年の7月からになります。
Avoid the 3️⃣ Cs.
— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 16, 2020
There are certain places where #COVID19 spreads more easily:
1️⃣ Crowded places
2️⃣ Close-contact settings
3️⃣ Confined and enclosed spaces pic.twitter.com/JStNgij5Gh
英国のコロナ対策は「3密+2」 日本版に2項目を追加 ロンドン=下司佳代子2020年10月12日 23時36分
新型コロナウイルスの感染者が再び急増している英国で12日、首相官邸で開かれた英政府の記者会見に出席したイングランドのジョナサン・バン・タム副主任医務官が、日本が感染防止のために掲げる「3密」(英訳は3Cs)を紹介した。これに独自の2項目を加え、英国流の「3密+2」を披露した。
~省略~
こうした措置に、効果が見込める科学的根拠はあるのか――。12日の記者会見でそう問われたバン・タム氏は「ウイルスが拡散する条件は、日本の『3密』の助言にうまく要約されている」と切り出し、3密の概念を説明した。日本政府は3密を3Cs(Closed spaces,Crowded places, Close-contact settings)と訳して海外向けに広報している。
バン・タム氏はこれに独自のDとVを加えた。Dはduration(継続期間)で、3密の状態が長く続くこと。Vはvolume(音量)で、歌ったり叫んだりすることでウイルスが遠くに飛び、感染が加速する強力な証拠があるとし、「これらの要素が当てはまる状況を許せば、ウイルスは拡散する」と語った。
このように、日本側が最初に感染対策の肝を提唱し、それを世界に発信し、他国が参考にしたという事案としても「3密」というのは重要なものです。
・ワクチン確保の道筋
6月14日の時点でアメリカのモデルナとイギリスのアストラゼネカのワクチン開発に触れ、同年12月から2021年前半からの接種開始の見通しを立てていました。両国との良好な関係があればこそ、と言い得るでしょう。
◆国葬実施に値する功績を残した故安倍晋三元総理大臣
第二次安倍政権は初めて日本独自の国家戦略を策定し、日本自身の主体的な判断で米国とだけでなく、豪印英加などの防衛協力を強め、日本の国際的地位を高めようとしてきた。その意義はもっと評価されてしかるべきだ。
「国葬が実施された吉田元総理と比較して、安倍は国葬に値するのか?」
これに対する答えとして江崎氏の指摘は重要でしょう。
つまり、安倍主導・日本主導での国際枠組みを構築し、その枠組みを米国など諸外国が支持・維持して現在も続いているということ。こんな事を戦後の国際社会でやってのけた政治家は他に居るのでしょうか?戦前の、列強と渡り合い「当時の国際社会」の一員となり国際社会維持のために奮闘した宰相らと比肩しうるのではないでしょうか?
しかも、自衛隊創設や主権回復、沖縄の本土復帰など、振り返ってみれば時代の流れでほぼ必然的だったような事柄ではなく(大変大きな功績であるのは言うまでもない)、自らの意思で戦略を練り主導してきたと言えます。
◆Appendix:故・安倍晋三元内閣総理大臣を悼む声明・各所の動きなど
A personal bond shared by the leaders and the many memorable interactions that they enjoyed over the years.@The_Japan_News publishes a tribute written by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi titled ' My Friend, Abe san'.
— India in Japanインド大使館 (@IndianEmbTokyo) July 12, 2022
Read it at : https://t.co/BNJid6tCCo
Today, both houses of Parliament of India, Loksabha and Rajyasabha paid tribute to former Prime Minister His Excellency ABE Shinzo. A tribute to a leader who has worked tirelessly to enhance 🇮🇳🇯🇵 bilateral partnership. @AbeShinzo @narendramodi @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/OxOM70CHG9
— India in Japanインド大使館 (@IndianEmbTokyo) July 18, 2022
陳氏はあいさつで、安倍氏は台湾が最も苦しい時に、日本社会に対して「台湾有事は日本有事」と呼びかけ、台湾人を大いに感動させたと指摘した。
また「安倍氏の台湾に対する最大の貢献は台湾問題を国際的な問題にした」と強調。安倍氏は台湾の世界における戦略的地位を際立たせた上で、全世界に対して台湾問題に関心を持ち、自由や民主主義、尊厳、主権を追求する台湾人を守るべきだと訴えたと振り返った。
To Be Continued…
いいなと思ったら応援しよう!

