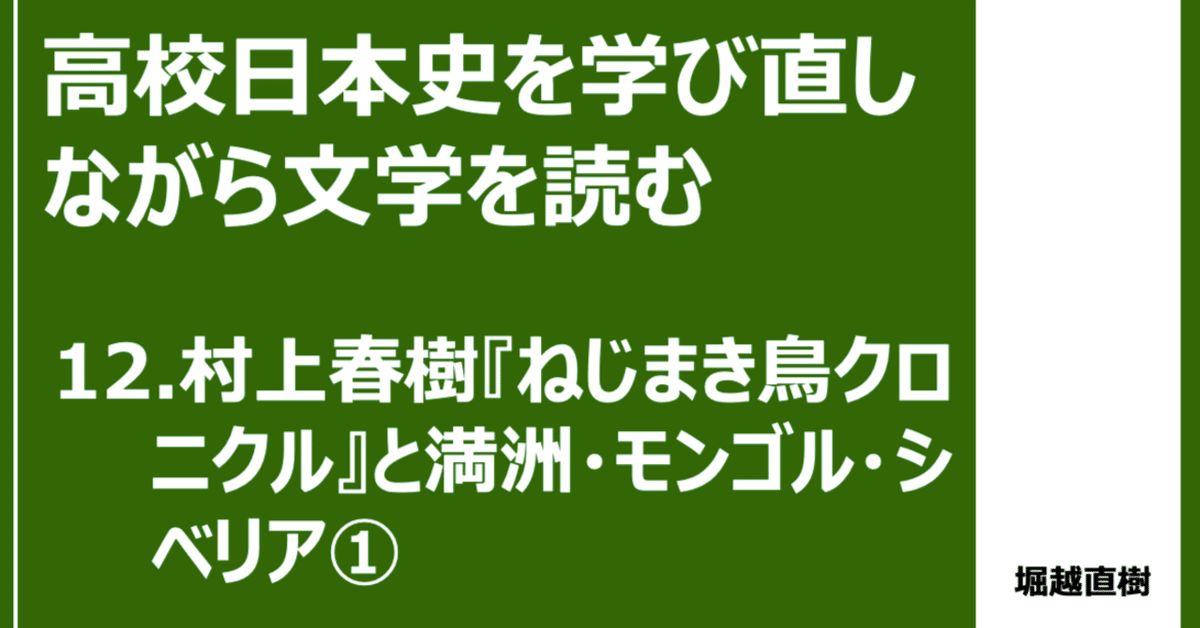
村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』と満洲・モンゴル・シベリア①【高校日本史を学び直しながら文学を読む12】
今回は村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』を取り上げます。新刊が出ると必ず買ってしまう作家が僕には何人かいるのですが,村上春樹はその中の一人です。書籍化された作品はすべて所持しています。『ねじまき鳥クロニクル』は,いなくなった妻を主人公が取り戻そうとする物語を主軸としつつ,ノモンハン事件などの歴史が交錯していくので, 高校日本史を学びなおしてから読むとさらに面白くなるはずです。まずは満洲事変から日中戦争への流れを理解しなければならないので,長文になることをご容赦ください。
日露戦争後,1905年のポーツマス条約により遼東半島の旅順と大連が日本の租借地となりました。この地域は関東州と呼ばれ,管理のために関東都督府が置かれています。日本は南満洲に鉄道経営・鉱山開発などの権益を獲得し,その中核として,1906年に南満洲鉄道株式会社(満鉄)が設立されました。さらにこの権益保護のために関東都督府陸軍部が置かれ,1919年に関東軍に改組されました。
ところで,この時期に日本が権益を拡大していた「満洲」ですが,以前は高等学校の教科書で「満州」と表記されていました。それが2022年度から新学習指導要領にもとづいて設置された新科目「歴史総合」「日本史探究」「世界史探究」の教科書では「満洲」と表記されるようになっています。満洲人はもともとツングース系でジュシェン(女真)と呼ばれていました。その後,マンジュと改称し,漢字を使用していなかったので最初は音だけだったのですが,漢字を当てるときは「満洲」の文字を当てるようになりました。前王朝の明から「火」が連想され,その火に勝るものということで,清は「さんずい」,つまり水にこだわったとされています。だから,「清」も「満洲」も「さんずい」がつくのです。
日本は満洲を地名のように用いていますが,満洲はもともと人間集団をさす名称であり,清の東三省周辺の地を「満洲」または「マンチュリア」と呼んだのは日本と西洋だけでした。地元の人たちは地名として用いてはいないのです。のちに日本では満洲と東部内モンゴルをあわせて「満蒙」と呼び,これが「満洲国」の領土とされました。現在,中華人民共和国はこの地域を中国東北地区と呼んでいます。
第一次世界大戦中の1915年,大隈重信内閣は中華民国の袁世凱政権(北京政権)に対して二十一か条の要求をつきつけ,一部はアメリカなどの反対で撤回したものの,最後通牒をつきつけて大半を承諾させました。その内容は,南満洲の既得権益を認めさせつつ,さらに権益拡大をはかるものでした。
しかし,中国への進出競争で他の列国より出遅れ,日露戦争前から「門戸開放」を唱えていたアメリカは,中国において日本が権益拡大を続けることを許しませんでした。1921年,アメリカ大統領ハーディングの呼びかけによりワシントン会議が開催され,日本も参加します。この時に締結された九か国条約では,中国の主権と独立の尊重,領土の保全と門戸開放・機会均等が確認されました。これにより,中国で軍事行動による領土拡張をはかることは国際条約上できなくなります。のちの満洲事変の国際的な位置づけを理解するためにも,九か国条約の内容はおさえておきましょう。
日本の外交は列国との協調方針がとられ,その象徴として憲政党・立憲民政党の内閣で外務大臣を歴任した幣原喜重郎がクローズアップされることが多く,その名を冠して「幣原外交」とも呼ばれます。立憲政友会の田中義一の外交(首相の田中義一が外相を兼任)を強硬外交ととらえ,幣原外交(協調外交)と対比的に論じるような人がいますが,僕はそのとらえ方の大部分が誤りだと思っています。
幣原外交は,平和や人道主義を優先した外交というわけではなく,国益を追求する産業立国策と連動した経済主義外交ととらえるのが妥当です。満蒙権益を保持しつつ,中国の他の地域には経済的進出を拡大するという方針を優先させるためには,米英との協調が得策と考え,米英を刺激するような中国への内政干渉は避けました。
田中外交の方針は,満蒙権益確保,通商政策の進展,対米英協調外交など,ほぼ幣原外交と共通しています。違いがあるようにみえるとすれば,この時期の政府の方針が,居留民保護と権益擁護を名目にすれば軍事介入をしても内政干渉には当たらない,という考え方へ徐々に転換していっていた時期にあたるからです。1926年,蔣介石のひきいる国民革命軍が,北方軍閥を打倒して中国統一をめざす北伐を開始しました。北伐が完了し,中国が統一されれば,日本の満蒙権益が脅かされると考え,田中は中国に軍事介入することを考えます。1927年,在留邦人保護を名目として山東省への出兵がはじまりました。さらに,東方会議をひらいて,陸海軍の代表者や外交官と方針を確認しています。その内容は,満蒙権益を保持するためには積極的な行動をとる必要がある,というものでした。東方会議での方針決定から翌年にかけて,第2次・第3次の山東出兵がおこなわれました。第2次山東出兵で日本軍は済南城を攻撃し,中国側には民間人を含む多くの死者が出ました(済南事件)。ここで確認したいのは,山東出兵で多くの死者を出したにもかかわらず,田中は名目的とはいえ在留邦人保護を前面に出しており,米英とともに締結した九か国条約を無視する姿勢を対外的にとるつもりはないということです。
しかし,田中義一首相と,現地の関東軍の首脳との間には,対中国政策に関する見解の相違がありました。田中首相は,長城以南は国民政府の統治を認め,長城以北の満蒙の権益は維持し,そのために満洲軍閥の張作霖の勢力を支援しつつ利用する方針でした。一方,関東軍の首脳は,張作霖を排除し,満蒙を中国本土から切り離した上で日本の統治のもとにおくことを画策するようになっていました。
田中首相は,張作霖が北京で国民革命軍を待ち構えている状況を憂慮していました。張作霖が戦闘で敗退した場合,奉天まで敗走していくのを国民革命軍が追撃し,満洲にまで戦闘の余波が及ぶようなことになれば,それが最悪のシナリオだと考えていたのです。そのため,張作霖に対して北京を離れて奉天へ戻ることを勧告します。張作霖は勧告に従い,全軍撤退の指示を出してから,自身は鉄道で北京を離れました。ところが,張作霖の乗った列車が奉天郊外で爆破され,重傷を負った張作霖はその日のうちに死去しました(張作霖爆殺事件)。
張作霖爆殺事件は,関東軍参謀の河本大作が主導したものであり,爆殺は中国側の仕業だとして軍事行動をおこし,満洲一帯を支配下におこうとする計画でした。つまり,鉄道爆破は関東軍の自作自演だったのです。
事件は関東軍の暴走によるものであり,首相である田中の意向に沿うものではありませんでした。田中義一は真相公表と関係者の厳罰を昭和天皇に上奏します。しかし,陸軍幹部らの反対にあい,軍法会議にもかけずに曖昧に事件を終わらせようとし,犯人不明と上奏しました。そのため昭和天皇に叱責され,その後,田中内閣は即座に総辞職しました。
張作霖を亡くした北方軍閥は,息子の張学良が後を継ぎました。張学良にとって日本は実の父を殺した不倶戴天の敵です。張学良はライバルであるはずの蔣介石との提携を決意し,奉天軍は国民党の青天白日旗を掲げる「易幟(えきし)」をおこないました。
関東軍の暴走は,目的を達成するどころか,むしろ中国を結束させ,反日の動きが強まる結果となりました。
満洲事変の説明に移る前に,中ソ戦争の話をしておきましょう。かつて清王朝の支配下にあったモンゴル民族は,自治・独立の動きを見せていました。その一部は,ソ連の支援を得て,1924年,外蒙古にモンゴル人民共和国を建国しました。また,日本軍も独自に内蒙古のモンゴル人への工作をおこなっていました。
張学良は,易幟の翌年,蔣介石の支持を得た上で,ソ連と武力衝突しました。しかし,蔣介石の中央政府軍が動かなかったこと,ソ連の装備が優れていたことから,結果はソ連軍の圧勝でした(中ソ戦争)。
中ソ戦争により,関東軍はソ連軍を脅威と感じるようになり,それと同時に中国のナショナリズムの高まりに対する警戒を強めます。そのため,関東軍は,武力を使って満洲の権益を維持しようとする姿勢をより強めていきました。
1929年,ウォール街における株価の大暴落をきっかけに世界恐慌が始まりました。10月24日の大暴落を「ブラック・サーズデイ」と呼びますが,1日だけの現象ではなく,その数日前から市場は続落しており,その後の11月上旬にかけて何度も暴落を繰り返しました。立憲民政党の浜口雄幸内閣は,大蔵大臣に就任した井上準之助を中心に緊縮財政を進め,産業合理化を目指しました。ここでいう産業合理化とは,国際競争力の弱い産業を切り捨ててでも,長期的な視野で国際競争力を強化する政策です。しばらくの間,中小企業の倒産数増加や失業率の上昇が起こることはやむを得ないとする,失業した当事者の立場で考えれば大変残酷な政策と言えるでしょう。浜口内閣は社会政策の推進も同時に掲げ,それに向けた具体的な法令整備にも取り組んでいるので,国民生活の荒廃を無視しようとしていたわけではありません。また,民意を背景として,ときには軍部からの圧力にも立ち向かう浜口首相の政治姿勢などは,政党政治の成熟を感じさせる部分があると言ってもよいのではないかと僕は思います。しかし,国民生活と比べれば,大企業を中心とする経済成長を明らかに優先させていたことは間違いないと思いますし,その姿勢が悲惨な状況を招くことにつながってしまいます。ウォール街における株価大暴落を認識した後も,産業合理化の方向性を一度止める決断ができず,日本経済は深刻な不況に陥りました。特に農村部では子女の身売りや欠食児童の増加などが社会問題化しています。満洲事変は,このような国内の危機的な状況の理解を前提としなければ語ることのできない出来事です。
1931年,「満蒙の危機」が叫ばれ,強硬論が高まっていきました。関東軍参謀の石原莞爾らは,満洲領有を主張します。石原という人物は思想的に首尾一貫したところがなく,時期が異なれば別人のようになってしまうほど変節が激しい人なのですが,この時期の石原は「世界最終戦」について論じていました。「世界最終戦」とは,西洋の盟主・アメリカと,東洋の盟主・日本が最終的に戦うことになるという想定です。アメリカと戦うためには満洲の石炭・鉄などを国防資源としておかなければならないと考え,満洲確保のためなら強硬手段も辞さないという考えにつながっていきます。ただし,アメリカはあくまで「最終戦」の相手国であり,石原はその前におこなわれる可能性が高いと想定した対ソ戦のための国防計画策定を急いでいました。1931年9月の段階では,極東ソ連軍6個師団に対して,関東軍・朝鮮軍3個師団であり,兵力差は歴然としていました。
1931年9月18日,関東軍が奉天郊外の柳条湖付近で南満州鉄道の線路を爆破し,これを張学良軍の仕業だと偽って軍事行動を開始しました(柳条湖事件)。関東軍による自作自演がまたおこなわれました。この柳条湖事件以降,1933年5月に塘沽(タンクー)停戦協定が結ばれるまでの日中間の戦争状態を「満洲事変」と呼びます。
1931年10月27日の『東京日日新聞』の紙面は「守れ満蒙-帝国の生命線」というタイトルで,関東軍の行動を正当なものとし,中国への敵意を募らせています。また,立憲民政党内閣で外務大臣を務めている幣原喜重郎についても批判的なスタンスをとっています。この頃から,メディアは軍部の行動を追認するようになっていきました。多くの日本人は,日本人居留民が中国人の暴動的な「排日」により危険にさらされているという情報を信じ,関東軍の行動を熱狂的に支持しました。関東軍が線路を爆破した事実は,敗戦後まで国民に知らされてはいません。
柳条湖事件を計画したのは石原ら少数で,実行部隊も数名です。線路の片側1メートル前後の破損程度の小規模な事件でしたが,これをきっかけに軍事行動を開始することが目的でした。立憲民政党内閣を浜口雄幸から継承していた第2次若槻礼次郎内閣(外務大臣は幣原喜重郎)は,アメリカ・イギリスとの協調が損なわれることを恐れ,「不拡大方針」を発表しました。しかし,それを無視して,関東軍は戦線を拡大していきます。当時,関東軍の戦力は約1万人,それに対して張学良軍は,警察部隊を含めれば40万人以上の兵力がありました。関東軍の軍事行動が当時の内閣から支持されていない状況を考えれば,出兵の経費支出を閣議で承認してもらうことも期待できません。つまり,関東軍単独で満洲を占領することは不可能と言ってよい状況だったのです。しかし,朝鮮軍司令官の林銑十郎が,独断で国境を越えて満洲に進撃する命令を発します。本来,国境を越えて軍隊を出動させる際には,統帥権にもとづく天皇の命令が必要不可欠です。林の行動は,大日本帝国憲法を,そして天皇をないがしろにする行為でした。それでも関東軍や朝鮮軍の幹部が後に厳罰に処されるわけではなく,天皇からは今後気をつけるようにという戒めだけであり,政府は「事変」という言葉を使って,「戦争」ではないので国際条約に違反しないという態度を対外的にとるようになります。軍隊というのは組織や指揮系統を大切にするというイメージが僕にはあるのですが,その観点からすると,当時の日本軍には軍隊として致命的な欠陥があるように思いますし,その軍隊の行動を正すべき立場の人たちも曖昧な態度を続けてしまったという印象を受けます。
先制奇襲攻撃を徹底した石原の作戦により,関東軍は短期間で奉天政権軍の本拠地を占領します。五か年計画の完遂を優先して介入してこなかったソ連,世界恐慌後の経済復興を優先して介入してこなかった欧米などの要素も重なっていますが,最も大きかったのは蔣介石が国内整備と共産党鎮圧を優先していたために,抵抗ではなく長城線の南への脱出を指示したことでした。
1932年3月1日,新国家「満洲国」の建国が宣言されました。清朝最後の皇帝であった溥儀(ふぎ)を執政とし,人々の自発的な独立運動によって誕生した国家であり,関東軍はそれをサポートしているだけということにしています。しかし,実際には関東軍の主導であることは明白であり,傀儡状態でした。「満洲国」は国籍の制定がなく,国民もいなかったので,傀儡「国家」とすら呼べません。満洲の住民の多くは張学良の圧政を嫌い,中華民国への不信感もあり,関東軍の占領にも反発していました。そのため,満洲では複雑で多様な自治運動が生じています。
1932年5月15日,海軍青年将校らが首相官邸を襲撃し,犬養毅首相を射殺しました(五・一五事件)。犬養は,国家としての「満洲国」は承認せず,満洲における中国の主権を認めたうえで自治政権をつくるという構想を持っていたようです。
犬養の後継首相として推薦されたのは海軍大将の斎藤実であり,これにより政党内閣が終わりを告げることになります。その斎藤内閣が「満洲国」を承認し,日満議定書を締結しました。日満議定書では,「満洲国」のすべての部門に日本人の参議(顧問)を任用し,その任免権は関東軍司令官が掌握することが定められています。国際連盟はリットンを団長とする調査団の報告書にもとづき,日本の軍事行動と満洲占領を不当であると認定しました。日本の「満蒙」における特殊権益を容認するなど,日本に対して甘い内容もあったのですが,それでも日本は1933年3月,国際連盟に脱退を通告しました。
1933年5月,塘沽停戦協定が調印されました。河北省東部を非武装地帯とし,日本の満洲・熱河省支配を中国に事実上承認させています。これにより,満洲事変は一旦終息しました。
塘沽停戦協定以降,日中間の外交関係は一時的な友好ムードとなりました。斎藤実内閣の後に組閣した岡田啓介内閣では,外務大臣の広田弘毅が中国に対する不脅威・不侵略を唱え,蔣介石も好意的に受けとめています。しかし,政府による外交関係と現地の陸軍の動きは別でした。1935年,支那駐屯軍(北京・天津などに駐屯した日本の陸軍)と関東軍は,華北分離工作を推進しています。華北分離工作というのは,「満洲国」の外側の中国の領土に非武装地帯をつくり,国民党の組織などがこの地域で活動できないようにするための策動です。中国には,張学良や中華民国よりもかつての清王朝への親近感が強い人なども存在するので,様々な理由で「満洲国」に協力する人がいました。こうした動きが進むなか,中国では民族的危機感と抗戦意識が高まっていきました。しかし,蔣介石率いる国民党がこれまで中国共産党の討伐を最優先としていたため,日本を不倶戴天の敵ととらえる張学良はかなり強引な手段に打って出ます。西安へきた蔣介石を監禁して,中国共産党の周恩来とともに内戦停止と抗日を要求し,蔣介石に同意させました(西安事件)。これにより,国民党・共産党両党は内戦を停止し,抗日民族統一戦線が結成されました。
1937年6月,華族の名家出身の近衛文麿が,各方面の大きな期待を集めて組閣しました。その直後の7月,北京郊外の盧溝橋で日中両軍が衝突する事件がおこります(盧溝橋事件)。支那駐屯軍の一中隊が軍事演習をしていたところ,実弾が数発飛んできて,さらに日本側の兵士が行方不明となったため,日本側が攻撃命令を出した,というのが盧溝橋事件の流れです。日本の兵士が方向を誤って中国側の陣地に近づいたために発砲されたようですが,その兵士は長時間行方不明となっていたわけではなく,30分もたたずに帰隊しています。兵士が帰ってきたので,これ以上大きな事件になるとは考えにくいのですが,近衛内閣はこれを機会に抗日運動を屈服させつつ,華北の資源・市場を獲得するチャンスと考えて,派兵を決定しました。その後,戦火が拡大し,国際連盟規約や不戦条約の規定に反する全面的な侵略戦争に発展していくのです(日中戦争)。宣戦布告がなかったから戦争ではないという理屈で,日本は支那事変と呼びましたが,実態は日中全面戦争です。
12月,日本は大軍を投入して,国民政府の首都南京を占領します。首都に大きな一撃を与えれば国民政府は屈服し,日本側主導のもとで早期に戦局は終結する,というシナリオでしたが,中国の抵抗は日本の予想をはるかに上回り,首都を奪われても屈服はしませんでした。日本軍は南京で,捕虜ばかりでなく逃走していた敗残兵や民間人を含むおびただしい数の中国人を殺害し,略奪・放火・暴行をおこなって国際的な非難を浴びました(南京事件)。作戦が短期決戦であっても,長期戦になることも想定して補給のための兵站を重視することは近代以降の戦争では特に重要だと思いますが,その点からみると日本軍は不備だらけであり,食糧などが「現地調達主義」となっていました。略奪が多かった背景には,このような理由があったのです。満洲事変のところで,指揮系統がおかしくなっている日本軍の様子を指摘しましたが,「兵站」という重要な部分にも致命的な欠陥がありました。最も重要な部分が整備されていない状況で管理者が拙速に決断し,不合理な命令が現場の人間へ下され,それを精神論の流布で無理にカバーしようとします。残念ながら,現代でも似たような組織がどこかにあるかもしれません。この南京事件がなかったと主張する人が一部でいるのですが,歴史学研究が積み上げてきたものを無視した状態で,自分に都合のよい解釈のみをするのは許されないと思います。殺害された人数に関して,南京市が示す30万人というのが多すぎると言う人がいます。この事件で殺害された人数を正確に把握することは難しいと思いますが,人数のデータが多すぎるか少なすぎるかは,事実そのものを消去する根拠にはなりません。「兵士が民間人のふりをすることがあったから全員殺すしかなかった」や「他の国だって略奪や強姦をしているだろう」などの言説も,事実そのものを消去する根拠にならないことは明白です。このとき日本政府が居留民の保護を主張している以上,それとはかけ離れた南京での行動が国際的非難を浴びるのは必然だと思います。
村上春樹は『猫を棄てる 父親について語るとき』(文藝春秋)で,父親の戦争体験についてかなり字数を割いて説明しています。村上春樹は父親が第十六師団の歩兵第二十連隊(福知山)に所属していたと勘違いしていましたが,実際は同じ第十六師団に属する輜重(しちょう)兵第十六連隊でした。輜重兵とは,補給作業に携わり,主に軍馬の世話を専門とする兵隊のことです。この勘違いと関連して,南京事件に触れている箇所があるので,少し引用します。
父が第二十連隊に所属していたと思い込んで
いたせいで,僕は父の軍歴について詳しく調
べるために,というか調べようと決心するま
でに,けっこう長い期間がかかった。(中
略)それは歩兵第二十連隊が,南京陥落のと
きに一番乗りをしたことで名を上げた部隊だ
ったからだ。(中略)この部隊の行動にはと
かく血なまぐさい評判がついてまわった。ひ
ょっとしたら父親がこの部隊の一員として,
南京攻略戦に参加したのではないかという疑
念を,僕は長いあいだ持っており,そのせい
もあって彼の従軍記録を具体的に調べようと
いう気持ちにはなかなかなれなかったのだ。
(中略)父親が入営したのは1938年8月1日
である。歩兵第二十連隊が,南京城攻略一番
乗りで勇名を馳せたのはその前年,1937年
の12月だから,父はすれすれ一年違いで南京
戦には参加しなかったわけだ。そのことを知
って,ふと気がゆるんだというか,ひとつ重
しが取れたような感覚があった。
また,戦争中の残忍な光景についても言及があります。
一度だけ父は僕に打ち明けるように,自分の
属していた部隊が,捕虜にした中国兵を処刑
したことがあると語った。(中略)無抵抗状
態の捕虜を殺害することは,もちろん国際法
に違反する非人道的な行為だが,当時の日本
軍にとっては当たり前の発想であったよう
だ。だいいち捕虜をとってその世話をしてい
るような余裕は,日本軍戦闘部隊にはなかっ
た。1938年から1939年と言えば,ちょうど
父が初年兵として中国大陸に送られていた時
期であり,そのような行為を下級兵士たちが
強制されていたとしても,決して不思議はな
い。それらの処刑の多くは銃剣による刺殺を
用いて行われたようだが,そのときの殺害に
は軍刀が使われた,と父は言っていたと記憶
している。
蔣介石は,駐華ドイツ大使トラウトマンを介して日本との和平交渉を進める姿勢を示していました。しかし,首都占領で勢いにのって,振り上げたこぶしを下げることができなくなってしまった近衛内閣は,「国民政府を対手(あいて)とせず」という声明を発表してしまいます。蔣介石らと交渉はせずに,中国で新しい政権が成立することを期待し,その新政権建設に協力する方針を示したのです。日中戦争を収拾させる道を自らとざしてしまう行為でした。南京を脱出していた国民政府は,首都を重慶に移し,アメリカ・イギリス・ソ連などの援助を受けて,抗戦を続ける姿勢を示しました。これにより,日中戦争が長期化・泥沼化する可能性が高くなりました。しかし,短期決戦を想定していた日本の陸軍は,すでにこの段階で動員力が限界に達していました。
近衛内閣は,ひそかに国民党の有力者の一人である汪兆銘(汪精衛)との間で和平工作を進めていました。蔣介石の政策に反対する勢力を重慶から離脱させ,その勢力を結集させて,重慶政権を和平に転換させたいと考えていたのです。汪兆銘は重慶を脱出しますが,南京に汪の新政権を樹立する方針があることを知って,汪からすでに多くの人が離れていました。新政権が日本の傀儡政権になってしまう危険性が高かったからです。
1938年11月,近衛首相は日中戦争の目的が「東亜新秩序」建設であると表明します。新秩序とは,日本・満洲・支那(中国)が「互助連関」の関係を樹立することであるとしています。これ以前の日本軍兵士は,戦争の目的も知らされないまま動員されていたことになりますが,これ以降は目的を認識し,納得して戦っていたかというと,新秩序の内容があまりにも抽象的で曖昧なだけに,おおいに疑問が残ります。このようなスローガンを掲げながら,汪兆銘を通じた和平工作を進めるという意図もあったと思いますが,汪に続いて重慶を脱出する有力者がほとんどいなかったため,それも実現は不可能でした。
「満洲国」の建国後,日ソ間の緊張が続き,満ソ国境紛争がおこるようになっていました。日本側はソ連およびモンゴル人民共和国の軍事的脅威の増大を警戒し,ソ連側は「満洲国」を警戒しながら軍の技術装備強化・近代化を達成していきました。1936年に日独防共協定が結ばれ,日本とドイツがソ連とコミンテルン(共産主義者の国際組織)への対抗姿勢を明確にすると,ソ連は自国の軍事力増強だけでなく中華民国やモンゴル人民共和国との軍事同盟を締結して東アジアにおける集団安全保障体制を構築していきました。
1939年5月,関東軍が,「満洲国」とモンゴル人民共和国との国境地域であったハルハ河東岸で,ソ連・モンゴル軍と衝突しました。日本では「ノモンハン事件」,ロシアやモンゴルでは「ハルハ河戦争」と呼ばれることが多い戦いです。ところで,「ノモンハン」は「満洲」と同様,地名ではないのに地名のように誤用されることが多い言葉です。ハルハ河東岸に「ノムンハーネイ・ブルド・オボー」(チベット仏教の聖者の塚)があったことから,日本軍が「ノモンハン」と呼んでいたのです。ちなみに「ノモンハン」とはチベット仏教の僧の位階を示す言葉であり,直訳すれば「法王」になるので,地名にはなりません。
ノモンハン事件では,関東軍がソ連軍の火力・機動力に圧倒されて壊滅的な打撃をこうむったと説明することが一般的です。それは間違ってはいませんが,日本軍が一方的に大敗したと説明すると誤りになってしまうので注意が必要です。近年の研究では日本軍、ソ連・モンゴル軍どちらも多くの死傷者を出したことが明らかになっています。正確な死傷者数は断定できませんが,日本軍は2万人弱,ソ連・モンゴル軍の死傷者数はそれを上回っていたのではないかとも言われています。そのような情報から,「実は日本が勝っていた」のような言い方をする人もいるようですが,戦後の結果を見れば,国境線はモンゴル側の主張が通っているので,日本の敗北です。
日本軍については,参謀本部と現地の関東軍との間で戦略方針が統一できていなかったことがよく知られています。参謀本部は局地的解決を求めていましたが,関東軍の作戦参謀である辻政信や服部卓四郎ら強硬論者が上官を動かしました。外蒙古の航空基地への攻撃は,国境を越える作戦なので天皇が命令しなくてはなりませんが,関東軍は天皇の許可を得ずに強行しています。一方のソ連軍も,中央の赤軍参謀本部と現地の軍司令部との間で戦略方針の相違がありました。赤軍参謀本部が主力部隊の投入をとめたにもかかわらず,現地の軍司令部が実行し,戦車部隊を使用したことが記録に残っています。このように両軍が大きな問題を抱えていたからこそ,双方の被害が甚大になり,現地では様々なことがおこり得る状況だったのではないかと思います。
村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』は,主人公の岡田トオルが失踪した妻のクミコを探索し,取り戻すまでの物語が軸になっていますが,第一部と第三部でかなり長めの歴史記述があります。歴史と現在が交錯しながら,主人公が自身の内面にある闇の部分を掘り下げていくことで,重厚な物語とすることに成功し,間違いなく作者の代表作の一つとなっています。
ここではまず第一部の歴史記述を紹介します。岡田トオルとクミコは,結婚してから月に一度,本田さんという老人の家を訪問しています。クミコの実家である綿谷家が,それを条件に結婚を許可したからです。本田さんは綿谷家が高く評価している〈神がかり〉の一人でした。本田さんはノモンハン戦争に関東軍の下士官として従軍した経験があり,そのときの体験を毎月語ってきかせていました。その話の中で「帝国陸軍にとっては生き恥を晒したような戦じゃった」と語るのですが,「どうしてノモンハンの戦争が陸軍にとってそれほど恥ずかしいものだったんですか」という問いかけにはこたえてくれません。
結局,綿谷家と疎遠になったことで,本田さんの家への訪問は一年間で終わってしまうのですが,あるとき広島県に住む間宮徳太郎という人物から手紙が届き、そこには本田さんが自宅で亡くなったこと,また形見の品を配分する人物の中に岡田トオルの名があったことが記されていました。間宮氏は戦争中に本田さんと生死をともにした経験があり,今回,形見の配分を引き受けているということでした。その間宮氏が岡田トオルの自宅を訪れ,本田さんの話をします。本田さんとは同じ部隊にいたわけではなく,ノモンハンの戦争に先立つある小規模な作戦行動の際に行動をともにしたことを話します。「岡田さんのようなお若いかたにはこんな昔の話はつまらんでしょう」と言い,「ただひとつ私の申し上げたいのは,私たちは,あなたと同じようなごく普通の青年であったということです。私は軍人になりたいと思ったことなぞただの一度もなかったのです。しかし大学を出てすぐに召集を受け,半ば強制的に幹部候補生になり,そのまま内地には戻されることなく終わってしまいました。私の人生なぞはかない夢のようなものです」と続けます。それに対し,岡田トオルは「もしよかったら,あなたと本田さんとが知り合われたときのお話を聞かせていただくわけにはいかないでしょうか」と言って,真剣に話をきく姿勢を示します。
個人的な話で恐縮ですが,僕はこのシーンが好きです。僕は毎年4月になると「今年の授業はうまくいくだろうか」と考えて緊張します。毎年,生徒との年齢差が開いていく中で,僕が歴史の授業をしたところで生徒たちは関心をもって参加してくれるだろうかと考えてしまいます。僕なりに歴史教師としての信念はあります。歴史と現在を往復することで,現在を深く理解し,それを未来につないでいくために歴史を学んでほしいと願っています。しかし,授業の中でそのような場がつくれるだろうかと4月の授業開始前の時期に心配になってしまうのです。それでも,授業が始まると,こちらが気圧されるほどの生徒の真剣なまなざしに毎年出会います。僕はそのまなざしにこたえるために,歴史の授業をつくっているのです。
間宮氏も真剣なまなざしにこたえるように長い話を語り出します。
ノモンハン事件の前年,間宮氏(当時は少尉)は参謀本部に呼ばれ,山本という男に同行して国境地帯の調査をするよう命じられます。山本は民間人ということにしていましたが,軍人であることは明らかで,情報関係の高級将校ではないかと推察されました。山本に同行するのは,大学で地理学を専攻した間宮少尉の他に,実戦経験豊富な浜野軍曹,特に実戦経験もない本田伍長の3人でした。山本はハルハ河を越えて外蒙古まで進むことを告げますが,これは明らかな国境侵犯です。モンゴル人民共和国には反ソ連派もいたので,山本がモンゴル人の内通者と連絡を取り合っているのではないかなどと推測しながら,3人は山本が戻ってくるのを待っていました。その中で,根っからの兵隊である浜野軍曹が日本の戦争への疑問を口にするシーンがあります。少し長いですが引用します。
自分は兵隊だから戦争をするのはかまわんの
です,と彼は言いました。国のために死ぬの
もかまわんのです。それが私の商売ですか
ら。しかし私たちが今ここでやっている戦争
は,どう考えてもまともな戦争じゃありませ
んよ、少尉殿。それは戦線があって,敵に正
面から決戦を挑むというようなきちんとした
戦争じゃないのです。私たちは前進します。
敵はほとんど戦わずに逃げます。そして敗走
する中国兵は軍服を脱いで民衆の中にもぐり
込んでしまいます。そうなると誰が敵なの
か,私たちにはそれさえもわからんのです。
だから私たちは匪賊狩り,残兵狩りと称して
多くの罪もない人々を殺し,食糧を略奪しま
す。戦線がどんどん前に進んでいくのに,補
給が追いつかんから,私たちは略奪するしか
ないのです。捕虜を収容する場所も彼らのた
めの食糧もないから,殺さざるを得んので
す。間違ったことです。南京あたりじゃずい
ぶんひどいこともしましたよ。うちの部隊で
もやりました。何十人も井戸に放り込んで,
上から手榴弾を何発か投げ込むんです。その
他口では言えんようなこともやりました。少
尉殿,この戦争には大義もなんにもありゃし
ませんぜ。こいつはただの殺しあいです。そ
して踏みつけられるのは,結局のところ貧し
い農民たちです。
作戦は失敗し,山本はモンゴル兵に拘束されます。山本は生きたままナイフで全身の皮膚を剥がすという恐ろしいやり方で虐殺されます。この「皮剥ぎ」はあまりにも衝撃的で,有名な場面です。読んでいる本から目をそむけたくなってしまうような残忍な場面です。間宮少尉も目を閉じるのですが,目を開けるまでモンゴル兵に殴られ続けます。そして,何度も吐き,吐くものがなくなったあとも吐き続けます。
近年では,戦争を題材としたコンテンツが「泣ける作品」として消費されることが多いと思います。記憶を消費対象として都合よく切り取る手法の増加に,僕は危機感を抱いています。しかし,村上春樹は決して戦争をそのようには描きませんでした。あえて血なまぐさい描写をすることで,読者に目を開かせ,奥底から揺さぶり,揺さぶったあとにあらわれるものを,そのようなことを経なければ向き合えない過去を,そして現在を大切にしているような気がします。
司馬遼太郎は10年以上もノモンハン事件の調査を続けながら,あまりにも絶望的な内容であることから,作品化を断念しています。すでに日本軍の致命的な欠陥がたくさん表出し,それがノモンハン事件には凝縮されていました。冷静に考えることができれば,ここで引き返すべきなのに,その後の日本はアジア・太平洋戦争で戦線を拡大し,自らの欠陥を大きな失敗につなげる道を選択します。
村上春樹がなぜノモンハン事件直前の場面をここで入れてきたのかを考察することで,この『ねじまき鳥クロニクル』はより味わい深い作品になるのではないかと思います。学び続けながら,時間をかけて理解を深められる作品を,今後も僕は大切にしていきたいと考えています。
さて,まだ第一部までしか進んでいませんが,かなり長文になりました。今回はここまでとし,第三部の歴史記述は次回扱うことにします。
②に続く
※主要参考文献は最後にまとめて記します。
