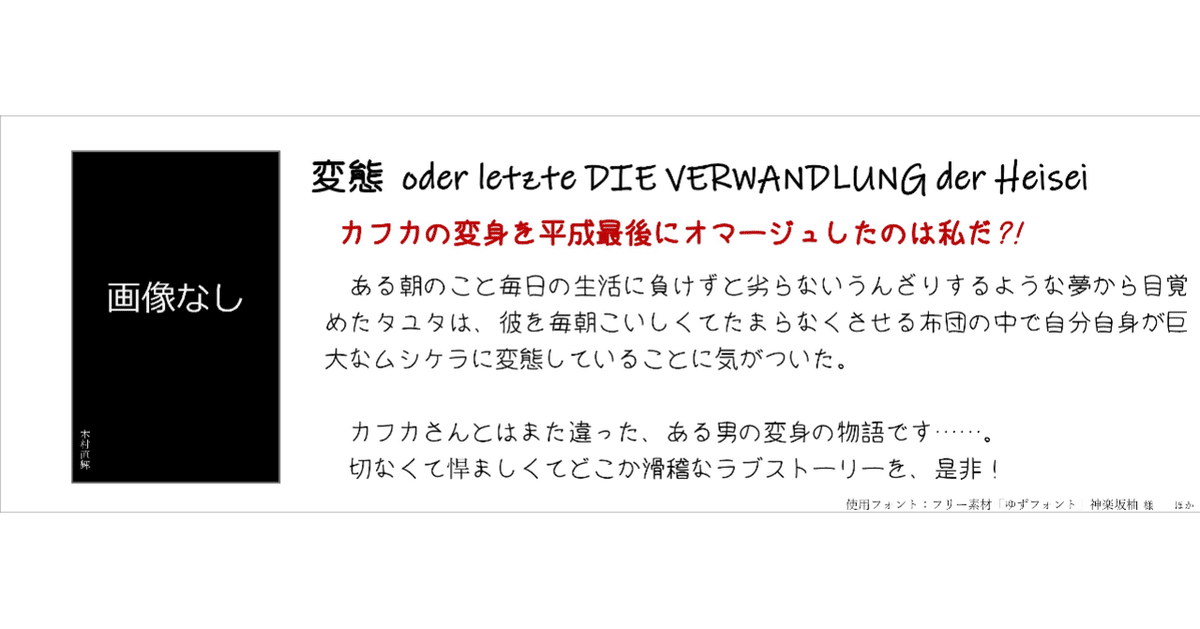
2
静かな室内にメグの鼻歌だけが響いている。
メグは彼の家でキッチンに立ち料理を作っていた。鍋の中でブラウンのスープが白い湯気を立てて煮込まれている。シンクの脇ではまな板の上に乗せられたキャベツやトマトが、色とりどりにそれぞれの大きさで切り揃えられていた。
時間は正午を周った頃。間もなくメグは手製のビーフシチューを皿に盛りつけ、ムシケラがいる部屋へと運んでいった。
「できたよ、タユタくん。ビーフシチュー、好きなんだよね?」
メグはタユタの好物がビーフシチューであることもリサーチ済みであった。
「タユタくんに、初めての手料理はビーフシチュー、って決めてたんだ。いっぱい練習したんだよ。あっ、待って、今のナシ!」
メグは慌てて発言を取り消しながら、ムシケラの突出した頭部の前に皿を置いた。皿から立ち昇る湯気がムシケラの頭を熱気で包み込む。ムシケラは頭部両脇の細い触覚をヒクつかせながら、針金のような不気味な脚をもぞもぞと動かし後退した。
「どうしたの? 美味しい、と思うよ?」
メグは皿を掴むと、床を滑らせ再びムシケラの頭部の前まで皿を運んだ。ムシケラは再び湯気に頭を巻かれ、身を縮込めるように後退する。薄気味悪く艶めく背中からわずかにはみ出した、細かな毛に包まれている腹部が壁にぶつかった。
「……食べられない、の? そっか。そうだよね。その身体じゃ、ビーフシチューなんて食べられないよね。当たり前だね。ごめん。私、こんな時にちょっと舞い上がってた。初めての手料理だったから、ずっと、ずっと憧れてた、ビーフシチュー作ってあげれるって……」
メグはうつむきがちに自分の右手を左手で握りしめ、弱々しく言葉を詰まらせる。
「……勝手、すぎたよね。ごめんね」
そう言って顔を上げたメグの表情にはもう、陰りは一つもなく、かわりに明るく微笑んでいた。その瞳は心なしか、キラキラと光を反射しているように見えた。
「待ってて。サラダもあるから。葉っぱだったら食べられるでしょ? 流石にその辺に生えてるのじゃ汚いし、キャベツだけど、平気だよね?」
そう言うとメグは慌ただしく部屋を後にし、間もなく無造作に盛りつけられたキャベツやトマトを運んできた。床の上に置かれると陶器の皿はゴトリと音を立てる。ムシケラの前にあったビーフシチューは脇に置かれ、替わりにサラダが置かれるが、ムシケラはピクリとも動かない。
「……どうしたの? もしかして、お腹空いてない?」
ムシケラは何も答えない。ただ、小さな瞳でメグをじっと見つめているだけである。メグは困ったように笑って首をかしげた。
「じゃあ、お腹が空いたら食べてね。私はちょっと、後片付けしてくるから」
そう言い残し、メグはキッチンへと引き上げていった。残されたムシケラは、一度ビーフシチューとサラダに目をやると、後は虚空をじっと見つめ思案にふけった。
メグはというとキッチンで、鍋の中に大量に残ったビーフシチューを相手にしていた。温かな湯気を吐く鍋から、おたまでシチューをすくい上げ、桜色の唇をそっと近づける。
「……美味しい」
小さく呟いたメグの目から、涙がすーっと流れ落ちた。
「……美味しいよ。……美味しい、よ……」
大好きな彼に食べて貰えない、上手く出来たビーフシチューをすすり、メグは静かに顔を濡らした。
