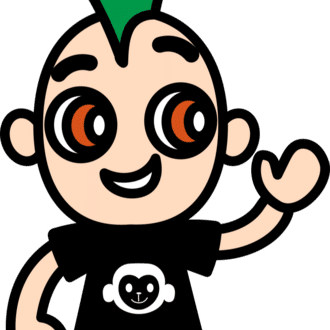ベトナムから見る日本の発達障害者のあれこれ
最近、発達障害のと言う言葉が目立つようになってきたように思います。日本にいる人と話をしても、問題のある若い人が多いというお話も。
ベトナムから見た景色として、この問題は実は産業構造と関係があるのでは?と感じることが多いので書いておきたいと思います。
(表紙は「飴売与太郎 市村羽左衛門」という浮世絵です)
結論:
「実際に増えている事もあるかもしれないが、それよりも問題として取り上げられる様になったのは社会の要求が変わった から」
欲求が代わり問題視されている、更に乗っかって違う人までレッテル貼りしてない?というのがわたしの現在の持論です。
少し前まではあまり知られていなかった発達障害
じつはゲーム業界には変わった人が集まるため20年くらい前にはすでにこうした話は話題になっていましたが、情報は海外のものがほとんどでした。
奇妙な行動をする人と、それを元にした社内摩擦やお客様からの苦情が絶えず頭を悩ませることがゲーム業界では格段に多かったです。コミュニケーションが出来ないのは当たり前ですが他によくあるのは
ルールが守れない(時間、約束)
複文・複合条件が理解できない
見えたり見えなかったりする(認知が怪しい)
など。クリエイターはそうでなくても変人が多いため『大目に見る』ということで皆が我慢してやり過ごして対処していましたが給与を払う側としては常に損失リスクを抱えるため特に締め切りが近いときなどは毎夜寝た気がしませんでした。
当時調べたときには自閉症スペクトラムも1つの見立てで他に重金属由来の自閉症問題という形で特に欧州で研究が進んでいました。日本でもBBCかどこかの海外ドキュメンタリーが放送されています。
↓の記事を読むと、現在は自閉症スペクトラムともくっついているようですね。いずれも当時は非常にマイナーな話でした。
増加した? 発達障害問題は確実に広がっている
検索をすると現在ではたくさんのコンテンツがあり、日本でも増えていることに驚きます。アフィリエイト目的で学術的な知見のない間違った情報も多いかな?という印象で、専門家の情報を探したほうが良いな、と改めて。
統計の取り方や医療のあり方が違うため、あまり正確さは無いかもしれませんがこんな統計があるようです
発達障害が多い国ランキング
— 発達障害 令和を生きる★情報と活路★ (@mirai4510) July 8, 2023
第5位:アメリカ(北アメリカ)
第4位:デンマーク(ヨーロッパ)
第3位:スウェーデン(ヨーロッパ)
第2位:イギリス(ヨーロッパ)
第1位:日本(アジア)
日本が一番!#発達障害 #ランキングhttps://t.co/Z0OInsKkNq
ベトナムでも同じっぽい、しかし…
IT営業が売りたいがために「ベトナム人は優秀」というのは嘘、というのは以前に書いたとおりです。教育システムや文化の積み上げのある国の人に優る、ましてや後進国の環境のハンデでは努力だけでは限界があります。というのは↓に書きました。あくまで仕事をする上でのパフォーマンスの話で人種や国籍の差別的な思考にならないように注意が必要ですが、広告文句は逆差別でもあり慎むべきではないのかなとは思いました。
ベトナムはまだまだ後進国で他のことも大変な環境なため、症例や研究は非常に限られているようですが、下の貴重な記事では(記事では比較はありませんが)他の国と同じくに遺伝的変異や男性の方が女性より格段に多いことも示されています。
外国人目線では日本より多そうだが…
先程のリストでもベトナムは存在せずきちんとした統計もまだ無いようです。
しかし、実際に外国人としてベトナムに暮らすと、日本より格段に多く知的障害のある人と遭遇します。 米国は正式には認めていないですが、有名な枯葉剤や米軍基地などで投棄された有害物質などで汚染があり今でも多くの先天異常を持つ人が苦しんでいるのが実情*で、知的障害のあるお子さんも頻繁に目にします。脳の異常はチェルノブイリ汚染の地域でも顕著で、特別に複雑な器官である脳と心臓の異常としてわかりやすい形で異常がでるそう。
(※米国は公式には認めていないものの実際には拒否を投じて浄化などの支援をしています。)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/asej.12265
↓気が遠くなるような規模で枯葉剤(Agent Orange)が大量散布されました

(「ベトナム戦争の長期的影響: エージェント・オレンジと30年後のベトナム国民の健康」より)
与太郎っぽい人が多い
また障害者ではなくても仕事場でも「大丈夫か」「採用した人だれ?」ということは日常茶飯事で、オフィス仕事では日本の基準では到底採用されない人だらけです。開発業務は推して知るべし。よくある会話では
「OOOは終わりましたか?」
「はい終わってます!(元気いっぱい)」
「見せてください。」
「あ、、、。まだやってませんでした。」
こんな会話は日常の範囲です。不思議と事務職のオフィスにこうした人が多く、銀行などでも頻繁に適当対応があります。全員がそうなわけでもなく、カフェなどでテキパキ働く人たちも普通にいます。
面白いのはオフィスなどでトンチンカンな問題があってもらベトナム人はことさら問題視せず「普通のこと」と振る舞っていることです。(裏ではわかりませんがそう見えます)
銀行処理などを間違えたり、知らないのに適当なでっち上げの話をしてたのがバレても悪びれる様子もありません。
ベトナムではまだ認知されていない模様
発達障害についてはベトナム社会ではまだこの問題は大きく取り上げられていないと思います。理由として考えられることは
労働需要は1次産業、2次産業が多いので目立たない
一般の人の処理能力が低いので目立たない
社会自体の効率レベルが低い(日本の1/8ともいわれています)
まあベトナムですから!という風土(ダメを気にしない)
ではないかと思います。1次産業では肉体労働、2次産業では単純作業という需要が多くあり特に農業では家族経営であるため家族内で問題が吸収されてしまうからと考えられます。三次産業では抽象概念や複数の要素の同時処理が普通なので認知能力が問われる仕事の割合がかなり大きいのと対照的ですがベトナムではまだ割合が少ないです。
日本で目立つようになったのは上記の逆の状態になった、ということかと思っています。
別の厳しい現実も
発達障害とセットでパワハラやいじめの話をよく見ます。ベトナム人同士のやり取りを見ている時に、障害者には温和でも職業や年齢、性別で厳しく当たる、というのはよく見ます。中高年のリッチ層でこれは顕著ですが若い人でも店などでかなり横柄なのは普通。日本の昭和より厳しい雰囲気です。
都市部の人の田舎や特定地域への偏見や差別も強いと聞きます。実際にお手伝いさんを雇う時に「OOO省の人なのでダメ」という話もごく当たり前です。先入観が強い古い保守的な考え方や、人権とかの細かいことよりまず拝金、という壁が高くそびえている雰囲気があります。
専門の例を見てハッとする
ベトナム人と会話をすると真円の話が正方形の話になるような、良くわからない認知や反応を見ることがありますが、認知の歪みがあるのでは?と検索していたらこんなのを見つけて驚きました。
これってかなり当てはまるんですよね。。。皆さん子供のような振る舞いなので発達障害と言えばそうかも知れませんが、大昔の生活をしている人がまだまだ多いこの地では多数派なのかもしれません。
1. 白黒思考(全か無か思考)
すべての物事に対して、白か黒か、0か100かで完全に分けて考えようとする
2. 過度な一般化(行き過ぎた一般化、極端な一般化)
自分のわずかな経験や出来事を、すべてのこととして結論づけようとする
3. 認知のフィルター(心のフィルター)
物事のネガティブな面ばかりを見てしまう
4. マイナス思考(肯定的なものの否認)
良いことがあっても、良いと思えないばかりか、悪いことにすりかえてしまう
5. 破局的な解釈
根拠がないのに、「最悪な結果」を想定し、ネガティブな結論を出してしまう。下記の2つがある
・読唇術思考:周りの人の気持ちを勝手に悪いように決めるつける
・先読みの誤り:まだ分かりようがない将来のことを悪いように決めつける
6. 過大解釈と矮小化
自分の短所を必要以上に大きく、長所を極端に小さく考える。他人に対しては、逆に良いところが大きく、悪いところが小さく見える
7. 感情の理由づけ(感情的決めつけ)
自分の感情を根拠に、ものごとを決めつけてしまう
8. 「~すべき」思考
何かをやろうとするときに「〜すべきだ」「〜すべきでない」とかたくなに決めつけて考える。自分に向くと、できなかった場合に罪の意識を感じる。他人に向くと、その通りに動いてくれなかった場合にストレスを感じる
9. レッテル貼り(ラベリング)
一度のできごと・一部の性質だけで、自分や他人のイメージを作り上げ、そのイメージを固定化させてしまう。「過度な一般化」が極端に行き過ぎた状態
産業構造の変化と受け皿の変化が犯人
ベトナムに居て強く感じたのは、日本で発達障害が問題となっているのは日本人に学校などで植え付けられたメンタリティーに起因する部分と猿の頃にすでに芽生えたと言われる本能、平等価値観です。
ベトナム政府の分かりやすい思惑
ベトナムでは留年は稀だそうで、大卒でも知識があまりなく文章作成や計算能力すらも底辺な人が多すぎるので適当にテストをやってトコロテンのように「人材」を生産して企業に売りつけている事が伺えます。
実際に新卒を採るときには先生に賄賂を支払わないとまとも(でもないですが)な学生を紹介してくれないというのは常識です。コネにもならずシガラミもない外資なら紹介の序列は低いのも間違いないでしょう。
さらに教育がないとかトラブルのある若者は研修制度などと称して海外に「労働輸出」(実際にこの言葉を使っています)をするのが国策となっています。
こうした社会要求があるなかで「問題がある子供」は存在しないほうがよく「みんな」が卒業・就職して金を稼ぐ!よっし!という事になっているようです。
日本の高度成長期、日本も同じだった?
日本でも同様のことが大規模に戦前戦後に行われ、多くの若者が農地から都市部に送られて工業に従事して「発展」しました。
日本は産業と政治が一体化している国体ですので、社会的欲求は
政財界:工場で人がほしい
役人・学校:なんとかします
という構造があったでしょう。大量に人を動員するにはムードが大切なため「みんな」で増産・金儲け、ということにして高度成長期でワイワイやる中で不都合なことには目をつぶってきた側面もありそうです。例えば留年やトビ級がないのはその大きな問題の1つでしょう。
この1つの弊害は、日本で現在問題になっている「下に合わせた制度化」となって副作用が現れているような気がします。
公立校では落ちこぼれが出ないようにスローダウン(ゆとり)
給与は能率が低いところに合わせて年功序列
損害賠償や生活保護など補償も「最低」にフォーカス
(資本主義や市場経済は本来は適者生存、競争・切磋琢磨を是としているので社会が矛盾だらけになってしまい、身動きがとれないのが今の日本かもしれません)
日本の学校問題とベトナム研修制度の類似性?
毎年卒業する生徒を、一定の仕事なら出来る人に仕立て上げて産業界や政府が若者を工場、事務職に割り当てるということが大規模に行われ、落ちこぼれが大量発生して学校での暴力や暴走族など社会問題が大量発生しました。
現在は同じことを研修制度と称して日本とベトナム政府ががやっていますが、日本は自分の過去を忘れて問題を輸入しているところに業を感じてしまいます。
発達障害が増加した2つの段階
産業構造の変化でサービス業に居場所がない人が発達障害者として目立ってくる段階と、雇用を柔軟に(派遣や一時雇用がしやすくなる)で社会に吸収させようとして「皆同じ」欺瞞をふやした段階があるように思います。

日本が転機を迎えたのはプラザ合意の1985年。それから程なくバブルが崩壊。冷戦も終わり日本を優等生にする必要もなくなり、欧米は韓国台湾中国へ生産シフトします。代わりに増えるのはサービス業ですが、この分野はコミュニケーション・抽象的なことを多く扱います。単純労働向きの人にはキツい仕事なのです。

可処分所得の推移
日本の可処分所得が順調に上がったのは90年代前半まで。
ウハウハな輸出産業が衰退しかわりとなる他の産業が出ず海外に投資したリターンや海外生産置き換えのコストダウンで衰退の穴埋めをしていたのがこの2〜30年でしょうか。

農業・工業が衰退し、派遣など雇用が変わっていくなかで可処分所得も横ばい下落していき、雇用環境や仕事が年々厳しくなっていったのが2000年以降でしょう。
こうしたことを踏まえて発達障害が増えたのではなく、元々一定数がそのような特性の人であり、この過程で企業や家庭で吸収できなくなった人が「発達障害」として社会で問題とされるようになった、と考えています。
「発達障害」というククリを産んだ「構造に宿る悪」
そもそも、発達障害という定義は的確でしょうか。
違う=障害、ということですがこれは「人間は一定以上の能力を持つ」「全員同じはずだ」「多数派が正しい」というバイアスから来ているような気がします。
前述したように、発達障害の問題を産んだ1つの原因は産業と学校が結びついて行った人間の「単一化」「平均化」であると考えています。その単一化、平均化する価値観はどこで植え付けられてしまったのでしょうか。
言うまでもなく社会ですが、学校と産業界の欲求が主な原因だと思います。生産が上がるためには「OOしよう!」を積み上げた結果の大惨事。目的は一時期、円が安く若い労働者が多かった時代には達成できたが副作用が生まれてしまった、その一つが発達障害、というアイデアかも知れません。
これについて哲学者がうまく説明しています。
天才哲学者マルクス・ガブリエルは悪には2つあり「エントロピー的な悪=破壊」と「構造に宿る悪=例えば官僚主義」と言っています。
官僚や企業の個々の人に悪気はなくても、「目的を達成する」ために目的外のことが度外視され、エスカレートするとナチスの悪行のようになる、ということをドイツ人の青年哲学者が説明しているのは皮肉なことですが、全くそのとおりだと思います。
集団心理・村のインセンティブ
工業のための学校教育批判をすると、産業や国が生産を高めるためにやったのに何が悪いのか!という短絡的・自分の利益優先の方もいるでしょうが、わたしの考えは違います。その組織、集団のプラスと個人のプラスは同じどころか利益相反があるのが普通だからです。会社は儲かっても社員が儲かることと同一ではないのと同じで、学校の先生の仕事の都合と生徒の理解度は比例するどころか反比例もあるでしょう。
利益相反が大きければ生産が上がっているようでも実際は相殺される損失があり、最終的には共産主義国のように貧乏になってしまいます。
そもそも同じくらいの人が多い前提で競争して優劣をつけよう、みたいな発想は基本「使役したい人」の都合です。経営をずっとしてきたのでこれはよくわかります。「あいつは出来るのに、お前はなんだ!」と決めつけ命令しやすいのですから好都合です。(笑
企業の利益が優先課題と信じるのは勝手ですが現代では他人に思想を押し付けたり利益のために無理強いするのは犯罪ということになっています。
俯瞰してみれば、強制労働をさせて利益を出すような企業は本質的な競争力がないので労働者の無駄遣いというものです。
組織の悪
こうした企業や組織中心の考えは封建時代やその前から根強くあるでしょうが今のように強烈になったのは産業革命後の第一次世界大戦の時期でしょう。今とは比較にならない武装と少ない人口の時代に3700万人が5年という短い期間に犠牲になりましたが、これを可能にするために「工場」「学校」「軍隊」が必要であらゆる事が戦争に向かって最適化されました。
そしてそれを世界中が真似してしまったことから、機械的に人間を作ることが当たり前の時代が2000年前後くらいまで当たり前のことととして続きます(国による)その最も純真な信者は日本でしょう。未だに当時のドイツが開発した運動会や朝礼行進、学校の集団運動競争(野球など)などで人づくりをしていますから。これらは残念ながら世界大戦のアイデアの一部なのです。北朝鮮と日本は残念ながら今も続けていますが。
サービス業や知的分野開発が富の創造に重要になってからは各国が変更し、組織論も米軍ですら逆三角形型を導入、前線の兵士の情報や判断を重視する戦略を取っています。これは損失を最も嫌うのは前線の兵士だから、という当たり前の理屈があるそうです。インセンティブが明確ということですね。
都合が悪いので攻撃しているに過ぎない
同僚の人には心中お察しして同情しますが、経営者が「発達障害」という場合には「金儲けの都合に合わないから攻撃している」に過ぎないでしょう。
一定の基準を作り、会社業務と合わなければ解雇すれば良いだけです。(労働力が足りないというのはまた別の話。金儲けしたいなら労働力が必要ない事業を作るしか無いし、作れなければ他の多数派と同じく雇われるしか無い。)
一方で国の福祉がダメで無責任に企業に押し付けたいがために解雇が難しい、という意見もあるかと思いますが、実際には日本の法律では解雇は可能(訴訟のリスク面倒さはあるでしょうが)なので解雇する経営力をつけるべきと思います。
まあそうすると今の産業構造では発達障害の人は社会との接点を失うわけですが…日本の憲法ではこれは国の責任なのでエリートが真面目に考えろ!と国民が大合唱する必要はあるのかも。税金を払って分業をしている意味がないですから。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。(憲法3章12条)
実際には国でなんとかする場合は結局税金であったりケアを誰がが分担しないといけません。嫌なら平等や幸福で文化的な生活の権利を憲法や法律からなくせばよいですが、「自分が大変なことになったら」と腰がひけるでしょう。
今の日本の問題は「国でやる=分担は嫌だ」
=>「でもいざ自分が困ったら助けてほしい」
=>「とはいえ、国に圧力をかけるとか無理」
=>「手近な経営者のせいにしよう」
くらいの感じでしょう。
日本に元々あった発達障害『与太郎』
落語には発達障害の定義とかなり似通っているキャラクター「与太郎」が頻繁に登場します。社会保障や福祉がない時代は丁稚奉公などの形で親が子供を早くから放出したり売ってしまう風俗だったため、与太郎は様々な形で街の中にも吸収されていたことが伺えます。
さらに子供の成人率も非常に低い時代であったため、成人できないケースも多かったと思われます。

人間は急に変わらない
どうしても気がついた瞬間に「変化がおきた!たいへんだ!」と反応的になってしまい、またそれを利用するメディアや広告があるため助長されてしまいます。
そもそも何百万年もかけて今の形になったのに急に変わるというのはどう考えても理屈が変です。
正規分布のように人間はバラバラな特性の人が身を寄せて生き、その特性の割合は統計である程度示されて積み上げられているのですから、安易な結論は「怪しい」と考えて、具体的な計測のもとに判断したいものです。
関連:マルクス・ガブリエル
(セールで501円だったので貼っておきます)
いいなと思ったら応援しよう!