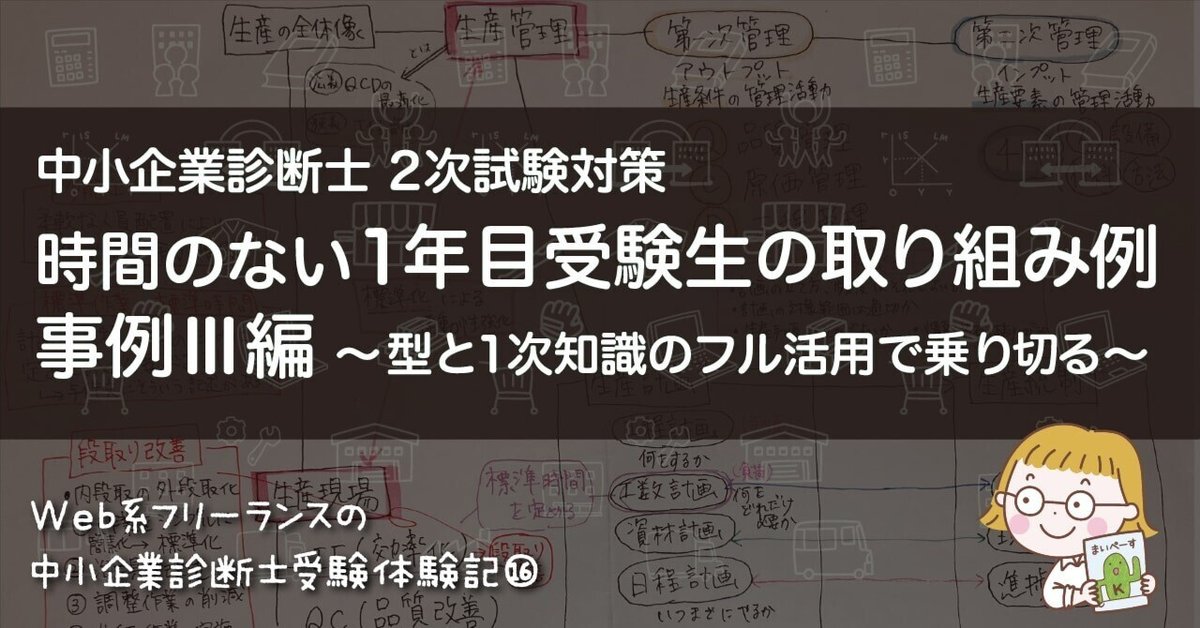
型と1次知識のフル活用で乗り切る【診断士2次事例Ⅲ】1年目受験生の取り組み例《第16話》
7月になりました。今年令和5年度の中小企業診断士試験 1次試験を受験される方は、いよいよ直前期に入ってきますね。今回の話は2次試験を見据えながら1次試験の追い込みをしたい方の参考にもなると思います。
中小企業診断士試験 2次試験対策・時間のない1年目受験生の取り組み例、最後は事例Ⅲの話です。
始めはまったく解答欄を埋めることすらできなかったところから、なんとか当落線上までもっていくためにどういう感じで知識を整理したのかをまとめました。
結果61点というギリギリでしたので、合格するためのヒントというよりは、このくらいまでもっていってようやく挑戦権獲得、くらいにお考えください。
製造業に馴染みがないと、最初は何も書けない
事例Ⅲは「生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」、つまり製造業がテーマになります。
勤務先が製造業だったり、工場で働いた経験がないと、なかなかイメージすらしづらいのが事例Ⅲのつらいところです。
かくいう私も製造業での勤務経験は皆無ですし、お取引先さんでも製造業は少ないです。
あっても製造小売業で、小売部門の方としか接していなかったりとか。
これはWeb業界の特性で、特に私が会社員でバリバリ現場を飛び回っていた2000年代後半は、下請け中心の製造業さんでWebサイトを持とうという会社さんはまだ少なかったんですね。あっても、Webサイト制作の打ち合わせは事務所でするので、実際の生産現場まで見せていただく機会はほとんどなかった、そんな時代です。
最近では、中小製造業でも自社製品を一般向けにアピールしたりとか、BtoBでも取引先さんとの関係強化とか、新規顧客開拓のためにWebサイトを活用したいと考える会社さんは増えている印象です。これは、中小企業診断士試験 事例Ⅲの与件文でよく登場する内容そのままだと感じます。
あとは、人材採用のため。製造業のWeb活用の目的としては、近年はこれが大きいですね。
ただ、私自身は元々製造業さんとのコネクションが少ないので、なかなか製造業案件のお声がかかりません。2次請け、3次請けの仕事ならたまにありますが...
ということで、製造業の中小企業様からのWebサイト制作のご相談、ぜひお待ちしております。今なら学んだ知識を活かしながら、製造現場もじっくり見て、現場スタッフのみなさんのお声も取り入れてのコンテンツ制作ができると思います。
話を戻しますが、そういう感じで製造業の現場イメージが乏しい私でしたので、初めて事例Ⅲの過去問を解いたとき、制限時間80分を大幅に過ぎてもそもそも解答欄にどんなことを書いたらよいか全くわからず、白紙のまま諦めて模範解答を見るという悔しい経験をしました。
「課題」と「問題点」の違いすらも分かっていなくて、試験問題解答のために必要なお作法から調べていく...というスタートでした。
事例Ⅲは、最も過去問が成果に繋がりやすいはず
一方で、事例Ⅲは似たような論点・問題が繰り返し繰り返し問われているのも特徴です。
他の事例でも過去問と近い論点が問われることはありますが、「まるまる一緒」ってことはまずありません。ところが、事例Ⅲは「またか」っていうの、結構あるんですよね。納期全然守れてなかったり、複数の生産方法が混在して現場が混乱していたり、ベテランの作業がめっちゃ多いのに若手は空いてたり、C社長が高付加価値製品にめっちゃ前向きだったり。
私が受験した令和4年度なんか、「設計課が2次元CADを活用」ですよ。令和2年度にも出たばかりで、私にとっては何度もやった過去問ですが、2年前なら実際に現地で解いた人も多いでしょうに。一緒すぎて「何か引っかけで裏があるのでは...」と逆に疑ってしまいました。試験委員の先生、2次元CADに親でも殺されたんでしょうか...。(解答では使いましたが、実際CADやってる人からしてみたら、「いきなり3D入れても使いこなせないだろ!しかもその金はどこから!」と言いたくなるのでしょう。Web屋にとっての事例Ⅱと一緒だと思います...)
他にも、「ロットサイズがでかい」やら「生産計画の期間が長い」やら、とにかく「見たことあるやつ!」のオンパレードだったのが令和4年度でした。とはいえ設問間の解答の切り分けが微妙に難しかったり、課の数が多くて流れを理解しながら与件文を読むのに時間がかかってしまい、最後時間が足りなくなったりと、決して簡単とは言えなかったですが、過去問をしっかりやってきた人が報われやすい年だったのかなと感じています。(だから私もギリギリ6割取れたのかなと)
今年度以降の傾向がどう変わるのか、変わらないのかは不明です。ただ、TBC受験研究会の山口先生も無料講義動画の中で「苦手な人も、勉強すれば一番伸びるのが事例Ⅲ」とおっしゃっていました。これは自分の感触から言っても本当にそのとおりだと思います。
「生産の全体像」を1次試験知識をもとに整理
事例Ⅲでも、ファイナルペーパーを作りました。
「生産の全体像」というと大げさですが、1次試験の「運営管理」は範囲がめちゃくちゃ広いので、特に2次試験で重要度が高そうな点に絞ってまとめ直したのがこちらです。

枝葉の知識としてはもっといろいろあるのですが、それは『速修2次テキスト』の抽象化ブロックシートに任せ、このペーパーでは本当に軸となる部分だけを書いています。
この図をざっくり説明すると、
「生産管理」と「生産現場」の2つの話に分ける
「生産管理」は、「生産計画」(Before)と「生産統制」(After)の2つに分ける
「生産計画」は、インプット(4M)とアウトプット(QCD)の最適化
「生産統制」は、生産計画通りに進めるための活動
「生産現場」の改善活動は、「効率化」と「品質改善」の2つに分ける
「効率化」をめざす主な活動が、IE(Industrial Engineering)
「品質改善」をめざす主な活動が、QC(Quality Control)
という形で整理したものです。
厳密には、「IEは管理にも絡むよね」とか、細かいことを言い出すときりがないと思いますが、できる限り短時間でそれぞれの設問の意図をつかみやすくなるよう、かなり簡略化した形にまとめました。
そのうえで、1次試験知識(主に抽象化ブロックシート)の再インプットを進めていきました。
例えば
受注生産と見込生産、それぞれの特徴
製品開発や設計に関する知識
需要予測や計画の立て方についての知識
トヨタ生産方式に関する知識(JITや7つのムダなど)
サーブリッグ分析や段取り改善の知識
QC7つ道具、3S、5S、ECRS
などなど。その中でも、頻出で覚えにくかったものを中心に追記し、コピーしてトイレに貼っていました。
事例Ⅲは、最も「型」と「1次試験知識」が活かしやすい
事例Ⅱの「だなどこ」と同様、ふぞろい界隈では「DRINK」という有名な語呂合わせがあります。生産管理のIT化において重視すべき点を表した言葉です。(※これも私は受験後に知ったのですが)
※D(データベース)、R(リアルタイム)、I (一元管理)、N (ネットワーク)、K(共有化)の略。
「受注・生産情報のデータベース化を行い全社一元管理し、リアルタイムに各部門で情報共有」
みたいな感じで書いとけ!ということらしいです。
他にも
「熟練工の暗黙知を形式知化するためマニュアルを作成してOJTやジョブローテーションを実施し多能工化を図り、柔軟な人員配置を可能にし設備稼働率を向上させる」
のような感じで、ある程度定型化した文章作成を練習しました。(スタディングの綾部先生の言う、「ルール集」のようなもの)
もちろん、定型文だけ覚えて合格点に達するわけではありません。
しかし、ある程度は自分の引き出しに入れておいて与件文に合わせて崩していく、という練習を繰り返すことで、80分という短時間でそこそこ戦えるレベルまで持っていくことは可能だと思います。
さらに、製造業に馴染みのない人間にとって、頼るべきはやはり「1次試験で学んだ知識」になります。どの事例も1次知識が重要といえますが、特に事例Ⅲは、1次試験用に学んだ知識が活用しやすい(というか、1次知識がないと全然話がわからない)という印象でした。
1次試験では、生産分野の点数があまり振るわなくても店舗・流通分野で稼げば合格は可能です。しかし2次試験のことを考えると、1次試験の時からある程度高得点を目指して勉強しておくというのは、悪くない戦略だと思います。
最初は苦しいかもしれませんが、逃げずにがんばってください!
ここまでの全16話で、1年間の受験体験記で書きたいことは一通り書ききりました。
次回は一旦の締めくくりということで、総括とこれから受験される方へ向けての私なりのメッセージを書きたいと思います。
質問があれば、コメントかTwitter、マシュマロにてお寄せください。
いいなと思ったら応援しよう!

