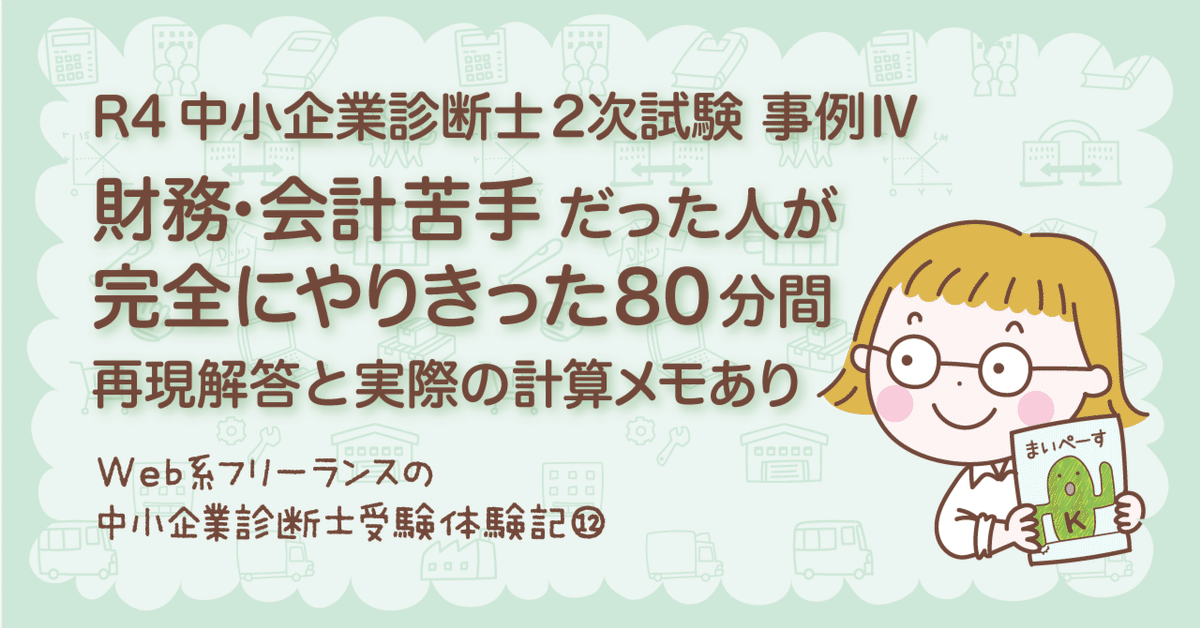
R4 中小企業診断士2次試験 事例Ⅳ〜財務苦手だった人が完全にやりきった80分間 再現解答と計算メモあり《第12話》
前回の記事で、「財務・会計が苦手でも、何とか事例Ⅳに喰らい付くために私が工夫したこと」を紹介しました。今回は、そんな準備をしていった結果がどうだったかを振り返ります。
本番の時間配分はこうだった
前回の記事でも書きましたが、本番前にイメージしていた事例Ⅳの時間配分は以下のような感じでした。
経営分析 18分
CVP 20分
投資の意思決定 30分
記述問題 7分
見直し 5分
上記はあくまで理想として、令和4年度の2次試験本番で実際に解いた順番とかかった時間はおおよそこのくらいです。
第1問 経営分析(配点25点):25分
第4問 記述問題(配点20点):8分
第2問 (1)(2) セールスミックス(配点20点):25分
第3問 (配点35点)
(1) CVP:15分
(2) 投資のキャッシュフロー・回収期間:5分
(3) NPV :2分
※厳密に計っていたわけではなので、多分このくらい、という目安値。
※実際は、解きながら別の問題に行ったり来たりしています。
80分の流れ
まず問題用紙に受験番号を書き、次に問題用紙の表紙を破りました。(※第7話参照)
ざっと全ページを俯瞰し、
第1問に経営分析があること
指標数は前年度の4つではなく、例年通りの3つであること
第4問が記述問題で、100字で20点あること
第2問がセールスミックスであること
第3問が投資の意思決定だけどめちゃ長くて最後だなということ
というのを確認し、メモしました。(実際のメモはこの記事の最後に掲載します)
そして、1−4−2−3の順で対応することに決定。ここまで約2分くらい。練習通りです。
実際に解きはじめると…
第1問の経営分析では、「生産性指標」で必要な付加価値額の計算方法が出てこないのと、優れている方の指標の選択の根拠に自信がなく時間をロス!
さらに記述部分が80字埋まらず、気付いたら25分かかってしまっていました。
記述はこれ以上悩んでも出てこないなと判断し、字数足りないけど割り切って第4問の記述問題に移動。第4問も「財務的観点から2点指摘」のうち1つが決まらず。「財務的」でないことは承知の上、強引に埋めて、もう一度第1問の記述に戻っています。
ちょっとだけ記述を足したところで、次へ。
第2問はセールスミックスで、問題集でもやっていたので粛々と解いていきます。 ※ただし、(2) は解き方間違えてるんですがこの時点ではそんなこと考える余地なし
時計とにらめっこしながら進めていて、第3問を残して残り20分ちょっと。やばいやばいと焦りつつも、3の(1)はCVPなのでここまでは取ろうと決めて集中します。
あとは、(2)(3)の(b)欄を執念で埋めて、タイムアップ。
終わった瞬間は「やられたー」、と思いましたが、合格後に振り返ってみるに、タイムマネジメントがうまくいったのかなと自己評価しています。
これは過去問などでの反復練習の成果です。
前回の記事で書きましたが、
設問の順番通りに解かない
解いてる途中でも詰まったら別の問題と行ったり来たりする
問題を何度も行ったり来たりしながら、徐々に(b)欄を埋める
といった練習をしていき、試験当日もその通りに取り組みました。
難しい問題はやっぱり解けるようにはならなかったのですが、多くの人が言う「皆が取れる問題を落とさない」というのが合否の分かれ目になることを身をもって感じました。
再現解答はこちら
雑な手書きで恐縮ですが、計算問題の再現度はかなり高いと思います。
一方、記述の再現度は低めです。特に第1問(2)は、本番ではもうちょっとしっかり文字数埋めたはずなんですけどね…。

当日現場で書いた計算メモ
こっちはなかなか書籍で見る機会も少ないと思います。私は学習中に他の人がどういうメモを書いてるのか気になっていたので、掲載しておきます。どなたかの役にたちますように。

経営分析では、いつも空欄を3分割して収益性・効率性・安全性の指標をメモしていました。この年は生産性指標の指定があり、しかも与件文全体から「明らかに劣っている」のが生産性だよ、っているのは伝わってきたため、残りの優れている2つをどれにするか検討し、与件文から根拠をまったく読み取れなかった安全性を外すことを選択。
与件文には、記述問題の根拠を探した痕跡が残っていました。ピンクのマーカーが「優れている点」、グリーンのマーカーが、第4問の記述の解答のヒントになりそうな箇所です。


今回、大事な情報である「従業員数」もメモ
単位が「万円」であることをチェック

第3問(設問1)はまず固変分解。

ほっといて第4問に集中。
前回の記事で「苦手な人はボックス図を描こう」というのを強くおすすめしました。
もちろん本番でも実践しましたよ。

第3問の(設問1)まで解いたところで計算用紙が足りなくなって、問題用紙をもう1枚破りました。

なお、結果的に78点という謎の高得点になった理由としては、第1問・第4問をしっかり埋めたことに加え、第2・3問の(設問1)、特に3(1)の412,500円を正解できたためと推測しています。事例Ⅰ〜Ⅲで貯金を全然作れていなかったので、この計算問題2問を落としていたら…と考えるとゾッとします。
ただどちらも基礎が身に付いていて、落ち着いてやれば解けるはずの問題なので、基礎練習の繰り返しは本当に大事だと思いました。
以前の記事でも
スポーツでも同じだと思いますが、「考えてから動く」んじゃ遅いんですよね。考えなくてもバットやラケットを振ればボールが飛ぶように、皆素振りをするわけです。問題を見た瞬間にパッと解き方が頭の中からでてくるかどうか、これはトレーニングです。数こなすことで克服できる話です。
と書きました。とにかく邪念がなくなるくらい基礎を繰り返し繰り返しトレーニングできていれば、当日、試験会場で「頭真っ白」って状態にはなりづらいはずです。
焦りはどうしても出る。でもパニックを起こさないように、練習する。
財務・会計が苦手な受験生の方に伝われば幸いです。
次回は、学習中に買った文具などの振り返りを書きます。
質問があれば、コメントかTwitter、マシュマロにてお寄せください。
いいなと思ったら応援しよう!

