
映画『はちどり』のこと
2020/07/12鑑賞
テレビでニュースを見るときみたいに、淡々と流れていく情景を見て、「裏側でなにがあったのだろう」と醒めた心持ちで思い巡らす、そんな感覚になった。
映画でこういう作品に出会うのは意外に思う。
なぜかというと、映画の仕事は観客を夢中にさせ「受け身」にすることだと思ってたから。そして観客を作品の中に取り込んで「能動的」にするのは演劇の仕事だと思っていたから。
解釈の幅を持たせた演出は映画でも効果的にできるのだ、と知れたのは収穫だったかもしれない。
と、一介の演劇オタクが申しております。

演出のこと
演出面で、
登場人物たちの感情に対して説明的な台詞もショットも最低限に削ぎ落とされていることが印象的だった。
まず、それぞれの人物がなにを考えているのかわからない。すごく私的な少女目線の話だから、主人公に感情移入して「わたしらしくありたい!」みたいな叫びに共鳴していくような作品だと予想していた。けど、ほんとうにみんなが何考えているのかわからない。
要所要所で主人公・ウニの顔がクローズアップされまくってたけど、喜怒哀楽のどれでも無い。
会話も少ないし、思いを吐露するようなこともない。
ドラマティックな展開など起こりようもない。
ただ淡々と、抑圧に溢れた息苦しい日常の風景が流れていく。だからこそ、さまざまな年代の、さまざまなアイデンティティを持った人が、それぞれの経験をもとに解釈を当てはめていける作品になりえただろう。
そんな「観客に解釈を委ねる」また「心の中を簡単に透かせない」姿勢は、本編中の印象的な台詞にも聞けたんじゃないだろうか。
「むやみに同情はできない、知らないから」
「顔を知っている人は何人いて、その中で心をわかる人は何人?」
人に対して真摯な作品だ。
人の心は簡単じゃないからこそ、簡単に言い表してしまわない。一緒に考えよう、と語りかけてくるような気がした。
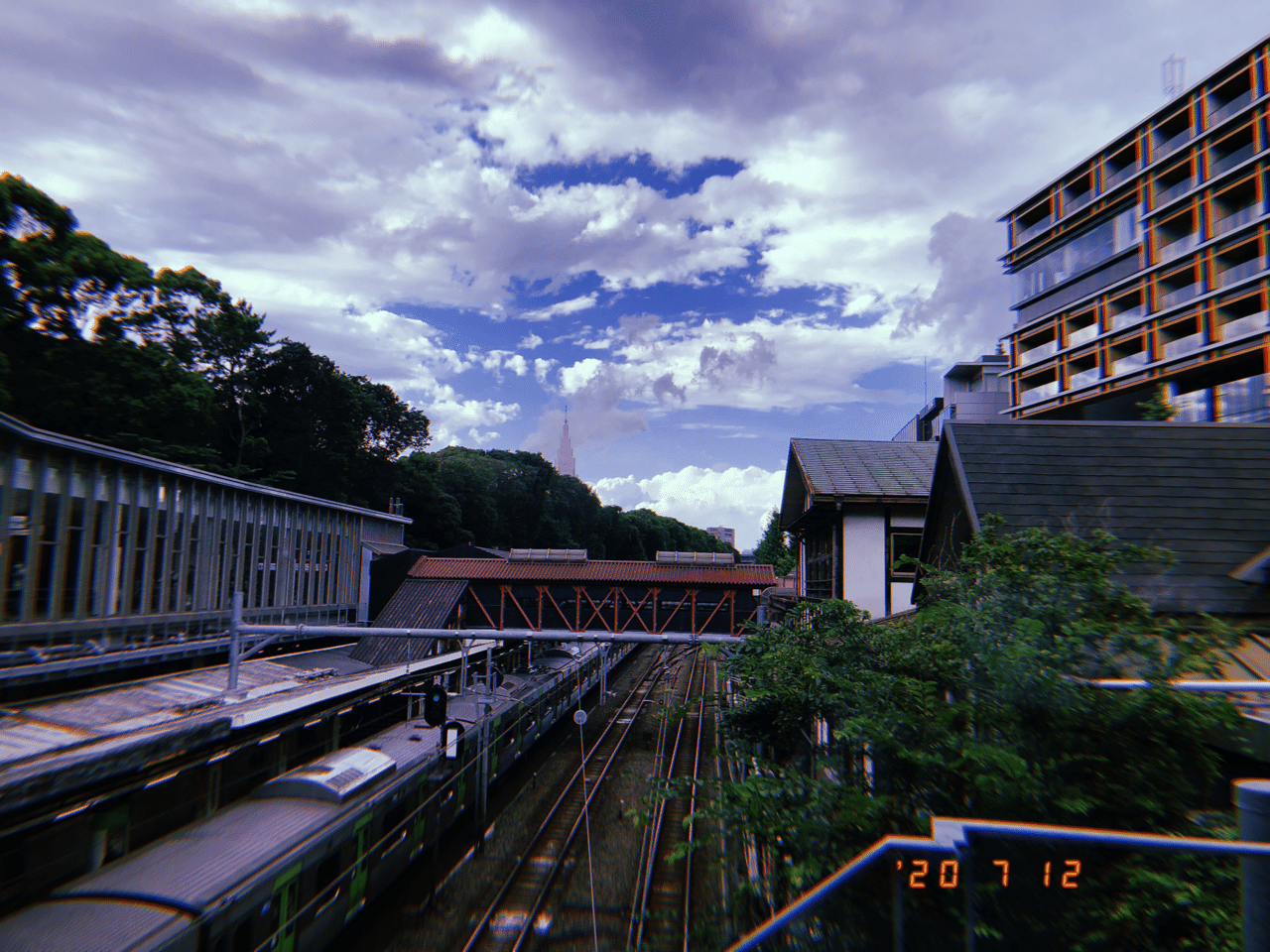
何を描いていたのか
この作品は少女目線で描かれてはいるけど、女性に限らず人間誰しも出会うだろう抑圧と、そのほころび描いた作品だとわたしは思う。
たとえば
ウニのお父さんは、いかにも亭主関白な旧時代的な人だ。家庭内の女性には暴力を振るうし、息子には「いい大学に入るいい子でないと許さない」「俺の子なんだから〜はできて当たり前」とモラハラしまくる。少女目線で抑圧を描いた作品では「悪」に分類され、抑圧の象徴として登場するのが普通。
でも、お父さんもいっぱいいっぱい。
ウニが手術で耳の裏を切開することになった時には、顔に傷がつくんじゃないかと情けなく泣き出す。いつもは大人しく殴られたり暴言を受けている母や娘が反抗してきたら、目に見えてオロオロとする。
本当はお父さんも、そんなに強い人じゃなくて、ただ家庭の中で自分を保つためや世間体のために「父」としての枠に自分を押し込めているだけなのかもしれない。
みんな、無理をしている。
お父さんだけじゃなく、お母さんも、兄も、姉も、親友も、彼氏も、それぞれに周囲から求められるものがあって、殺している部分がある。そしてそのほころびがそれぞれに見えた。
そういえば最近、
わたしの母親に「昔こんなことで怒られてわりとトラウマ!」って話したら「親も親で余裕なくてそんなこともしてしまったかもね...」と言っていた。わたしから見た母は、一人の人間である前に母として存在するような人で、食べ物の好みとか趣味とか人生とかそういう個人的なことは成人した今になって明らかになりつつあるくらいで、いつも正しくて強かった。だから母という一個人の中にある抑圧とほころびが見えたことが結構衝撃的で、映画を見ながら母のことも思い出した。
どこにでもある、誰でも経験していること。他人事には思えない。でも演出上、感情移入というわけにもいかなくて。
だからこの作品の感触は、テレビのニュースに似ていた。
父や母、妹がこの作品を見たらどう思うだろう。何を考えるのだろう。他の人の感想も聞いてみたい。そして、また時間を置いて見返したら未来のわたしは今のわたしと違うことを考えているかもしれない。
写し鏡みたいにそれぞれに形の違う人の心を見せてくれる、器の大きな作品でした。
