
子育て世代が気になる! AIのこと
こんにちは。今回の記事はMuSuBi CLUB編集部の”きなこ”がお届けします。
皆さん、「AI」と聞くと
どんなイメージをお持ちですか?
「便利!どんどん使いたい!」という方もいれば、
「ちょっと怖いな」と感じる方もいると思います。
「AI」は、誰もが毎日どこかで接したり非常に頻繁に見聞きするワード。
しかし、定義は様々のようで…
例えば、呼びかけたら答えてくれる「Siri」。
何かと便利で、スマホで使っている方も多いと思いますが、
SiriってAIなのでしょうか?
その答えは「AI」の定義によって違ってきます。
-機械学習を用いて人間が知能によって行うことができるという点では、SiriはAIである ※1。-
日頃、私たちが生活の中で接しているのは「AI技術」という意味でのAIだそう。Siriもその一つです。
私の持っていた「AI」のイメージは、
「人間の脳の働きをモデルに開発されていて、
目と同様の機能を持って見たり、耳と同様の機能を持って聞いたり、さらに人間に近づくように進化していっているんじゃない?
技術がどんどん進歩して、最終的にはほぼほぼ人間の知能ができあがるのでは?」
というものでしたが…そうではないようです。そして、
仕事がどんどんAIに置き換わって取られていくの?
子供が成長した将来、どんな状態になっているのか…
漠然と不安も感じます。

AIに関してほとんど知識がなかった私。
少しずつ勉強している段階ですが、「実像を知らなければ余計に不安になる」という思いもあり、親として知っておきたい背景や、これから子供に伝えていきたいことなど、ここで皆さまと共有していけたらと思っています!
そして、この「AI」のテーマは、ひとくくりにするには非常に大きいので、何回かに分けて記事にしていきたいと思います。
※1 参考:https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1706/04/news012.html
今回は「AI」の基本的な定義や背景と、そこから考えられることを中心にまとめます。
■ AI=人工知能で合ってる?
まず、「本当の意味でのAI」と「AI技術」は異なるということ。
AI技術のことを一般的に「AI」と呼ぶようになっているので、少しややこしくなっているようです。
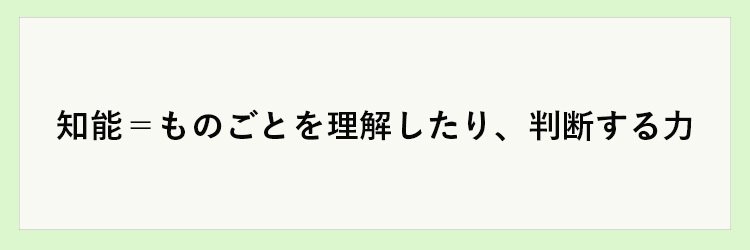
「人工知能」と言うと、厳密には自らの意思を持って知識活動を行うもの。
人工知能の目指すところは、「人間の知的活動を計算で表現するか、もしくは表現できていると私たちが認める程度まで近づくこと」なのですが、人類の知能を超える「真のAI」はまだ登場していません。※2

これに対して、「AI技術」は、上記の「真のAI」を実現するために開発される様々な技術のこと。音声認識、自然言語処理、画像処理など近年かなり発達しています。
学習して大量のデータから予測を行う、予測が外れても、学習することで軌道修正していけるのがAI技術の特徴。でも、そのレベルはまちまちで、かなり限られた条件でデータ予測を行うようなものも全部まとめて「AI」と呼んでいるのが現状です。
商品やサービスに「AI搭載!」などと書いてあると、ついつい注目してしまいますよね?
でも、ひとくくりにするには大きな違いがある状況なので、「AIだから何でもできそう!」と連想するのは危険かもしれません。
※このあとの文章では、AI技術全般のことを「AI」と呼びます。
※2 参考:新井紀子『AI VS.教科書が読めない子どもたち』東洋経済新報社
■ AIには「可能性」も「限界」もある

将棋でAIがプロに勝利したというニュースも記憶に新しいと思います。
AIの技術進歩は、ずっと順風満帆に進んできたかと言うと、そうではないようです。これまで何度かの波があって、いま私たちがいるのは「第3次AIブーム」の時代。
1950年代に「AI」という言葉が初めて登場してから、1960-70年代の第1次AIブーム、1980年代の第2次AIブームを経て、現在の3回目の波で飛躍的に進化しています。コンピューターの計算能力の向上や、インターネットの普及でビッグデータが活用できるようになったことが技術革新を後押ししました。
その飛躍的な進化は、生活の中でも実感できます。
Chat GPTなどの「OpenAI」や自動翻訳に触れるだけでも、以前とは比べ物にならないほど自然な文章をAIが紡ぐようになっていますよね…!?
今後10年でさらに高度な技術での応用が見込まれます。そして、時期の違いはあれど、いよいよ人間の能力を超えてくる可能性も予測されています。
複雑で大規模な課題にもAIが解決策を提案できるようになる世界。
より便利に、快適に暮らせるテクノロジーが生み出されて私たちの生活にも大きな変化が訪れそうです。
でも、その一方で、AIが判断を誤る可能性や倫理的な問題も無視できません。すべてAI任せで大丈夫!?
無限の可能性があるように見えるAIですが、「限界」があることも知っておきたいです。人間がしていること全てを代われるわけではない。AIにも苦手な領域があります。
参考:https://the-owner.jp/archives/11424
■ どうなるの? 子どもたちの将来の仕事

「AIの進化で、将来の仕事はどうなるの?」
これには、さまざまな意見があります。
「AIの進化で消える職業、残る職業」と言ったデータが国内外で出されたりしています。
AIにすべての仕事は置き換わっていくの?
AIによる効率化や自動化が進めば、人間がしている仕事がAIに置き換わっていくことは必須。
それなら、単純作業ではないクリエイティブな仕事や、コミュニケーション力が必要な職種に就けばいいんじゃない?と思いますよね。
しかし、どうやらそんな単純なことではないようです。広範囲で雇用のシステムが崩れれば、社会全体に大きな影響が。他の職業にも波及する可能性は避けられません。個々の職業でなく全体の問題なんですね。
その一方で、AIが普及することでこれまでになかった新しい仕事ができる可能性も大きい。子供を育てる親としては、それを安心材料にしたいところですが・・・AIにできないような仕事は、そもそも誰でもできるような仕事ではないという課題もあります。
映画製作や翻訳など、クリエイティブな現場でも既にAIが活用されています。
「積極的に活用している」、「部分的にツールとして使用する」、そして「創作にはAIを使用しない」といった幾つかの立場があるようです。
(具体的には別の記事でまとめたいと思います!)

AIは、今で言う「エクセル」のようなものだと位置付ける人もいます。
使いこなせる人は、様々な機能を使って仕事などに活用し、活用シーンも活用度も個人差があります。そしてもちろん、全員が使っているわけではありませんよね。
AIと一緒に生きる時代に突入していく中で、技術や情報に振り回される側ではなく、自分の目標や責務に必要なツールや機能をうまく使いこなせる側になっていってほしい。
そのためには自ら思考したり、理解し洞察する力を培うことが大事。
そんな風に考えると、
子どもたちの未来予想図が、少し描けそうに思いました!
■ 本の紹介

今回ご紹介するのは、池上彰さん監修の『正解のない問題集 ボクらの課題編』(Gakken)。
池上彰監修の大人気シリーズ続編『正解のない問題集 ボクらの課題編』発売! AI、格差、子持ち様などの問題について、自分で考える力をつけよう!!https://t.co/wqo7U2SIii pic.twitter.com/5ENwOliVRB
— 学研グループ公式 (@GakkenGroup) July 22, 2024
書店では児童書のコーナーにありますが、大人も楽しめます。 AIと仕事について考えるページのほか、幅広い分野のテーマが掲載されているため興味のあるページだけ拾い読みもOK。
さまざまなことに関心が広がってきたお子さんと、世の中のことや日頃ギモンに思うことを話すきっかけに。裏付けとなるデータも、必要なものが抜粋され、見やすく整理されています。
小学生、とくに中高学年なら自力で読めて、自主学習のヒントにもなりそうです♪
「正解がない」とタイトルにあるように、答えが提示されたテキストではなく、個々にさまざまな意見があるという認識を深め、思考力や理解力を培うきっかけや課題にアプローチするヒントをたくさんくれる一冊です。
ぜひチェックしてみてくださいね!
本日も最後までお読みいただきありがとうございました♪
「ふくをつむぐ。ふくをつなぐ。」
▶︎MuSuBi cotton ブランドサイトはこちら
