
【アーカイヴ】第234回/「世界に誇る日本アナログ」の組み合わせを夢想する[炭山アキラ]
先日収録した「オーディオ実験工房」では、ゲストにオーディオテクニカの小泉洋介さんにお見えいただいた。小泉さんは同社カートリッジ開発の要石というべきエンジニアで、世界最大の供給量を誇る同社だけに、「小泉さんの音作りでレコードを楽しんでいる人が世界で最も多い」といって過言ではなかろう。
小泉さんには2回分の収録に参加してもらった。1回目の収録は、2016年の発売以来世界のアナログマニアを騒然とさせてきた「ダイレクトパワー方式」発電回路を有するMC型AT-ART1000に、2018年発売の"純正"昇圧トランスAT-SUT1000ならびにフォノケーブルAT-TC1000まで、一切合切を持ち込んでいただいた。

いろいろ持ってきていただいた上、他ではなかなか聞くことのかなわない話もいろいろと伺えた。カロリーの高い放送回になったと確信している。(11月18日・12月2日放送予定)

一度自宅システムで鳴らしたことがあるが、強烈なスピード感と高解像度、
品位の高さをごく何事もないかのように表現してしまう、とてつもない器の大きさを感じさせた。「指先に載る怪物」である。
このカートリッジ、詳細を知るにつけ、キャリアの長いアナログマニアにとっては、記憶から呼び起こされる製品があるのではないか。そう、ビクターMC-L1000である。スタイラスのダイヤモンドを背の高いものにしてカンチレバーから上へ突き出させ、そこにIC技術を応用したプリントコイルを貼り付けて、直上の磁気回路へ突っ込むことで発電する、という「スーパーダイレクトカップリング」発電方式が画期的なカートリッジで、実際にも音の生々しさ、立ち上がり/立ち下がりの鋭さは類を見ないものだった。
MC-L1000は、故・長岡鉄男氏が亡くなられるまで愛用されたカートリッジとしても有名で、「先生がどこかでL1000へ言及されるたびに、必ずいくつかの販売店からオーダーが入りました」と、ビクターの昔を知る人から伺ったこともある。「アナログは、デジタルが及びもつかないハードでシャープで高解像度の音である」という長岡氏の持論は、このカートリッジの再生音とともにあった、といってよいだろう。
AT-ART1000には、そのL1000を凌駕する部分がある。前述した通り、L1000はプリントコイルを用いて発電しているが、ART1000は拡大写真を見るとお分かりの通り、スタイラスの直上にコイルが見えている。即ち、L1000が"IC"であるのに対し、ART1000は"ディスクリート"なのである。
私は両方の音を実際に聴いているが、異様なくらいの生々しさと立ち上がりの俊敏さは、両者に共通する部分として挙げることができる。一方、音の品位というか、メリハリを特に立てることなく強烈なスケール感とダイナミズムを表現することにかけては、ART1000に軍配が挙がるように思える。

アナログ全盛期でも、本機に匹敵する一刀両断の切れ味と噴出するパワー、
長岡氏おっしゃるところの「ギョッとするほどの生々しさ」を
有するカートリッジは存在しなかった。

SL-1200GAEを引っ提げて同社がオーディオ業界へ復帰した時ですら、
この21世紀にこの形へ相見えることができるとは、正直全く想像すらしていなかった。
アナログ再ブームを支えるファンの皆様と、テクニクス開発陣の尽力へ、
満腔の感謝を捧げるとともに、
現実となったこの製品を手にすることがかなわないわが身の甲斐性なさに、
切歯扼腕の思いでもある。
考えてみれば、30年以上の時を経て登場し、なおかつ価格も、往時とは売れる本数がケタ違いとはいえ、やはり数倍に上がっているのだ。この間に積み重ねられた技術の厚み、深みからも、投入できたコストからも、それは当然といってよいかもしれない。しかし、アナログが退潮の一途をたどった20年以上の歳月を経て、なおオーディオテクニカがこれだけの技術を蓄積し、それを現実に商品として世へ出すことができた、これはやはり掛け値なしに瞠目すべきことであろうと思わざるを得ない。
1個60万円を超えるカートリッジというと、もちろん簡単に購入できるものではない。私のような貧乏ライターには、5年ローンくらい組まなければとても手が出ない代物だし、何より手元の装置がそれを受け入れるだけの品位に欠ける。それで、本機をわがリファレンスとして受け入れることはとっくに諦めているのだが、それでも夢を見ることは自由である。そこで、AT-ART1000を生かし切るためにと、こんな夢想をしてみた。
わが師匠・長岡鉄男といえば、トレードマークのひとつにテクニクスのターンテーブルSP-10シリーズがあった。ご存じの通り、これも近年に復刻というか、全く新たな製品としてSP-10Rが登場してきた。残念ながら純正アームというべき同社EPA-100シリーズは、チラホラ開発中という噂が聴こえたり聴こえなかったりしているレベルだから、ここでは登場させられないが、アームにはとてつもない新作が登場してきている。そう、サエク北澤慶太氏による畢生の大作、WE-4700である。11月4日の放送で、北澤氏をゲストに迎えてWE-4700と往年の傑作WE-407/23と聴き比べも行っているので、アナログファンはぜひとも聴き逃さないようにお願いしたい。
この両者を組み合わせ、さらにサエクが開発中という巨大金属製SP-10R専用キャビネットを加えると、オール・メイド・イン・ジャパンで究極のプレーヤーが出来上がるのではないかと思うのだ。

外観は、それこそ往年のWE-407/23と「間違い探し」程度の違いしか看取できないが、
音は明らかに違う。番組をお聴きになった人なら、肌感覚でお分かりになると思う。
あくまで個人的な好みであるが、私なら一も二もなく4700を採る。
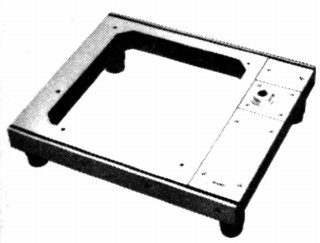
写真は最もベーシックなショートアーム1本用のSBX-7だが、
究極は藤岡誠氏が現在もお使いの特注4本アーム仕様であろう。
開発中のキャビネットがどのあたりを目指しているのかまだ分からないが、
とにかくとてつもない剛性・強度を有することは間違いないだろう。
アクセサリー系はそうだな、ヘッドシェルにヤマキ電器のアルミナセラミックス製AHS-01L、シェルリードにはKS-Remastaの太いOFC単線の上級品(商品数が多すぎて型番が覚えられない!)を採用、フォノケーブルはサエクのSCX-5000か前述のテクニカAT-TC1000か、もうちょっと贅沢をするならアコースティック・リヴァイヴのPHONO-1.2-TripleC-FMがいいかな。昇圧手段はもちろんAT-SUT1000が大いに魅力的だが、ヘッドアンプによる昇圧も捨て難い。そうなると、8月12日の番組にゲスト出演してもらったフィデリックス中川伸さんの傑作ヘッドアンプLIRICO(リーリコ)を投入すれば完璧だ。
開発中の製品もあるから価格は不明とならざるを得ないが、おそらくここまで集めると、300万円は軽くオーバーするだろう。もちろん私にとっては単なる白昼夢でしかないが、この組み合わせが実現したら、世界中のハイエンド・アナログと伍して戦うことができる、日本アナログの精粋が現出することであろう。
もちろん、わが日本の陣内には先日発表されたテクダスのエアフォース・ゼロ(何と予価4,000万円程度とか!)というモンスターもあり、文字通り上を見れば切りがないが、それでもSP-10RとAT-ART1000を中心にした前述のシステムは、結構いい線をいくのではないかと思う。すべての製品が世へ出た暁には、どなたか篤志家の方が実験してみて下さらないものであろうか。もしこの組み合わせを実現される人がおいでなら、ぜひ一度でいいからお聴かせいただきたいと、これはもう私としては手を合わせるしかない。
書き始めたら、ART1000にまつわる話題だけで結構な分量になってしまった。小泉洋介さんをお呼びしての2回目に何が登場したかは、もう大体の推測がついている人もおられようと思うが、それらについてはまた別稿に譲りたい。こちらも実に面白く、意義深い放送になるものと確信している。お楽しみに。

変哲のない四角い箱だが、これを接続した時のアナログの繊細さとパワー、
芳醇な潤いは、まさに比類がない。
中川伸さんは個人的に「天才だ!」と堅く信じているが、
今作もまたそれを証明してくれた。
(2019年10月11日更新) 第233回に戻る

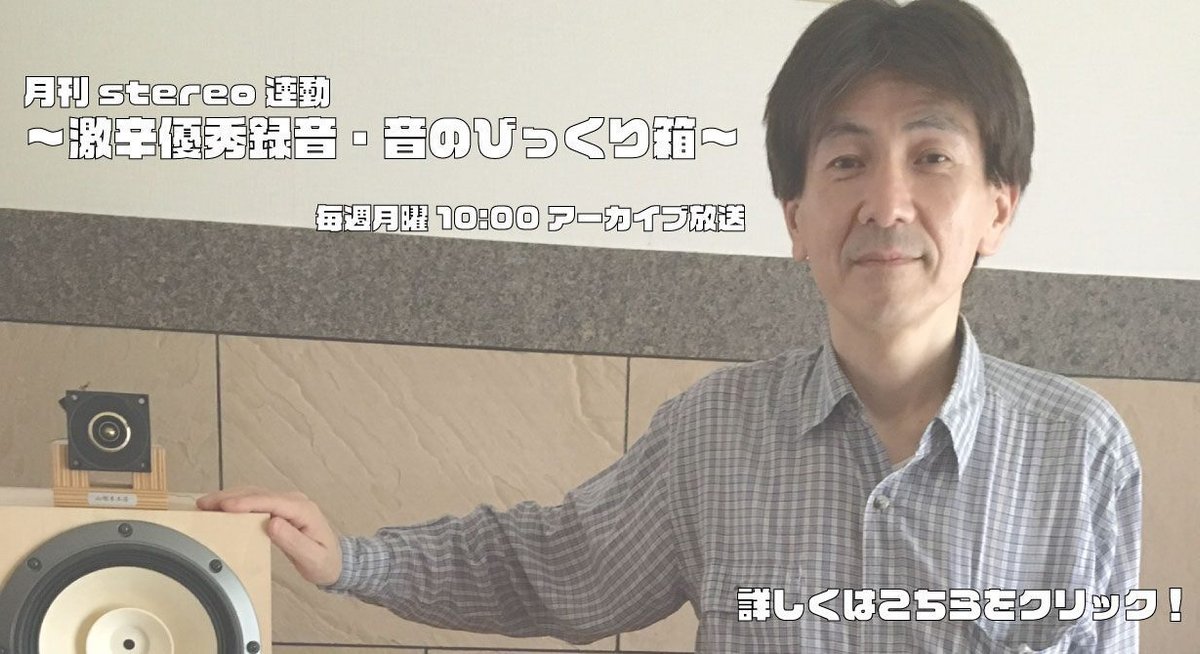

過去のコラムをご覧になりたい方はこちら

昭和39年、兵庫県神戸市生まれ。高校の頃からオーディオにハマり、とりわけ長岡鉄男氏のスピーカー工作と江川三郎氏のアナログ対策に深く傾倒する。そんな秋葉原をうろつくオーディオオタクがオーディオ雑誌へバイトとして潜り込み、いつの間にか編集者として長岡氏を担当、氏の没後「書いてくれる人がいなくなったから」あわててライターとなり、現在へ至る。小学校の頃からヘタクソながらいまだ続けているユーフォニアム吹きでもある。
お持ちの機器との接続方法
コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー
