
『釜石の風』照井翠の思索から
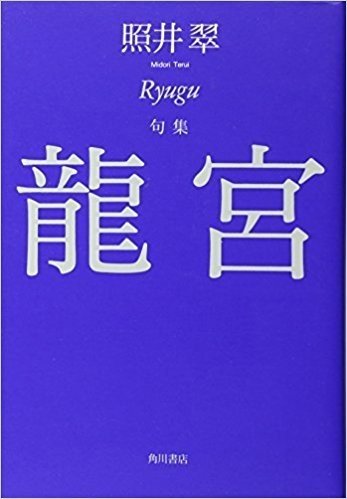
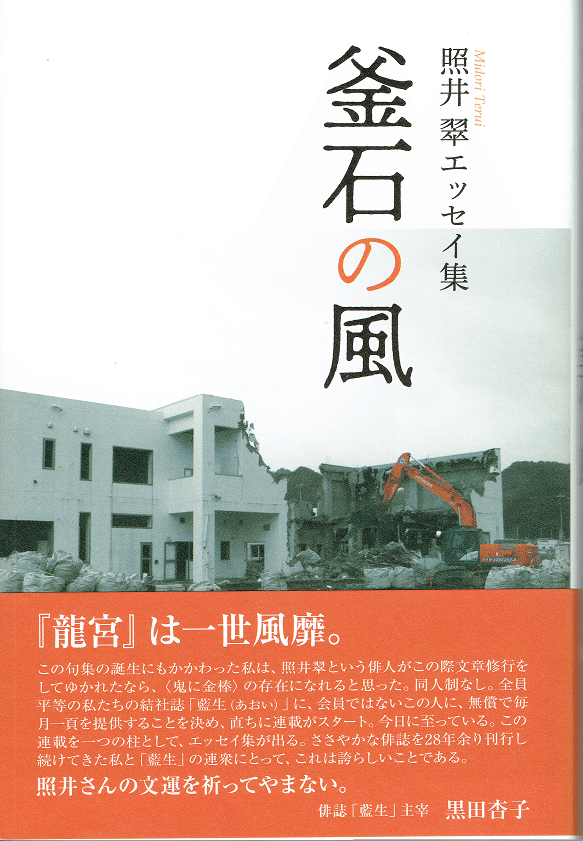
Ⅰ
「あなたに俳句があってよかった。俳句にあなたがあってよかった」
句集『龍宮』を上梓した後、照井翠の元にはたくさんの感謝の書状が寄せられたという。その中で照井がハッとさせられたのがこの詩のように書かれていた言葉だという。
その後に続く文を照井翠エッセイ集『釜石の風』(コールサック社二〇一九年三月十一日)より以下に摘録する。
※
「あなたに俳句があってよかった」の意味はよく分る。〈俳句の虚実〉があったからこそ、極限状態の中でも、私は気がふれることなく、自分自身を何とか保つことができた。実際、俳句の断片をメモや手帳に書きつけている時は、避難所での辛く重苦しい生活を忘れることができた。
※
俳句を詠むという文学的行為とは、実体験をそのまま言葉にすることではない。非被災者が根本的に理解し損ねているのは、被災者が直面したのは「言葉を失うほどの過酷な災害現場」だったのであり、並みの精神ではそのとき言葉など思いもつかない状態だったということだ。被災者たちの口からついて出たのは言葉ではなく、意味をなさない叫びだったのである。『龍宮』で「気の狂れし人笑ひゐる春の橋」と詠まれているように狂気に陥り慟哭する姿が活写されている。そんな状態の被災者に「励ましの句」を贈ろうなどということを思いつくような、合〈目的〉的な非文学的姿勢が、いかに場違いであるか解るはずだ。
そんな「言葉を失った」情況の最中に、それでも何か表現しようとするところに、文学が文学である必須条件の、自己表出に向かう心的欲求の起点がある。その起点から言葉を立ち上げ得たものが、文学的表現者となり得るのだ。
照井翠は「震災詠」であることを目的として俳句を詠んだのではない。それは結果である。言葉の真空状態という過酷な生の最中に、なんとか言葉を与えようという自己表出への思いだけが、彼女の「正気」を支えたのだ。
照井翠の『龍宮』所収の俳句は、作者の一元的な「わたくし性」に張り付いた伝統俳句的な現実の「写生」でも、作者の直接的な心情吐露などでもない。創作的〈表現の虚実〉という文学的な自己表出への心的欲求を自己の内部に奮い立たせて詠んだ俳句なのである。そうすることで彼女は凄絶な狂気を孕む惨状から、自己を立ち直らせたのだ。『龍宮』の俳句表現の内面的な強度が、同じような被災体験をした者たちの心を震わせるのだ。「あなたに俳句があってよかった」とは、その表現に立ち向かった困難と、それを乗り越えようとする意志の在処に、自分を重ねることができるからだ。非被災者の私にはその資格はない。
先に引いた照井のエッセイは更にこう続く。
※
一方、「俳句にあなたがあってよかった」とは、一体どういう意味だろう。(略)「俳句という詩にとって、照井翠という表現者がいたことは良かった」という意味なのだろうか。もしそうだとしたら、なんと有り難く勿体ないお言葉だろう。/私は加藤楸邨の俳句に深い感銘を受け、俳句表現の道に入ったのだが、その楸邨門の先輩の方から、「この『龍宮』は、二十一世紀の『野哭』(注記参照)だと思います」とのお言葉をいただいた時は、あまりの有り難さに涙が溢れた。(略)これらのお言葉を糧に、今後の俳句創作に邁進していきたいし、なお一層〈俳句の虚実〉を見据えていきたいものと念じている。
※
戦争も望まない死と受苦という言葉の真空状態を生む。楸邨の『野哭』も、その言葉の真空状態に文学者として言葉を与えようとして詠まれたという意味で、『龍宮』と文学的等価性を有する句集であると言えるだろう。
近代化の象徴企業による大量無差別殺人・殺人未遂の被害地区で、言葉を失うような体験をして育った私は、青年初期に『苦海浄土』を刊行と同時に読み、「文学に石牟礼道子があってよかった」と心から思った。そんな私なら、「俳句に照井翠があってよかった」という資格はあるのではないだろうか。『龍宮』から数句を引く。
双子なら同じ死顔桃の花
卒業す泉下にはいと返事して
流灯にいま生きてゐる息入るる
寒昴たれも誰かのただひとり
亡き娘らの真夜来て遊ぶ雛まつり
朝顔の遙かなものへ捲かんとす
注記『野哭』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『野哭』は次の言葉書きと作品からはじまる。
この書を
今は亡き友に捧げる
火の中に死なざりしかば野分満つ
戦争末期の東京で空襲の恐怖におびえながら『火の記憶』という句集を上梓した加藤楸邨は、戦後すぐに句集『野哭』を上梓する。
第一章の「流離抄」は1945年5月から1946年7月までをおさめる。
句集の冒頭の5句。
一本の鶏頭燃えて戦終る
富士の紺すでに八方露に伏す
わが家なき露の大地ぞよこたはる
かくかそけく羽蟻死にゆき人飢えき
飢せまる日もかぎりなき帰燕かな
一本の鶏頭の赤が無惨で悲惨な敗戦を象徴する。
家も焼かれ、焼け野原となった東京から富士山が見えたか。
羽蟻のような死者の姿と生き延びた者たちの飢え。
そんな地獄図の光景の中でも燕は帰ってくる。
死や霜の六尺の土あれば足る
草蓬あまりにかろく骨置かる
何がここにこの孤児を置く秋の風
死にたしと言ひたりし手が葱刻む
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅱ
蜩や海ひと粒の涙なる 翠
この句は句集『龍宮』を象徴する句として胸に刻まれている。
海嘯の合間あひまの茂りかな 『釜石の風』所収
三・一一神はゐないかとても小さい 『龍宮』所収
流灯を促す竿の撓ひをり 『釜石の風』所収
三月の君は何処にもゐないがゐる 〃
また雪の舐めてくれたる涙かな 〃
照井翠エッセイ集『釜石の風』には、『龍宮』以後のこのような句も収録されている。
「海嘯」の句のエッセイでは、この後に「人間とは、津波と津波の間に僅かに茂らせて貰っている存在なのか」という言葉が添えられている。「三・一一」の句では「冒頭で私は述べた。私達は三月を愛さないし、三月もまた私達を愛さないと。悲しみは薄まらないし、心の傷も癒えないと。(略)三年目にして深まる喪失感と絶望感に打ちのめされる」と書かれている。
言葉を失うような凄惨な被災体験という言葉の真空状態に遭遇し、それでも〈俳句の虚実〉という自己表出に向かう内なる意志を奮い立たせて、「震災後」の歩みを続ける作者の魂は、震災の記憶を希薄化するに任せている大多数の日本人と、次元を異にして生きている。
この魂の位置と真逆の位置にあるのが「復興=善」という通俗的常識である。そんな俗識が支える経済発展優先で突き進んだ「昭和」の「戦後」、その結果のバブル崩壊と停滞の「平成」、「オウム事件」、「阪神淡路大震災」、「東日本大震災」と原発事故や多数の自然災害が成長神話に留めを刺した。「復興=善」という俗識はすでに賞味期限切れの「成長神話」の残滓に他ならない。被災者に「励ましの一句」を贈ろうと思いつく考えも、この賞味期限切れの「成長神話」の残滓を引き摺る精神が言わせる言葉だ。被災者を励ますという行為は、「回復」を無条件に「善」と見做す単純思考の為せるわざだ。そのような精神の者は、この照井翠の「私達は三月を愛さないし、三月もまた私達を愛さない」「悲しみは薄まらないし、心の傷も癒えない」という言葉の前で途方に暮れるだろう。「なぜ、いつまでもそんなところに留まっているのか」と、訝しがるに違いない。「励ましの言葉」は被災者たちを「はやく立ち直れよ」と無神経に追い立てる行為なのだ。
心の傷は癒すことが善なのか。大切な人を喪った人はその悲しみからいち早く立ち直ることが善なのか。
「三月」の句には次の言葉が添えられている。
※
大切な人を喪った者は、この世の枠組みなどとうに超え、やがて魂と触れ合い始める。肉体など、何ほどの価値があるだろう。魂と対話できるようになれば、永遠はすぐそこだ。
※
大多数の日本人は震災の記憶など風化するに任せ、目先だけの「今」に縛られて右往左往し、今や東京五輪話に浮足立ち、改元騒ぎに酔いしれている。
癒されることを拒み、自己の内部深く、死者と、喪失の悲しみを抱きしめて「震災後」を歩んできた被災者の魂は、「世の枠組みなどとうに超え、やがて魂と触れ合い始め」て、「永遠はすぐそこ」という未踏の地平に足を踏み入れているのだ。大多数の日本人にはその後ろ姿は見えていない。どうやって照井翠はその地平に辿り着いたのか。
それは、震災が起こったその日、その瞬間から私たちの「日常」と照井翠たちの〈日常〉が、まったく違ったものになったことに始まる。照井翠たちは非日常が日常化する日々を、長時間にわたって体験することになる。一方、非被災地域に住む私たちは、日常のちょっとした異状を体験して、やがて元の日常にさっさと帰還してしまったのだ。
照井翠とその生徒たちはそこで何を体験したのか。
高校教師の照井と、その生徒たちは破壊尽くされた町の瓦礫と遺体の見分けも付きがたい非日常の中で、避難所生活を送っている。時間は超低速度となって遺体の回収と瓦礫の撤去が進行する永い非日常を生きた。照井たち教師は高校という学びの場を整え自分たちの力で学校に〈日常〉を作り出した。生徒たちは先生たちが悪戦苦闘して作り出した学校という〈日常〉に、遠くばらばらなった避難所から、非日常の風景の中を通って登校し、その〈日常〉を健気に「運営する」役目を果たした。生きようとする意志が作り出した〈非日常的日常〉が、先生と生徒たち共通の心の支えだったのだ。『釜石の風』で照井はこう述べている。
※
大震災の時も、避難所となった体育館には、教職員も全員いて、同じ所に眠り同じものを食べ、生徒にそっと寄り添った。私たち教師には、生徒達の〈日常〉が学校なら、その学校生活をより良いものにしていこう、この学び舎を彼らの幸せな場所にしていこうじゃないかとの思いがあった。そしてまた、私たち教師にとっても、普段通りに授業ができる学校こそが、貴重な〈日常〉だった。
※
〈日常〉とは力を合わせて作り出す「心の場」なのだ。それは照井翠の『龍宮』の深い精神性と通底する。そんな奇跡のような「場」が、あの荒涼とした被災地の中に生まれていたことを、非被災者のだれが想像できただろうか。「復興」によって土建工事で町を更地にして、「喪失」を上積みして「取り戻す日常」とは全く別のものだ。
震災直後、臨時避難所となっていた体育館に、十日前に卒業した女生徒が、在校生の安否を確認するために訪ねてきた。誰かに貰ったタオルで身体を吹いていたが、津波泥まみれのひどい姿だった。ここに来る途中、津波に呑まれて死にかけた体験をしたばかりの姿だったのである。「先生、私、津波に負けなかったよ」と「目を異様にぎらぎらさせて」告げたという。犠牲者の一人になっていたかも知れにない彼女の瞳の力を、照井翠は胸に刻みつけている。
Ⅲ
世間語と被災者たちのものごとの受け止め方が決定的に違うのは、次のようなことだ。
「復興=善」
「喪失の悲しみから早く立ち直ること=善」
という世間語的な善の感覚である。
被災現場を生きる者にとって「復興」はさらなる「喪失」でしかない。故郷は今や更地化の後、盛り土の下だ。
「悲しみから早々と立ち直れ」というのは、「死者のことなど早く忘れてしまえ」というに等しい。
心は物ではない。心はあらゆるものを内面化して、人を内側から生かしている力という作用である。だから、心の中に刻まれた死者は、その生前のすべてを含めて、恒久的現在として存在し続けるものだ。悲しみは人を内側から生かす力そのものだ。
文学は現代社会の「物象化」とも闘ってゆかなければならないが、その意志でさえ、一つの正義として幟を立てるように主張するものでもない。ただ内なる自己表出へ向かう欲求によって、自立した言語表現をしてゆくだけのものである。俳句界ではこのことが根本的に理解されていないように感じるのは私だけだろうか? 自己表出された俳句作品が、一元的な「わたくし性」を脱して何ものにも絡めとられない、普遍的な地平へと解放される瞬間の体験を、照井翠はこのエッセイで次のように述べている。北鎌倉の寺院の庵で『龍宮』の朗読会が行われたときのことだ。
※
ああ、見える、見えてくる。三月十一日の雪が、泥が、釜石が。(略)野口さん(※朗読者)の低く深い声は、此の世と異界の壁を易々と乗り越え、私は見知らぬ時空へと連れ去られる。
野口さんの声は、憑依の声、霊界の声。此の世と彼の世の「あはひ」の声。どの一句も、聴く者の魂にダイレクトに深々と届く。
異界の声による朗読を聴きながら、ふと、不思議な感覚に捕らわれた。これらの俳句の作者は、一体誰なのだろうかと。もちろん実作者は私だ。しかし私は「書いた」だけなのかも知れない。本当の作者は、非業の死を遂げた方々の御霊なのではないだろうか。
『龍宮』の作者は、誰なのだろう?
※
言葉の物象化に抗う力は、作者という固有の身体から発しながら、その個体を置き去りにする彼岸と此岸の「あわひ」で作用し、すべての魂に共有されて発現するものだ。
Ⅳ
情報は正確なときに真理となり、詩は自立したまとまりを持つときに真理となる。(E・M・フォースター 評論「無名ということ」小野寺健訳)
◇
情報については誰がどこで目撃したかが重要。だからそこには署名が必要だ。が、詩は逆。重要なのは誰が書いたかではなく、目の前の事象以上に「本質的」な世界を生みだす作品そのものであって、作者も読者もそれに「創造的」にかかわる時、作者が誰かはもはや問題ではない。文学は「無名の状態を目ざす」と英国の批評家は言う。
(朝日新聞 鷲田清一「折々のことば1383」)より。
照井翠の震災時から現在までの文学的思索に一貫している姿勢は、言葉によって命と存在の在り様を噛みしめることだったいえるだろう。そして重要なことは、フォースターの言葉を引き合いに出すまでもなく、「本質的」「創造的」な「無名」性、つまり前回述べたように、「作者という固有の身体から発しながら、その個体を置き去りにする彼岸と此岸の『あわひ』で作用し、すべての魂に共有されて発現する」という意味での「無名」性である。
※
桜は、何のために咲いたのだろう。
あの日、朝「行ってきます」と家族に挨拶したきり、帰ることのなかった人々。「あなたに会えてよかった」、「幸せでした」、「今までありがとう」、「さようなら」……。伝えられなかった言葉や念が、被災地の虚空を厚く覆っていた。呼吸をしていて、息苦しかった。
そして、ある時了解した。震災後、辛くも被災を免れて咲いた桜は、さよならを告げるために咲いたのだと。咲くことで、念を絶ち切った。咲くことが、別れだった。あの春、被災地の桜は咲かなければならなかった。亡くなった人の念を取り込み、桜は咲いた。
(『釜石の風』41「さよならを言うために」より)
※
被災地の被災桜が奇跡的に咲いたということは、確かな目撃証言があるので「真理」だといえる。だが被災遺族たちの心に「さよならを告げるために咲いた」というのは、作者の主観であり事実とは異なる。言葉が「本質的」「創造的」な「無名」性を獲得し、多くの魂たちと共有されるとき「真理」となる。照井翠の俳句と言葉はその「真理」だ。照井翠の『龍宮』に始まり『釜石の風』にいたる自己表出に一貫するのは、そういう文学的姿勢である。最後に、『龍宮』以後の照井翠の俳句を次に引く。
螢(ほうたる)や握りしめゐて喪ふ手
話すから螢袋を耳にあてよ
分かるのか二万の蟬の溺死なら
霧がなあ霧が海這ひ魂(たま)呼ぶよ
別々に流されて逢ふ天の川
滅亡の文明ほどに土盛らる
もう一人、東日本大震災の被災体験俳人に高野ムツオがいる。「俳句αアルファ」二〇一九年春号の掲載の、高野の著書『語り継ぐいのちの俳句 3・11以後のまなざし』についての、神野紗希による書評の中で、照井翠の俳句について触れた箇所があるので、その全文を転載させていただき、本稿の結びとしたい。
※
炊き出しや余震にゆるる蜆汁 熊沢れい子
仙台在住の作者が、東日本大震災句集『わたしの一句』に寄せた句だ。配られた蜆汁を啜ろうとしたら、余震が来て汁の水面が揺れた……避難所での一瞬間が切り取られている。高野はこの句を、従来は美味しい春を告げる食べ物だった蜆汁の本意に、震災の不安が加わり「季語にもう一つの面が加わって、しかも俳句に生きている」と読んだ。当時、原発事故の放射能汚染が季語の意味を変えてしまったことを嘆く論調があったが、高野は季語のまとう不安を
ネガティブに捉えるのでなく、本来の力に加え新たな面が加わったと受け取るべきだと、力強く語る。
この本は、東日本大震災以後約七年間に高野が書いた文章や講演録に、自身の震災詠百句の自解を加えた散文集だ。自他の多くの震災詠が紹介された貴重な記録であると同時に、震災を契機に俳句の言葉がどう変化したかを考察した評論文献でもある。
蜆汁の句に対する態度のように、高野は一貫して嘆かず前を向く。そして、震災を経て見えてきた俳句の本質―沈黙の力、無名の詩であることなど―を、具体的な句を挙げ、一つずつ確認してゆく。なかでも震災を経た高野が重要視するのは「想像力」だ。
泥かぶるたびに角組み光る蘆 高野ムツオ
喉奥の泥は乾かずランドセル 照井 翠
震災直後に詠まれた二句である。高野の句、実際には蘆はまだ芽吹く前だったが、自宅前の川のさざなみの光を見て、来るべき春を想像した。照井の句は一見リアルだが、高野は「喉の奥の泥というのは、たとえ亡くなった子供の姿を実際に目にしたとしても、見えるはずがありません。だから、これもやっぱり、想像力が捉えた俳句」と読み解く。
震災は、人間がいかに小さく無力であるかを突きつけた。だが同時に、だからこそ言葉の想像力が、生きる力を支えることも再確認させてくれた。
草の実の一粒として陸奥にあり 高野ムツオ
草の実の一粒である私が、ここに生きていることを詠む。言葉で生を、自己の存在を確認するあり方を、高野は俳句の根源に見る。
※
この高野ムツオも照井翠と同様、命と存在の在り様を見つめる文学的姿勢を貫いてきたといえるだろう。
それこそが、現代俳句の本来の姿ではないか。
照井翠はいち早くその原点に立ち戻っていたのだ。
非日常の中に自力で〈日常〉という「場」を作り出し、俳句を詠み続けることによって狂気の淵から生還し、命と存在の在り様を見つめる文学を創造し続けている。
照井翠がこれから向かうであろう、その向こうに、現代俳句の「明日」があることを、句集『龍宮』とエッセイ集『釜石の風』が、私たちに示している。
