
映画鑑賞の備忘録「東京物語」
「東京物語」★★★★★

小津安二郎監督の代表作。
「人情」というジャンルがある。「コメディー」「恋愛」「アクション」「ホラー」と映画には様々なジャンルがあるがその中に「人情」というジャンルがある。「ヒューマンドラマ」と云うジャンルもあるが、それとはややも異なっている、ように思う。
小津安二郎監督の世界は「人情」である。
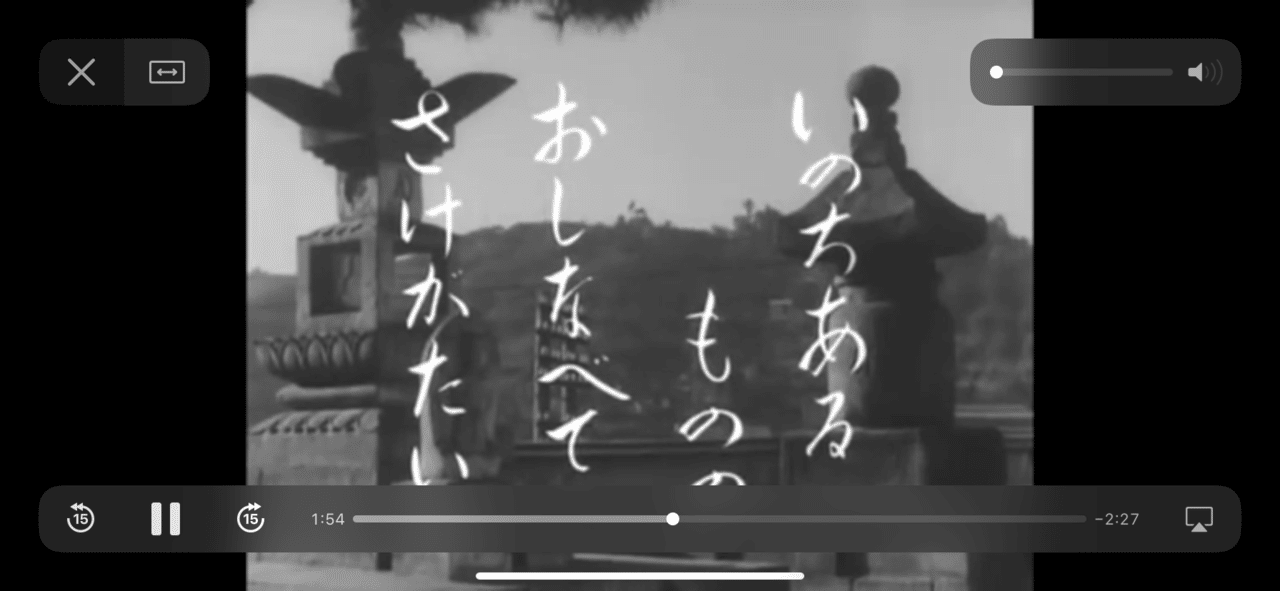


この話は落語にも通じていて、落語にも「滑稽噺」、所謂「オチ」のあるユーモアの他に「怪談噺」、「人情噺」がある。人情噺は仄かにユーモアを交えつつもほんのりと温かみのあるヒューマニズムを奏でることで観客の情愛を引き出す。
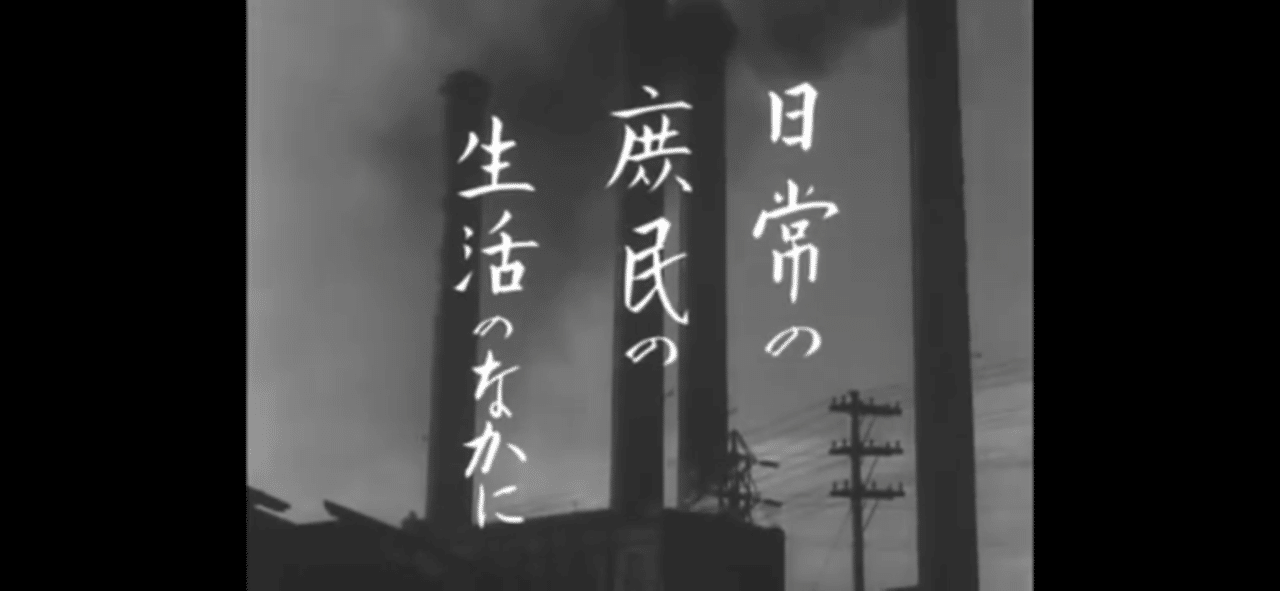

「東京物語」は岡山の老夫婦が東京に暮らす子供たちの様子を見に上京する話。老夫婦の朴訥として温厚な人柄の良さが際立つ。笠智衆最高だ。その老夫婦が子供たちから邪魔者扱いされて邪険にされて、居場所を無くしていく。だが文句など一言も言わない。文句など言ってはいけない、と彼らには鉄の意思がある。温厚である、という事は意志力なのだ。だからこその人徳なのだ。
それが憐れでならない。全編に渡って繰り広げられる哀愁の極地。これを人情と呼ばざるして何をか況や。
ストーリーとは主人公を虐め抜く事なのだと聞く。当に。本映画に於いて老夫婦への世間の仕打ちは切ない。
「東京物語」というタイトルの面白みの無さから、本作品を長らく敬遠していたが、世界に名だたる小津安二郎の代表作だけあって素晴らしい作品であった。タイトルが悪いようにも思うが「東京物語」以外のタイトルも考えられない。己が不明を恥じる。


かつて近代の日本が「家」を生活単位とする大家族制であった事に対して、親世代と同居を事にする「核家族制」が戦後日本では進行する。親は働き、祖父母は孫たちの面倒を見る、という大家族の構図が喪われゆくことの盛衰を見るようでひたすら哀しい。親の権威が喪われて世代交代していくことはハムレットなどのシェイクスピア作品にも通じる。古今東西が共通して抱く哀愁なのであろう。ちからを亡くして死ぬる自分。子を育てる、育て終わる事の世代交代を経て後は迷惑を掛けずに死ぬばかり。人間の一生はなった哀しい。だが、後続に継ぐ事の喜びもある。
小津安二郎監督作品は役者が固定されていて、作品ごとに役者が異なる芸風を披露するのが面白い。配役にも当たり外れがあるので、当の役者たちも良縁に恵まれた、と喜ぶ作品もあれば、今回の役は今ひとつ、と残念がる姿を想像できる。そうした現実世界の悲喜こもごもが小劇場的で小津安二郎作品の「温かさ」に通じる。
素晴らしい作品だった。






登場人物が悉くカメラ目線。小津安二郎の手法は映画史の中でかなりマニアックです。
舞台芸術は「客に尻を向けるな」とか観客視点で構図を決めます。そうした古き良き小劇場感覚が映画の中に生きております。
