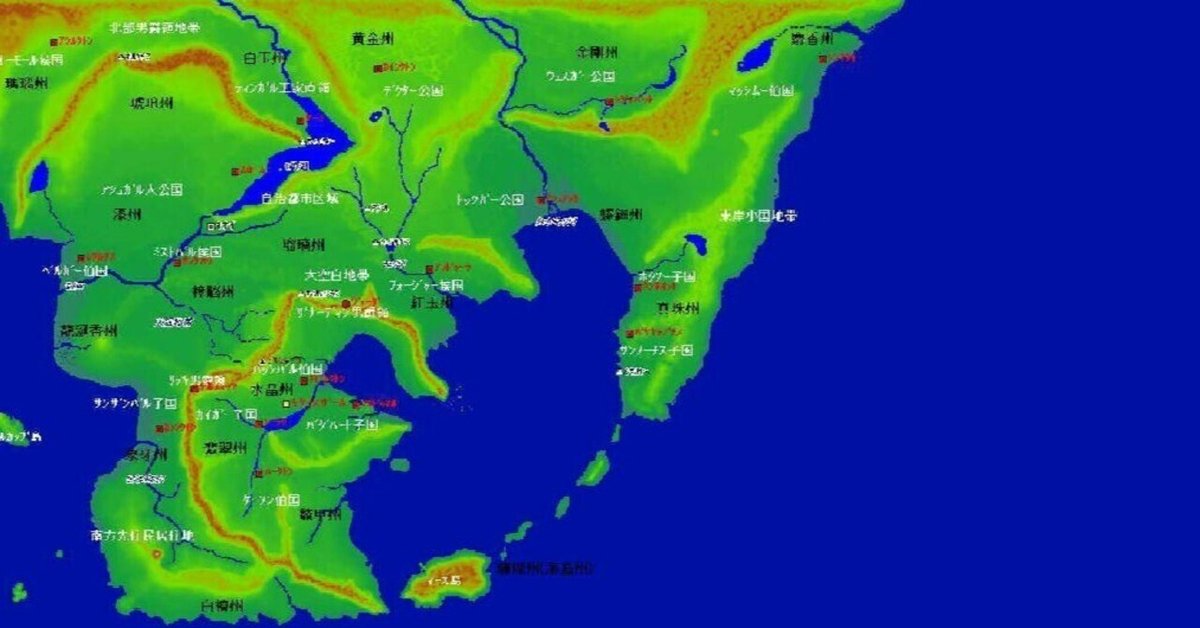
ティルドラス公は本日も多忙④ 都ケーシの宮廷で(59)
第十二章 兇刃迫る(その1)
ティルドラスの周囲の者たちにしてみれば、いったい何が起きたのかという気持ちだった。
お褒めの言葉と願い出の聞き入れがあると告げられ勇んで王のもとに向かったティルドラスが、四半時(30分)と経たないうちに放心した表情とひょろひょろとおぼつかない足取りで戻ってきて、何やら意味不明の言葉を二言三言呟いたきりへなへなとその場に座り込んでしまったのである。
余興を演じた芸人たちが呆気に取られて見守る中、とりあえず担ぎ上げるようにして彼を王宮の裏門から運び出し、そのまま馬車に押し込んで親王家へと向かう。「伯爵、お気を確かに!」「どうした、何があったんだ!」左右からティルドラスに声をかけるホーシギンとミッテル。
親王家に到着し、両側から抱えられるようにして馬車を降りるティルドラスの姿に、出迎えに出たエウロナも驚く。「ティル、どうしたの! まさか王のご機嫌を損ねでもしたの?」
「王は喜んでおられました。それなのに……、それなのに……。」焦点が定まらない眼でうわごとのように呟くティルドラス。
そのあと奥の間に集まった者たちを前に、いくらか落ち着いた彼は事情を話し始める。饗宴そのものは王のお気に召したらしいこと。実際に旧バグハート領の領有は認められたこと。だが、ティルドラスの結婚についての願い出は、なぜか王家の娘との縁談を進めるという話になっていたこと……。
「なぜだ。」さすがにミッテルも驚いた表情になる。「一体どこからそんな話が湧いてきたんだ。」
「家臣の方々が王家の姫を伯爵の正妻として迎えることを願い出ていたとは考えられませぬか。」傍らからホーシギンが口を挟む。「摂政の君にとって、伯爵がミレニア公女を正室に迎えてトッツガー家を後ろ盾とすることは決して望ましいことではないはず。その意を受けた方々が、伯爵に知らせぬまま密かに朝廷に働きかけていたとすれば……。あくまで憶測でございますが。」
「まさかそんなことが……。」目を見張るティルドラス。
「いや、大いにあり得る。」悔しげな口調でミッテルが言う。「抜かった。摂政に阿る君の家臣たちが、君がミレニア公女との縁談を進めようとするのを黙って眺めているだけだったはずがない。それに気付いて手を打っておくべきだった!」
「明日、宮廷に赴いて真偽を確かめて参ります。」ホーシギンは言う。朝廷の官吏である自分ならば、大鴻臚の府に赴いて誰からどのような願い出があったかを調べることができる。本来は監視役でもある諸侯の付き添いが行うことではないのだが、ここは自分もティルドラスのために働かねばというのが彼の気持ちだった。
翌日ティルドラスは、朝から食事も取らずに寝所にこもったままだった。ナガンとヨースタン、クリシア、そしてたまたま来ていたグロリオが心配そうに様子を窺う中、ティルドラスの周囲の者たちが親王家から出て四方に散っていく。やがて日が傾き、それぞれの情報を持って戻ってきた者たちを集めての報告が行われることになった。
「思った通りでございました。伯爵がケーシに到着されていくらも経たぬうちに、伯爵の正妻として王家の姫を迎えたいという願い出がなされております。」宮廷で経緯を調べてきたホーシギンが口を開く。「願い出を行ったのは――」
「フォンニタイか……。」ティルドラスは嘆息する。考えてみれば、サフィアが随員の中にフォンニタイを加えたのも、今回の参朝で自分たちの徒党に都合良く事が運ぶようにするためだったはず。当然フォンニタイの方でも、彼女の意を受けて朝廷への働きかけを行っていたはずである。
しかしホーシギンはかぶりを振る。「実はそうではございません。おそらくフォンニタイどのも関わってはいるのでしょうが、願い出は尚書丞であるチノーさまの名で出されております。」
「チノーが?」愕然と目を見張るティルドラス。
「その願い出を受けて、誰を君に嫁がせるかの人選も始まっている。候補の筆頭として名前が挙がっているのがルシルヴィーネ王女らしい。」今日一日、宮廷内外の事情通たちに話を聞いて回ってきたミッテルが言う。未婚で婚約もしていないゴディーザムの姪は数人いるものの、娘を遠いエル=ムルグ山地に嫁がせることに親たちが揃って難色を示しており、話がまとまりそうな人物がいない。一方、十一人いるゴディーザムの娘のうち王妃が産んだ嫡出の王女たちは伯爵では爵位が低すぎて格式に合わないという理由で候補から外されている。他の庶出の王女たちも、すでに嫁いでいたり婚約者がいたりして条件に合う者がおらず、結局ルシルヴィーネが唯一の候補として残っている状態だという。
「そんな……。」混乱した表情のまま呟くティルドラス。「だいたい、ルシルヴィーネ王女はまだあんな子供で――、しかもデクター家の公子と婚約していて――」
「その婚約が破談になりそうな動きがある。表向きの理由はハリオス公子の健康状態だ。ハリオス公子は以前から体が弱く、最近では病床に伏すことが多くなっているらしい。実際にはルシルヴィーネ王女をオーモール家の公子に嫁がせたい勤王の士連中が朝廷の内外に働きかけて縁談を破談にさせようとしているのが真相のようだがな。デクター家との縁談を進めた王女の伯父のアニコフ男爵が暗殺されたのも彼らの仕業と囁かれている。今のところ証拠は掴めていないが。」そしてミッテルは難しい顔でかぶりを振る。「厄介なことになるぞ。勤王の士たちにしてみれば、手を尽くしてハリオス公子との縁談を破談にしたところに、突然君が現れてルシルヴィーネ王女を横取りしようとしていると取るだろう。下手をすると命を狙われることにもなりかねない。」
「デクター家としても、伯爵が朝廷に働きかけて自国の公子とルシルヴィーネ王女との縁談を破談にさせたのではないかと疑いましょうな。場合によっては両国の間に無用の緊張を生むことにもつながりかねませぬ。」ホーシギンも言う。
予期せぬ事態に彼らが互いに顔を見合わせているところに、親王家の取り次ぎの者が現れてティルドラスに声をかける。「伯爵にご来客でございます。」
「今忙しいのだが、どちらの方か?」
「それが、伯爵にお会いせぬうちは名乗れぬと仰っておりまして……。ご婦人で、どうやら宮廷の方のようでございますが、伯爵の将来に関わる重要な件でお伝えしたいことがあると言付かっております。」
「誰だろう?」訝るティルドラス。
「いちおう通してみるか。昨日の今日で刺客が来るとも思えないしな。ただ、サクトルバスには付いていてもらった方がいい。」ミッテルが言った。
間もなく姿を現した来客は、ベールで顔を隠した年の頃三十前後の女性と、やはり頭巾で顔を隠した男性の二人連れだった。「ザネア=ハイマーと申します。」ベールを取って顔を見せながら女性は言う。「実は以前、籍田で遠目にお目にかかったことがございますが、ルシルヴィーネ王女の侍女を務めております。こちらは夫のチコン。」夫は大司農府の書記で、官位でいうと中の下か下の上くらいの小役人だという。
