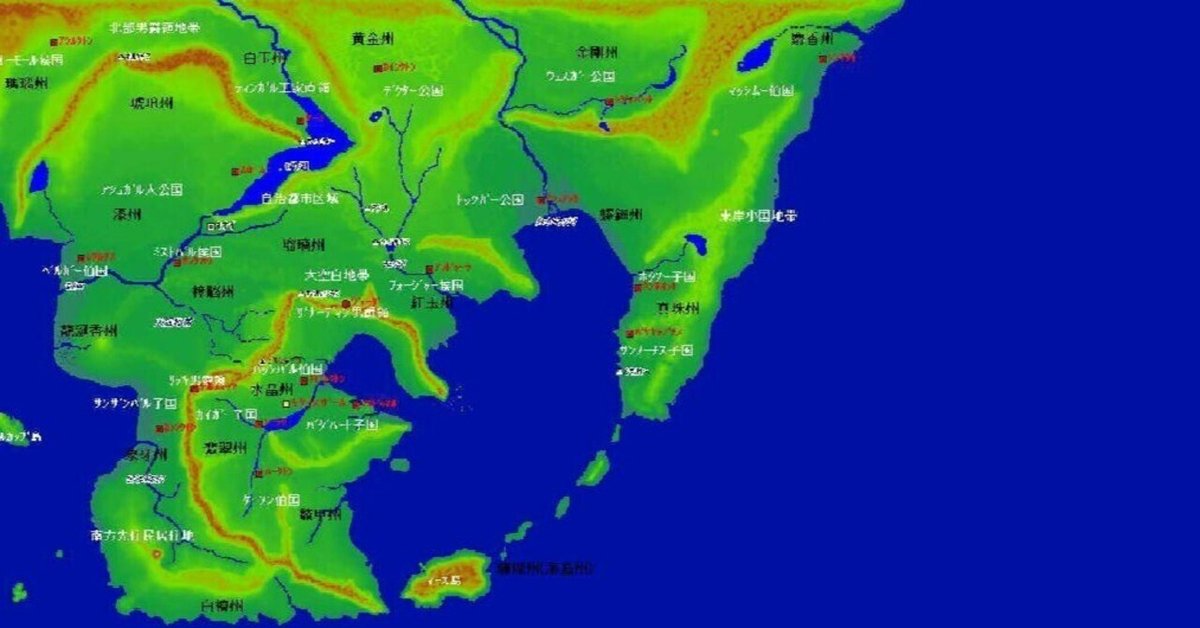
ティルドラス公は本日も多忙④ 都ケーシの宮廷で(61)
第十二章 兇刃迫る(その3)
一方、彼らが帰ったあとの親王家では、他の者たちを下がらせた奥の間で、ティルドラスがチノーと二人きりで向き合っていた。「チノー、一つ尋ねたいことがある。私と王家の姫との縁談を朝廷に願い出たか。」突然に呼び出されて戸惑った表情のチノーに、静かな、しかしどこか冷たい口調でティルドラスは訊ねる。
「それは――」チノーは口ごもる。
「お前の名前で朝廷に、王家の姫を私の正室に迎えたいという願い出があったと聞いた。それは真か。」重ねて訊ねるティルドラス。
「――仰せの通りでございます。」少しためらったあと、チノーは頷いた。
「私の気持ちは知っているはずだ。」
「存じてはおりますが……、しかし……私が思いますに……、伯爵の正室として相応しいのは、やはり王家の姫ではなかろうかと……」
「要らざることをする!」決して大声ではなかったものの、これまで聞いたことがないような怒気を含んだティルドラスの口調に、チノーは慄然とする。しばらくの沈黙のあと、感情を押し殺したようなくぐもった声でティルドラスは短く「今後、私の許しなく王宮を訪れて朝廷の官人と接触を持つことを禁ずる。――下がって良い。」とだけ言った。
ティルドラスの前を退出しながらチノーは青ざめる。どうしよう。大変なことをしでかしてしまったかも知れない。
ティルドラスと王女の縁組みの願い出だが、もともと自分の考えで行ったことではなかった。ネビルクトンを出発する直前に上司のネイカーからサフィアの意向として命じられたことである。今回のケーシへの参朝にあたって最も重要な役目と念を押されていた。ティルドラスが参朝に踏み切った目的がミレニアとの結婚に王からの口添えを得ることにあるのは分かっていたが、それとは別に王女との縁組みを願い出ることでハッシバル家の王家への忠誠心を示すことができると言われていた。実際は形だけのことでおそらく聞き届けられることはないだろうということだった。ならばティルドラスがミレニアとの縁談を進める邪魔にもならないだろうと考えていた。たとえティルドラスの本意ではないにせよ、それによってハッシバル家に対する王家や朝廷の印象が良くなるなら、結果としてティルドラス自身のためになるはずだと――。
そう、彼女も――ユニもそう言っていた。
それが予想に反して話がまとまるのが早く、昨日の小宴の後には候補者選びが始まったことを王直々にティルドラスに明かしたという。ティルドラスにしてみれば、チノーが勝手に行った願い出で、ミレニアとの縁談に王の口添えを得るという自分の目的が潰されたことになる。彼はどう思うだろうか――。
そのティルドラスは、チノーを下がらせたあと、しばらく黙然と宙を見つめながら考え込む。そこにやって来たヨースタンが、いつになく厳しい表情の彼におずおずと声をかけた。「叔父上、ジェイクソン先生がお会いしたいとのことです。」
「お通ししてほしい。」我に返ってティルドラスは答える。そういえば今日はジェイクソンが礼儀作法の指南に親王家を訪れる日だったが、しかしその彼が突然何の用だろう。
「本日は伯爵にお伝えしたいことがあって参りました。」ティルドラスの前に通され、挨拶もそこそこに慌ただしくジェイクソンは切り出す。「先日は申し上げませなんだが、実は私は古代より伝わる卜筮についても研究をしておりまして、伯爵の運勢を占わせていただきました。それによれば、近く伯爵に剣難が降りかかる兆しがございます。お気を付け下さい。」
「?」いきなりやって来てわざわざ占いの話を持ち出す彼に、怪訝な表情になるティルドラス
「お気を付け下さい。」戸惑うティルドラスには構わず、真剣な口調でジェイクソンは繰り返す。「事は伯爵が思われる以上に切迫しております。伯爵が占いを信じぬお方なのは存じておりますが、ここは何とぞ、聞き流さずにお聞き入れを。」
「――なるほど、分かりました。」少し考え込んだあと、何か合点が行ったような表情になってティルドラスは頷く。「ご忠告、感謝いたします。」
『自分が言わんとしたことを察していただけただろうか。』親王家を辞去し、輦に乗って自宅への道をたどりながらジェイクソンは考える。
最近、勤王の士たちの間に不穏な動きがあるという話が耳に入ってくる。もともとハッシバル家が戦で得た旧バグハート領を朝廷に返上しないのは王家に対する不忠であるという糾弾はマウアーが始めたことだが、それが次第に弟子たちの間で尖鋭化し、ティルドラスに対する襲撃計画まで立てられている気配さえあった。特にこの数日は、ティルドラスとルシルヴィーネ王女の縁談が表面化したことで情勢が一気に緊迫しつつある。マウアー自身も弟子たちのそうした動きを制御できずにいるようで、ジェイクソンとの会話の中でも彼らに対する困惑や不安を漏らすようになっていた。
今や状況は何が起きるか分からないところまで来ている。何も知らぬままではティルドラスの身に危険が及ぶかもしれない。かといって自分も彼らの動きを正確に掴んでいるわけではなく、とりあえず占いにかこつけてそれとなくティルドラスに警告したのだが、彼は察してくれただろうか――。
ジェイクソンの危惧は杞憂ではなかった。その日もケーシの某所では、勤王の士たちが集まって口々にティルドラスへの怒りを並べていたのである。
「ハッシバル伯爵の不敬・不忠がこれほどのものとは!」酒の注がれた椀を片手に、集まった者たちの一人が息巻いてみせる。「旧バグハート領を王に返上しようとせぬばかりかルシルヴィーネ王女までを我が物にしようと企むなど、増上慢にも程があろう!」
「昨日の小宴では、あろうことか、卑しき河原者どもを王宮に引き入れて王の御前で芸を演じさせたというぞ。」別の一人も言う。
「バグハート領のことだけであれば他国にも似たような例はあり、まだ許すこともできる。だが、オーモール家の公子にルシルヴィーネ王女を娶せて王室の藩屏とするという天下の大計を邪魔するようなら捨て置くわけには行かぬ。諸侯の地位にある者であろうと斬って、天下に正義のあることを示さねばならぬ!」
「おう! ハッシバル伯爵斬るべし!」
同じ考えの者たちばかりが集う閉ざされた空間で叫ばれる言葉は、誰一人異議を唱える者のない中で暴走を始める。しかし当人たちはそれに気付かず、今や自分たちが全世界の正義を体現する選ばれた存在であるかのような気持ちにさえなっていた。
「友らよ、その言葉に偽りはないか。」その時、一座の中から声を上げた者がいる。ジーセンだった。そもそもこの会合は彼の呼びかけで開かれたもので、事実上、彼がこの集まりの主催者である。「不義・不忠の諸侯に、身を捨てて天誅を下す覚悟はあるか。」
「おうとも。念を押すまでもないことよ!」「義のためであれば、命など惜しくはない!」口々に叫ぶ一座の者たち。
