
【序】UJDラボが出来るまで~経験の差は一生埋まらない~
こんにちワンリキー!やさいです。
先日、あごおに氏のnoteを封切にジャッジのための事例研究会、UJDラボの立ち上げを発表させていただきました。

あごおにさんの記事。概要について簡潔に書いてもらってます。
昨日はちぅさんの記事もあがっています。プレイヤー視点のお話。
僕の方では本企画をより詳細に語っていきたいと思います。あごおにさんのより具体的な記事の位置づけです。今日から何日かに分けて記事を書いていきます。序とか書いておきながら明日すぐに急を迎えるかもしれません。
序では、UJDラボを始動するに至った経緯を書きます。2019年にジャッジ資格を取得するに至った人間の葛藤をお見せできれば。
いつもよりは短く書いたつもりなんですが、ほかの二人に比べて圧倒的に長くなってしまいましたので、いつも通りお時間あるときにお付き合いいただければと思います。
知りたいのはQ&Aのその先
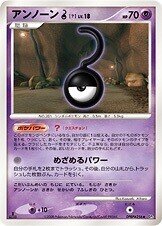
正直、普段からポケモンカードで遊んでいるジャッジであればQ&Aレベルの話でわからないことってほぼないと思うんです。もちろんその場ですぐに答えが出るというレベルを言っているわけではなく、Q&Aを確認して、ルールガイド(後掲)を参照すればどういうロジックになっているかは理解できると思っています。
特に最近のジャッジ試験を受ける方は、恒常的に自主大会等にプレイヤーとして積極的に参加していて、その上でジャッジ資格取得してみようと思う方が多い印象です。これはゼンリョク会をやらせてもらったときに強く感じました。かくいう僕自身も仲間内で頻繁に集まり練習をし、2か月ごとに行われるシティリーグに参加しています。
そうなると、それなりに普段からあれっと思ったことは自分で調べていたり、適宜上級プレイヤー用ルールガイドを確認していたりするんです。
では、何がわからないかというと、Q&A等の知識を前提に実際に現場で起こったトラブルに対してどのような対応をし、どのような裁定を下すか、という部分です。
この点に関連して、公式からペナルティクイックチャートなるものが公表されていますが、いくつかの例示があるのみで、それ以外についてはここに記載されたポイントを指標にどれくらいのペナルティを出すか判断してくださいというスタンスです。
それもそのはず。実際の現場で出される裁定につき、一つとして同じものはありません。その裁定は対戦状況に応じた複雑な事情が絡み合い、それを考慮したうえで各々のジャッジから出されております。複雑な事情、それはすなわち山札の中身を把握するタイミングがあったか、プレイエラーによるトラブルが起きたのは対戦の序盤なのか終盤なのか、そして、プレイエラーの直前・直後にはどんなカードを使っていたか、とかとか…挙げ出したらキリがありません。
そうすると、過度に「こういうときはこう」というルールを一般化してしまうことはジャッジに対して裁定の裁量を狭めることになってしまいます。裁定の裁量が認められなくなる結果、刻一刻と変化しうる対戦の事情を汲み取れない硬直した裁定が量産されることになります。もちろんこれはこれで一つの解決策だとは思いますが、公式のスタンスは少なくともそうではないようです。
じゃあすでにジャッジにやっている人たちに対して、過去のトラブルとその時に出した裁定を公開してもらえればよいのではないか。裁判例のように。そうすれば、稼働せずともそれを読んで裁定について学べますよね。よく「裁定をプレイヤーに対しても公表してくれ」という話は耳にしますし、とても良い施策なのではないでしょうか。
しかし、裁判例は判決を出す裁判官とは別に記録の役割を担う書記官さんが法廷内にいます。彼らの記録作業があって初めて全国民に周知され、後世に残る形で裁判記録が蓄積されているのです。現状、それぞれの生活があり、かつ、ボランティアで稼働しているジャッジに対して、実際に出した裁定の詳細な記録までさせるのはいくらなんでも求めすぎであり、本当にそうしようと思うのであればこれは公式が制度的に解決しなければいけない問題になります。
それに多くのプレイヤーに裁定の導かれ方が理解されていない、かつ、長い文章をまともに読める人間が少ない今の状況で裁定を公にしていくとなった場合、わかりやすい部分のみが流布してしまう恐れが高いです。つまり、その裁定を導き出されるまでに検討された事項等は捨象され、裁定だけが独り歩きする結果になりかねません。
…困りましたね。公開された裁定の記録もないのであれば、裁定を出すための思考プロセスはどこで学ぶことができるのでしょうか。

そう、もちろんこれは実際にジャッジをやってみることです。
当然といえば当然なのですが、ジャッジ制度が創設されたのは、ありえないくらい複雑な教室事例をSNSで検討するためでも、連綿と続くポケモンカードのテキストの統一的解釈を研究するためでもありません。大会等の場で生じた対戦のトラブルを適正かつ公正に治めるために公式により組成されております。したがって、実際の大会の現場でジャッジとして参加しないと養われません。
僕も過去の記事の中でこんなことを言っていました。
どんなにルールに精通して、ロジカルモンスターになったとしても、現場でしか学べないことはたくさんあります。事件は現場でしか起きないからね。
ルールというのはいつの時代も人々の生活の中で使われるために存在しているのですから、実際に使われる場所に行かないとその運用のダイナミズムは学ぶことができません。
ちなみにこの文章はまだ知り合う前のあごおにさんに刺さっていたようです。
「実際に稼働。」わかっちゃいるけど…

じゃあ実際にジャッジやればいいですよね?という話になるのですが、様々な要因からそれをするには容易でない状況になっているのが昨今です。
まず、公認ジャッジ資格保有者の増加により、ジャッジとして稼働することが狭き門となっていることです。
ご存じの通り、ジャッジの人口は受験者の拡大とともに2018年以降増加していると認識しております。直近では、大会等がことごとく中止されているにもかかわらず合わせて500人の方々がジャッジ資格・オーガナイザー資格を取得しております。内訳は公表されておりませんが、ジャッジ試験が先にオンライで売り切れましたのでジャッジ人気はすさまじかったように思います。
しかしながら、大型大会の規模は実は数年前から変わっていないようです。
そこで稼働しているジャッジの人数も多少増やしているかとは思われますが、合格者の数に比して大幅に変わっていないと考えられます。ということは、ジャッジ資格を保有して稼働を希望する人は増える続けるのに肝心のジャッジの稼働先は昔と変わらないままであれば、ジャッジ稼働できない人が続出します。
さらに言えば、大型大会では絶対に失敗できない・失敗しても最小限に抑えたいという公式側の意向があることを考えれば、新しく資格取得した人だけを登用するわけにも行きません。大型大会はジャッジ育成の場ではなく、プレイヤー第一主義の世界です。そうすると、リスク低減化のために黎明期から大会運営に携わっている方々をジャッジメンバーに入れておくことは公式の取るべきスタンスとして当然です。
大会で求められるジャッジの人数は変わっていないにもかかわらず、経験のあるジャッジの枠は公式としてもある程度確保していることを考えると、新しくジャッジ資格を獲得した人間が大型大会で稼働できるハードルはかなり高いのです。
個人的には、ジャッジを大量に合格させておいてそのような体制になっていることは公式側の制度不備も問題にあるとは思いますが、それはおいおい直していっていただくとして…
実際、私が最初に機会のあった2019年東京CLでは、新人ジャッジの稼働も許されましたが、抽選により僕は希望をかなえられず。直近で行われた2020年横浜のジャッジも抽選。悲願かなって稼働ができましたが、それでもやはり抽選に落ちてしまった人もTwitterを見る限りではいたようです。何度も抽選を通ってジャッジをやれてらっしゃる方々は豪運の持ち主だなぁと思いました。
大型大会で稼働できないのであれば、シティリーグのジャッジをやればいいんじゃないかね、という話が一つにはあります。
しかし、少なくとも僕が資格を取得した2019年のタイミングではシティリーグのジャッジ募集はとてもクローズドだったと理解しています。すなわち、店舗お抱えのジャッジ資格保有者が存在し、彼らが知り合いのジャッジに声をかけ、そのジャッジがさらに知り合いのジャッジに声をかける。基本的にはこのサイクルでシティジャッジは回っていたように見受けられます。
シティリーグの回数が2020年シーズン以降急増したため、最近でこそ多くの店舗さんや、店舗と交流があるジャッジさんからTwitter等においてジャッジ募集が多くなりました。この傾向は未経験ジャッジの人にとってとても喜ばしいことだと思いますし、今後も開かれた場所でのジャッジ募集が増えていけばいいと願ってやまないです。
とはいっても新型コロナウイルスが一向に収束を感じさせない中で「シティリーグで稼働してみましょう」というのは多様性を無視した暴論にも聞こえます。そう、これがジャッジ稼働を困難ならしめるもうひとつの事情です。
新型コロナに対する価値観やスタンスは人それぞれでありますので、この状況の中でシティリーグのジャッジとして稼働することをためらいなくできる方もいれば、ご家庭に高齢の方や小さいお子さんがいらっしゃるから自分は平気だけど人が集まるところでの活動を泣く泣く断念している方もいらっしゃると思います。
さらに、そのコロナのせいで大会およびシティリーグがキャンセルになっています。特に私は昨年開催予定だった2020年京都CLにジャッジとして稼働しようとしていたにも関わらずこのコロナによる大会中止で抽選に参加する機会すらもらえませんでした。最近でも、緊急事態宣言の有無でシティリーグの開催が流動的になっております。現状、ジャッジとして稼働できる場は当初想定よりも少なくなっています。
「ジャッジとして稼働して経験を積もう」というのは真理ではあり、新人ジャッジ全員が理解してはいるものの、上記の事情によりあまねくすべての人に対してこれを求めるのはいくらなんでも時代錯誤です。
かといっている間に、ある日突然大型大会やシティリーグが開催され、晴れてジャッジとして稼働できるかもしれません…何の準備もできてないままに。
検討の場を作る

そんな時に思いついたのがケーススタディです。
これはもともと私が参加させていただいたジャッジ研修会にて行われていたものでした。講師の方々が、この日のために準備してくださった対戦時のトラブルを実際にカードを使って実演してくださいました。それに対して6人のグループに分かれてどのようにジャッジとして進めるかをそれぞれ検討すし、代表者が実際のジャッジとなってロールプレイするというものでした。
当時これを受講したとき「これこれこれ!これなんだよ、新人が知りたいのは。これだけで一日講義してほしい!」と思ったことがあります。これがあれば公開されない裁定の導き方の思考プロセスを少しずつだとしても養っていける、と感じました。
そんな思いが前々からあって、今回、実際に企画として立ち上げるにいたりました。
事例研究である以上、現場と同じ状況を100%再現できるわけではないのですが、現場に立つ前に考えていると考えていないとでは本番で似たような事象に遭遇した時の心の持ちようが違います。そして、事例研究の中で裁定を導き出す過程で考慮した要素は、実際の現場でも意識的にプレイヤーから聴取しようと動けるかもしれません。考えた経験は決して無駄にならないはずです。
全く予想外の事例に直面したときに、現場で何が起こっているかを全く把握していない人間と多少なりとも座学で学んできた人間とでは、後者の方がより適切な解決を導き出してくれると私は信じています。
かつ、以前のジャッジ研修会と違うのは、少人数にすることで、参加者一人一人の考えを表明する機会を確保した点です。ジャッジとしてトラブルが発生したとき、そこに赴くのはまずはあなた一人です。あなたが両プレイヤーから事情を聴取し、それを前提に対戦が続行できるように適正な処理を行わなければいけません。
なので、UJDラボではまずは自分一人で考え、それを他のみんなに伝える場を大事にしたいと考えています。結局それがジャッジとして求められる役割の核にある部分と考えています。
その後にゲストの方も含めて議論します。議論することで、他の人がどこに着目してどういう裁定を出すのかも知ることができ、多様な考え方を学ぶことが可能となります。裁定に正解はありませんので、考え方の多様性を学び、自分の中の思考プロセスをより肉厚なものにしてもらうことも目的です。
もちろん大型大会やシティリーグでは、経験を積んだジャッジの方々が同じ空間にいますので、少しでも不安を感じた場合にはすぐにサポートいただける体制になっておりますのでご安心ください。
最後に

とりあえず企画始動に至った動機は上記の説明の通りです。すでに告知済みですが、第1回は3月14日(土)の10時からです。
え、なんで10時からなんですかって?
だって、「ジャッジの朝は早い」でしょ?
募集開始は3月5日(金)19時に後日掲載するフォームからお願いします。この記事を読んで共感してくださったジャッジの方々、ぜひよろしくお願いいたします。
明日は、企画そのものへの動機ではないですが、私がどうしてこういう心の動きになったかを書こうと思います。
だって今日の記事、やさいにしては刺激弱かったでしょ?明日は読んでいると思わず「うっせぇわ」が流れ出すポップでキャッチーな記事を書こうと思いますね😍
いいなと思ったら応援しよう!

