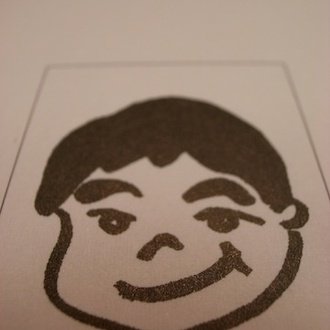Thinking about the Style of University Lessons
Covid-19による遠隔授業への対応は、オレらの講義のスタイルというか、目的みたいなものも問われている気がする。
もちろん、学生さんには、オレらが考えている講義のスタイルとか、目的が何かってことは、直接的には関係ないだろうし、たぶんほとんど伝わってないと思う。
いろいろな大学がリモート講義に舵を切っているので、インターネット上でも、ちょっと調べるとリモート講義の方法、tips、実際の講義例など、関連する様々な情報が出てくる。
にしても、それらの情報は、オレ自身にとってはなんか今ひとつしっくり来ない。。。
でも、別にインターネット上にあるそれらの情報が間違いだとか、そーいうことを言うつもりはないし、むしろ、そんなことはないと思う。
で、大前提として、大学の講義は、先生ごとに違ったっていいし、違うことこそが大学での講義だと(少なくともオレは)考えているんだけど。
たとえば、オレがいまYouTube上にアップしているのは、「企業法」という会社法を中心とした内容を扱う科目だけど、多分、実際に見学したことはないんだけど、会社法について講義しているほかの先生方の講義内容とはかなり違う気がする。っていうか、もし、同じ企業法や、会社法を担当している先生方が、オレのYouTubeの講義動画を見たら、結構な数の先生が「そんなこと(やり方)やってんの?」って思うだろう。。。でも、たぶん、企業法、会社法という名のつく講義を担当されている先生方の講義内容って、10人の先生がいたらまさに十人十色な感じがする。
で、繰り返しだけど、オレはそれでいいと思っている。だってね。科目名がつくくらいの学問領域って、多分、どの分野・領域でも話すネタはいーーーっぱいあるもんね。
だから、先生ごとにどこに重きを置き、何を話すか?ってことは違ってくるもんだし、何を到達目標に置くかってことからしても違ってくると思う。
とくに、オイラの担当している科目は、法律分野でも、比較的改正が多い方だし、次から次へと判例も出てくるし、関連する事件も次から次へと出てくる。
最近だと、外為法の改正で、安全保障上、重要な企業の株式を外国人投資家が取得する際に事前の届け出を求める基準について、持ち株比率で「10%以上」から「1%以上」に厳しくしたってニュースとか。。。
今のご時世に、一定の企業とはいえ、1%以上の取得に届け出が求められるなんてね。その背景にどんな考慮があって、それをどー捉えればいいんだろうね。。。とか考えると、このネタを話すかどうかは別として、講義の内容として入れる内容やその量は、ほんと毎年、っていうか、日々変化していくもんだよね。。。って思っている。
で、どのネタを扱うかはほんと先生次第。。。話すべき核となる内容は共通するかもだけどね。。。
こんなのわざわざ図にするのもなんだけど、講義で扱っていい内容と、実際に限られた講義時間の中で話す各先生の内容って、イメージにしたら↓な感じだと思う。

で、オレは上の図で言うと、(A、B、Cの先生が近いところを話してるとしたら)、たぶんDに近いのかな。。。ってか、本当は扱っていい内容の枠からはみ出してることもけっこうしゃべてるのかな?って思う(笑)。
で、オレが(けっこう行き当たりばったりに)話す内容を決めている基準は、学生の皆さんに、今すぐは役立たなくても、そして将来にわたっても役に立たなくても、何人かの人たちに役に立つかもしれないちょっとした「引き出し」の中身になるような講義を目指している(少なくとも)つもりだから。こう書くとちょっと偉そうだけど、要は「今ある問題が何で、それに対して、どーいう対応が現状で考えられていて、それに対してオレの意見を(主張しない程度に)ちょっとほのめかす」、それでもって、オレの専門である会社法や金商法の分野に関して「オレが講義で話したことを踏まえて、学生さんなりに、自分なりの感想とか意見を持ってもらう経験をしてもらう」ってことを考えて、(それができているかどうかは別にして)そーーなったらいいな、っていう講義をしている。
そーすると、少なくともオレの講義は「何かを一定レベルまで理解して欲しい、わかって欲しい」っていったことは到達目標にはならない。どっちかって言うと、なんか言いっぱなしで、あとは自分で考えてほしいんで放置。。。的な講義、でも、いつか俺の話を聞いた経験が何かの役に立って欲しいなぁ...っていう内容の講義になってしまう。
なので、オレみたいなスタイルの講義は、一般的なリモート講義の方法、tips、実際の講義例などがどうも自分の講義にはあまり当てはまらないような気がしている。
で、結果、人の講義録コンテンツをそれほど参考にすることなく、なるべく普段の時分のダラダラ感のある講義の感じをできる限り、リモート講義でも再現しつつやろう!って考えたら、今のところこーなった、ってのが↓
(↑なんか、映像を一部切り取って、カラグレしたサムネ。ちょっといい感じじゃない?)
ていうか、こーーいうこと書いてたら、昔、行政法の講義で、1年間のほとんどをいわゆる「悪魔ちゃん事件(Wikipediaのリンク)」を題材に「受理」について話をされていた先生を思い出した。
今はもうそーーいう授業はできない、ってよく言われるけど、個人的にはやったっていいんじゃないか?って思っている。
今でも行政法に詳しいわけではないけど、なんか物理的に書類を役所に出す行為を普通に考えたら「受理」って考えてしまうけど、それは考え方によっては「受付」で、必ずしもそうじゃないし、他方で、じゃあ「受理」をするかどうかの権限・裁量を行政機関はもっているのか?ってな問題が起こり得る、っていうことは、オレの記憶に残っている。(すいません。でも、正確にこーゆー問題意識でいいのかわかんないス...)
あと、「受理」でほぼ1年間(オレの学生時代は、基本、1年かけて4単位、っていう科目が多かった)しゃべれる先生がいるって言うことも!
オレも、ある意味、そーゆー感じで記憶が残ったり、何かの折に思い出すような講義ができたらなぁ、って思っています。
。。。ってとこまで書いて。。。
今日のnote記事は、最初は何かまとまった誰かの参考になる話を書こう!って思ってたけど、結果、まとまることなく、とりとめもなく文章を書いちゃった。。。
。。。
何にしても、もうすでにYouTube上の動画コンテンツ、最近のnote記事に対して、いろいろとフィードバックやアドバイスをくれている方も何人かいるけど、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします<(_ _)>
ちょっと前に日テレ系のanother skyで、 市川紗椰さんがメキシコに行ってて、タコスは自由だ!ってのを見て、なんか打ち抜かれた感じがして、おうちで作ってみた。
自己流でも美味かったッス!! やっぱり「自由」って大事だ!!
いいなと思ったら応援しよう!