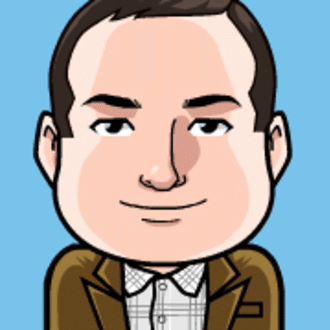水道哲学の誤解
経営の神様と呼ばれる松下幸之助翁。
松下思想の骨格となるのが、水道哲学です。
ただ、世間一般が解釈している水道哲学は、多分に誤解されすぎているかな、と思います。
というのも、本来の水道哲学は、
生産者が繁栄するための利潤を確保出来ることが前提
となっているからです。
水道哲学をもって、遍く貧しさが払しょくされる理想郷の如く受け止められる方が結構多いのですが、突き詰めて考えると、決してそうではないのです。
あくまでも、生産者が利益を得ることが出来る範囲での低価格化と一般化を謳っているのです。
では、本来どの部分で評価を得たのか?
というと、低価格の限界値をたゆまぬ努力で突破し続けていく、という姿勢にあるのです。
その本質部分がポッカリと抜け落ちた状態で広まっています。
これが私の独りよがりの解釈というわけではなく、実際に松下幸之助翁から直接教授された人たちは皆一様に
適正価格(生産者の利益確保)
を前提にしたうえでお話をされます。
そんなん常識やから、一々説明要るか?
というのが質問した時の回答ですので世間一般の解釈との乖離を痛感させられます。
この誤解を生む根源となっているのが、語源となった水道の水です。
水資源が豊富な日本では長い間、水はタダ同然のものという認識がありました。
今でこそペットボトルで水を買う時代ですが、私が子供の頃は、水を買うという感覚が皆無に等しかったのを覚えています。
松下幸之助翁の述懐でも、他人が自宅の水道水をがぶ飲みするのを平然と許す姿を見て水道哲学が組み上がっていった、とされています。
この述懐が「タダ乗りOK感」を感じさせ過ぎなのも問題ですよね。。。
喩える対象がタダ同然のものだったため、生産物もタダ同然になっていくものとして世の中に受け止められたのです。
そんなわけないよ
という反論があるかもしれません。
ですが、水道哲学は誤解された格好で、松下電器産業に襲い掛かってくることになります。
消費者サイドの意向を代弁する形になるのが、ダイエーの中内功氏です。
のちに、ダイエー・松下30年戦争とまで言われました。
希望小売価格から15%以上値引きする格好で販売をしたことに端を発したいさかいです。
そもそも、中内功氏のモットーは、
「人の幸せとは、まず、物質的な豊かさを満たすことです」
としているように、松下幸之助翁の水道哲学と同根、同じ視点から始まっています。
そこから消費者目線での価格破壊を志向したのが中内氏。
生産者の利益確保を前提とした上での低価格化を志向したのが松下氏。
です。両者の原点は非常に近いのですが、消費者目線であるか?
生産者目線であるか? の違いにより、大きな対立を生んでいくことになるのです。
どちらの考え方も、世界規模で大量生産・価格破壊を推し進める以上、いずれは生産者が破綻するところまで価格が下がってしまうわけです。
需要を度外視し、供給力を強化し続ける考え方だからです。
価格は需給バランスで決まるものである以上、大量生産で安さを追い求め続けると価格破壊が生じてしまうのは理の当然なわけです。
二人に欠けていたのは、
足るを知る
の精神です。
本来、不要なものは作らないことが、製造業における究極の社会貢献になるのです。
そういう意味では、トヨタのプル生産方式は正しいのです。
水道哲学はプッシュ生産で人類すべてにモノが行き渡るまで拡大し続ける考え方だったため、こうした問題を孕んでいたわけです。
だから、私は水道哲学は誤解を生じさせやすく、かつ、プッシュ生産では地球全体に良くないから問題が多い哲学であると考えています。
日本では、水道の水は盗まれても怒らないほどありふれたものでした。
そのありふれたものを目指すという姿勢と適正利潤の確保は相容れないのです。
なぜなら、価格は需給バランスで決まるものだからです。
奇しくも、消費者目線(需要側)の中内功氏 と 生産者目線(供給側)の松下幸之助翁が対峙することになったのが、証拠です。
どこででも簡単に入手可能なものをつくってしまえば、適正利潤を維持できるわけが無いのです。
大量生産のツケとして、企業は在庫一斉処分によるたたき売りで保管管理料の圧縮を図るしか道は無くなります。
やがて、消費者は在庫セールの利得を学んでしまい、在庫セールでしかモノを買わなくなってしまいます。
服飾業界が典型的なんじゃないでしょうか?
もちろん、流行に敏感な人が高額で先に購入してくれますので業界的にはそれで成り立ってきましたが・・・
そういうのを破壊したのが、ユニクロとかしまむらの立ち位置でしょうか。
いずれにせよ、日本人に強いデフレマインドを植えこんだのが水道哲学であると言えるでしょう。
我々日本人は、
より良いモノを より安く
でやってきたわけですし、それを世界に推し進めすぎてしまったわけです。
近年になって、下記の記事のように、それではマズイという意見が見受けられるようになってきました。
それでもマダマダといったところでしょうか。
さて。松下幸之助翁が目指した水道哲学は、本来はこういった安さこそ正義という考え方とは別物です。
冒頭でもお話したように、
生産者が適正利潤を得た上での安さの追求
という大前提があるからです。
別物なのですが、理念や哲学により生み出されるものが原初の理想を失っていることは往々にして発生します。
マルクスの資本論なんかが代表例でしょうか。
哲学や理念は、
他人の手に渡ると、際限なく原理主義的になるか?
換骨奪胎され違うものになるか?
本人の志向したものとかけ離れた点で批判されるか?
こういった風に予期せぬ方向に転がる危険性を孕んでいます。
どんなに丁寧に説明を施したとしても、読者側が自分に都合が良い部分だけを切り取って使ってしまい、それが大勢を占めれば、そういうものだと再定義されてしまうからです。
そうそう。三波春夫さんが言った
お客様は神様です。
なんかも、言葉(理念)が独り歩きした事例でしょうか。
歌う時に私は、あたかも神前で祈るときのように、雑念を払ってまっさらな、澄み切った心にならなければ完璧な藝をお見せすることはできないと思っております。
ですから、お客様を神様とみて、歌を唄うのです。
また、演者にとってお客様を歓ばせるということは絶対条件です。
ですからお客様は絶対者、神様なのです
三波春夫さんの思いを飛び越えて、
お客様のどんなワガママも聞き入れなければならない、という格好で広まってしまいましたが、本来は、神前で歌うかの如く心を澄み渡らせるために、お客様を神様に見立てて歌う、というものでした。
いかに、理念を人に伝えることが難しいかの好例ですね。
さて、水道哲学の締めくくりですが・・・
そもそもモノが行き渡る世界が、本当に人類の幸福に繋がるのか?
仮に行き渡るようになれば、生産者はどのような立場になるのか?
松下幸之助翁は、そこまで思考を巡らせたでしょうか?
直接話が出来ていたら、そう尋ねていたかもしれません。
モノというのは、使う人が価値を感じ、大事に使えるモノであればイイのです。
高い安いを判断するのは消費者であり、価値を感じれば年収の何倍の価格であっても買います。
価値を感じなければタダでも要らない、となります。
つまり、価格・価値の多様性です。
しかしながら、松下幸之助翁は、値ごろ感という表現を使い、
「消費者全て」が安いと感じる価格設定
に照準を置いてしまいました。
ここに水道哲学の失敗がある、と私は見ています。
時代は進み、日本ではモノが溢れかえる時代になりました。
世界レベルで見た場合、モノがあふれかえるにはマダ遠いので、松下幸之助翁が目指した世界には届いていないかもしれません。
ですが、時代は大きく転回し、今は、
必要と感じる人が必要と感じるものを適正な価格で購入する
そういう時代になったのではないでしょうか?
残念なことに、日本人の多くはいまだに水道哲学や中内功哲学の影響下にありデフレマインドを保有し続けています。
まだ何世代かは、このままなんでしょうか・・・
いいなと思ったら応援しよう!