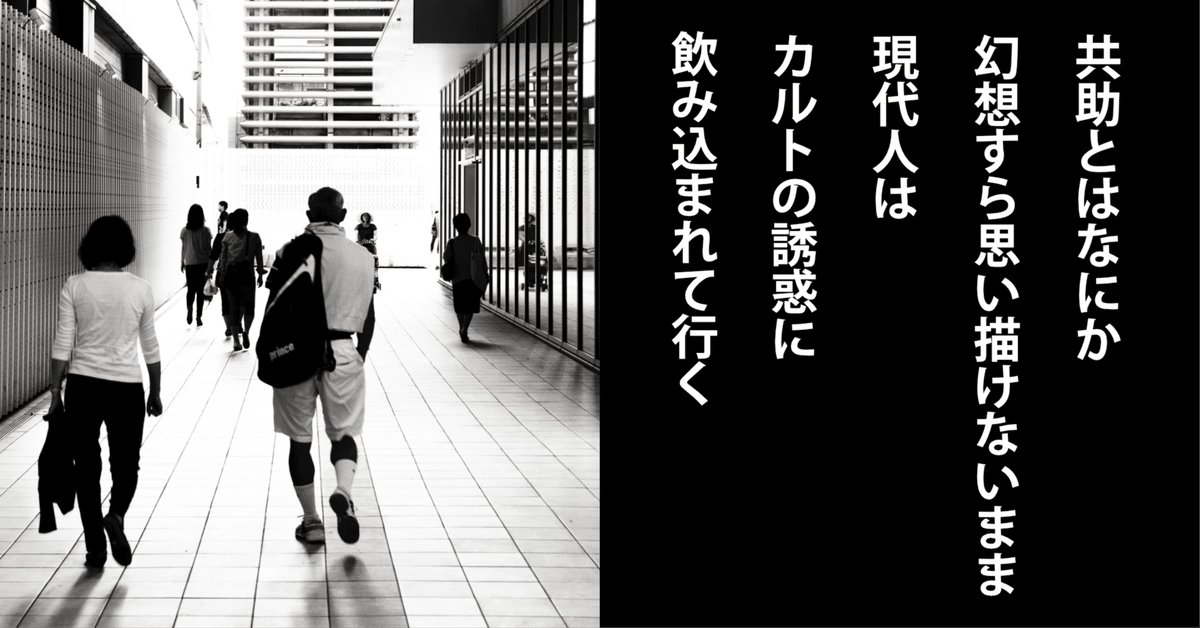
共助とはなにか幻想すら思い描けないまま 現代人はカルトの誘惑に飲み込まれて行く
『男はつらいよ』の寅さんには、何はともあれ迎え入れてくれる葛飾柴又というファンタジー世界がある。だが私たちは世知辛さからの緩衝装置として働いていた幻想上の共同体すら捨てさってしまった。
加藤文 (Kヒロ)
素っ裸で世間に放り出されている我々
安倍晋三氏暗殺事件で逮捕された山上徹也容疑者が旧統一教会・世界平和統一家庭連合信者の二世だったことで、彼の生い立ちが同情を集めている。いっぽう容疑者の母親が旧統一教会に入信するきっかけとなった絶望について問う声はあまり多くない。
山上徹也容疑者の母親は夫を自殺で亡くしたのち、長男が小児がんになり失明したほか不幸が続いていた。そして山上容疑者の叔父が残された家族の生活資金や学費などを援助しても、彼女の絶望は解消されていない。容疑者の母親にとって同教団は、洗脳以前に唯一の命綱に見えたのではないだろうか。
自助、共助、公助と言うが、容疑者の母親が自分自身でどうにもできなかった絶望をコミュニティーが救えたとは思えず、彼女を救える公助もなかった。
この現実を意識したとき不意打ちを食らった気がして、カルト集団神真都Q構成員の家族を思い出さずにいられなかった。
人格が崩壊し、暴言を吐き、暴力を振るい、団体に金を貢ぐ親族について彼らは、「私たちは何もできないですし、近所の人にも頼れません」と言う。家が隣りあっているだけで相手にプライバシーを打ち明ける気になれず、そもそも専門家でもない隣人にできることはないというのだ。「素っ裸で寒空の下に放り出されたような──」感じがするとメールで書き送ってきた人もいる。
陰謀論者の家族は何ものからも守られていない、こころもとなく無防備な状態で孤立している。追い詰められた心理がそう思わせるのではないのは、共助とはなにか銘々が考えてみればわかる。「私たちは何もできないですし、近所の人にも頼れません」という言葉通り、共助に幻想すら思い描けなくなるはずだ。
素っ裸で寒空の下に放り出される──言い得て妙である。カルト問題に限らず万事このような状態だ。
手助けすることが異常という常識
共助について考えるとき、苦い記憶が心中に去来する。
私と当プロジェクトのハラオカは、原子力発電所事故にまつわるデマに騙されて自主避難した人々を関西や沖縄から帰還させる手助けをした。避難する必要がなかった自主避難者のほとんどが政治的背景を持つ集団に囲い込まれていたため、帰還の手助けは集団から離脱させるところからはじめなければならなかった。
自主避難者の多くは女性であり母親と小学生以下の子供だった。被災地からの自主避難者には公的な支援があったが、関東などから逃げた人々は引っ越しにすぎないため援助の対象ではなかった。住む場所から仕事まで面倒を見るといっていた似非支援者たちに見捨てられると、家族の関係を破壊して避難した人々の心と生活は日に日に荒んでいった。
自主避難者の帰還を手助けするうえで多少の持ち出しは覚悟していたが私だけでも50万円程度の貸付け金が返却されなかっただけでなく、抵抗勢力から誹謗中傷と嘘を流布されたことで仕事が流れたり精神に痛手を負い、腕っ節の暴力までふるわれた。さらに弁護士に相談し、心の治療を受けるなど数年間は混乱のきわみにあり、これら損失を金銭に換算すると貸し倒れた50万円などかわいいものに思えてくる。
私がやったことは共助の枠を超えているが、このお節介がなければ路頭に迷い人生が破滅していた女性や母子がいた。だが被害を警察に訴えたとき「そういうことを、あなたがやらなければよかっただけですよね」と言われ、これもまた真理なのだった。
自主避難者が放射線デマに騙され洗脳状態に陥る直前も、帰還してからも、コミュニティーの人々は手を差し伸べなかっただけでなく、救いを求める声を無視した例がいくつもあった。現代の社会では「そういうこと」を手助けするほうが異常なのだ。
溶けて消えたコミュニティー
共助とは地域やコミュニティで人々が支え合うことだ。しかし共助とは何か具体的なものを思い描くことができない。
自主避難者のプライバシーに踏み込んだ帰還支援は共助の枠を超えていた。神真都Q構成員の家族は隣近所に助けを求めるなどあり得ないと言っている。さらに他人の生活を救うため自己犠牲をはらうなど馬鹿ばかしいにもほどがあると警察さえ言う。
こうなると、共助の幻想だけでなくコミュニティそのものが溶けてなくなっているとしか思えない。
コミュニティーと共助が結びついていたものにママ友がある。だがママ友に入るための「公園デビュー」は緊張を強いられる通過儀礼として忌み嫌われ、子育ての不安を解消するはずのママ友関係がストレスの原因にさえなっていた。
このためコミュニティーのママ友はインスタグラムに取って代わられた。
インスタグラムのママ友に脱ステロイドなどニセ医療が蔓延している問題を取材してわかったのは、インスタグラムはサムネイル画像を見ただけでコミュニティーの趣味性だけでなく参加が望まれている人の社会階層や年収までもが直感的に把握できるのが好まれていることだった。自分とそっくりな人たちと関わりたいのであって、少しでも違う人たちの登場は願いさげなのである。
住まいを構えるコミュニティーは社会階層や年収が反映されるが、それでもばらつきがある。さらに年齢、趣味嗜好、政治性、規範といったものはばらばらだ。自分と似ているようでまったく違う人たちとの付き合いかたが社会から失われ、そんなことをしても得るものがないと考えられるようになれば、隣人といかに関わるかではなく、関わらずに済まそうとする人のほうが増えるのはとうぜんだ。
たとえば生活道路で遊ぶ人たちを嫌悪して「道路族」と呼ぶ風潮がある。ともに隣近所同士だが、道路族と呼ぶ側には被害者の認識、呼ばれる側には言い掛かりをつけられている認識があるだけで、トラブルを解決するきっかけすらつくれないまま反目が続いている。両者にはコミュニティの一員としての共同体意識がまったくない。
カルト宗教、自主避難、陰謀論で共助を語るまでもなく、現実世界のコミュニティーに誰も何も期待せず、もうこの世に共助が可能なコミュニティーは存在していないのではないだろうか。
暴力装置も幻想の盾も存在しない
味噌や醤油の貸し借り、夫婦喧嘩の仲裁が遠い昔は隣近所にあったと言われる。このまま真に受けるのはどうかと思うが、共同体幻想が現代よりはるかにましな働きをしていたのはまちがいない。
映画『男はつらいよ』の寅さんはテキ屋稼業で全国を巡り歩いては生まれ故郷の葛飾柴又に戻り、地域の共同体は異質な人である彼をひとまず迎え入れる。
飲まず食わずで柴又にたどりついた寅さんが行き倒れ騒動を起こしたときは、「このたびはお騒がせして申しわけありません。長旅による極度の疲労ならびに栄養失調ということでして、まあ安静にして滋養のあるものを食べればじきに回復するということですから、今日はお引き取りください」と団子屋とらやの店頭でおいちゃんが挨拶をするだけで皆が納得して日常が戻る。
寅さんでさえ受け入れられるのだから、物語のなかで柴又暮らしの人々が見捨てられることがないのは言うまでもない。いまやこうしたファンタジーを理解できない人がいても不思議ではないが、コミュニティーに属していることで守られているぼんやりした感覚が数十年前まではあった。
恋愛の相談や喧嘩の仲裁だけでなく新興宗教に食い込まれた家庭に入り込んで信者を撃退した顔役が、祭礼で有名な東京の下町にかつていた。彼がコミュニティーの権威としてトラブルを解決できたのは町の暴力装置と目されていたからで、何人もの信者をたった一人で威圧するさまは「死人が出ると思った」と語られたほどだった。だが暴力装置の顔役と、彼のおせっかいを許容できる人はもういないのである。
こうして世知辛さの緩衝装置として働いていた幻想すら自ら捨て去ったのだから、私たちはたった一人で不安と向き合い、忍び寄ってくるカルトな存在と対峙しなくてはならない。
人は弱いのである。長者番付で無双するイーロン・マスクでさえSNSで何か喋っていないといられないくらい弱いのだ。幻想の盾を失い、公助もまた信じられないなか、正気をたもってカルト宗教に騙されていないのはまぐれであると思うくらいでちょうどよい。
こちらの世界には共助のための暴力装置も幻想の盾もないが、あちらには両方そろったコミュニティーがある。あちらのほうがよっぽどましと思ってしまう瞬間が巡ってこないことを祈ろうではないか。
いいなと思ったら応援しよう!

