
『みちのだい』15号対談「芹沢光治良氏と語る」を読んで
はじめに
天理教婦人会が出している『みちのだい』の古い記事を読んでいて興味深いことがあったので、紹介したい。昭和34年1月のものであるが、作家の芹沢光治良氏と婦人会の宇野たきゑ氏の対談である。宇野たきゑ氏が芹沢氏に『みちのだい』14号に原稿(第三者の目)を依頼したようだが、反響が大きく、そこから宇野氏が芹沢氏のお宅を訪問し、対談した内容を『みちのだい』15号に載せたようだ。時期的には教祖70年祭も終わり2年経ち、稿本天理教教祖伝が出て、芹沢氏が『天理時報』での「教祖様」の連載が終わった頃のようだ。
ハッピをどう思う
対談で宇野氏がハッピについてどう思うか尋ねているが、芹沢氏はきっぱりと反対し、世間の人は広告だと思っていると述べている。その理由を「教祖は大変謙虚な方だから、良いことをみせびらかしはなさらなかったと思う」とずばり指摘している。それに対して宇野氏は次のように答えている。
ハッピは、教祖がおつくりになったものではありません。おこりは私もよく知らないのですが、何でも大正十年頃から、ぽつぽつ各詰所あたりから着だした様です。それで背中に郡山とか兵神とか最上級の名をつけたでしょうが、東京の震災の時、そのハッピでひのきしんに出たところが、世間の人達は、天理教には別派が沢山あるのか、と聞くのです。これはいけない、というので背文字を天理教と統一したと聞いています。おそらく、この震災のひのきしんが天理教が団体で世間に出た始めだろうと思います。ですから、天理教、と背中に書いたのは、宣伝というより、ひのきしんをする人達を、責任持って統制のとれた仕事をさせる為の、一つの方法であったのですね。それと同時に天理教の中の平等をも含んでいます。系統によって別々の心を使わぬようにと言う意味です。この背文字が、遺物になるか、続くかは将来の問題でしょうが、ひのきしんをするのに本当に便利がよくて、変な物をまちまちに着るより、凛々しくていい物ですがね。

大正十年頃ということは倍化運動の頃かとも思えるが、大正十二年の関東大震災で、ハッピを着てひのきしんをしていたのだろう。これに対して芹沢氏はハッピを着だしてから世間が反感を持つようになったのじゃないかと述べている。芹沢氏自身は「着ても着なくても同じだと思うが、着かえないで、きたない仕事も、神様のこともするのが嫌だ」と述べて、「世間の目は天理教が皇居の掃除をして来たぞ、と威張っている様で嫌だと思っている」ことを具体的に述べている。
その後、ハッピについての問題点を話し合っているが、芹沢氏のハッピの失敗談は微笑ましい。夜遅く、真柱邸に行った時、ハッピを着た婦人をひのきしん者だと思い、「もしもし君」と世話してもらっていたら、翌日その夫人が真柱奥様(後妻のおあい様)だとわかり、すっかり恐縮してしまったようだが、これは教内でもよく起こっているようなことかとも思える。本部員でも勤務者でも両襟に「天理教教会本部」と書いたハッピを着ていれば、立場などわからないであろうし、注意深く名札でも見なければ失礼なことも起こりうる。大教会のハッピも然りである。ハッピに関しては賛否両論があるのは知っているが、昔から続いている問題なのかとも思える。

復元と教会制度、階級等について
次に宇野氏が芹沢氏に話し出したことだが、教理の復元のことや教会制度のことについて話している。前の14号に芹沢氏が書いた原稿の内容を再確認しているようでもある。少し引用させていただく。
宇野 教理が復元しているのに、教会制度はそのままであることや、特権階級があって、平等でない、これでは天理教が人類の進歩の邪魔物になる、と言う様なことでしたね。
芹沢 ええ、そうです。
宇野 教祖は、教会をつくれとはおっしゃらなかったのですが、おゝぼうの道として、色々な道中があって、今日教会制度がそのままある訳ですが、教理が復元した今日、何うしてそれも教祖にかえらぬのか、と言う訳ですね。
芹沢 そうなんです。
宇野 私にはむつかしいことは解りませんが、私なりの悟りがあるんです。恥ずかしいけどお話しましょうか。
芹沢 どうぞきかせて下さい。
想像に過ぎないが、『みちのだい』14号の芹沢氏の原稿は教内で、かなりな反響があったことが感じられる。芹沢氏の作品を読んだことがある方なら、わかるだろうが、作家として赤裸々に身内でも誰のことでも忖度なしに書くから、恐らく思うところをズバリ述べたのであろう。しかし、婦人会の宇野たきゑ氏も『みちのだい』という教内の婦人向け雑誌に思い切ったことをしたものだと感じる。昭和33年12月の頃だから、二代真柱もご健在で芹沢氏の著書『人間の運命』や二代真柱との交流記のような『死の扉の前で』も出る前のことで、資料不足に苦しみながらも『教祖様』の連載を続けていた頃かと思う。それだけ『天理時報』に連載されていた「教祖様」を書いている人物だから、原稿を依頼したのだろうが、かなり大きな問題になったのではないかとも思えてくる。
宇野氏はこのあと、自分の経験を述べていく。
本部員や大教会長は神様で、その子供は別あつかい
宇野 私も、子供の頃あまり苦労をしたので、天理教に対していろんな疑問を持ちました。父が亡くなって、母がその後をついで、宣教所長になって、私は詰所の炊事や事務員や、親代わり等々娘ざかりを真黒になって働いていましたが、或る時、お正月のお節会のお餅をお供えに行きながら、しみじみ嫌になったのです。教会数に応じてお餅の数がきまっているんです。それで大教会なんかは、車に大きなお餅をうず高く積んで、何台も何台も賑々しく御本部へ繰り込む中に、私のとこは小さい宣教所ながら、直轄なのでやはりお供に行かねばならず、大八車にわずかのお餅を積んでいく時の恥ずかしいことってないんです。それでも教会数としては精いっぱいなのです。何で教会なんてあるのだろうとしみじみ思いました。私は、子供の頃から人の何倍かよく勉強して皆に尊敬されていたし、今も力一杯働いて少しも怠けていない。それなのに、小さな教会の娘であるばかりに、こんな恥しい思いをしなければならない。大教会や本部員の子供さん達は何にも苦労しないで偉ばっている。こんな矛盾の中に私は教祖を慕うことは出来ないから、せめて弟妹に気がねなしに学校へ行かせたい、と思って働きに出ようとしました。
色んな道すがらの中、今日つくづく考えるのは、何と立派な天理教になった、と言うことです。私の子供の頃は布教師は因縁の悪い人と言う見方をされていた様な気がします。これは私のひがみであったかも解らないのですが。その頃は天理教の全盛時代で、本部員や大教会長なんて言ったら神様みたいで、その息子や娘は別あつかいをされていました。それが今日では、本部員、大教会長の息子さん達が、次々布教に出て、お席人一人つくる苦労がどんな物か、又その喜びがどれ程大きいかを味わっています。そしてみんながとてもその人達を尊敬するのです。
宇野氏が「子供の頃、苦労して」というのは恐らく天理教の全盛時代ということであるから、昭和初期の頃のことかと思うのだが、今と同じようにお節会の餅を各大教会で運んでいたのだろう。教会制度があるために、その教会の規模で恥ずかしい思いや苦労もしたようである。
「本部員や大教会長なんて言ったら神様みたいで、その息子や娘は別あつかいをされていた」とのことであるが、大正期に混乱した本部が山澤摂行時代に入り、もう既に天理教は江戸幕府のような封建制度を確立しつつあり、おかしくなっていたのかとも思える。宇野氏の話からも分かるように、人間なのに神様扱いしていたことが窺われる。
また、宇野氏は自分が大教会長の家内になり、分離によって四百近い教会数のあった大教会から、六十余りの小さい大教会の家内になってとあるが、越乃國大教会のことだと思われる。宇野氏の言う通り、天理教の全盛期で大教会の分離がよく行われ、現在に続く各系統が出来上がりつつある時期かとも思われる。宇野氏は色々勉強になったと語っているが、結局、この方も教会制度に翻弄された方なのかとも感じる。
なぜなら大教会長夫人になり、教会制度の中にどっぷりつかり、別席を運ぶ人を作ることが布教だと思っているように読めるからである。現在まで続いている別席者数やお供えの額などを基準とした系統同士の競い合いの中に浸かりすぎているのではないかと文面から感じてならない。筆者は真のよふぼく、助ける心をもったよふぼくを作ることが布教であり、それが教祖の望みだと思う。違うだろうか?
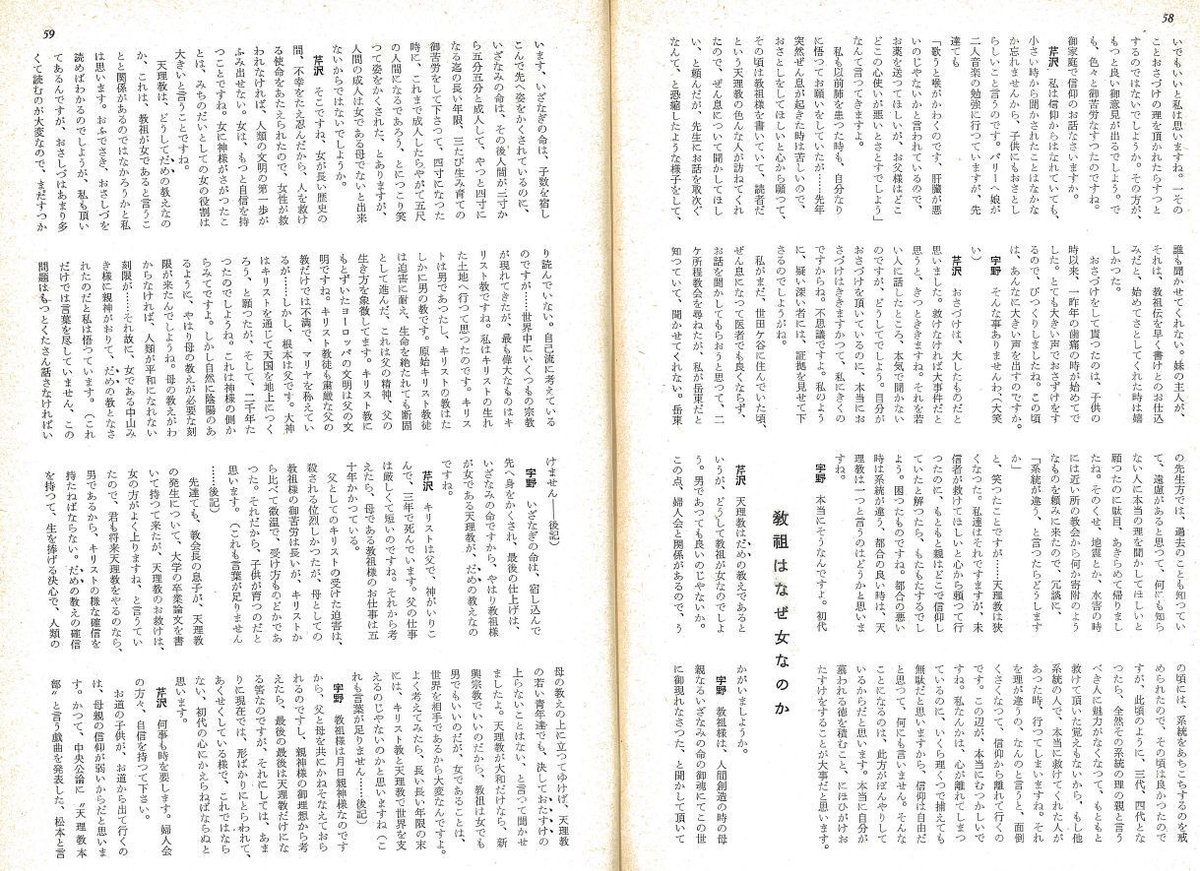
「理の親」についての話
その後、対談は芹沢氏が岳東を破門された話に移るが、二代真柱の計らいで解けたという話に移っていく。詳細な話は芹沢氏の作品の中にもよく出てくるので、ご存じの方も多いだろう。「理の親」についての話も興味深い。芹沢氏が「都合の悪い時は系統が違う、都合の良い時は、天理教は一つと言うのはどうかと思う」という問いかけに宇野氏は答えている。
宇野 本当にそうなんですよ。初代の頃には、系統をあちこちするのを戒められたので、その頃は良かったのですが、此頃のように、三代、四代となったら、全然その系統の理の親と言うべき人に魅力がなくなって、もともと救けて頂いた覚えもないから、もし他系統の人で、本当に救けてくれた人があった時、行ってしまいますね。それを理が違うの、なんのと言うと、面倒くさくなって、信仰から離れて行くのです。この辺が、本当にむつかしいですね。私なんかは、心が離れてしまっているのに、いくら理くつで捕らえても無駄だと思いますから、信仰は自由だと思って、何にも言いません。そんなことになるのは、此方がぼんやりしているからだと思います。本当に自分が慕われる徳を積むこと、にほひがけおたすけすることが大事だと思います。
以前の記事「理の親子について」でも述べてきたような問題が、この対談が行われた昭和30年代でも、既に大きな問題となっているのがわかる。大教会長の妻であり、本部の婦人会の重責を担っている方が、信仰から離れる原因をズバリ言っていることには感心する。
宇野氏は『みちのだい』十号に「神一条に生きぬいた女性」上田ナライトさんについても書いており、信仰に関して強い意思をお持ちだったように感じる。しかし、筆者には教会制度というものが、長い歴史の中で形作られ、揺るぎないものになり、本来の教祖の望みとは違うことになっていても従わざるを得ないようにもなっている気がしてならない。

おわりに
宗教二世問題がテレビでもよく取り上げられるようになったが、他の新興宗教二世の子供たちの意見を聞いていると、理不尽なことや理解しがたいことなども多いと感じる。宗教はその中にいると感覚が麻痺してしまう部分があるようにも感じる。普通に考えればおかしいことでも、組織の中にいれば、おかしいと感じながらも従っているというようなことも多いのかと思う。
天理教は江戸末期に教祖の神懸かり、天啓から始まった宗教であるが、長い歴史の中で姿を変え、名前こそ「天理教」とはなっているが、神とつながった天啓宗教ではなく、他の新興宗教と同じく、神不在の教祖といわれる人間中心の宗教ビジネスのようなものになっているようにも感じる。しかし、それでは世界の救済などは難しくないのだろうか。
