
【新刊試し読み】 『まんぷくモンゴル! 公邸料理人、大草原で肉を食う』|鈴木裕子
在モンゴル日本国大使館の公邸料理人を務めた鈴木裕子さんの日本での初の著書『まんぷくモンゴル! 公邸料理人、大草原で肉を食う』が2023年3月15日に発売されたことを記念して、本文の一部を公開します。
本書について
「あなたモンゴルでも行く?」この一言で、給食のおばちゃんだったわたしは、在モンゴル日本国大使館の公邸料理人になった。
モンゴルでの生活は驚きの連続。マイナス30度の極寒で車がなくては買い物にも行けない。モンゴルの若者は酔ったら家には帰らない⁉︎ 食事は肉と乳ばかり。友人曰く、草を食べた家畜の肉を食べているのに、なんでわざわざ野菜を食べるのか。そこには大草原をかける遊牧民ならではの理由が…。
公邸料理人が見た、モンゴルの知られざる食と暮らし。
モンゴルの家庭料理を紹介したコラムも掲載!
試し読み
前書きにかえて
ある夏のモンゴルから成田への機上。わたしは三人席の真ん中、左右はそれぞれ違う旅行会社の大きなツアーグループの参加者に挟まれた。公邸料理人としての任期を終え帰るところだった。お互いの帰路でモンゴルでの思い出を振り返り話し出すと、これが年代を超えた修学旅行のように盛り上がり、あっという間の五時間。降りる時に前後のお席の方々に「お休みになれなかったのでは? ごめんなさい」とお詫びしたら、「あまりに面白い話に聞き耳を立てちゃった、こちらこそごめんなさい」と返され、周りからはわたしも、わたしもと声が上がった。
きっかけは小柄な年上の女性たちの手荷物を座席上にあげた、なんて些細なことだったかと思う。お二人は素晴らしく気立てがよく社交的な楽しい方々だった。星空や馬に出逢いたくて旅した彼女たちは、自然豊かな地方まで足を伸ばしていた。また彼女たちからすれば実際にモンゴルに住み、肌感覚で彼の地を楽しんでいたわたしの話は興味深かったに違いない。
彼女たちはとてもたくさんの旅をしていた。「行っていない都道府県がないかも」「ヨーロッパや北欧、さまざまな国々を訪ねたわ」なんて話が飛び出した。目的は、買いものでも、快適さでも、グルメでもない彼女たちの旅。体当たりで旅先を感じ愉しむ。そんな人たちにモンゴルはもってこいだ。
彼女たちは自立した人たちでもあった。モンゴルの大自然の中に飛び込むということは、不便を許容することと同義だ。人から受けるサービスに贅を求めるタイプの人は、モンゴルを旅先に選ばない。
いや、選べない。そもそも日本の快適さを手放せない人はゲルに泊まろうとは思わないだろう。彼女たちは心惹かれることのみに導かれてモンゴルに向かっていた。自ら稼いで、自らの足で自由を手にした人たちの真摯なキラキラとした瞳は忘れがたい。隣にいるとワクワクが伝染する、そんな人たちだった。
モンゴルは私たちが今まで目にした事もない世界を体験させてくれる。旅した人達は、地球上に、ほかの生きもの達と肩を並べて暮らせる人間の在り方があることを知る。自然との一体感と研ぎ澄まされた自分の感性をお土産に日本へと帰っていく。それは目に見えたりはしないけれど、一生の宝になるに違いない。
大草原の国モンゴルの寒さは長く厳しい。冬ともなれば、首都ウランバートルでも外に出て鼻から息を吸い込めば鼻毛が一瞬で凍りつきピキピキする。慣れてくるとその「ピキピキ」でマイナス20度超えか、なんてことがわかる。十月から五月は氷点下が普通のモンゴル。冬は長いが、意外なことに雪は少ない。降水量は日本の十分の一という超乾燥地の平原で家畜たちは餌を探す。そう、モンゴルでは基本家畜は敷居のない大地で自分の食い扶持を自分で稼ぐ。それをほんの少しだけ助けるのが遊牧の仕事だ。
羊や山羊がいつ子供を産むかをご存知だろうか? モンゴルの春、とは言っても二月末頃、旧正月を過ぎ寒さがやっと底を打った辺りのことだ。そこからあたたかさに向かうとはいえ、草が生えはじめるのはまだ二か月も先のことだ。しかし早くも家畜たちの体内時計は春を打ち鳴らす。早く産んでお乳を卒業させなくては。短い夏に充分に草を食べさせて秋までに脂という天然の防寒具を身につけさせなくてはならない。蓄えのない痩せた仔は次の冬を生きて越えることができない。母となる家畜たちは命がけだ。新しい命が生まれるのは、緑が絶えた一年で一番飢えるまさにその時期。体内で仔を育て、生まれれば身を削ってお乳をやらなくてはならない。まさに身を分け、命を分け与える。命の循環の定めは厳しい。
そんな家畜と共に暮らす遊牧民は幼い命を見守り、決して奪うことはしない。ゲルのフェルトの壁一枚を隔て、恐ろしい冬を共に耐え抜く同志といっても過言ではないからだ。もちろん経済効率という意味もある。草原に柔らかな緑が萌えるまでに離乳を終えて草を食べさせれば、あとは草原が秋まで子供を育て肥え太らせてくれる。あわてて小さく少ない肉を食べる道理はない。それは、自分の命を削って仔を育てる野生の生き方への尊重かもしれない。そうでないかもしれない。いずれにしろ、モンゴル人は仔羊・仔牛をはじめとする幼畜たちのお肉を扱わない。
わたしはモンゴルに暮らし、初めて本当のモンゴルというものを知った。まさか人口の20倍以上の家畜がいる国で、仔牛・仔羊を食べられないとは想像もしなかった。けれど彼の地に暮らすうちに、それがとても気持ちが良いことだと感じるようになった。もちろん生きていくためにたくさんの命はいただく。けれども「生きもの同士だものね」という彼らのくらしは、人である以前に同じ大地を分け合う生きものとしての正解だ。
季節のめぐりも家畜との生活にならっている。モンゴルの春は、羊や山羊といった家畜たちが出産を始める季節。日本で春といえば、水が温み草が萌え、花々が咲き始める時が春だから、はじめは違和感が半端なかった。しかし歴史を遡れば納得だ。人が生きる根幹は食だ。人は食べることによって生かされてきたのだから。日本が稲や野菜・果実などの植物を暦の中心に置くなら、モンゴルは家畜ということだ。考えてみると、人は食べものが命を育むその先駆けをよろこびの春と呼んできたのかもしれない。何を食べてきたかで季節の区切りが変わるなら、気温は関係ない。農耕民族出身のわたしにとっての冬は遊牧民族には春だった。大切な食べものであり貴重ないのちを育む草原はモンゴルの価値観の源だ。
このような気づきをたくさん与えてくれた、モンゴルでの三年間。わたしの少し長い旅の味わいを、皆さまにもおすそ分け。
目次
前書きにかえて/くらべて分かる!モンゴルと日本/わたしとモンゴル
第一章 食べることは生きること
遊牧の真ん中にお肉
赤はいのちの色/ 肉こそ人が食べるもの/一頭の牛も軽々/ラクダのお肉はいただけない/からだを温め冷ますお肉/鶏と豚はコチコチ 羊の尾をカジカジ
聖なるミルクのおかげさま
ミルクの厚皮/幻の味オーラック/お乳の甘酒/馬乳酒案内/ミルクのおかげ
公邸料理人の仕事
くせ者だらけの食材たち
冷たいは痛い/岩塩王国/マッシュルームのネックレス/個性はすべて正解/匂いの飢餓
お肉のあとに
お肉を食べれば皮が出る/人骨の笛/胃袋はいれもの
第二章 草原をゆく
草原の掟
草原でアレをして/ゲルは着替える家/乾燥は安全/トナカイのブーツ/一枚何役?のデール/これがあれば生きられる/光が沁みる/地平線にはじまる天の川
大地を分け合うくらし
1300メートルのミクロとマクロ/白馬の王/道路はカイロ/コブに掴まる/狼たちの脅威/犬と歩んだ歴史/雪がなければ生きられない/みつばちたちの時間
第三章 モンゴルで旅人
ダルハンへの小さな旅
シベリア鉄道の夜/犬たちを籠絡/鶏の読心/夭折の皮たち
異世界ウランバートル
メモはいらない/酔ったらお家に帰らない/終電ないから/ペンキのドア/自分の先があなた/空気とお肌/コスモポリタン
おわりに
これを食べたい! モンゴルごはん
網脂巻きの羊レバー
田舎のホルホグ
国民食三兄弟
モンゴル人なら作れなきゃのボーズ
作り手次第の家庭の味ホーショル
肉のエキスを絡め焼くツォイウァン
羊沁みわたるバンタン
モンゴル版鏡餅!? ヘヴィンボーブ
ショルロックは煙に巻くお肉
著者紹介
鈴木 裕子
1968年東京都生まれ。保育園の調理師から在モンゴル日本国大使館公邸料理人に転身。離任後は大好きなモンゴルに健康としあわせを贈りたいと『Japanese chef YUKO’s vegetable and cookbook for MONGOLIANS』をモンゴルで出版。国家資格の専門調理師全六部門を取得した食いしん坊。
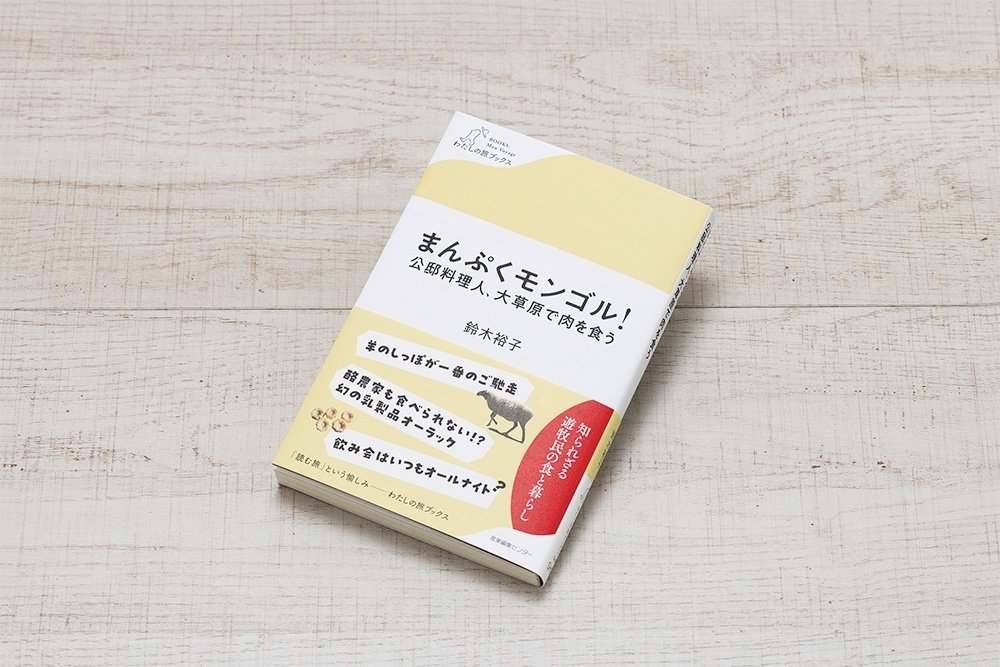
『まんぷくモンゴル! 公邸料理人、大草原で肉を食う』
【判型】B6変型判
【ページ数】240ページ
【定価】本体1,320円(税込)
【ISBN】978-4-86311-356-5
