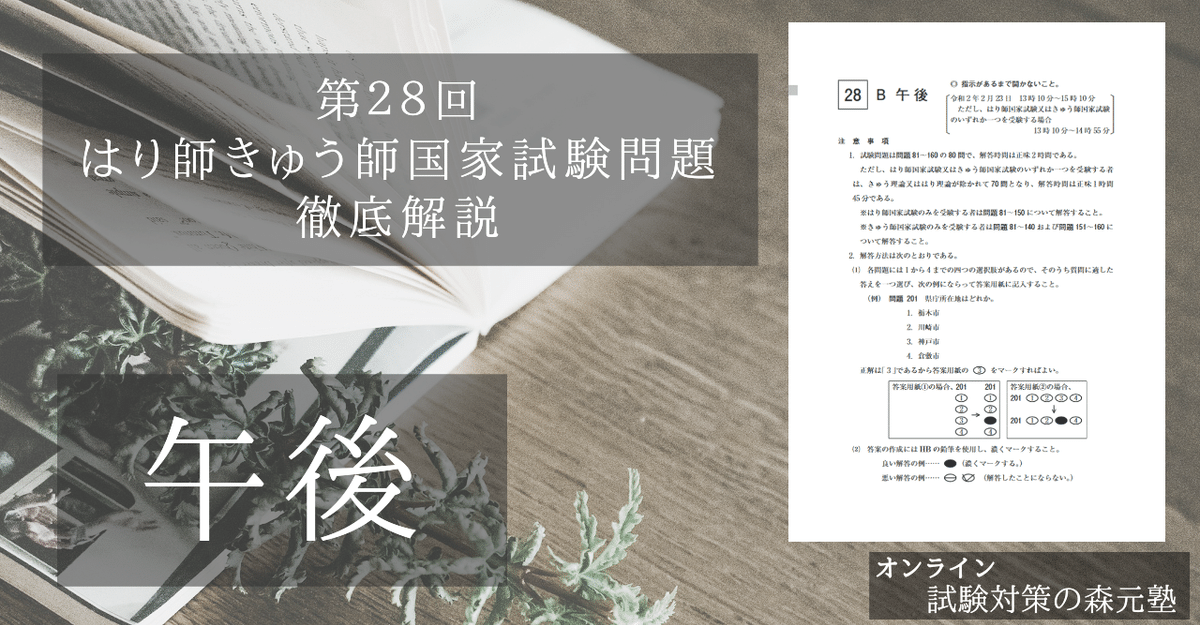
【過去問解説】第28回はり師きゅう師国家試験問題(午後)徹底解説
【2021/08/07 更新】このアカウントは鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・言語聴覚士などの国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
【有料記事】
⏩ 鍼灸師第28回国家試験問題(午後)
についてを徹底解説
【Back Number】
▶第31回鍼灸師国家試験問題(午前)徹底解説
▶第31回鍼灸師国家試験問題(午後)徹底解説
▶第30回鍼灸師国家試験問題(午前)徹底解説
▶第30回鍼灸師国家試験問題(午後)徹底解説
▶第29回鍼灸師国家試験問題(午前)徹底解説
▶第29回鍼灸師国家試験問題(午後)徹底解説
▶第28回鍼灸師国家試験問題(午前)徹底解説
▶第28回鍼灸師国家試験問題(午後)徹底解説
【解説内容の見本】
ショックの分類と原因の組合せで正しいのはどれか。
1.血液量減少性ショック 熱傷
2.心原性ショック 緊張性気胸
3.血液分布異常性ショック 心筋梗塞
4.閉塞性ショック 消化管出血
【解説】ショックの分類に関する問題もちょくちょく出題されます。
【血液減少性ショックの主な原因】
▶出血
▶火傷
▶下痢
【心原性ショックの主な原因】
▶急性心筋梗塞
▶心筋炎
▶拡張性心筋症
▶不整脈
▶心タンポナーデ
【血液分布異常の原因】
▶敗血症性ショック
▶アナフィラキシーショック
▶脊髄性ショック
(+エンドトキシンショック)
【閉塞性ショックの主な原因】
▶肺塞栓
▶急性大動脈解離
▶大動脈閉塞
上記のように、単純に答えだけでなく、それに関連した内容も解説しています。
第28回はり師きゅう師国家試験問題(午後)
問題 81 回復期リハビリテーション病棟で作業療法としてよく行われるのはどれか。
1.歩行訓練
2.巧緻動作訓練
3.嚥下訓練
4.立ち上がり動作訓練
問題 82 正常歩行のサイクルで正しいのはどれか。
1.立脚中期に全足接地をする。
2.二重支持期は40%である。
3.立脚相で膝関節は1回屈曲する。
4.遊脚相が立脚相より時間が長い。
問題 83 脳卒中片麻痺患者の動作について正しいのはどれか。
1.衣服を着るときは健側から行う。
2.ベッドでの起き上がりは患側を下にする。
3.歩行時には杖を健側で持つ。
4.階段は患側から上がる。
問題 84 脊髄損傷の損傷レベルとkey muscle(主たる残存筋)の組合せで正しいのは どれか。
1.C5 上腕三頭筋
2.C8 深指屈筋
3.L3 腸腰筋
4.L4 下腿三頭筋
問題 85 前腕義手のうち能動義手の特徴はどれか。
1.装飾が主な目的である。
2.ケーブルでフックを開閉する。
3.モーターで動作をコントロールする。
4.四辺形ソケットを用いる。
続きの問題文に関しては、公式サイトよりご確認ください。
過去問引用:https://ahaki.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/mondai_28_harikyu_pm.pdf
問題 81 解説
問題 81 回復期リハビリテーション病棟で作業療法としてよく行われるのはどれか。
1.歩行訓練
2.巧緻動作訓練
3.嚥下訓練
4.立ち上がり動作訓練
答え:2
【解説】回復期は特に関係なさそうです。
回復期のリハビリテーションと書いていますが、あんまりここらへんは関係しません。
作業療法士といえば「コレ」みたいな選択肢が1つしか無いからです。
ただもう少し深堀りして、もっと言えば病院で務める人や、理学療法士・作業療法士とも一緒に仕事したいという人は、「回復期」とか「急性期」とかっていうのをもっと知っておいたほうがいいかもしれません。
【医療各時期のリハビリテーション】
▶予防的リハビリテーション
▶急性期リハビリテーション
▶回復期リハビリテーション
▶維持期リハビリテーション
上記の4つからなります。
【予防的リハビリテーション】
疾病の予防、障害者の合併症の予防と健康維持など
【急性期リハビリテーション】
廃用症候群の予防など急性期からのリハビリテーション技術の応用
【回復期リハビリテーション】
身体機能・精神機能・心理を含めた包括的なアプローチ
【維持期リハビリテーション】
障害者や療養中の生活社の活動レベルや社会参加を低下させないこと
合併症の予防・健康維持。
今回は回復期リハビリテーションの話なので、一段落した患者が身体機能や精神機能をなるべく可能な限り回復させる時期です。
そしてもう一つは各セラピストの業務内容です。
これだけだともちろん間違ってはいますが簡単に分けると、
下肢は理学療法士、上肢は作業療法士 とざっくり分けることができます。
理学療法士:運動療法・物理療法
作業療法士:身体障害・精神科作業療法
言語聴覚士:言語や聞こえの障害・摂食嚥下障害
【理学療法】
▶運動療法
▶温熱療法
▶水治療
▶電気療法
▶物理療法
歩行訓練とか起き上がり訓練とかは全部「運動療法」に該当します。
【作業療法の種類】
▶機能的作業療法
▶ADL訓練
▶職業前訓練・職業前評価
▶精神医学的作業療法
【該当する作業療法】
▶手芸
▶刺繍
▶編み物
▶〇〇細工(木工・金工・陶芸・革細工)
▶足踏み機器の使用
▶園芸
初めて聞く人は意外かもしれませんが、嚥下訓練は言語聴覚士の分野になります。
問題 82解説
問題 82 正常歩行のサイクルで正しいのはどれか。
1.立脚中期に全足接地をする。
2.二重支持期は40%である。
3.立脚相で膝関節は1回屈曲する。
4.遊脚相が立脚相より時間が長い。
答え:1
【解説】歩行のサイクルはリハビリテーションのお約束問題。
でもややこしい…
【歩行】
歩行は四肢の交互運動による重心の移動と定義することができる。
杖や装具を用いても歩行であるが、車椅子での移動は歩行ではない。
【歩行のサイクル】
1サイクルとは1側の踵接地からふたたび同じ側の踵接地までをいう(1.03±0.10秒). すなわち2歩に相当する。
【歩行のサイクルの分類】
▶立脚期:60%
▶遊脚期:40%
▶二重支持期:15-20%
いつもの100%超えとるやないか問題がありますが…
これは二重支持期が立脚期に含まれているからです。
〇〇期はざっくりいうとこの3つですが、この3つにそれぞれ時期があります。
【立脚期】
▶踵接地
▶足底接地
▶立脚中期(全足接地)
▶踏み切り
【遊脚相】
▶加速期
▶遊脚中期
▶減速期
【二重支持期について】
▶歩行速度が早くなると少なくなる
▶0になる状態を「走行」という
よく間違えるところで膝の曲がる回数についてです。
実際に歩いてみてもよくわかりませんが、立脚期に膝が二回曲がります。
問題 83 解説
問題 83 脳卒中片麻痺患者の動作について正しいのはどれか。
1.衣服を着るときは健側から行う。
2.ベッドでの起き上がりは患側を下にする。
3.歩行時には杖を健側で持つ。
4.階段は患側から上がる。
答え:3
【解説】実際に一度やってみるとわかります。
動かない方の四肢を後回しにすると、動く方の四肢をどうするんだって話になると思います。
では順番にイメージしていきましょう。
「衣服を着るときは健側から行う。 」
どちらかの手を動かさずにワイシャツ(ボタンついて前が開くやつ)を着たと想像してみてください。
動く方の手はすんなりいきますが、動かしたらいけない方の手はどうやって手を通せばいいかわからなくないですか?
こういった服を着る際は腕のみならず、肩甲骨や肋骨の動作も行って着ています。
施術所でも四十肩の患者を見ることがあるかもしれませんが、そのときにアドバイスするといいかもしれませんね。
「ベッドでの起き上がりは患側を下にする。 」
ベッドから起き上がる時、よっぽどトレーニング好きじゃない限り、手で押して起き上がりますよね。腹筋だけで起き上がるなんてツワモノはごく僅かです。
そのときに、どちらの手で押しやすいか想像してもらえると、健側側が下になるのはイメージ付きますよね。
「歩行時には杖を健側で持つ。 」
ここまでのながれを見ると、これも間違ってそう…に思えますが、あっています。杖は本来歩くときに使いますよね。
患側、つまり体重をかけれない足を一歩前に出した時、患側に杖があったほうが安定するように思えます…
ですが実際、歩行を行うと、健側に杖がある方が重心の位置が安定します。患側に杖があると、患側側に重心が寄りすぎてしまうことがわかるはずです。
「階段は患側から上がる。」
どうやって上がれるんだ…って話です。
足捻挫したときに捻挫した方の足から登るなんていう人めったにいないと思います。
これは逆も同じ…ではありません。(2021/01/07 解説修正してます)
階段を降りる際は患側を先に下ろしてから健側をおろします。
杖や手すりがある場合、先に患側を下ろし、健側で支えながら両足を揃える方が安全です。先に健側をおろそうとすると、膝が曲がることがあり危険です。
しかし、手すりが片方にしかない場合は、後ろ向きで降りるなどして体重を支えることが大切!
問題 84 解説
問題 84 脊髄損傷の損傷レベルとkey muscle(主たる残存筋)の組合せで正しいのは どれか。
1.C5 上腕三頭筋
2.C8 深指屈筋
3.L3 腸腰筋
4.L4 下腿三頭筋
答え:2
【解説】お約束問題なんですが、一向に覚えれない。
という声をよく聞きます。
とりあえず上記のスプレットシートにまとめていますので、細かい内容はそちらを見ながら確認してください。
▶C5 :三角筋・上腕二頭筋
▶C8 :指屈筋群・手内筋
▶L3 :大腿四頭筋
ここはいつもの「あの手この手」で覚えていきましょう。
【C5の覚え方】
上腕「二」頭筋・「三」角筋 C(4)5
偶然にも2・3・4・5となります。
【C8の覚え方】
お手々のC(し)8(わ)
手内筋とか手に関する筋肉はC8です。
【L3の覚え方】
エルサの四頭筋
エルサ(雪の女王)の四頭筋というパワーワードで一気に覚えて下さい。
問題 85 解説
問題 85 前腕義手のうち能動義手の特徴はどれか。
1.装飾が主な目的である。
2.ケーブルでフックを開閉する。
3.モーターで動作をコントロールする。
4.四辺形ソケットを用いる。
答え:2
【解説】能動義手がなにか知っていたら、なんとなく答えがわかります。
上腕義手と前腕義手には以下の種類があります。
【上腕・前腕義手の種類】
▶能動義手
▶装飾用義手
▶作業用義手
▶電動義手
▶筋電義手
今回はこの能動義手に関する問題です。
【能動義手】
フックや手の形をした手先具によるもので把持などの機能を持つ
フック船長のあれです。
一見、フックと聞くと作業用義手に該当しそうってところが引っ掛けです。
他の選択肢も解説します。
【装飾用義手】
機能は持たないが、見かけをよく作ってある。
【作業用義手】
農作業用とか重作業用など特殊な目的に作られたもの
【電動義手】
電動で把持機能などをもたせたもの。
【筋電義手】
断端からの筋電をスイッチにして操作させる。
【四辺形ソケットは?】
四辺形ソケットは義手ではなく、義足で用いられています。
大腿部から切断した場合に用いることが多い。
無料記事も多数用意しております。 役に立ったと感じましたらチップもお待ちしております。

