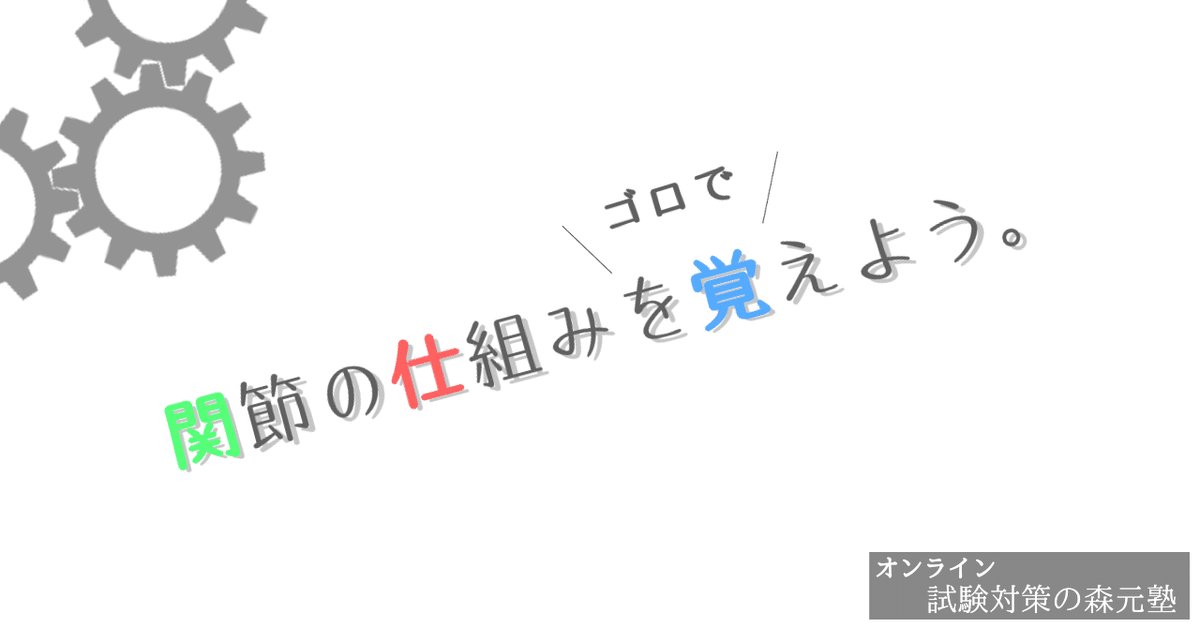
【解剖学】図解イラストとゴロで簡単「関節の仕組み(1軸・2軸)と軟骨の種類(弾性軟骨・硝子軟骨)」の覚え方
【2024/02/18 更新】このアカウントは鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・言語聴覚士などの国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
【解剖学】
⏩ 関節の仕組みと種類 の解説
こんにちは!
オンラインで試験対策を学ぶなら森元塾 塾長です。
関節って簡単そうにみえて色々難しいところがたくさんありますよね。
例えば、線維軟骨と弾性軟骨の違いとか、2軸・3軸なんていう分け方をしたり。
毎回調べるのもしんどいと思いますのでまとめてみました。
【解剖学】関節の定義について

肘を曲げたり、膝を曲げたりするときに降りまがるところを関節っています。
具体的には以下のように記されています。
「関節は、骨と骨とが関節腔を隔てて可動性に連結する」
今回は関節の仕組みと種類についてお伝えしていきます。
関節の仕組みと種類【関節の構造】
関節には、関節と関節軟骨・関節包・関節円板があります。
▶︎関節
「関節は、骨と骨とが関節腔を隔てて可動性に連結する」
2つの骨の骨膜をお互いに連なり関節包となる。関節包は滑液で満たされた関節腔を囲んでいる。
上の教科書の内容をわかりやすい日本語にするとこんな感じ。
①骨と骨との間を「関節包」といいます。
②「関節包」は「骨膜」でつながっています。
③その「関節包」だけだと、骨と骨滑りが悪いので「関節腔」と呼ばれる袋があります。
④「関節腔」の中には滑りやすくするために「滑液」というものが入っています。
【関節の定義と特徴】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 骨と骨とが関節腔を隔てて可動性に連結していること
▶ 骨膜をお互いに連なり関節包となる。
▶ 関節包は滑液で満たされた関節腔を囲む。
▶︎関節軟骨
関節腔に面する骨表面は薄い軟骨層、すなわち関節軟骨でおおわれている。
関節軟骨は「硝子軟骨」であるが、軟骨膜を欠き直接に滑液に接する。
浅在層を形成する軟骨細胞は扁平で、膠原繊維は表面に平行に配列する。
中間層から深在層にかけて、球形の細胞が細胞群をつくって柱状に重なり、膠原繊維は表面に向かって垂直に並ぶ。
これ読んで意味わかる人いるのでしょうか。教科書をそのまま書き写したものです。
つまり関節の中の骨の先端は軟骨っていう骨よりもさらに滑りやすいものでできていますよって話です。「骨膜」とかがあると滑りが悪くなるのでそれもなくしたよ。てこと。
後半については今まで国家試験で出たことないのでこんなところまで覚える必要はありませんが、「硝子軟骨(しょうしなんこつ)」というキーワードはとても大切です。
「硝子軟骨」についてはまたのちほどお伝えしていきます。
【キーワード】
「関節軟骨」 「軟骨膜を欠く」 「硝子軟骨」
▶︎関節円板
関節腔内には、「繊維軟骨」の関節半月や関節円板が介在することがある。
衝撃を和らげる働きとともに、移動や変形によって関節面を広げるに役に立っている。
衝撃が多い関節にはクッションがあるよって話です。
ここでも「繊維軟骨」というキーワードが出てきました。
教科書後半の「移動や変形によって関節面を広げるに役に立っている。」は少しだけ頭の片隅に置いておきましょう。
4択の一つとして使われる可能性がありますよね。
じれったいですが「繊維軟骨」についてはまた後ほどまとめてお伝えしていきます。
関節の仕組みと種類【軟骨組織の種類】
先ほど出てきた「硝子軟骨」「繊維軟骨」ですが、軟骨は軟骨基質の性状3つに分けられます。
▶︎硝子軟骨(しょうしなんこつ)
膠原繊維の間に多量の「コンドロイチン硫酸」を含み、すりガラスのように半透明の乳白色を示す。関節軟骨・肋軟骨・気管軟骨で見られる。
「関節軟骨」・「肋軟骨」・「気管軟骨」で見られる…
これが最重要キーワードです。硝子軟骨でない軟骨は次のうちどれか?という問題が作れます。
【キーワード】
「関節軟骨」「肋軟骨」「気管軟骨」「多量のコンドロイチン硫酸を含む」「乳白色」
ただし、硝子軟骨はもっともよくつかわれている軟骨の構造なので他の2つを覚える方が早いです。
硝子軟骨
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 関節軟骨
▶ 肋軟骨
▶ 気管軟骨
ゴロ:ガラスのカンロ器
ガラス(硝子軟骨)のカン(関節軟骨)ロ(肋軟骨)器(気管軟骨)
コンドロイチン硫酸とかはもしかすると聞いたことがあるかもしれません。
よく膝の痛みにはコンドロイチンが聞くとか言われるのは、軟骨組織がこのコンドロイチン硫酸を多量に含んでいるからだと考えられます。
実際に効果あるかは知りません。
ここでは臨床的なことは何も言いません笑
▶︎弾性軟骨(だんせいなんこつ)
軟骨基質を構成する繊維の約30%が弾性繊維からなり、弾力性に富む。
透明感のある淡い黄色を呈し、耳介軟骨や鼻軟骨の多くがそれにあたる。
「耳介軟骨」や「鼻軟骨」が大切なキーワードです。
【キーワード】
「耳介軟骨」「鼻軟骨」「淡い黄色」「弾力性に富む」
弾性軟骨
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 耳介軟骨
▶ 鼻軟骨
ゴロ:男性の耳と鼻
男性(弾性軟骨)の耳(耳介軟骨)と鼻(鼻軟骨)
弾性軟骨は書いてある通り、耳と鼻にありますので、上記のように「男性の耳と鼻」でまとめると覚えやすいです。
▶︎繊維軟骨(せんいなんこつ)
大量の膠原繊維が束を作って走り、その間に軟骨細胞と少量の軟骨基質が存在する最も強靭な軟骨である。脊柱の椎間円板、骨盤の恥骨結合、膝関節の関節半月などに見られる。
名前だけ見ると繊維軟骨が軟骨の構造の一番オーソドックスなものなのかなって思いましたが、オーソドックスなのは「硝子軟骨」です。
またいつも通り場所が大切です。脊柱の椎間円板・骨盤の恥骨結合・膝関節の関節半月の3つは覚えておきましょう。
繊維軟骨(繊維軟骨)
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 脊柱の椎間円板
▶ 骨盤の恥骨結合
▶ 膝関節の関節半月
ゴロ:船医の判決追加
船医(線維軟骨)の判(関節「半」月)決(恥骨「結」合)追加(椎間円板)
繊維軟骨といえば「椎間円板」「恥骨結合」「関節半月」。
半月板ってよく損傷するからやわらかいイメージがある人もいるかもしれませんが、強靭にできていたんですね。
関節の仕組みと種類【関節の種類】
いよいよ関節そのものの種類と分類です。
関節には1軸・2軸・多軸という分け方があります。
これはどの方向に動くかです。右と左だけなら1軸、そこに上下が入る2軸ってな感じです。
【関節の種類】
▶︎1軸性
蝶番関節・螺旋関節・車軸関節
▶︎2軸性
楕円関節・顆状関節・鞍関節
▶︎多軸性
球関節・臼関節・平面関節
▶︎可動性がほとんどないもの
半関節
【1軸性の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 蝶番関節
▶ 螺旋関節
▶ 車軸関節
ゴロ:一張羅
一(1軸性)張(蝶番関節)羅(螺旋関節)
【2軸性の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 楕円関節
▶ 顆状関節
▶ 鞍関節
ゴロ:2時だから
2時(2軸性)だ(楕円関節)か(顆状関節)ら(鞍関節)
【多軸の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 球関節
▶ 臼関節
▶ 平面関節
ゴロ:卓球久兵衛
卓(多軸関節)球(球関節)久(臼関節)兵衛(平面関節)
【ほとんど可動性が無い関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 半関節
覚え方:半永久的に動かない
次にそれぞれの分類に具体的な関節の部位がついてきます。
▶︎1軸性
蝶番関節:関節軟骨・関節包・関節円板
螺旋関節:距腿関節
車軸関節:上橈尺関節・正中環軸関節
下橈尺関節
【蝶番関節の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 腕尺関節
▶ 指節間関節
▶ 膝関節
ゴロ:蝶はわしの膝
蝶(蝶番関節)はわ(腕尺関節)し(指節間関節)の膝(膝関節)
【螺旋関節の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 距腿関節
ゴロ:巨大な螺旋階段
巨大(距腿関節)な螺旋階段(螺旋関節)
【車軸関節の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 上橈尺関節
▶ 正中環軸関節
ゴロ:車は上等にせい!
車(車軸関節)は上等(上橈尺関節)にせい(正中環軸関節)!
▶︎2軸性
楕円関節:橈骨手根関節・環椎後頭関節
顆状関節:中手指節関節・膝関節
鞍関節:第一手根中手関節
※橈骨手根関節は楕円関節であり、顆状関節でもあります。
【楕円関節の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 橈骨手根関節
▶ 環椎後頭関節
ゴロ:妥当感
妥(楕円関節)当(橈骨手根関節)感(環椎後頭関節)
【顆状関節の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 中手指節関節
▶ 膝関節
ゴロ:過剰に膝にチュウ
過剰(顆状関節)に膝(膝関節)にチュウ(中手指節関節)
【鞍関節の関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 第一手根中手関節
ゴロ:安全第一
安全(鞍関節)第一(第一手根中手関節)
▶︎多軸性
球関節:肩関節・腕橈関節
臼関節:股関節
平面関節:椎間関節・肩鎖関節・手根間関節・足根間関節
半関節:仙腸関節
太字は教科書に例として載っているものなので必ず覚えましょう。
また、「正中環軸関節」とは首にの第1頸椎と第2頸椎との間の関節で他の頸椎の間は椎間関節で平面関節ですが、ここは「車軸関節」なので覚えておきましょう。
もうひとつ、膝関節については基本は蝶番関節ですが、顆状関節にも属するといわれていますのでそこは覚えておきましょう。
関節【関節円板を持つ関節について】
何気にこの問題を一番よく見かけるような気がします。
覚えるのは下記の5つ
下橈尺関節・橈骨手根関節・顎関節・胸鎖関節・肩鎖関節
ものによっては恥骨結合の間にも関節円板があるとか…
一番後回しで大丈夫です。
【関節円板をもつ関節】
— もぬけ@鍼灸・柔整国試対策 (@monuke_kokushi) December 29, 2019
▶ 下橈尺関節
▶ 橈骨手根関節
▶ 顎関節
▶ 胸鎖関節
▶ 肩鎖関節
ゴロ:円盤の加藤投手、今日が検査
円盤(関節円板)の加藤(下橈尺関節)投手、(橈骨手根関節)今日(胸鎖関節)が(顎関節)検査(肩鎖関節)
これはなかなかきれいなゴロになりました。
ぜひ使ってください。
よく考えたら、円板投げの選手は投手じゃないですが…細かいところは気にしないように…
関節の仕組みと種類【問題】
では実際に問題を解いてみましょう。
関節の仕組みと種類【まとめ】
覚えることが多くて大変ですが、どんどん覚えてどんどん忘れてまたどんどん覚えなおしましょ…
何度か覚えなおして忘れてるかと思ったら4択になったら思い出せることもあります。
どうせ忘れるから覚えないではいつまでも変わりませんので繰り返し覚えなおすことが重要です。
毎日国家試験対策や臨床で必要な知識をお届けしています。
ためになった・気に入ったって人は
「♥:いいねボタン」と「アカウントのフォロー」
をお願いいたします。
【国家試験オンライン塾:まいにち頑張るコース】
鍼灸師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の学生の方でちょっと不安がある、何を勉強して良いのかわからないって人向けの有料期購読です。
【国家試験オンライン塾のコンテンツ内容】
▶テスト形式での問題の配布
▶詳しい解説
▶勉強の仕方・ノウハウ
▶質疑応答
現在3年生・4年生の方はもちろん。そうでなくても早いうちから国家試験で安心したい人や普段の定期テスト・実力テスト・模試などの点数を稼ぎたい人にもおすすめです。問題集を買うより断然お得です。
【頻出問題特化マガジン】
国家試験で必ずといってもいいほど出題する部分をまとめています。
過去問の解説をまとめた赤本マガジンも販売中です。
ここから先は

【森元塾】まいにち頑張るコース(柔整・鍼灸・あんま)
毎日勉強しないと不安な人・自分を奮い立たせないと頑張れない人向けのコースです。 このコースに入るだけで勉強ができるようになるというわけで…
無料記事も多数用意しております。 役に立ったと感じましたらチップもお待ちしております。
