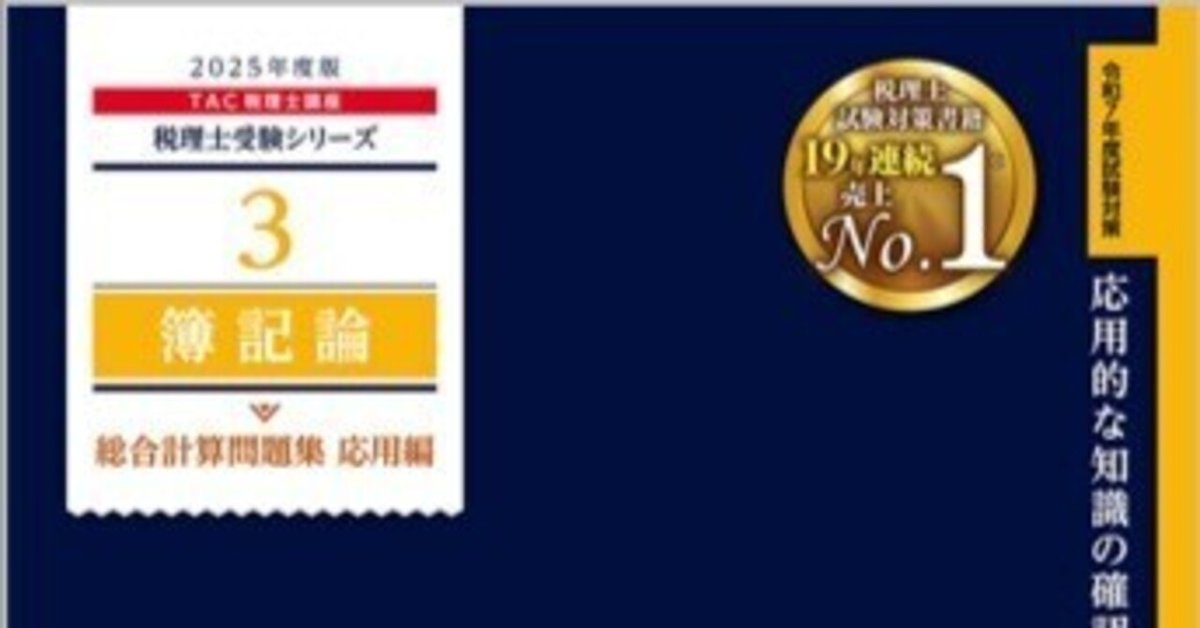
簿財独学のしおり4(簿記論・総合問題対策~見た目は変わっても本質は大体同じ~)
この項目では、簿記論の総合問題の学習について紹介します。
個別問題に比べて、総合問題の点数は例年安定しやすいので、総合問題で30点(6割)以上を安定して取ることができれば、一気に合格率も高まります。
総合問題に取り組む時期は、「個別計算問題集」を2回転した後くらいが目安です(仕分けが、ほぼわかるようになるレベル)。
1 使用教材について
① 「税理士 簿記論 総合問題の解き方(TAC出版)」
個別問題と同様に、解き方を習得するために使用します。
② 「簿記論 総合計算問題集 応用編(TAC出版)」
総合問題の演習という意味では、これと過去問で十分です。
回を追うごとに、各論点の難易度が段階的に上昇しており、苦手な論点も把握することができるため、良書です。
2 使用法
各テキストを使用する順番は、次のとおりです。
① 「税理士 簿記論 総合問題の解き方(TAC出版)」
② 「簿記論 総合計算問題集 応用編(TAC出版)」
まず、「総合問題の解き方」を時間制限ありで、一通りやってみましょう。
最初は問題量に圧倒され、心が折れることは間違いありません。
でも、心配しないでください、練習すれば、必ずできるようになります。
この際、問題を自力で解くことや得点については、深く考えすぎず、解き方や問題の着眼点、飛ばすべきポイントはどこか、という点を意識しながら、解説を読み込みましょう。
この際、「個別問題の解き方」と同様に、全てできるようになる必要はなく、解き方が身に着けばよいと割り切りましょう。
2回転して、一通り解法が身に着いたら、「総合計算問題集」に進みます。この問題集を解く際のポイントは、制限時間以内にどれだけできるかを把握し、自分はどこに必要以上に時間がかかっているかを理解することです。
そのため、時間制限ありで解く⇒時間不足部分に取り組む⇒採点という流れで解いていました。最初は、解くだけでも2時間くらいかかってしまうと思います。
しかし、2回・3回と繰り返すうちに、多くの論点が繰り返し、日本語を変え数字を変え出題されていることに気付けるはずです。
そうなれば、あと一歩です。
3 気を付けること
合格のための目標レベルは、制限時間以内に、30点(6割)以上を安定して取れるレベルです。
総合問題で苦手な論点は、おそらく個別問題でも苦手な論点です。
時には、テキストや個別問題を振り返ることも必要です。
また、最終的には、どの論点を捨てるか、という判断になるかと思います。
私の場合は、基本的に原価計算・貸倒引当金・税効果は捨ててました。
(もちろん、問題によっては瞬殺できるので、最初から捨て論点を決めるのは危険です。)
以上が、簿記論の総合問題の学習法です。
次の記事では、「財務諸表論・理論問題の対策」について書きたいと思います。
ありがとうございました。
