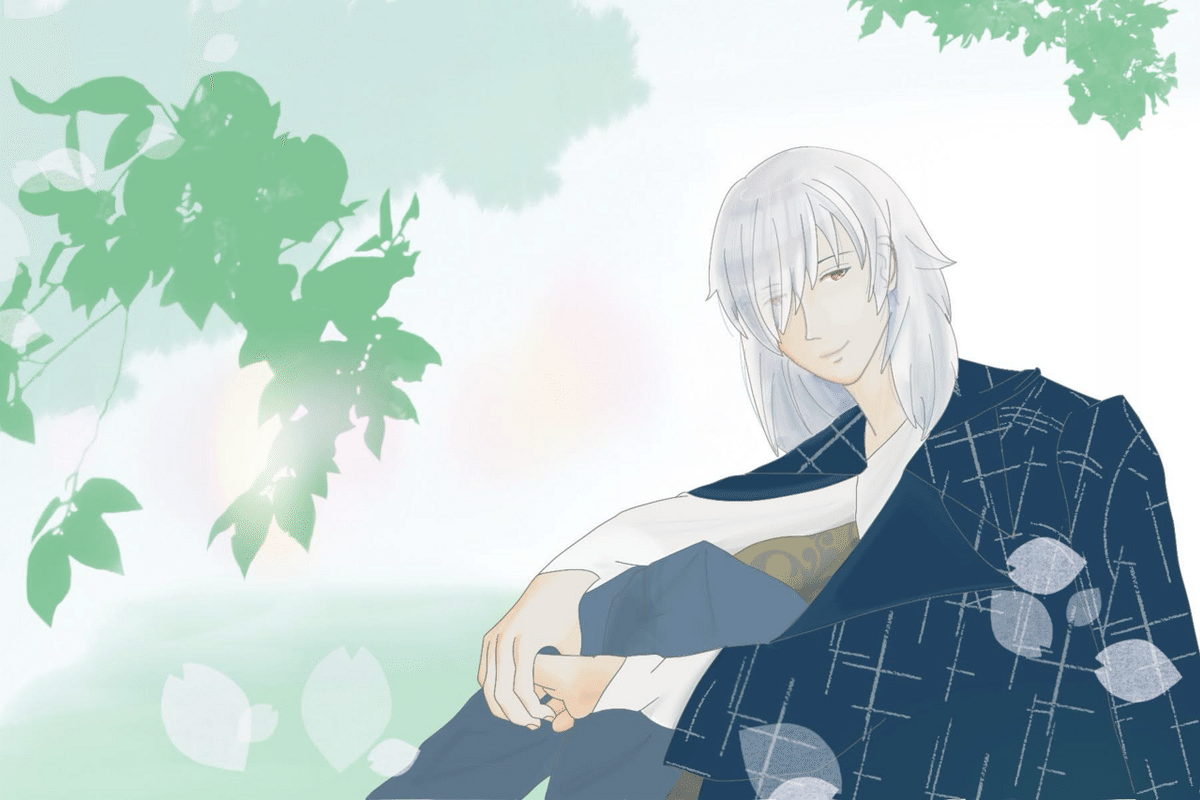第三十四話
千聖を人が多い場所に連れて行くのを避ける満月だが、この遊園地だけは唯一の例外で、良く2人で来ていた。というのも医療拠点が10ヵ所弱ありナースキャストもいて、具合が悪くなるとすぐ対応してもらえるという安心感があるからだ。至る所にいるスタッフも良く訓練されていて屋内アトラクションも多く、休む場所もたくさんある。夏は暑さで心臓に負担がかかるので外出しないことが多いのだが、この遊園地だから誘いに乗れたというところはあった。
千聖としては推しが一緒に来てくれたら嬉しいというだけの気持ちだったのだろうが、満月的には正義がいることも心強かった。正義も、自分の患者が気になるから来たというのが少しあるんじゃないかと思っている。
「そろそろ休憩するか?」
時計を見て、満月は千聖に声をかけた。
今は屋外移動中なので暑いのは暑いのだが、千聖は嬉しそうでとても元気だ。夏にたくさんの人と一緒に出かけるなどという経験は人生で初めてなので、この日のために良く食べ良く寝て規則正しい生活をし、万一にも体調を崩さないように頑張っていた。今日も定期的に休憩をとり、皆に迷惑をかけないように気をつけている。
「あ、ホントだ。つい楽しくて忘れちゃうよ」
「ちょっと飲み物買って来るから。そこの椅子で休んどけよ」
と、ドアが開いた店から少し冷房が届く、建物の影になっているベンチを示した。
「満月。僕ここで待ってるから、いろいろ乗って来たら?」
遊園地には【心臓が弱い方はお控えください】と書いてある乗り物があり、千聖には一部、遊べないアトラクションがある。けれどそういうアトラクションには人気があるものも多い。満月は全て千聖に付き合ってくれるので、この遊園地でも行ったことがないアトラクションがいくつもあるのだ。
「別にいいよ。そんなに乗りたいわけでもないし」
だがあっさり断った満月は
「ちょっと待ってろ。周年記念のドリンクがあるから、それ買ってくるよ」
と、売り場がある建物に行ってしまった。
できないことがあっても十分楽しめるように、満月はいつもいろいろ調べて来てくれている。今までずっと頼りきりで甘えて来たが、自分のせいでいろいろなことを我慢させている気がして、時々心苦しい。
「珍しい所で会うね」
つま先を見ていたら、頭上から声が落ちてきた。
「えー⁈ヤマイ先生?びっくりした!」
隣に座って来たのは大学校医の床伏健助先生だ。
昔は千聖が入院していた大学病院の小児外科医をしていて、千聖の手術をしてくれたのもこの先生だった。小児科病棟ではいつもヤマイ先生と呼ばれていて、千聖も未だにそう呼んでしまう。だがそれは「床伏」という苗字から来たあだ名だったということを後々知った。子どもにとっては難しい苗字だったので、皆そう呼んでいたのだろう。
「家族で来てるんだよ。妻と娘が店にいるんだけど長くなりそうでね。中は混んでるしここで待っとこうと思って」
という手元に、英語で書かれた論文のコピーを持っている。結婚して子どもができた頃、外科医としてのピークであるにも関わらず、大学病院から校医に移動してきた。何か考えるところがあったのだろうなとは思うのだがはっきり聞いたことはない。だが未だにこうして、最新医療の勉強をし続けている。
「そういえば満月くんは?」
「飲み物を買いに行ってくれてるんです」
言うと、先生はいつものフワリとした笑顔を見せた。
「彼がいるなら安心だな。君の体のことを良くわかってるからね」
「でも、なんかいつも悪いなってちょっと落ち込んじゃって」
千聖の言葉に、少し考えてから言った。
「…そう思っているのは、逆に満月くんに悪いんじゃないかな」
子どもの頃から見慣れている、優しい眼差しだ。
「看病したり治療したりしたことを、ごめんなさいって言われたらね。そんな思いをさせて申し訳ないと、僕だったら思うよ」
そこまで言うと店の入り口に目をやった。どことなく先生の面影がある少女と、その手を引いた女性が紙袋を持って出て来ているところだ。
これが先生の家族かと思い、千聖は立ち上がって頭を下げた。席を立ちながら先生は笑う。
「君しか満月くんを助けられないという時は、きっとあるよ。その時、自分ができることを精一杯やればいいんじゃないかな」
そして娘を肩車すると、奥さんと去って行った。
途中で満月とも会ったらしい。
綺麗な色のサイダーを渡してくれながら、満月が言う。
「ヤマイ先生来てたんだな。びっくりして変な挨拶しちゃったよ」
それに頷きながら、千聖はさっきまでの会話を思い出していた。
そっか。ごめんなさいじゃないよね。
「ねえ、満月」
千聖の横に座り、サイダーのストローを咥えた満月がこっちを向く。
「いつもありがとう」
言うと、千聖の永遠のヒーローの頬にキスをした。