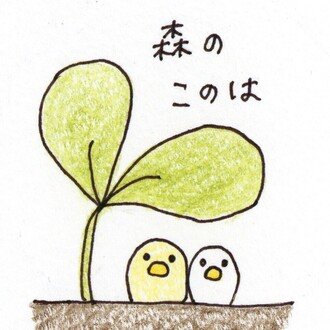オーガニック アロマキャンドル 制作秘話
やさしい香りが好評の "炎をみつめるソイキャンドル" シリーズ🕯️
オーガニック精油のみを使い、炎が美しく見える容器を使用することで、鼻👃と目👀の両方で楽しんでいただけるアロマキャンドルとなっております♪
以前、この「外装」の制作過程についてnote記事でご紹介いたしました。
今回は、この「中身」が生まれた過程についてご紹介したいと思います😊
1)そもそも、なぜこのようなキャンドルを作りたかった?
◆理由①:やさしくて&自然な香りのキャンドルが欲しかったから
私は匂い(臭い)に敏感な方で、例えば会社のエレベーターに乗っただけで、「あの人が乗ったな…」と分かってしまったりするほど。
そんな訳で(?)、香りやアロマテラピーにはかなり昔から興味がありました。
ブレンドされたアロマオイルを買って、アロマポットで加熱して楽しんだり、お香を買って楽しんだり・・・といろいろな形で香りを楽しむ習慣がありました。
でも、アロマポットはいちいち引っ張り出してきて、水を入れて、キャンドルに火をつけて、過加熱にならないように気を付けて、またしまって・・・という作業がメンドクサイという理由で、だんだん手をつけなくなってしまった。
お香は、喘息気味になってしまったのを機に避けるようになってしまった。
残る代表選手はキャンドル、だったのですが、このキャンドルで「自然なやさしい香り」を探すのがなかなか難しく😓
世の中に出ているアロマキャンドルの多くが人工香料を使ったもので、点灯すると頭が痛くなったり気分が悪くなってしまうような経験もしばしば💦
精油(エッセンシャルオイル)を使ったものは数が少ないため、まず選ぶ余地が少なく、あっても「ラベンダーの香り」とか「ゆずの香り」とか、単体の香りが多い。
もっと複雑だけど自然でやさしい香り、欲しい!!
と思うと、今度はかなりのお値段💰になってしまい、実際に試してから買える訳でもない商品に対してそれだけのお金を支払う勇気もなく・・・
・・・という訳で、自分で作るしかない!!となったのが第一の理由です。
◆理由②:炎とちゃんと対話できるキャンドルが欲しかったから
アロマキャンドルのほとんどは、密閉できるようにスクリュー瓶に入っている and/or 遮光のために着色された瓶に入っています。

「アロマキャンドルなので単に香りを楽しめればいい」ということであれば、これらのデザインで全く問題ないと思うのですが、私はキャンドルの炎を見つめてボーっとしたい、というのがキャンドルを使う理由の一つなので、これらの2択ではどうしても満足できませんでした。
そんな訳で、これまた「自分で作るしかない!」となるワケです。
◆理由③:自分の世界観を「香り」で表現してみたかったから
作家としていろいろモノづくりをしていく上で、表現の方法はいろいろあると思います。
・「形」で表現する
・「色」で表現する
・「手触り」で表現する
・「香り」で表現する
・「音」で表現する ・・・etc.
これらすべての表現方法について、私はとても興味があります。
「形」や「手触り」は木工品、「色」は "童謡キャンドル"(こちらについてまた後日記事にしてみたいと思っています)・・・で作っていきたいと考えた時、「香り」で自分の世界観を表現する方法の一つとして、アロマキャンドルの制作に挑戦してみたい、と思いました💪
2)では、どんな香りを作ろうか?
① まずは柱づくり
自分が欲しい香りや使うシーンを考えて、3つのテーマ(柱)を打ち立てました。
* リフレッシュ系(すっきりした香り)
* リラックス系(ちょっとリッチで優雅な香り)
* あったかい系(包んでくれる香り)
② 商品名の考案
次に、自分の中で明確なイメージを創るため、中身の制作よりも先に商品名を考えることに。
↓ その時考えた名前の一例がこちら
<リフレッシュ系>
・新緑の風
・風遊ぶ森
・森の小道 ・・・etc.
<リラックス系>
・秋の月夜
・月かおる夜
・月のあかり ・・・etc.
<あったかい系>
・陽だまりの庭
・ひだまりのネコ
・冬の灯 ・・・etc.
これら3つの系統を同時に考えることで、「シリーズ」としての統一性を図りました。
最終的に決まったのが・・・
「森のささやき」

「月のかけら」

「陽のほほえみ」

・・・の3つです🎊✨
全て「漢字1文字+ひらがな」にすることで、やさしい印象だけど、漢字部分の一文字だけでパッと区別できるようにしました。
3)いざ、調香!
① まずは下準備
名前が決まり、自分の中でイメージがしっかり固まったところで、いざ調香!
しかし、これまでアロマオイルを購入することはあっても、自分で調合して香りを作るのは初めて。
とにかくモノがないと始まらないので、3mlのお試しサイズでちょっとずつ精油(エッセンシャルオイル)を買い揃え、効能等の基本情報と共に香りの特徴をノートに書き出してみました。
<例>
ローズマリー
:薬草っぽい清涼感ある香り。湿布感アリ。
そんなこんなを繰り返すうちに、気付いたら40種類以上まで増えていた精油たち ↓

また、調香の仕方や精油の知識を得るため、図書館でアロマテラピーの本を片っ端から借りて読みました。
当初は、せっかくなら「アロマテラピー」として効果があるブレンドにしようと考えていましたが、調香しながら自分自身に試すうちに、
『結局その時いいなと思った香りが、その日の自分の体調に合ったものなんじゃないか』
という結論に至り、精油が持つ効能については言及しないことにしました。
(そもそも言及して販売できる資格を持ってないですしね😅)
※ 妊娠・授乳中の方や基礎疾患をお持ちの方は禁忌品があるので、しっかりご確認くださいね。
その他もろもろ、基礎研究を重ねた中で決めたMy ルールがこちら ↓
A) オーガニック認証品(USDAなど)のみを使用する
B) 絶滅危惧種は使わない
C) いわゆる「ノートの黄金比」にはこだわらないで配合する
それぞれについて少し詳しくご説明すると・・・
A) オーガニック認証品を使用する
せっかく天然香料にこだわって作るので、オーガニック認証を受けた精油のみを使うことにする。
B) 絶滅危惧種は使わない
「自然と共に生きる」をモットーにした生き方をしていく上で、すでに絶滅が危惧されている植物の精油は使用しない。
<例>
・サンダルウッド
・ローズウッド
・フランキンセンス
※どの香りも私はとても好きでしたので、断腸の思いです。
C) 「ノートの黄金比」にはこだわらない
この黄金比率は、書き手によって数値が異なるのですが、一例としては
「トップノート:ミドル:ベース」=「4:4:2」or「3:5:2」
・・・がおススメと言われています。
つまり一般には、「トップノート」や「ミドルノート」と呼ばれる、揮発しやすい(=パッと香りを感じやすい)精油を多めに配合するようです。
しかし、私の個人的な好みとして穏やかな香りが好きなため、この比率にこだわるとうまく調香できないことが判明。
よって、とにかく思うままにブレンドして、自分が好き!と思える香りに仕上げることにしました。
※「ノート」についてもう少し知りたい方はこちらのHPをご参照ください。
② ひたすらブレンド ⇒ 燃焼
この後は、自分が思い描いた香りになるまでひたすらブレンドしていくのみ。
例えば「森のささやき」はハーブ調(薬草系)のすっきりした香りにしたかったので、メインになる香りとして
・ユーカリ
・ティートゥリー
・マヌカ
・ローズマリー
・・・が候補として挙がりました。
これらについて配合比率を変えたり、ブレンドする相手を変えたりしながら調香しました。
この時悩まされた現象が2つ。
<1> 加熱すると匂いが変わってしまう😱😱😱!!
<2> 1日にできる配合作業は2~3種類が限界👻👻👻!!
<1>
ブレンド後の香りとしてとても良い感じに仕上がったものを実際にキャンドルにして燃焼してみると、全然香りが変わってしまうことが分かったのです。
場合によっては「点火してしばらくすると頭が痛くなる」というレベルのものも・・・せっかくうまくいったと思ったのに。。
そんなこんなで、「ブレンド ⇒ キャンドルに成形 ⇒ 燃焼」・・・というサイクルを何十通りも繰り返し、ようやく配合比が決定しました。
<2>
よく言われることではありますが、人間、ずっと同じにおいの中にいるとそのにおいを感知できなくなります。
そんなわけで、1日に挑戦できるのは2~3種類が限界。
カメの歩みです🐢
※後で知ったのは、コーヒーのにおいを嗅ぐと鼻がリセットされるようです。
世の中の調香師さんたち、すごいです!!
4)キャンドルとしての性能調整
精油の配合比率が決まったところで、最後はキャンドルとしての性能調整です。
① どのような容器が良いか?
② どのくらいの太さの芯が良いか?
③ どのくらい精油を入れるか?
① どのような容器が良いか?
これは、上記1)の②で書いた「炎とちゃんと対話できるキャンドル」にするため、こだわって選びました。
様々な大きさや形のガラスビンを購入し、実際にキャンドルにしてみることで、炎が美しく見える形のものを採用!
② どのくらいの太さの芯が良いか?
これは、以下の③と同時並行して実験する必要がありました。
なぜならば、精油の配合量によってキャンドルの燃焼性が変わってしまうため、です。
しっかり香らせようとして精油の配合量を上げると、キャンドルの燃焼性が悪くなってしまい、太い芯を使う必要が出る
↓
芯を太くすると、炎がやたら大きくなってしまい、不格好
↓
炎の大きさに合わせて精油の量を調整
・・・と言った感じです。
③ どのくらい精油を入れるか?
通常のキャンドルづくりでは、(合成香料ではなく)精油を使用する場合、3~5%を目安に配合するということだったので、この範囲で配合量をいろいろ変えて、香りの立ち方と上記②とのバランスから「4.5%」の配合率に決定しました。
この4.5%の配合率というのは、こんなにたくさんの量!

なんと、キャンドル1つにつき小瓶(3mL)1本分です😶!!
※ 写真は5mLの瓶を使用してます
5)ようやく完成!使用した方のお声は?
そんなこんなで、約4ヶ月の開発期間を経て、ついに完成!
香りに敏感な家族や友人に使ってもらい、いただいた感想が・・・
◎ とにかく良い香り!
◎ においがキツくなくてGood!
◎ 火をつけるだけで手軽に香りを楽しめて良い
◎ 思ったより長持ちする(ちょこちょこ使って、1年持った)
◎ 香りが3種類あるので、その日の気分に合わせて選べて良い
◎ 瓶の装飾がかわいい
◎ プレゼントにも最適!
・・・と、今のところ大好評いただいております🥳🎶
まだお試しいただいていない方、BASEでもCreemaでも販売中ですので、どうぞよろしくお願いいたします!!
<BASE>
<Creema>
長文に最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございました🌟
いいなと思ったら応援しよう!