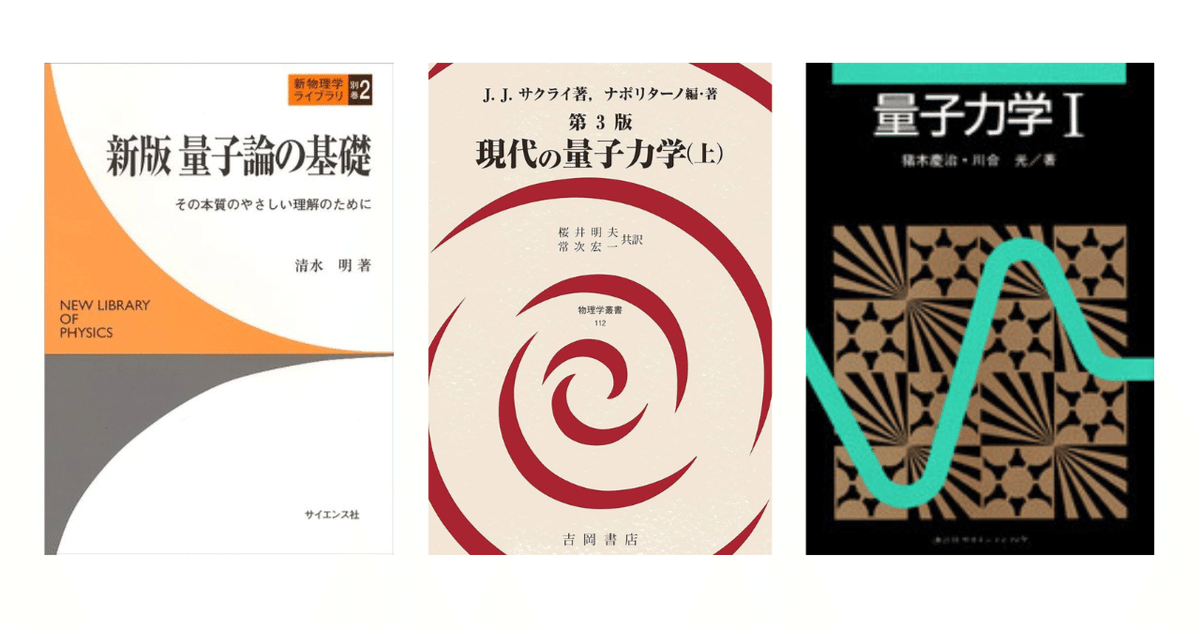
おすすめの量子力学の教科書
おすすめの量子力学の教科書
おすすめの量子力学の教科書をこの順に読むのが最良だろうと思う順番で紹介します。
ヨビノリの講義動画
清水量子論
JJサクライ・現代の量子力学(上)
猪木・川合量子
1.ヨビノリの講義動画
今や物理界隈のスーパースターになられたヨビノリさんですが、自分は量子力学に限らず新しい分野を勉強するときは、(動画があれば)ヨビノリから入るのがいいと思っています。
構成もよく考えられていて、具体例も豊富でとっつきやすいです。
2.清水量子論
自分は清水量子論こそが量子論の入門として唯一絶対の教科書であると思っています。
「要請」という形で明確に書かれた前提からスタートし、量子力学を誤魔化しなく(しかもできるだけ簡潔に)構成していく本書を読んで、自分は「この本に頼ればいいんだ」と思い、心の支えになりました。
3.JJサクライ・現代の量子力学(上)
恐らく量子力学の教科書として最も有名であり、評価の高いJJサクライですが、自分とJJサクライの出会いは苦い思い出でした。
当時、大学2年生の秋学期の量子力学Ⅰの試験の出来が散々だった自分は、
何とかしなければと思い、駒場の書籍部でJJサクライを手にして春休みに読み始めました。
しかし、まったく理解できないのです。
1.1節の「シュテルン・ゲルラッハの実験」、1.2節の「ケット,ブラの演算子」から何を言っているのか分からないのです。
今なら、なぜ理解できなかったかが分かります。それは、取りも直さず清水量子論を読んでいなかったからでした。
先述の通り、自分は清水量子論こそが量子論の入門として唯一絶対の教科書であると思っています。
清水量子論で量子力学の最も基礎的な原理を学び(そしてその説明は難解なものではありません)、その原理に基づいて読めばJJサクライを読み進めることも全然可能なのです(一部、ブラベクトルの定義と
内積の定義が清水量子論と異なっていますが、清水量子論の定義を踏襲して問題ありません)。
そして、これも強調しておきたいのですが、1.2節の「ケット,ブラの演算子」までを読み終えればその後の説明は非常に明快です。
つまり1.2節の「ケット,ブラの演算子」までが(上巻では)一番の挫折ポイントなのです。
そこを乗り越えれば、その後は空間並進操作、時間並進操作、空間回転操作の考察から、運動量演算子、ハミルトニアン、角運動量演算子についての非常に見通しの良い考えが得られ、量子力学が一気に明快なものとなります。
ちなみに、下巻は摂動論や散乱を扱いますが、行間が広く難しいため、以下で述べる猪木・川合で勉強した方が良いと思っています。
4.猪木・川合量子
こちらの教科書は清水量子論・JJサクライ(上)を読んだ上で、摂動論や散乱といった計算手法を身に着けるのに有効な教科書です。
逆に言えば、基礎的な部分については清水量子論・JJサクライ(上)の方が圧倒的に詳しいため、そちらの教科書を読んだ上で同じ原理を踏襲して読み進めて構いません。
また、猪木・川合量子は東大理物の量子力学のカリキュラムと合致しているので(というより本書は東大理物の量子力学の講義に基づいて書かれたものなので)、基礎的な部分にこだわらなければ、この本2冊(上下巻)で量子力学の基礎分野を一通り学ぶことができます。
入門書として有名な小出量子ですが、個人的には入門書としてはお勧めできません。
個人的には内容があまり一貫しているとは言えないからです。
演習書:演習しよう量子力学
演習書としてお勧めなのが「演習しよう量子力学」です。
非常にオーソドックスな問題を見やすいレイアウトでそろえていて、解説も行間が広すぎず、取り組みやすいです。
高校の問題集で例えるならチャートやFocusGoldのような網羅系参考書の構成に近いと思います。
しかし、誤植も多いため、取り組み際にはネット上に転がっている正誤表を参照することを強く勧めます。
いかがだったでしょうか?今回は量子力学のおすすめの教科書について紹介してみました。
次回は熱力学・統計力学の教科書を紹介しようと思います。
