
「お口を閉じましょう」でも「歯は閉じてはいけません」
「お口を閉じましょう」は間違ったメッセージだった?
「口をポカンと開けているんじゃない!」「お口を閉じなさい!」
幼い頃から、周囲の大人にこう言われて育った方は多いのではないでしょうか?口をしっかり閉じる姿は、理性的で凛々しく見えるものです。
また、歯科医師からも次のような理由で「口を閉じることの大切さ」を聞いたことがあるかもしれません。
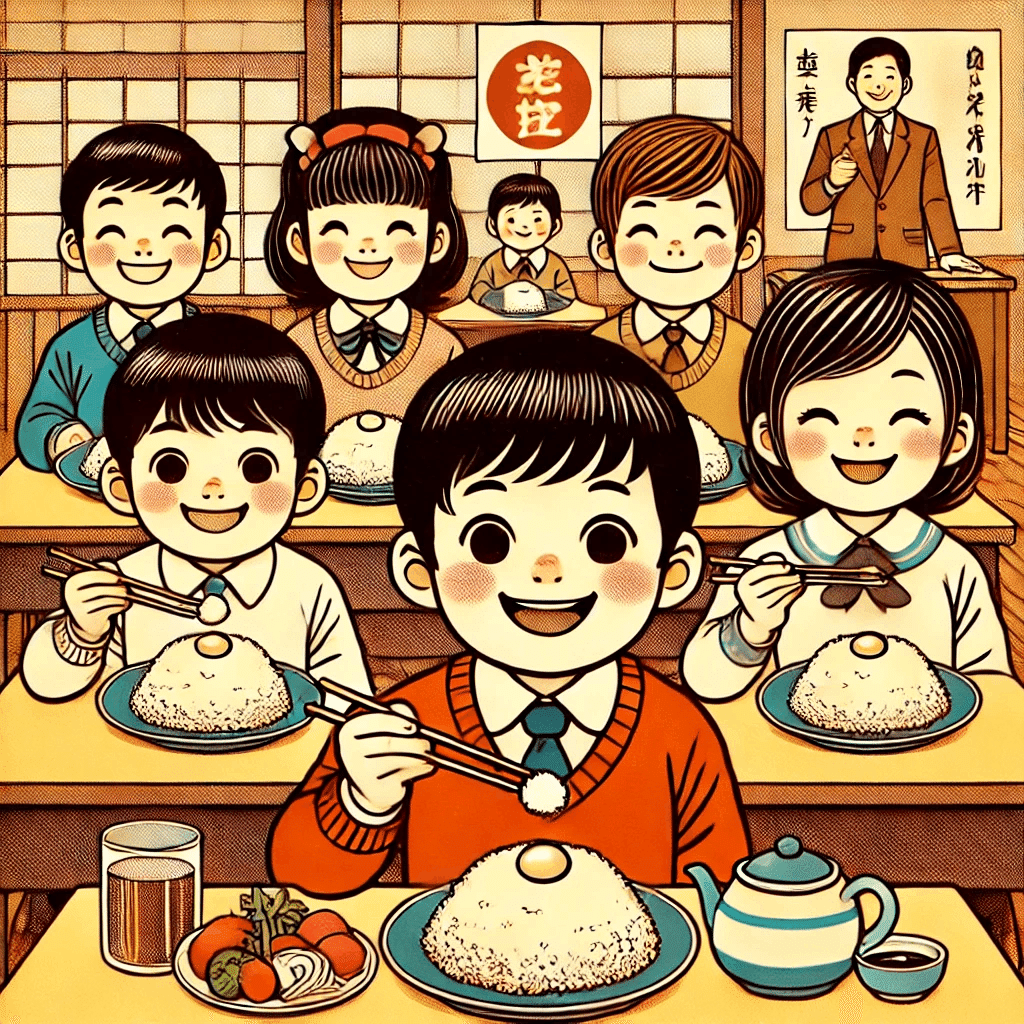
口の乾燥を防ぐ
虫歯や歯周病のリスクを減らす
風邪やアレルギーを予防する
出っ歯になるのを防ぐ
しかし、真面目に「お口を閉じましょう」を実践してきたあなたは、実は将来、大変な苦労をすることになるかもしれません。
健康寿命と口の関係
2000年にWHO(世界保健機関)が「健康寿命」の概念を提唱して以来、単に寿命を延ばすのではなく、健康的に生活できる期間をいかに長くするかが重要視されるようになりました。
厚生労働省のデータによると、健康寿命は少しずつ延びていますが、それでも平均寿命との差は依然として大きく、男性で約9年、女性で約12年の「健康でない期間」が存在しています。
ここで注目したいのが、歯の残存本数と健康寿命の関係です。8020運動(80歳で20本の歯を残そう)の達成率は、1989年当初7%程度だったのが、2016年には51.2%と大幅に向上しました。歯が多く残っている人は元気な傾向があるのです。
「元気な高齢者」と「お口の中」の共通点
歯科医院には、0歳から100歳を超える方まで、幅広い世代の方が訪れます。長年の診療経験を通して、元気な高齢者にはある共通点があることが分かりました。
それは、「口の中のスペース(口内ボリューム)が広い」ことです。
一方、寝たきりの方のお口は狭くなりがちです。健康で活動的な高齢者の口腔は、適度な筋力と柔軟性を持ち、舌が自由に動けるスペースがしっかり確保されています。そして、十分な唾液が分泌されていることも特徴です。
口内ボリュームが減少すると何が起こる?
ここで、簡単なセルフチェックをしてみましょう。
姿勢を正し、そっと唇を閉じてみてください。
上下の歯の位置関係を確認してください。
通常は、上下の前歯に2〜3mmの隙間(安静空隙)があるのが正常です。しかし、上下の歯が触れている方は、口内ボリュームが減少している可能性があります。
さらに、鏡でお口の中をチェックしてみてください。頬や舌に歯型がついていませんか?もし歯型がついていたら、舌が自由に動けず、口の中が狭くなっている証拠です。
この「上下の歯が常に接触している状態」を、東京慈恵会医科大学の杉崎正志先生と東京医科歯科大学の木野孔司先生は「TCH(Tooth Contacting Habit)」と名付けています。本来、TCHには歯ぎしりや食いしばりは含まれませんが、本投稿ではそれらも含めて“かみグセ”と呼ぶことにします。
“かみグセ”が招く健康リスク
“かみグセ”があると、次のようなトラブルが発生しやすくなります。
虫歯でもない歯が割れる
歯冠にクラック(ひび)が入り、虫歯を誘発する
歯周病が進行しやすい
顎関節症を引き起こす
詰め物や被せ物が取れやすくなる
入れ歯に過剰な負担がかかり、痛みが生じる
唾液の分泌が減少し、義歯が安定しなくなる
歯を失う主な原因は虫歯と歯周病ですが、“かみグセ”はこれらを悪化させる要因となります。
健康寿命を延ばす新しい習慣
「お口を閉じなさい」ではなく、
「唇を閉じて、お口の中は開きなさい」
これが健康寿命を延ばすための新しいキーワードです。

唇を閉じる
上下の歯は接触させない
口内ボリュームを広げる
舌の動きを自由にする
唾液をしっかり出す
これらを意識することで、健康的な口腔環境を維持し、全身の健康にも良い影響を与えることができます。
まとめ
私たちは幼い頃から「お口を閉じなさい」と教えられてきました。しかし、健康寿命を延ばすためには、単に口を閉じるのではなく、「口内ボリュームを確保し、舌が自由に動ける環境を作ること」が大切なのです。さらに口内ボリュームが広がると美容的にも嬉しいことが。別の記事も見ていただけると嬉しいです。
