
極上の肴①☆
蘇る想い
♪
その眼差しに触れ
胸は爆ぜ
その眼差しに触れ
喉は嗄れ
その眼差しに触れ
指は震え
告白はいつもこの喉の奥で空回り
独白はいつもあの後ろ姿で上滑り
何故別れたんだったか
今も喉は干上がり
(今もまだ痛いほど好きなのに)
今も胸は締めつけられ
(今もまだ痛いほど好きなのに)
今も指は伸ばせずじまい
(今もまだ痛いほど好きなのに)
嗚呼
何故 何故 何故
何故別れたんだったか
♪
その手を差し出せば
この全て差し出せた
命もくれてやれたのに
嗚呼
何故 何故 何故
何故離れたんだったか
♪
目覚めると古い歌が脳裏を駆け巡っていた。
唯一つの恋を揺り起こす慟哭が駆け巡る。
♪
今もまだ痛いほど好きなのに
嗚呼
何故 何故 何故
何故別れたんだったか
♪

「どうしたよ、フレ?
夢見が悪かったような顔してるぞ」

「あ、ああ、
夢は覚えてないんだが歌が、な……」

「歌? どんな?」

「ふっ……
其奴の為なら
死ねるほど愛してたのに
どうして別れたんだっけって歌、
随分前の外国の歌だ。
朝食は俺が作るよ。
ソー、玉子はどうする?」

「んー、ボイルドで。
あ!
水臭ぇなァ、
『香治』よゥ?
『音隠』の夢ェ、
見たんじゃねぇのォ?」
お袋の腹に居た頃からの付き合いの
幼馴染はベッドから跳ね起きると、
不良少年を気取っていた二十数年前のように
語尾を態とらしく伸ばして
その頃の偽名を引っ張り出し、
水を注いだ小鍋を私の胸へ突き出した。

「良く覚えてるな……
お前はあの時二日しか居なかっただろ」
我々は十七歳で一緒に家出して、
十九歳になる直前にソーは家へ戻り、
私はその直後に
音隠と響哉に出逢い、
三人の……
結果的に爛れた同棲生活が始まった。
その半年後の
ソーが陣中見舞いと言って
訪れた日を思い出す。
音隠、響哉、暫く隣室に暮らしていた音隠の双子の弟シャウ、
偶然同じ日に訪れた響哉の幼馴染里英、
なかなか癖の強い連中の
誰とも如才なく交流していた幼馴染を誇らしく感じたものだった。

「まぁな。
あン頃俺、
お前の事手放したくなかったからな」

「はぁ?!
『まじで』?」

「おう、『まじで』」

「え、は?
え、
その割には『つるっと』
聞き分けてくれたよな?」
ソーと私は、
家出前には共に赤裸々な『性的指向及び嗜好探険』をする仲だったから、
惚れた音隠に
その手の昔話を聞かせるのは勘弁してもらいたくて、
滞在費を持つ条件で口止めしたのだった。
あまりの動揺に意図せず、
四十を過ぎた今では
すっかり使わなくなっている言葉が蘇っていた。

「そりゃそうだろ、
嫌われるのは
もっと嫌だったんだからなァ」

「まじで?」

「おう、まじで」

「…………」
愛だ恋だ惚れたの腫れたのは
我々の間には一生有り得ないと思い込んで、
否、
有り得ないと思う事すら無かった私は
非情極まりなかったに違いない。
長過ぎる時間に思い至り、
とうとう私は絶句してしまった。

「くっくっく、気にすんなよ。
この八年は
ちゃんとミーナに惚れてっから」

「……なら良かったよ。
あの時も……
二十云年進展してない今も、
俺は彼奴の為にしか
死にたくないからさ」

「へっ、
俺はさ、
ミーナが教えてくれたんだよ、
そーゆーの。
俺はお前を愛してると思ってたんだが、
お前の為に死ねる気は
しなかったんだよな、
ずーっと。
お前の為に骨を折るのも
胃を傷めるのも苦にはならねぇけど、
死ぬのはまた別のハナシだと
思ってた訳なんだよ」
ソーは大きな泡が湯気と共に立ち上り始めた
鍋の火を止めて蓋を被せると、
パンをトースターへ放り込もうとした私を制して、
勝手知ったる冷蔵庫を漁って
肴をあるだけ取り出しては、
食卓へ運ぶワゴンに載せた。
二人が口を開く度に
未消化の茶色いアルコールが揮発して
台所に溢れ出てるというのに、
此奴は未だ呑む気らしい。

「まだ呑むのか?」

「まぁな、
また暫くお前とは呑めなくなるだろ、
十九時まで付き合ってもらうぜ」
私は観念して
応接室の飾り棚から
莫迦高かった果実酒の箱と
リムの狭まったクリスタルグラス二脚を取り出した。
私が己の力で初めての大きな成功と金を手にしたと思った
若かりし日に、
馴染みの調香師から運良く発売を報らされ、
何時かきっと訪れる
特別な祝いの為にと手に入れた限定生産品だ。
百年熟成された三二五種の原酒を厳選調合し、
この為だけに特別に誂えられた美しい瓶に詰められている。
瓶の封蝋と重厚な木箱に刻まれたシリアルナンバーは三二五/三二五、
箱だけでも空き瓶だけでも
言い値で買い取ると宣った者も在った品だ。

「おぉん?
とうとう舐めさせる気になったか!」

「ああ。
あとたった十時間とはいえ、
晩餐を控えてるんじゃ、
ばかすか呷る訳にはゆかないだろ」

「ああ、そうだな。
へへっ、
そーゆー所だよな、
お前の良い所って。
他の奴じゃ、
俺をとっとと帰すか、
質より量で酒瓶を掻き集めるか、
無理矢理俺の胃袋へ
珈琲牛乳をホットサンドの上から流し込むか、
だろ?」

「あー、
そうかもしれんな……
くっくっく……」
明日相愛のミーナと盛大な結婚式を挙げるソーを、
帰そうとするのは、
昨夜最初に酔い潰れたラースや、ラースの兄貴と従弟達。
質より量は、
昨夜最後まで粘ったジュリオや、飲み会では必ずビタミンC製剤を配るロザンナ達。
珈琲牛乳は、
今頃胸焼けでもんどり打ってそうなミーナだろう。
私の良い所なんて言ってはいるが、
誰も悪気は微塵もない事は此奴にも解っている。
ラース達のだって此奴とミーナにとっての最善を想っての判断だと。
ただ、
彼等の判断では手前がツマラナイというだけの評価基準だ。
私が木箱を手渡すと、
呑兵衛は一旦調理台へ箱をそっと置いて
舌なめずりしながら指輪と腕時計を外し、
肘まで手を石鹸で洗ってから、
恭しく開封の儀を執り行った。
マリエラセス神殿の西庭
(夭逝した者の内、
記憶の記録を司るマリエラセス神に仕える事を選んだ者が、
神殿内の雑務の合間に憩う場所で、
果樹に囲まれていると伝えられている)
の門を模した
寄木細工の箱の観音開きの蓋を開くと、
二人の翼人が腰掛けていた。
翼人は調香師の夭逝した両親に似せたのだそうだ。
二人の足元には原料とした……
葡萄、林檎、桜桃、李、梨、
これ等の果実が溢れている。
乳白色のガラスは、
光の加減と角度に依って淡く七色に輝き、
内に秘めていた生命を芽吹かせた。

32歳祝賀記念酒瓶】
穏やかなひとときを暫し共有した後に、
友が封蝋をナイフで丁寧に切ってから
栓を捻り開けると、
既に酒臭かった筈の台所に、
馨しくふくよかで
あたたかなのに瑞々しく
すっと背筋が伸びるような
清廉な香りが躍り出た為に、
思わず
二人して顔を見合わせて呻いていた。

「何だこれ……すげぇな」

「これは……これほどとはな」
香水屋の威信と道楽の総てを賭けて調合された果実酒は、
第一芳香だけで
調香師アルシャレストの創る香水同様に
我々を魅了したのだった。
ソーは半量をデカンタに移して栓を閉めると瓶を箱に戻し、
食堂の予定を変更して
勝手知ったる応接室へ向けてワゴンを押した。
二人差し向かいに応接室のソファに深く腰掛けて、
グラスを薫らせて
馥郁たる酒の香に暫し耽溺した後に、
彼は悪戯っぽく右口角を上げて笑んだ。

「味はチンキ並だったりしたら
ウケる(意:笑える)な」

「くくっ、
それじゃまんま香水じゃないか。
ミドルノートとラストノートも
所望しなきゃ
割りが合わない」

「そうだよなぁ、思い出したぜ。
三百二十五万したんだろ、これ。
アルシャレストへの祝儀も含めた
当人の値付けだと何処かで読んだよ。
くっそ巫山戯てるよなァ!」
そう、パーティ券に三百二十五万レイト(通貨単位)支払ったのだ。
尤も、
豪勢な個別休憩室付き客船会場での
豪勢な立食パーティだけで百二十五万レイトの価値はあったので、
酒だけに支払ったつもりは毛頭無いが、
二百五十二万レイトが
あの当時の法定最低常勤年給手取り額で、
これを十二で割った二十一万レイトが
一ヶ月の行政の生活保障(地代・家賃・上下水道費・光熱費は一定額まで行政負担)金額だった。
独り暮らしをしていた当時の
平均的な月の私の個人家計記録が、
収入四十五万レイト、
地代・家賃十万レイト、
光熱費一万五千レイト、
一日二回自炊・一回安価外食ながらさしたる切り詰めもせず
勤務日食費三万二千レイト、
週末食費二万八千レイト、
通信費五千レイト、
情報費(電子新聞雑誌等)五千レイト、
上下水道費四千レイト、
交通費二万レイト、
嗜好品(煙草・酒)費一万レイト、
日用品費三千レイト、
医療費二千レイト、
単独遊興費八万レイト、
交際費六万レイト、
教育費八千レイト、
被服費五万レイト、
貯金二万八千レイト、
以上だ。
三百二十五万レイトの価値が分かるのではないだろうか。
因みに法定常勤条件は一日七時間を週五日、
これを四週で一ヶ月計二十日勤務する事だ。
税や保険は雇用主が負担する。
行政負担額より多く支払った地代家賃水道光熱費は、
二割の行政管理費を差し引いた額が年金として無職時に給付される。
地主は国連で、
家賃も事細かに決められており、
不公平と不正は無い。
マリエラセス連邦以外の土地単価は
ヒューマンが健康な場合は鍛錬無く住める環境であるという理由で一律だ。
せっかく土地が肥沃であろうが
工場や住居を建ててしまうのがヒューマンだから、だそうだ。
ともあれ、
件の大成功月に
私は生業で初めて一千万の純利益を手にしていた。

「まったくだよなぁ、
二十歳まで生きられないと
医師に宣告されていた彼女が、
両親も迎えられなかった
三十二歳の誕生日
三月二十五日を、
無事越せた特別な祝いだから
祝儀を……
弾んで『もらう』と
自分で言い出す所が
彼女らしいとは言えるが、
くっくっく」
二十六年前家出直前に
上の姉に無理矢理連れられたオーダーメイド専門の香水屋は、
家出から帰ると既に代替わりしていた。
最初経営者に自慢の孫だと紹介された
アルシャレストは一歳しか上でないと
聞かされていたから衝撃的だったが、
彼女は彼女に好意的な誰の事も落胆させなかった。
己が受け継いだ両親の才能と、
己の努力と、
己の加護と、
己の環境と、
己の宿命と、
報われる未来、
これ等全てを強い意志で信じて、
常に減り張りを忘れる事なく
精進していたからだろう。
三十二歳祝賀パーティから十一年経ったが、
彼女は今も健在だ。
初回同様、
誕生日から半年後の九月二十五日に
毎年盛大なパーティを催す。
彼女の生きる事を謳歌し尽くす姿は
誰の目にも目映いばかりで、
年々招待を望む声が増す一方だというのも頷ける。
五十年熟成された三百二十五種の原酒を厳選調合して黒瓶に詰め、
毎年趣向を凝らした手書きラベルを貼って、
三万二千五百レイトのパーティ券と引き換えるが、
同じ日に
半量瓶に印刷ラベルの三百二十五本を
三千二百五十レイトで市場に放出する為に、
彼女を祝う気もない連中が
珍酒目当てに会場に押し寄せる事は無い。

「へぇ、ちゃんと美味いぜ」

「ほぅ、ちゃんと美味いな」

「驚きだな。
百年熟成なんか
精々八十種までしか
合わせないほうが良いだろうって
書いてた奴も居たろ?」

「ああ、読んだ事あるよ。
ふっ、これを舐めて
考えを改めたとも
その後に書いてたけどな。
奴さんとは好みが合わないから
あまり期待してなかったんだが……
美味いな」

「へぇ、
あの号でつらつら長ったらしく
持論を展開しやがったから
コノヤロウと思って
次は読まなかったんだ」

「お前の中の
便乗警察が出動した訳だな」

「そう、それ。
うーん、
堪らねぇな……
炭酸あるか?」

「ああ、(炭酸)要るな。
取ってくるよ」

「おう、頼むわ」
肴の後で口内を濯ぐ炭酸の瓶と、
口内に残る炭酸の刺激を鎮静させる
弱アルカリ性の軟水の瓶を手にして私が貯蔵室から戻ると、
幼馴染は勝手に飾り棚から引っ張り出した
私の自慢の逸品の
フルートグラスとタンブラーを磨いて待っていた。
こう見えて彼は美味い酒に対して、
またそれを以て饗した私に対して、
最上級の謝意と敬意を表しているのだ。

「さて、
残る極上の肴は
極上の想い出話だと思うんだよ、
俺は。
へへっ、
洗いざらい一切合切
話を聞かせてもらおうじゃないか、
『香治』君よぅ」

「まじか……」

「もちろん、まじさ。
音隠との出逢いがお前に無かったら
俺はミーナと出逢ってないんでな、
興味津々なんだよ。
今では、な」

「そうなのか?
一体どういう歯車だったんだ?」

「先ず、
異性体女性自覚者は熱烈歓迎だが、
女性体異性自覚者とは
好意的に話せる気がしなかったよな、
あのままの俺だったら。
お前の縁で
自主強制的に
響哉や音隠と、
いざ話してみたら
全然平気だった訳だが、
まぁ、
俺っておっぱい愛してるじゃん?」
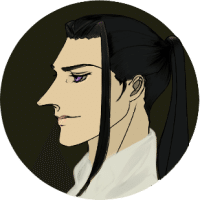
「あぁ……
くっくっく、
大小を問わず形を問わず、な……
乳房を棄てようとする奴なんざ
許せなかったよな。
作ろうとする奴は大歓迎したし?」

「へへっ、
そう、それなんだよ。
音隠と
音隠の双子の弟のお陰で
双子にも縁ができたらしくてな、
帰国して半年ばかし経った頃に、
前なら行かなかった
サワマナ宮東のクラブで
可哀想な双子に出会ったんだよ」
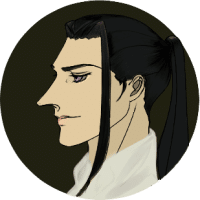
「ほう、
異性自覚者が集う地区だな」

「そう。
彼奴等と同じ二卵性の男女、
違うのは
二人揃って性自認が逆なんだ、
可哀想だろ?」

「それは確かに……」

「あの頃の響哉みたく
違和感に揺れてる時期ってんじゃ
なくてな、
確として
身体を交換したがってる訳だよ」

「あぁ、
ミーナの両親の
若かりし頃みたいな……」
ミーナの両親は恋愛結婚して
ミーナを授かった後で、
二人夫々に性自認に違和感を覚え、
最終的に父母の役割も交代したのだと、
以前この友から聞かされた話を
私は思い出していた。

「ずばりそれ。
ある有名な先達に話を聞きたいが、
手前等は半年前まで
『遠いどいなか』に居たから
伝手が全く無くてと言うんだよ。
先達ってのを軽く調べたら、
ウチの学校の卒業生で、
その昔は
ウチのお袋の
家庭教師だった人な訳だよ」

「ミーナの生母さんか!」
今でこそ異性自覚者は少数ではない事と、
性自認が揺れる事は何一つおかしくない事と、
自認される性別は二三では足りない事とが
広く知れ渡り、
各個人の自認性を尊重し、
性別は、
中性・両性・無性・女性・男性の中で
十歳から十年ごとの誕生月に選べる世になっているが、
ミーナの両親が社会運動を始めた頃は、
両性・男性・女性という三性しかない上に
人生に一度、
成人する誕生月にしか
性別の更新ができなかった。
彼等は最初に手を挙げ大きな声を上げた、
異性自覚者達にとっては
創神者に等しい存在となっていた訳である。

「そう。
前なら絶対に出さなかった親切心が
ミーナつぅ(という)
歯車を引き寄せた、
という次第なのさ」
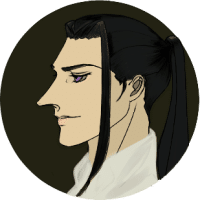
「なるほどな……
それは感慨深いよなぁ。
連るんでた頃のお前のままだったら
先ず
出会って直ぐの奴に
深入りしなかっただろうからなぁ」

「そう、
よしんば生業で携わるようになっても
ドライな関係を維持したと思うよな。
ま、そんなこんなでさ、
お前達は良縁結びの神の
(使徒精霊である)
黒金蜘蛛顔負けの
縁結びをしてくれた訳でな、
♪何故、何故、何故、嗚呼、何故……♪」
ソーは、
あの日あの時あの場所で繰り返し流れていた
歌を口ずさんで
次の歌い手の杯を満たした後に、
デカンタの口を私に向けて掲げ、
先を促した。

「♪その手を差し出せば、
この全て差し出せた、
命もくれてやれたのに、
嗚呼、
何故、何故、何故……♪
くっくっく、
あれ以来
聴いてもいないのに
良く覚えてるよなぁ」

「あの九柱戯場でずっと流れてただろ、
八時間も居りゃ洗脳に充分って事さ」

「間違いないな、ふっ。
…………
……本当に聞くのか?」

「おぅさ、話してくれよ。
聞いたハズの話は
当時殆ど右から左なんでな」
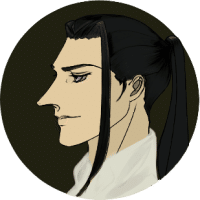
「あー……把握。
了解」
マリエラセス暦四〇三三年一月十日黒曜日
(第一話:蘇る想い:了)
いいなと思ったら応援しよう!

