
日本発ブラジルのドキュメンタリー映画『街は誰のもの?』グラフィティとサンバの共通点って
サンバに通ずること有り!
ブラジル好き必見の作品:『街は誰のもの?』
ブラジルの路上に絵を描き続ける人たち。
いったいなぜ?
「存在したかったんだ。
この街に存在したかったんだ。」
グラフィテイロ*がつぶやく…

Image:Mizuki Mashow
鑑賞後、阿部航太監督のトークショー有り!(土・日。夜の部はQ&Aも!)
ブラジルで6ヶ月もの間取材を続け
本作品をつくり上げた監督。
書き下ろし4万字のパンフレットを買いました。
観ればより興味をひかれる作品。
12/11から
渋谷シアター・イメージフォーラムにて上映中!
(終了しました)
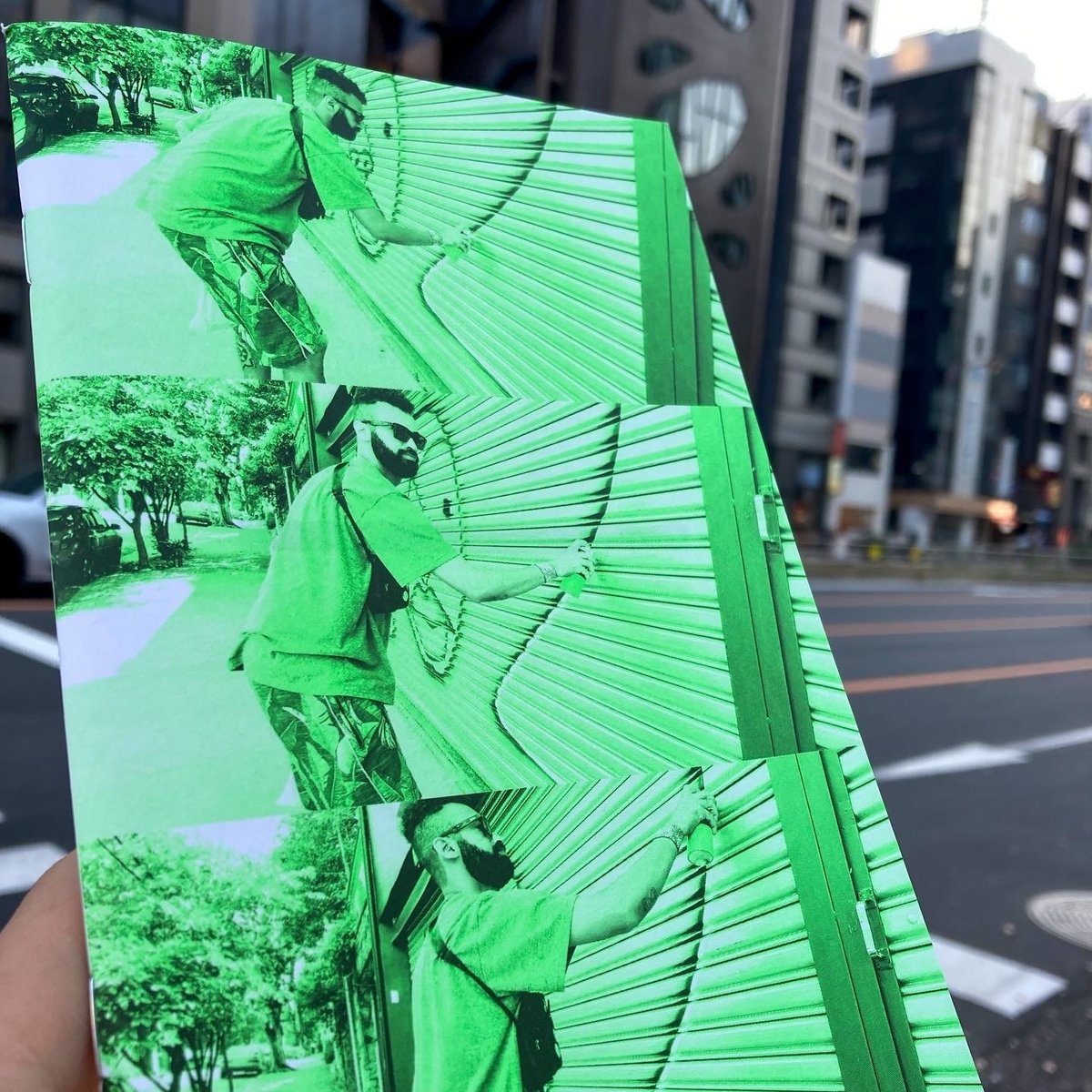
◇◆◇
■鑑賞後、パンフレットを読んで
(※一部ネタバレを含みます)
グラフィティとは
行政や壁の所有者に無許可で絵を描く違法行為、その絵のこと。
原則、報酬はありません。
摘発されれば(サンパウロの場合)
「罰金は5,000-10,000レアル(10-20万円)」(パンフレット35頁)
危険と隣り合わせで描く即興のアート
それがグラフィティ。
2006年
大型ビルボード広告の設置がサンパウロ市で禁止以降、グラフィティは新たな局面を迎えました。

サンパウロ市街で設置不可な広告
広告亡き後の世界
残された巨大な白い壁Empena(エンペナ)。
やがて巨大な壁画が描かれるようになりました。Projeto(プロジェット)といって
グラフィティとは別物。
合法かつ報酬があります。
(パンフレット25、29-31頁)

2018年3月サンパウロ市
Image;Mizuki Mashow
「その『仕事』を収入源として生活できるポジションを、多くのグラフィテイロたちは目指している。」(パンフレット30頁)
「プロジェット1本でしばらく暮らせる額が手に入る」(阿部監督談、トークショーにて)
卵が先か鶏が先か
グラフィティは
「多くの市民に『カラフルで綺麗なもの』として受け入れられている」そう。
(パンフレット31頁)
サンパウロ市
「選択」と「集中」でつくる観光地
Beco do Batman(ベコ・ド・バッチマン)
これらはグラフィティ?それともプロジェット…?
興味深いのはPichação/Pixação(ピシャソン)
「多くの市民には受け入れられていない」
ピシャソンは
自らのチーム名を暗号化して
黒一色で描くことが多い文字ベースの表現物。
グラフィティと同じく違法。
「アンダーグラウンド」
彼らはなぜ自らのチーム名を描くのでしょうか。
「昔はチームの縄張り争い的な要素が強く、抗争も絶えなかった。(中略)『不良の落書き』という認識にかなり近いように思える。」
(パンフレット31項)
◇◆◇
1980年以降、
産業の構造転換に失敗したとされるブラジル。
低成長率、高関税、慢性的に高い失業率。
土地所有の偏在。
世帯所得1万USドル(約110万円)を下回る層が56.2%を占めました。
(出典:経済産業省2020年)
劇中、鶏卵40個10レアルと宣伝する行商。
これを3でかけると日本の物価とほぼ同じ感覚に。600円で鶏卵40個。だいぶデフレですね…

資本格差が恒常化している
ように見えるブラジル。
ブラジルでは日本のように公的な創業融資金は借りられるのでしょうか。マイクロファイナンスがスタートアップで始まっているという話を聞きます(参考:TechCrunch)。また、孫正義氏のソフトバンク・グループが、オンライン金融会社のクレディタスに対する約256億円の投資を協議中との報道もなされています(参考:Bloomberg)。
ブラジルのネット銀行がNY証券取引所に上場!「初値での時価総額は約520億ドル(5兆8800億円)、(中略)スマートフォンを用いた簡易な口座開設やカード発行が利用者の支持を集めている。現在はブラジル、メキシコ、コロンビアで合計4800万人の利用者がいる。」(参考:日経新聞)。
ブラジルの産業転換について詳しくは、田中祐二「ブラジル:ラテンアメリカの経済動向との比較と『中所得国の罠』」(2017)後藤政子・山崎圭一(編著)『ラテンアメリカはどこへ行く』ミネルヴァ書房 をご参照ください。
資本の階級を駆け昇るため
プロジェット受注を目指し
グラフィティに励む。
一発逆転の手段、それが絵を描くこと。

『街は誰のもの?』
ブラジル好き、
サンビスタは
ぜひ観ておきたい、そんな作品です。

サンバ仲間Glória😎ポル語部🇧🇷で観てきました⏬

リオのカーニバルのパシスタ経験者いわく
「少しハイコンテクストな作品」
なぜグラフィテイロたちが「存在したい」というモチベーションを強く感じているのか。
ブラジル渡航の経験者いわく
「ブラジルで普通はなかなかいけない場所が見れたのが良かった」
かなり踏み込んだ取材だったのだと想像します…
コロンビア居住経験者いわく
「コロンビアも似ている」
本作が映すのは
階級社会のラテンアメリカ諸国に共通した現象
なのかもしれません。

◇◆◇
■2022年2月ブラジル取材について
(※以下、告知を含みます)
ブラジルのサンバも
Risingするための舞台であり、手段。
多くのダンサーやバテリア(楽器奏者)が
夢をみて、それを叶えつつあります。
2022年2月は、
そんな現地の様子を
地元密着で取材して参ります。
▼Bellinha Delfimさん
地元でショップ店員をする傍ら
複数のエスコーラでパシスタに選ばれ
リーダーを経験し
2021年Musa(タレント)にRisingしました
▼古巣Salgueiroに凱旋

↓にスクロールすると《音声📣》が流れます。
▼Risingを後押しするエスコーラSalgueiro
Salgueiroの本拠地に住み込んで
しっかり勉強・取材して参ります。
その様子はnoteやYouTubeで発信します。
見ていただけると嬉しいです。
▼詳しくはこちら
▼Twitterもフォローお願いします!
(おわり)
リオのガイドします✋
▼DMお待ちしています(Instagram or Twitter)



