
【連載企画】誠の人 小村寿太郎没後100年
世界経済の勢力図が激変するいま、小村が残した足跡は複雑化する外交課題を解くヒントとなる。没後100年を機にその業績と人物像に迫る。
※このコンテンツは、2011年11月24日~2011年11月28日まで宮崎日日新聞社・社会面に掲載されたものです。登場される方の職業・年齢等は掲載当時のものです。ご了承ください。最後に番外編があります。
1. 不世出
太平洋沿岸諸国の神経戦が続く環太平洋連携協定(TPP)問題、ギリシャ財政危機に端を発した円高・ユーロ危機―。中国、インド2大国の台頭も加わりアジアへの関心は増大、日本外交はいままさに正念場を迎えている。そんな中、日南市飫肥が生んだ外交官小村寿太郎が今月26日、没後100年を迎える。
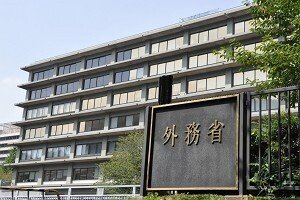
立場で臨む「小村外交」の精神は後輩外交官へと引き
継がれている
■絶賛 腹据わった名外交官
激動する世界情勢は、小村が外交官として手腕を発揮した1900年代、列強がアジアに向け牙をむいていた状況にも通じる。外務省事務次官、アジア大洋州局長などとして、北朝鮮による日本人拉致事件への対応など難しいかじ取り役を務めてきた薮中三十二外務省顧問(63)は「日本が世界に目を開いていく、スケールの大きいドラマチックな時代に大きな仕事をした人物」として先輩外交官2人の名前を挙げる。1人は不平等条約の治外法権を撤廃した陸奥宗光、もう1人が小村寿太郎だ。
薮中顧問が評価するのは、日露戦争時のポーツマス講和条約締結(1905年)をはじめ、幕末の開国時に放棄させられていた関税自主権の回復(11年)を成し遂げた小村の功績。よちよち歩きの日本を列強諸国と対等に渡り合える立場にのし上がらせた
手腕を「ボンボンでない、相当腹の据わった勝負をやれる人物。日本はいいときにいい人がいてくれた」と絶賛する。
■飫肥藩の戦略 列強諸国と果敢に交渉
小村が生まれ育った日南市飫肥。江戸期まで飫肥藩の城下町として歴史を重ねてきた街並みは旧家や城跡が昔の面影を残し、木材業などによる長年の繁栄を裏付ける。一方、藩の置かれた戦略的立場は決して恵まれていない。石高で10倍以上の差がある隣国・薩摩藩の島津氏と戦国期以前から敵対、脅かされながら明治期までしたたかに生き残ってきた。
長年、日露戦争について研究、外交史家として小村の業績を熟知する松村正義さん(83)=千葉県習志野市=は、大国ロシアに対し、一小国にすぎない日本を勝利へと導いた小村の的確な外交手腕は「故郷飫肥と薩摩の関係から学んだ」と指摘する。
迫り来るロシアとの激突は避けられないが、全面戦争では勝ち目がない、そこで「1年」と限定して戦いを優勢に持ち込み有力な仲介を介して講和に持ち込む―。薩摩をロシア、飫肥を日本、そして仲介者には徳川幕府をアメリカに投影して小国の生き残り策を模索したとし、その慎重で果敢な才覚を高く評価する。
日露戦争 1904(明治37)年2月、朝鮮・満州(現中国東北部)の支配権をめぐって日本、ロシア間で起きた戦争。満州占領を続けるロシアに、米英の支持を得た日本が宣戦布告。日本海海戦などで日本が勝利し、05(同38)年9月に米ポーツマスで両国が講和条約を結び終戦した。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
