
60年に一度の御開帳
ある町に竹造という若者がいた。
この若者は名前の通りまっすぐな性格をしている。だから仲間内の話であっても、ついついいらぬことを口走ってしまい、遂には誰からも相手にされなくなった。
また、この若者は信心深いことでも有名であり、自宅の近くにある観音菩薩が祀られた寺に日参している。
この寺の本尊とされる観音菩薩は秘仏とされ、通常は厨子の中に安置されたまま60年に一度だけ御開帳される。だが竹造は一度も見たことがない。前回の御開帳は竹造が16歳の頃なのだが、竹造には見たという記憶すらない。
実はこの寺には観音菩薩と並び称される弁財天も有名である。
その弁財天は寺域にある池の畔にたたずみ、微笑みを絶やさない愛らしいお顔とグラマラスなボディをされており、琵琶を持つ指先でさえ色気が漂う様子が人気を集めている。
この弁財天、実はとってもいたずら好きなのだが、もちろん人間にわかるようないたずらをすることはない。

竹造が日参するようになったのは10歳の頃。母が病の床についたのがキッカケだが、早朝に寺に詣り、本堂や弁財天のまわりを掃除、家に戻っても兄弟姉妹と家事などを行いそれから学校へ行く。
学校が終わっても遊ぶことなく(もっとも遊ぶ相手など竹造にはいないのだが)家に戻り家事をする。ある意味、寺だけが心安らげる場所であり、竹造の自由になる時間でもあるのだった。
竹造はこの寺に日参はするものの、何を願うわけでもなく、なんなら何を祈るわけでもない。ただひたすらに頭を垂れ手を合わすだけなのだ。
その真摯とも取れる姿をずっと見続けてきたのが池の畔の弁財天。
時には少女に扮し、竹造に話しかけたりもした。時には妙齢の女性に扮し竹造の隣で御自ら自身の弁財天像に手を合わせたりもした。
弁財天は真面目で一途な竹造が気になって仕方がないのだが、どれだけ気を引いてみても竹造がその気になることはなさそうだった。
『こんなに美しい私に興味を示さないなんてなんて人なの』

どうしても竹造に振り向いてほしいと願う弁財天は、近々御開帳を迎える観音菩薩に相談することにした。
『観音さま、毎日何十年と途切れることなく寺内の掃除などをしてくれている竹造という男をご存知でござりましょうや?』
『その声は弁天かや?』
『そうでございます』
『その竹造とかいう男はお前のなんだ?』
『わたくしが気にしてる男ではありますが、一向に靡いてはくれませぬ』
『ふむ。それで?』
『できますればこの次の御開帳で言い含めてはもらえぬかと』
『その男は絶対来るのか?』
『それは間違いござりませぬ。何十年もの間こちらへ詣るのを一度たりとて欠かしたことがございませぬ』
『それほどに熱心な男か。して、お前の僕となれと命じればよいのか?』
『それでは少々殺伐とはしておりませぬか』
『お前はその男と色事を望むのか?』
『できますればこの自慢の胸に顔などを埋めてもらえれば』
『それは良い。我らもたまには楽しまぬとな』
『観音さまもお好きでござりますか?』
『もちろんじゃ』
『ということは60年振りでござりましょうや?』
『まぁこの世ではそうなるな』
『ではごゆるりとお楽しみになられますように』
『うむ。ところでお前のその男、名は何と申したかの』
『竹造でございます』
『間違うとお前に叱られそうじゃからな』
『滅相もございません』
『して若いのか?』
『齢は今年おそらく76歳かと』
『ずいぶんな年寄りじゃな』
『我々の年齢から考えると赤子同然かと』
『役に立つのか?』
『さてそれは…………』
『開帳の日が楽しみじゃな』
『ではよしなにお願い申します』
『そちの願いはしかと聞いたぞ』
そして2025年2月2日の節分、ご本尊御開帳の初日が始まろうとしていた。この日もよく晴れた日である。遡ってみても御開帳の日は天気が良い。
竹造はいつも通り早朝に訪れ寺域の掃除をしている。

『そちが竹造か?』
『???』
『これ、この声が聞えぬか?』
『声はすれども姿は見えぬ』
『ほんにお前は屁のようなって誰が屁じゃ』
『儂に話しかけるんはどなたじゃ』
『今日が開帳の日だということは知っておるか?』
『知っとるよ』
『見たくはないのか?』
『そんな時間がねぇ』
『一日中忙しいのか?』
『そうだ』
『吾を見に来る時間も取れぬのか』
『吾? ひょっとして観音さまか?』
『ようやく気付いたか』
『ホントに観音さま?』
『そうじゃ』
『狐に化かされとるんか』
『今時そんなヤツはおらんじゃろ』
『…………』
『おまえの日頃の寺内の活動に鑑み、申し渡したいことがあるゆえ、夜でもよいから必ず来い』
『へぇ』
『必ずじゃぞ』
『へぇ』
『頼りない返事じゃな』
『へぇ』
『来れば良いことがあるぞ』
『へぇ』
『待ってるからな』
『へぇ』
『へぇばかりじゃな』
『ほんにお前はへぇのような』
『上手い‼︎ってなんでやねん』
『遅くなればお堂も閉まっとるのではありませぬか?』
『お堂が閉まっていれば当然厨子もしまっておろう』
『へぇ』
『お堂の前で一つ手を打て、さすれば扉が開くから中へ入るが良い』
『へぇ』
『入れば勝手に扉は閉まるが驚くでないぞ』
『へぇ』
『次は厨子の前で一つ手を打て、さすれば開帳となる』
『作法も何も存じませぬが』
『そんなものは手取り足取り教えて進ぜよう』
『よろしくお願いいたします』
『うむ、では夜に参るがよい』
『へぇ』
夜も更けた頃、節分とはいえ真冬。寺の参道はかなり冷える。そこを灯り一つ持たず、トボトボと歩く竹造が寺を訪れた。
『あっ!!』
竹造が一つ手を打った。
かすかな音が聴こえてくる。
もう一度手を打った。
もっと小さな音がして、本堂の中が光り輝いてるように見える。
『竹造、お前どこにおる?』
『観音さま、山門が閉まってますぅ』

ここで終わるのは不本意なれど、長くなり過ぎるのも考えもの。
このあと、観音さまの御開帳、弁財天とのやりとりへと続く予定ですが、今回はこの辺で終わりとしましょう。
機会があれば続きが読めるかもしれません。

John Lennon & Yoko Ono / Happy Xmas (War Is Over)

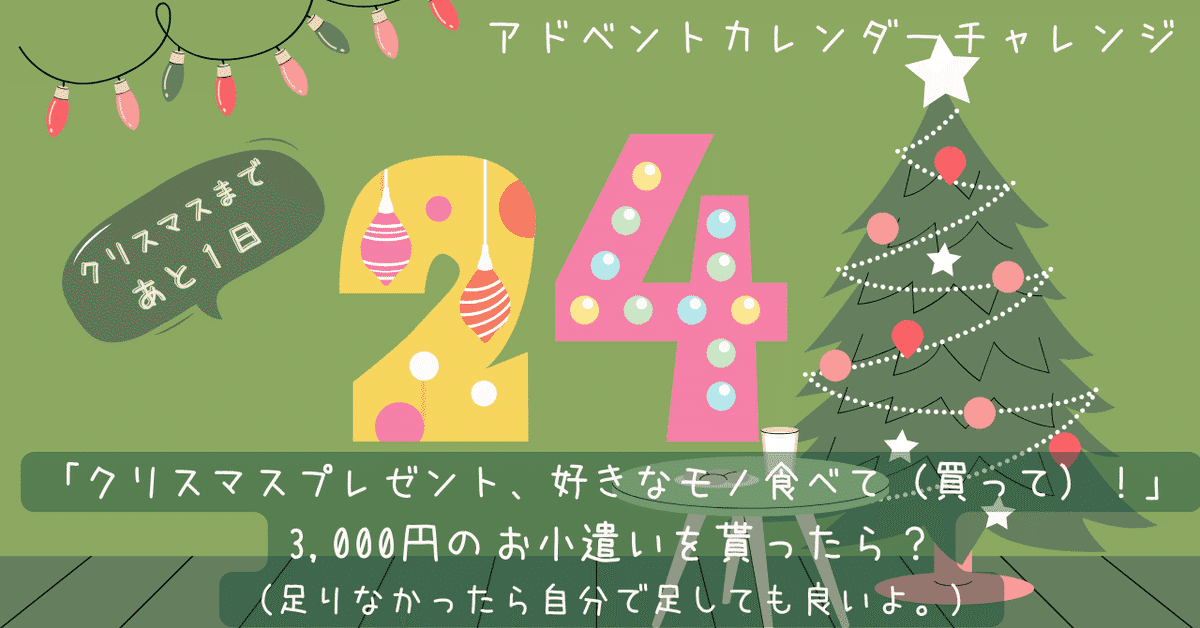
現状ずいぶんガタが来てるので新しい自分が欲しい
3,000円ではないかなぁ?
