
ピルケとシックの血清病研究を振り返る
1905年のオーストリア・ウィーンで、二人の小児科医が「血清病」と題した書籍を出版した。120頁に亘る詳細な研究論文であり、症状を慎重に特徴化させた初の作品だった[1]。この書籍は後に古典的作品となり、免疫学における多くの重要な問題を照らし出すこととなった。
抗毒素血清療法
19世紀後半、研究者は、特定の細菌性疾患に対する救命用の抗毒素の開発に励んでいた[2]。科学者は、実験室で培養させた細菌から毒素を取り出す方法を学んだ。彼らはその毒素を、馬を中心とした動物達に注射し、動物の免疫系に抗体を産生させた。その後、動物の体内から抗体を回収し、純粋化し、血清として人々に投与した。抗毒素は、コルネバクテリウム・ジフテリア(ジフテリア菌)等の、バクテリア毒素の中和に成功した[3]。
1890年に破傷風抗毒素が開発され、翌年にはジフテリアの抗毒素治療の初症例が記載された。こうした抗毒素は、すぐさま臨床現場で一般的なものとなった。臨床家は抗毒素を、感染者の治療や、感染爆発の制御等を目的とする予防的投与に使用した。C.ジフテリア菌の抗毒素注射は、約3週間に亘って患者に免疫を付与した[4]。
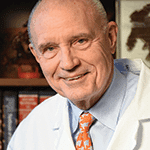
ワシントン大学セントルイス校医学部
ワシントン大学セントルイス校医学部のサミュエル・B・グラント教授、ジョン・P・アトキンソン医学博士は次のように述べている。
「抗生物質の登場前です。当時は有効性が明らかな唯一の治療法でした。」
救命に奏功する一方、瞬く間に抗毒素血清は時に副作用を引き起こすことが認知された。血清の投与後、稀に急速なアナフィラキシー様の反応が観測された。
しかし、それとは別のタイプの反応がほぼ毎回観測され、当初”血清発疹”と命名された。この自然治癒反応は致命的ではなく、然程重要と判断されなかった。しかし、この反応に関する理解が進むに連れ、免疫学における多くの重要なプロセスの広範な理解が得られることになる[1][5]。
血清病
1903年から1910年に亘り、ウィーンの小児科医クレメンス・フライヘル・フォン・ピルケ博士が緻密かつ重要な観察に取り組み、これは免疫学とアレルギー学の基盤を提供するものだった[5]。”Die Serumkrankheit(血清病)”のタイトルで公になった研究は重要な要素であった。ハンガリー出身の小児科医で、ウィーン大学でテオドール・エシェリッヒ(大腸菌の発見者で知られる)の研究室で助手として勤務していたベラ・シック博士と共同で研究論文を執筆した[6]。

アーサー・M.シルバースタイン博士(免疫学者、科学史家、ジョンズ・ホプキンス医科大学ボルチモア校眼科免疫学名誉教授)はこう述べている。
「実に驚異的で注目に値する研究であった」
「実に美しい。」アトキンソン博士が加わる。
「非常に論理的で示唆に富み、木目細かな配慮がなされています。生じる問題について、次から次に段落へ落としていくのです。血清の投与量、投与部位、治療対象の疾患、患者の年齢、病状、あらゆるタイミング等々。その全てが、長い臨床記事とも呼べる文書に慎重に記述されていました。」
二人は初めて症候を詳述し、免疫プロセスの果てに血清病が生じることを初めて提唱した[5]。
臨床的記述
論文の第一章”血清病の臨床的側面”が、文書全体の半分以上を占めている。ピルケとシックは、クリニックに来院した成人と児童の症例を参照しつつ、症候の性質と疾患の経過を深堀した。特徴的な臨床症状の生起するタイミング、白血球数や沈降素等の実験室での発見を示す詳細なグラフを掲載した。
冒頭で、二人は症候の改名をした。
「我々は”血清発疹”の表現を破棄した。この命名は、発疹が疾患の最重要の症状だと容易に連想させるものと考えた為である。故に我々は、”血清疾患”、或いは”血清病”の名を提案する。」
二人は、事前に抗血清剤の投与を受けていない患者の症状の生起するタイミングを慎重に記していた。
「多くの場合、病状は注射後8日から12日の間に突発的に始まる。…この潜伏期間は、外来血清の吸収の遅延では説明できない。血清の抗毒素効果は数時間以内に発揮される為だ。」
アトキンソン博士は、このタイミングが、現代人の知る所の抗体産生の時期に一致することを確認している。
「人間は抗体産生に5~6日を要します。まずIgM、数日後にIgGが生じます。それが馬血清…(免疫グロブリンと、精製の精度・純度次第で雑多なタンパク質も混じる)…と相互作用します。比率と沈降反応により、腎臓や関節部位に免疫沈降物を形成します。その後は二日以内に清掃されて全て消失します。」
「発疹と発熱はどちらも最も一般的な問題です。」アトキンソン博士は述べる。「二人は発熱のその温度と持続時間も記述しています。関節痛を訴える小数例についても、どの関節か、左右対称か非対称かに至るまでです。タンパク尿を出す患者にも言及しました。」また、症状の中にリンパ腺の腫脹と全身浮腫も指摘し、患者の体重の推移で慎重に記していた。
そして、ピルケとシックは、血清の投与量と症状の生起時期との関係について重要な洞察をしている。
「症状の強度もまた、血清の量に応じて明らかに増強する。血清病の予防措置は、第一に血清量を最小限にすることである。」
再投与
第二章では、二回目の投与を受けた場合の反応差を慎重に記述している。臨床病棟で感染したことによりジフテリア抗血清を投与された大勢の児童を観察した。そこで、事前の投与経験の有無の違いを指摘している。再投与を受けた児童は、しばしば急激な反応を呈し、時には24時間以内に生じることもあった。
「この差異は抗原(投与した血清)に起因せず、実験で証明した通り、同じ血清が多様な形式、多様な時期に反応を生起させた為であり、これは生体への初回投与か再投与に起因する。故に我々は、外来の血清注射により、生体側が特異的に変化したのだという結論に達した。」
血清病理論
最終章で、人間と動物の先行文献を引用し、疾患の病態生理について考察をしている。問題を複雑にするのは、臨床症状が血清中の沈降素の出現と完全には一致していないことであり、この事実が抗体の役割を曖昧なものにさせた[7]。しかし二人は、血清病症状が、馬血清と患者の抗体との化学反応で生起するとの立場をとった。
「我々は抗体形成と血清病には因果関係が存在する説を発表する。」
まるで反発を予想していたかの如く、以下のように書いている。
「疾患の防御をするはずの抗体が、同時に疾患の原因にもなるという構想は、一見不合理であろう。これは、我々には、疾患の中に生物への害悪のみを観察し、抗体を唯の抗毒素物質と見なす慣習がある事実に基づく。」
論文の締め括りに、研究の価値とその影響力を想定している。
「我々は、血清病が臨床的観点以外にも、一般病理学の立場からもその重要性を証明できたように思う。血清病は模倣できない有機的原因による疾患の最良のパラダイムであり、全身で進行する変化の研究対象として最適である。」
フォローアップと反応
ピルケ博士は、” Die Serumkrankheit(血清病)”で提示した多くの概念を、1910年、氏がジョンズ・ホプキンス大学小児科教授の時代に執筆した著書”Allergy(アレルギー)”で更に発展させた。ここで博士は”アレルギー”(ギリシャ語で”奇妙な活動”)を造語している[5]。以降、この用語は更に特殊な意味を持つようになるが、当時はアレルギーと免疫の区別はあまり明確ではなかった[7]。
シルバースタイン博士が解説する。「著書アレルギーで、皮膚症状、ツベルクリン反応、血清病やアナフィラキシーのような、当時知られていた観察を全て統一しようとしていたのです。」しかしシルバースタイン博士は、ピルケは、自身が、現代で言う所のアレルギー専門家とは考えていなかったと指摘する。「当時アレルギー専門医はいませんでした。人々はアレルギーとその根本にあるものがまだ理解できていなかったのです。」
"アレルギー"で、ピルケ博士は血清病の病理に関する更なる観察・分析・考察を実施した。ここで彼は、抗原と抗体で構成される免疫複合体(”毒性体”)を症候の沈降因子として正確に特定している[5]。
シルバースタイン博士は、”血清病”の重要性が医学界ではあまり理解されていなかったと語る。「当時はただ理解されず注目も浴びませんでした。人々は別のことに係りきりだったのです。ですので、期待したほどの刺激はありませんでした。」
抗血清療法はその後2,30年に亘って広く続けられた。血清病の病態生理は証明されなかったが、この期間中、血清療法を施された患者の大規模な回顧研究により、研究者はピルケとシックの臨床的発見を確認している[8][9]。抗生物質の登場により、異種抗血清の投与の機会は徐々に減った。しかし、破傷風、狂犬病、ボツリヌス、蛇や蜘蛛の咬傷治療等、幾つかの場面では実施されていた[10]。
病態生理を紐解く
1951年、シック博士個人がDie Serumkrankheitの英訳をした。前書きに、数年を経て論文への関心が増したと指摘し、
「アレルギー検査、並びにアレルギー疾患に関する知識のほぼ全ては、受身伝達、並びにその”逆”の血清病観察に起源がある。」
1950年代、Fred G. Germuth Jr., MD、Frank J. Dixon, MDらの研究により、血清病の病態生理の解明が進んだ[5][11][12]。アトキンソン博士曰く、その研究の多くはウサギモデルで実施された。
「注射を続けて腎臓に注目し、顕微鏡で組織の観察をしました。1920~30年代にはできなかった組織染色が可能になりました。研究者は、腎臓障害、関節腫脹の原因を特定しようと、このモデルを集中的に調べました。」
循環性免疫複合体が血清病の原因だと正確に証明された。研究者は、動物に外来タンパク質を注射すると強い抗体反応が誘発され、この抗体が注射した抗原と結合して循環性免疫複合体を形成することを観察した。この免疫複合体は、順次補体を活性化し、動脈炎や糸球体腎炎などの組織傷害を生起する[8]。
だが、これらの発見は、血清病自体の理解以上に意義があった。
「私が60年代後半から70年代頭に研修医としてこの分野に参入した時、血清病についてまず興味を抱いたのは、ループス患者に同様の症状が見られることでした。」
アトキンソン博士は語る。博士は、血清病が初めて記述された50年後、ループスの病態を明らかにする論文の内容が、血清病のように見えると言う。
「…重症のループス患者では、C3とC4は、私が知っているほとんどすべての分類でまだ使用されています...自己抗体、腎臓病、皮膚症状や関節症状など、ループスで観測される全てが血清病でも見られるのです。」
現代のパラレル
現代の治療で、抗体が時に副作用を起こし、効能を減弱させることがある為、研究者は未だ研究を続けている。これはPEG(ポリエチレングリコール)で化学的修飾がされた化合物にも該当する。例えば、ペグロチターゼ(Krystexxa)は、難治性慢性痛風の成人患者に対して承認された組換えPEG修飾ウリカーゼである。一見、一部の患者に非常に有効なようだが、多くの患者は時間とともに反応しなくなる[13]。この反応の消失は、高力価の抗ペグロチターゼ抗体の発現と関連している。この抗体はペグロチターゼのクリアランスを促進し、輸液反応のリスク増加とも関連する[14]。
「残念ながら、ペグロチターゼへの免疫反応が薬剤の有用性を制限していますが、他のPEG修飾治療薬の経験から得られる教訓があります。ペグバレーゼです。」
とアトキンソン博士は語る。
アトキンソン博士は、ピルケとシックの遺した血清病の特徴と、慢性的な血清病ともいうべき病気として近年詳細に記述される、フェニルケトン尿症(PKU)の治療に適用されるPEG修飾酵素への免疫反応との間に類似点を見出した。フェニルケトン尿症は、フェニルアラニンを代謝する酵素の遺伝的欠損により、フェニルアラニンの血中濃度が上昇する壊滅的な神経疾患である。
BioMarinが開発したペグバレーゼは、バクテリア由来の組換えフェニルアラニンアンモニアリアーゼ(PAL)であり、この酵素はフェニルアラニンから別の物質への変換を触媒する。ペグバレーゼで研究者はPALにPEGを結合させた[15]。アトキンソン博士は、
「現在、多くの薬剤がPEG修飾されています。理由はまず、半減期が延長するのです。また、薬剤をPEGで覆うことで免疫原性がなくなります。ペグバレーゼは恐らくその両方でしょう。」
PEG修飾化合物は、身近な環境(食品、香水等)に広く使用されており、多くの人々には既にその抗体があるとも解説する。
ペグバレーゼのような酵素補充療法は、時に抗薬剤抗体を誘導し、過敏反応を誘発する(潜在的に免疫複合体を介している)。そうした抗体は中和作用によって有効性も低減させる。更に、抗PEG抗体の存在も幾つか報告されてきている。BioMarin社の研究者は、ペグバーゼの特異的症例をより深く定式化し、安全性と有効性を最適化した投与プロトコルの開発に努めている[15]。
アトキンソン博士は、ペグバレーゼの安全性と有効性を特定するべく、その免疫原性を調査した2018年の研究の共同者の一人である。「多くの要因を制御可能な環境で詳細に調べました。」と言う。
「20年前と比較して、こんな研究はできなかったでしょう。投与する抗原量、IgGやIgM反応の測定、抗原である薬剤の進行のモニターができました。」
BioMarin社グループは、ペグバレーゼを投与した患者をモニターし、臨床データ、複数のアイソタイプでの抗体価と特異性の測定、酵素的中和、免疫複合体の評価、補体活性のバイオマーカーの評価を実施した[15]。
治療開始から6か月、IgGとIgMの抗PEG抗体、抗PAL抗体が出現した。治療後、抗PEG抗体はベースラインまで減少した。循環性免疫複合体が治療初期に最高値を記録し、経時的に減少した。過敏反応も治療初期に頻発し、免疫複合体形成の減少と補体濃度の上昇に応じて減少していった。これにより、ペグバレーゼの投与量を徐々に増やし、リスクを最小限にしつつ有効なレベルにまで到達させられたのだ。ペグバレーゼの増量と免疫反応の成熟に連れて、血中フェニルアラニン濃度も経時的に減少した[15]。
20世紀初頭、抗血清療法を受けた患者の中に、再感染が疑われた場合に血清の反復投与を受けていた人々がいた。しかし、外来血清の投与は、現在のペグバレーゼ治療とは対照的に慢性的なものではなかった。こうした継続的な投与は、ペグロチターゼの例と同じく独自の危険性と課題を生み出す。
アトキンソン博士が解説する通り
「数年に亘ってこの患者の治療に当っていました。C3とC4の低値にも関わらず、抗体形成にも関わらず、薬剤効果を免れたのです。」
「抗体が横ばいなのです。追加で抗原を投与しても、大半の患者はプラトー状態に陥りました。IgE抗体もないので急性のアレルギー反応でもなく、別の現象を考慮する必要があります。つまり、慢性血清病の一形態だと思われます。」
文献
[1]von Pirquet C, Schick B. Die Serumkrankheit. Leipzig: Franz Deuticke; 1905. English version, translation by Schick B. Serum Sickness. Baltimore: Williams &Wilkins, 1951.
[2]Becker EL. Elements of the history of our present concepts of anaphylaxis, hay fever and asthma. Clin Exp Allergy. 1999 Jul;29: 875–895.
[3]From DNA to beer: How did they make diphtheria antitoxin? National Institutes of Health. 2019 Aug (updated).
[4]Wendt D, Warnere M. Béla Schick and serum sickness. National Institutes of Health. Circulating Now. 2014 Feb 25.
[5]Silverstein AM. A History of Immunology. 2nd ed. London, England: Elsevier; 2009.
[6]Wolf IJ. Bela Schick. JAMA. 1968 Jan 1;203(1):44.
[7]Turk JL. Von Pirquet, allergy, and infectious diseases: A review. J R Soc Med. 1987 Jan;80(1):31–33.
[8]Lawley TJ, Bielory L, Gascon P, et al. A study of human serum sickness. J Invest Dermatol. 1985 Jul;85(1 Suppl):129s–132s.
[9]Hunt LW. Recent observations in serum sickness. JAMA. 1932 Sep 10;99(11):909–912.
[10]Beilory L. Clinical complications of heterologous antisera administration. J Wilderness Med. 1991 May;2(2):127–139.
[11]Weigle WO, Dixon FJ. Relationship of circulating antigen-antibody complexes, antigen elimination, and complement fixation in serum sickness. Proc Soc Exp Biol Med. 1958 Oct;99(1):226–231.
[12]Germuth FG Jr. A comparative histologic and immunologic study in rabbits of induced hypersensitivity of the serum sickness type. J Exp Med. 1953 Feb 1;97(2):257–282.
[13]Guttmann A, Krasnokutsky S, Pillinger MH, Berhanu A. Pegloticase in gout treatment—safety issues, latest evidence and clinical considerations. Ther Adv Drug Saf. 2017 Dec;8(12):379–388.
[14]Lipsky PE, Calabrese LH, Kavanaugh A, et al. Pegloticase immunogenicity: The relationship between efficacy and antibody development in patients treated for refractory chronic gout. Arthritis Res Ther. 2014 Mar 4;16(2):R60.
[15]Gupta S, Lau K, Harding CO, et al. Association of immune response with efficacy and safety outcomes in adults with phenylketonuria administered pegvaliase in phase 3 clinical trials. EBioMedicine. 2018 Nov;37:366–373.
いいなと思ったら応援しよう!

