
【音楽】「ASKAコンサート」で永遠の少年に出会えた夜
「Travel TV presents ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 Who is ASKA!?」に参加した。
※ネタバレにご注意ください! #ネタバレ
ASKAについて
ASKAと言えば、CHAGE and ASKA(略称:チャゲアス)というバンド名で活躍し数々のヒット曲を連発した歌手として知られている。今年67歳になる。
高校の同級生であるCHAGEとバンドを結成しメジャーデビューしたのは、1979年のことだった。
1986年に「モーニングムーン」、1991年に「SAY YES」、1993年には「YAH YAH YAH」を発表しており、いずれも大ヒットに繋がっている。
才能は留まるところを知らず、他のアーティストにも数多くの楽曲を提供している。中でも光GENJIに提供した1987年「ガラスの十代」、1988年「パラダイス銀河」は大ヒットを記録した。
歌唱力にも定評があり、才能あふれるアーティストであることに疑いの余地は無い。
しかし、ASKAについて語る時、あの事件について触れることを避けて通ることはできない。2014年に最終的には執行猶予つきながら有罪判決を受けた事件だ。
当然活動は停止され、関連作品の出荷停止・回収、デジタル配信の中止に追い込まれた。各方面に迷惑がかかったのはもちろんのこと、何よりもファンを哀しませたのが大いなる罪であった。
もちろん一度過ちを犯したからと言って人生を再起できない社会は違うと思うし、ASKAが今活動を続けられているのは、かつてチャゲアスの曲に心震わせた者の一人として、とても有難いことだと感じている。
だからこそ二度と同じ過ちは繰り返さないで欲しいと願っている。
コンサートの感想
会場
武道館は言わずと知れた音楽の聖地である。ASKA自身もMCで「ホームと言ってしまえばおこがましが、自分にとって特別な場所である」と語っていた。
席は1階席であったが、下のアリーナ席は見たところファンクラブのメンバーで固められているようだった。というよりも会場全体がファンで埋め尽くされていたと言っても過言ではないかもしれない。
今までに参加した他のアーティストのコンサートでは初参加者の割合が比較的多かったが、ASKAのコンサートでは曲が流れ始めた瞬間の「ウワー!」と一斉に湧き上がる歓声がもの凄く、コアなファンの割合が多いように感じた。
アリーナと1階席がS席で、2階席がA席に割り当てられていたようだ。
ちなみにチケットは学生に対してキャッシュバックをおこなっており、若い層の獲得にも意欲的だ。客層はやはり女性客の方が多めであるが意外と男性客もいた。年齢層は高めかと思ったが30代40代もけっこう見かけた。
武道館は今まで2階席しか経験がなかったが、1階席からはステージと同じ目線で鑑賞でき、とても見やすかった。
ステージ正面の1階席に招待席が設けられる例が多いようだが、あそこがステージに近すぎず遠すぎず、かつ客席までのアクセスを考えたら一等席なのだろう。
アリーナ席の経験はないが、ステージが高く設営された影響で見上げる角度となり、近さの割に鑑賞しやすいかは不明である。さらに、アリーナ席では半分くらいの時間は立ち上がっている必要がありそうで、ちょっと自分には無理かもしれない。
もっとも娘が足しげく通うバンドのライブではパイプ椅子すらない立ち見エリアがデフォルトであり、それに比べれば座れるだけマシかもしれないが、年寄りには辛そうだ笑。
ステージ
ASKAがMCで「今回のコンサートは中級編です」と言っていたので、ゴリゴリのファンでなくてもついて行けると期待したが、それでも初心者の自分には少しレベルが高かったようだ。
勉強不足もあったが、曲名がわかるのが数曲しかなく、自分にとっては上級編のように感じられてしまったのだ。
そのため今回はセットリストの紹介は残念ながらできない。
しかし、だからと言ってコンサートを楽しめなかったわけではけっしてない。むしろ会場の雰囲気に身を委ねて過ごした時間は楽しかった。
バラード調の静かな曲では音に耳を傾け、ロック調のノリのいい曲ではアリーナ席の人たちに合わせて手拍子したり拳を突き上げたりすればいいのだ。
特に、名曲「YAH YAH YAH」では、会場全体で拳を突き上げて歌ったのが嬉しかった。
「ヤーヤ ヤーヤ ヤヤーヤー!」
最高潮に盛り上がった熱気の中で、武道館が揺れていた。
Who is ASKA!?
今回のコンサートでは副題で「Who is ASKA!?」と謳っている。
「ASKAって誰?どんな人?」に対する回答は、副題を付けた本来の意図とは少し離れるかもしれないが、自分の答えとしては「永遠の少年」になる。
歌を歌っているときは紛れもないアーティストであるが、MCの時はまるで少年のようだ。「〇〇したんだよ」「△△なんだ」とか独り言のように語っている。
それはオトナがオトナに話す言葉ではない。
もしかしたら演出なのかもしれないが、音楽を語る時には自然と少年の心に戻ってしまうのだろうか。
ファンサービスのために、ステージの左端や右端の袖を縦横無尽に走り回って手を振る姿は、歳を感じさせない「永遠の少年」そのものであった。
曲作りの苦悩
多くの曲を作ってきたASKAだが、MCで曲作りの苦悩についても語っていた。
「曲は意外と何とかなるもんだ。問題は詩だよ。机の前に座ってとかノートパソコンを開いても何も出て来ないことがある。言葉が必要なんだ。小説とかドラマとかいろんなものに刺激を受けて書いたりしてる」
才能あるASKAでも苦悩があるようだ。
メロディより詩の方が難しいのは、やはり詩は独自の世界観を創らないと成り立たないからなんだと思う。曲一つに一つの世界観を創造して付与する必要があるから、曲作りは難しく時に苦しい作業なんだろうなと素人ながらに思った。
幕間の休憩
ASKAのステージは素晴らしく大満足であったが、一点だけ気になったことを書き添えておきたい。
3時間近くに及ぶコンサートの途中でトイレ休憩があったが、その間ASKAはステージから降りることなく、ステージに座り込んで喋りつづけていたようだ。
これは槇原敬之のコンサートと同じ方式であった。正直「休憩取ってくださいよ」と思うが、よっぽどステージが好きなんだろう。
トイレから戻ってきたら、休憩の間にちょうどバンドのメンバー紹介をおこなっている最中だった。
ちょっと驚いたのがメンバーとの距離の近さだ。
メンバー一人一人と肩を組むというよりも首に手を回して密着しているのだ。これ少年時代に写真撮る時に友達とよくやってたヤツだ。
「距離、ちか!」って思った。
親密さをアピールしたかったのかもしれないが、正直あそこまで近いと嫌だと感じる人もいるかもしれない。しかも女性ボーカリストに対しても同様に、肩をぎゅっと抱き寄せてけっこう長い時間密着していたのだ。
「うーん」って唸ってしまった。「ASKA大丈夫かな?…」
圧倒的に優位な立場で、しかもステージ上で絶対に拒否できない状況でアレをやるのはちょっとどうかと思った。相手が納得済みならばそれ以上言うことはないのだが…。
30年前なら男性に対してはOKだったかもしれないが、30年前でも女性に対してはNGだった行為だ。ましてや今の時代では、相手がもし嫌だったら両方ともNGになる。
ASKAは「永遠の少年」の心でアレをやったのかもしれないが、距離感のバグり方にちょっと心配になってしまった。
時代に合わせたアップデートをしないと、若いファンが離れてしまうかもしれない。
チャリティ
ASKAのコンサートでは、チャリティ活動にも力を入れているようだ。
グッズ販売の横のテントで小児がんの募金を実施していたので寸志を贈らせていただいた。
バッジは要らないと一旦は断ったのだが、けっきょく妻分を含めて2個いただいてしまった。
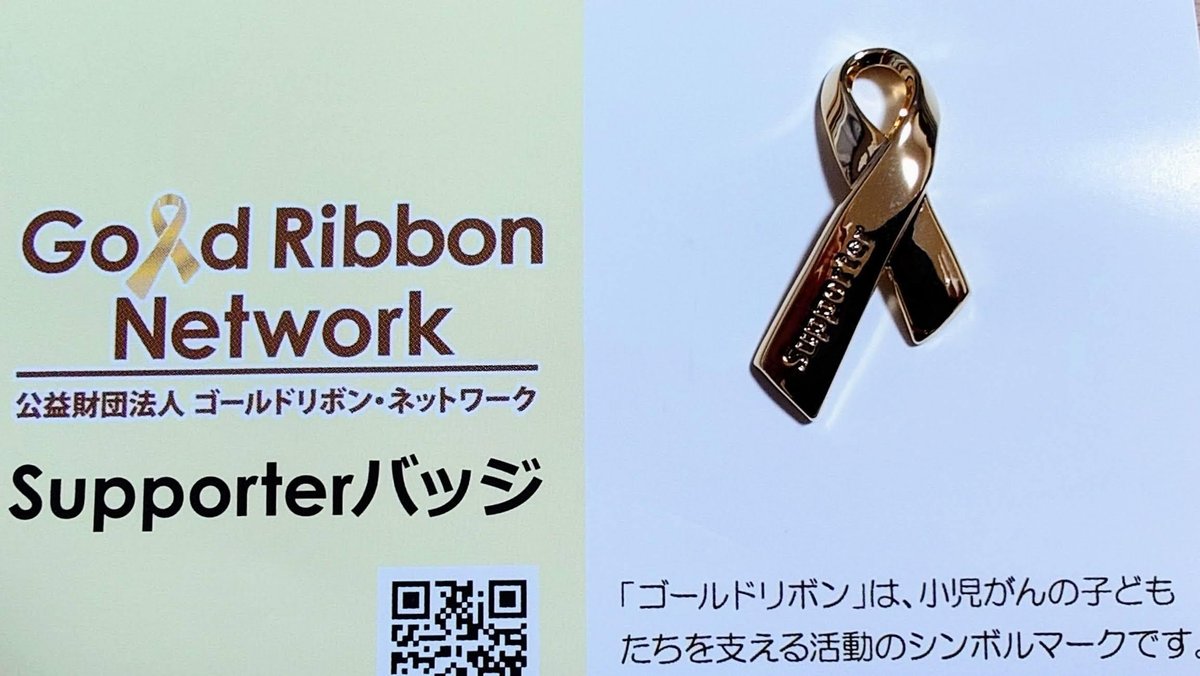
このようなチャリティ活動がもっと当たり前のように日本社会に広がればいいのになと思う。
表拍と裏拍
ここからは、まったくの余談である。
音楽の手拍子には表拍と裏拍の2種類が存在するそうだ。
表拍:
表拍は、ドラムを叩くタイミングなどで拍手をし、リズムを取る方法だ。
祭りで太鼓を叩く動作などと共通しており、日本人には昔から馴染のあるリズムの取り方だ。
図でいうと、★印のタイミングで拍手を打つ。
ドン ・ ドン ・ ドン ・
指揮棒で言うと、下に下がったタイミングでパンと打つのだ。
裏拍:
それに対して、裏拍は、ドラムを叩く音と音の間のタイミングで拍手をし、リズムを取る方法だ。表拍がお休みしているタイミングで拍手をするため、裏拍と呼ばれている。
これは日本人にはあまり馴染がないリズムの取り方だ。
図でいうと、★印のタイミングで拍手を打つ。
ドン ・ ドン ・ ドン ・
指揮棒で言うと、上に上がったタイミングでパンと打つのだ。
裏拍の効用
実際にやってみると裏拍の方が格段に難しいことがわかる。しかし、裏拍をマスターすることでリズム感が向上するのも事実だ。
裏拍を刻む時には、実は裏拍に加えて表拍でもタイミングを取る必要がある。もちろん表拍のタイミングでは拍手はしないのだが、体でリズムを刻む必要があるのだ。よくミュージッシャンが前奏などで顔を前後させてタイミングを取っているアレだ。
結果として体で倍の頻度でリズムを刻むことになるため、音楽の解像度が増し、リズム感も増すのだと理解している。
裏拍が苦手な理由
欧米人は裏拍が得意でリズム感があるのに対して、日本人は裏拍が苦手でリズム感に乏しいようである。
その理由の一つとして、我々が話す日本語が影響している可能性がある(あくまでも私見です)。
すなわち日本語を母語とする人はその言語的特徴により、他の言語、例えば英語を母語とする人と比べて、脳のニューロンネットワークの構造に違いが見られるようなのだ。
何かの本に書かれていたことだが、欧米人は虫の音色を聴いて雑音すなわち音楽と認識するのに対して、日本人(正確には日本語を母語とする人)は同じ虫の音色を聴いて言語として認識するそうだ。
人間の脳の特徴として、左脳が言語、右脳が音楽などの感情を司るとされているが、欧米人は虫の音色を右脳で処理しているのに対して、日本人(正確には日本語を母語とする人)は同じ虫の音色を左脳で処理しているようなのだ。
もちろん複雑な音楽を脳の一部分のみで認識していることはあり得ず、脳の様々な領域が関与しているのは間違いない。しかし、虫の音色をメインに処理している領域が異なるということは、脳の中のネットワーク構成が欧米人と日本人(正確には日本語を母語とする人)では異なるということであり、これは大変に興味深い話だ。
もちろんこれは欧米人と日本人とで、先天的に脳の構造に違いがあることを意味している訳ではない。
日系人で英語を母語とする人では虫の音色を音楽と認識することから、これは先天的な脳の構造(ハード)の違いではなく、後天的に獲得した性質(ソフト=ニューロンネットワーク)の違いであると解釈されている。
上記は虫の音色に関する研究結果であるが、日本語を母語とする我々日本人は音を言語的に捉えがちな民族であり、そのことが我々の音楽に関するリズム感を悪くしている可能性が考えられるのだ(あくまでも仮説です)。
コンサートでは表拍が基本
では実際のコンサートでの拍手は、表拍と裏拍のどちらが採用されているのだろうか?
自分が今までに参加したコンサートは全て表拍が採用されており、裏拍が行われていたコンサートは一つもない。
今回のASKAコンサートではロック調の曲も多かったが、やはり表拍であった。
楽曲が流れた時にステージ上の奏者やコーラスの人が、拍手を求める動作をすることがあるが、全て表拍となっている。
音楽を生業にしている人間が裏拍を知らないことはないだろうから、おそらくは観客が無理なく付いて来れるように表拍が採用されているのだと思われる。
裏拍の勧め
ここまで表拍と裏拍について語ってきたが、自分は音楽の専門家ではない。
しかし、この話はクラシックの指揮者をしている知人から聞いた話なので、裏拍を叩くことでリズム感が増しノリもよくなるのは間違いないと思う。
興味のある方は、是非裏拍にチャレンジしてみて欲しい。
ただし、コンサートなどでノリノリで裏拍を叩いていると、隣の人と拍手のタイミングがズレているのに気づくことがあるだろう。
仮にその場で微妙な空気が流れたとしても、そのような空気はノリで吹き飛ばして欲しいものだ。
※日本人が裏拍を取るのが不得意な理由に関する論評は筆者の個人的な仮説であり、一般に確立されたものではありません。
※この記事は、個人の見解を述べたものであり、法律的なアドバイスではありません。関連する制度等は変わる可能性があります。法的な解釈や制度の詳細に関しては、必ずご自身で所管官庁、役所、関係機関もしくは弁護士、税理士などをはじめとする専門職にご確認ください。
また本記事は、特定の商品、サービス、手法を推奨しているわけではありません。特定の個人、団体を誹謗中傷する意図もありません。
本記事を参考にして損害が生じても、一切の責任は負いかねます。すべて自己責任でお願い致します。
お知らせ
資産運用に興味のある方は、拙著『資産運用の新常識』をご覧ください。

