
気づいちゃったの_俳優養成講座vol.5
気づいちゃったんですよね。
早くも。
何がって?
このnote、劇団ブルア主催・代表さいとうさんが講師を務める『俳優養成講座』のレポートを記録していき、参加している方の振り返りになったりこれから参加する方の予習になったら良いなと思って始めたんですけど、
内容まとめていくってムズイ。
書くべきこととその順番と誰が何して何を言われてとか、全部書ききれない!
そして先週から我々『きらめく星座(いのうえひさし作)の台本のワンシーンをピックアップして読み方講座に突入してまして、一人ひとり3行のセリフを読んで、結構細かく個人個人に対してのフィードバックを繰り返す形式なので、さらにレポートがむずくなってきたなと感じておる次第です。
なので決めました。
これからは、講座の中でさいとうさんが伝えていた内容で特に私が心のメモに記録しておこうと思ったものを中心に、紹介していくことにしよう、と。
まとめるって復習にもなるので、誰のためでもない、私のためにこのnoteを更新してまいりたいと思います😎
そんなこんなで前置きが長くなりましたが、先週の講座の私の心のメモから、早速いくつかご紹介します💁♀️
◾️演出からの指示を言葉通りに受け取って表現しても演出の要求には応えられない

皆さんは、例えば稽古をする中で演出から「もっと声を大きく」と言われたらどうしますか?私は多分「もっとお腹から声を出したほうがいいのかなー?とか思って、声張っちゃうね。
例えば「もっと悲しそうに」「もっと楽しそうに」とか言われたら?一生懸命、悲しそうな声をだしたり、楽しそうな表現をしてしまいがちですよね。
でもこのやり方は実はNG🙅♀️
もし声を大きくと演出に言われたとしたら「結果的に声が大きくなってしまった」という出し方にしないといけない。
でも良く考えたら、普段の生活をしていて声が大きいなーって思う人よくいるけど、その人達のほとんどは声を大きく出そうと意識して出しているわけではなく、自分でも知らないうちに大きくなってるんですよ。だからこれは、演技に置き換えてもそうでないといけないってことですよね。
ここで、前回お伝えしたゲシュタルト構築が重要になってくるんですね✨
じゃあ、声が大きい人ってどういう人?あるいはどういう状態?
・元気なひと⇨よく笑ってるひと?テンションが高い状態?
・必死なひと
・遠いところに話しかけているひと
・酔っ払っているとき(制御が取れている)
・パニック状態⇨命の危険が迫っている状況?
・周囲のことを気にしないひと
・くしゃみが豪快なおじさんは声も大きい⇨おじさんって、50代くらい?
などなど。連想しながらとにかく出してみます。
色々出してみて、あとその役の人物のキャラクターと組み合わせてみて、しっくりきそうなイメージを具体化していく。そして、そのイメージを持って読んでみる。
すると、「あぁ、こういうことかもしれない」と意外としっくりくる時がある。
書いてあるセリフだけを捉えて読んでいた時とは比べ物にならないくらい想像力が膨らんだ状態で、「声を大きく出そう」という役者の意図ではなく、結果として声が大きくなってしまったという役の意図で声が出ている状態なので、当然こちらの方が臨場感のあるお芝居になります。
想像力。創造力。
これが、役作りにおいてもとっても大切なのだな〜!こうして書いているとむっちゃ納得感あるのだが実際にやってみると難しいんですよね。
もっと頭の柔らかい人になりたーい!

私自身の価値観にどうしても寄りがちだけど、自分の枠を飛び越えた想像力が必要なので、やはりこれは訓練だなと感じた次第でした。
人の観察は元々好きなほうですが、私の場合「この人ってこういう人なんだ」てな具合に思考のほうに意識が向きがちなので、その時どう体が動いているのかという行動の方にも着目してみると、ゲシュタルト構築や想像力の強化にも良いかもしれないです。
もっともっと人を観察しよう👀
◾️演技プランと検証

このゲジュタルト構築を行いながら、「このシーンはこうしてやってみよう」「ここはこういう気持ちで、こういうふうに(ここで息を吸う、高く読むとかそのレベルまで)読んでみよう」とか、細かく演技プランを立てていくことになります。
この演技プランは、細かく明確であればあるほど良いのだ、と。
ここで大事なことは、自分自身で「自信」を持つこと。
もし少しでも無意識のうちに「自分の表現は違っていたかも」という気持ちがあると、それがそのまま演技に表れる。それは役者の気持ちであって役の気持ちではないわけだから、ダメだよね。ってことですね。
で、より自分の中で確信を持つためには、計画した演技プランの検証が必要になるわけですね。
それは実際にやってみること以外にはなく、やってみて、自分の感情と身体に、フィードバックしていく。
このシーンのここで、息を吸うことで、止めることで、どんな感覚(表現や感情)になるのか。
感情が湧き出るのか、それは思っていたものかそうでないのか、情景がイメージできたか、などとにかく発見があればOK👌計画と検証を繰り返し、より明確なものにしていく作業が大切なんだ、と。
ここで、さいとうさんはいいました。
俳優の仕事とは、物事の説明ではなく心と心の説明なんだ、と。
だからこれは、書いてあるセリフの奥にある役の心の内を探究してアウトプットしていくことでその感情が湧き出る感覚を体現し、それによりまた更に理解を深めて、役と自分にある差を埋めていくような、そんな作業なんかなと思った。そうして洗練されていった表現が、心の説明に繋がるんかな。
でもさ、こんなふうにPDCAを回していくのは仕事とかでもよくあるけど、いかんせん検証していくのが自分の心と身体な訳で、たどり着く答えに客観性って皆無なわけじゃない?
それを頑張って客観的に捉えるようにしてみたりとことん主観的な感覚を掘り下げてみたりしながら、自分の中で「これだ」と確信する表現を探っていく作業なわけですよね。
ヴーン、奥深ぇ〜なぁ、演技って。
(習得までの道のり長ぇ〜🐢)
まぁ、一筋縄ではいかんけど、これを習得するための俳優養成講座なのですから、頑張りたいと思います☺︎
◾️セリフの中にある「。」と「、」の読み方
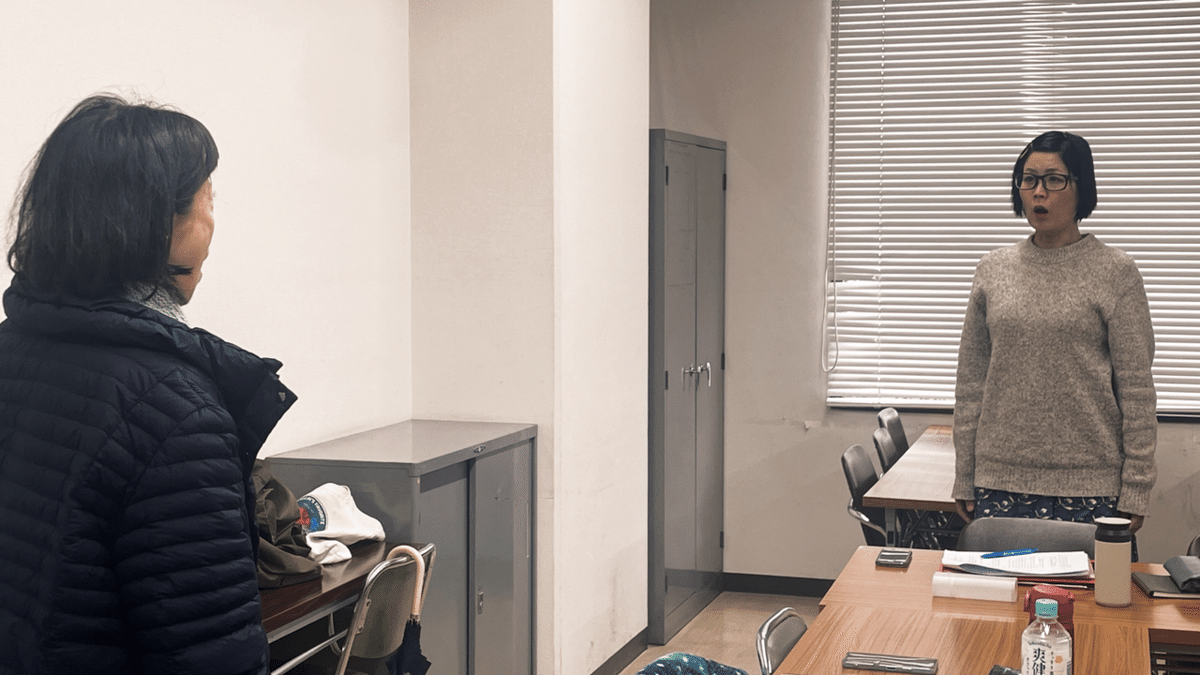
俳優養成講座では、ワークとフィードバックの合間に細かい演技テクニックを教えてもらえることがしばしばあります。この日教えてもらったテクニックの一つをご紹介しますね。それは、句読点の読み方です。
例えば、
「私はこのペンを、昨日買いました。」
というセリフがあったとします。
句読点をどう読むのが、伝わりやすい演技になる確率があがると思いますか?
「。」というのは、文章の終わりです。
つまり聞き手にとっても「あ、そうなんだー」と、一定の理解と満足感が生まれますよね。だからその「。」の後に間を空けると、間延びしてしまう確率が上がる。
逆に「、」というのはまだ文章の途中なので、聞き手にとっても「で?次はどうなる?」と、次の情報を待つ気持ちが生まれるので、間を空けても間延びしにくいんですって。いくらでも待てる感覚になるんだって。
確かに、「私はこのペンを、…………」って言われたら「うんうん?ん?なになに、それで?」って気持ちになるけど、「昨日買いました。…………」って言われたら、「……で?」みたいな気持ちになるかも!
この気持ちの違いが、間が長く感じるか心地よく感じるかの違いなんですね。
もちろん、これは全てのセリフで成立することではなく、そうじゃないシーンもあるし、あくまでも伝わる確率があがるってことですが、覚えておきたいテクニックだと感じた次第です👩🎓
◾️俳優養成講座、随時参加者募集中♪

はい、そんなこんなで今回は3つご紹介しました。
本当はもっとたくさんのことお伝えしているんです!なので気になる方はぜひ、直接俳優養成講座に足をお運びいただければ嬉しいです☺️
メンバーまだまだ募集中、オンラインでも受講可能ですので、ご興味ある方は是非お問い合わせくださいまし😊
俳優養成講座詳細ページ
ほいでは、またねー🙌
