
憧れなんて抱かない 自分の未来に繋げたいだけ
「憧れの女性は誰ですか?」という質問を受けることがある。
実はいつも答えに困っていた。どうも、「憧れ」という概念についてしっくりこないようだ。
子どもの頃、母は時折、ある女優やモデルがテレビに映るたびに「若い頃この人に憧れてたのよ」「彼女みたいになりたくてねぇ」と言った。今でもよく聞く。幼いわたしは、そのたびに不思議な気持ちになった。どうして、自分以外の誰か、しかも会ったことのない人に「憧れ」を抱けるのだろう、と思った。見た目、雰囲気、声、演技力、それだけでこんなに「この人になりたい」と思えることに違和感を感じた。だって、幼い子どもにとって、お母さんは一番だから。お母さんが、お母さん以外の誰かになることなんて全く望んでいないし、お母さんが自分以外の誰かになりたいと思うのも悲しかった。子どもにとってだけじゃない。人はひとりひとりが、もうそのままで十分すてきで、唯一で、尊い存在なんだ、ってことを、わたしたちはいつも忘れがち。「憧れ」という言葉を聞くと、なんだか切なくなってしまう。まるで、自分が自分のままで十分であることを認めてはいけないと言われているような気がして。「憧れ」なんてなくっていいと思う。そのままのわたしでいさせて欲しい。誰かに思い焦がれる必要なんてない。
同時に、「憧れの人」という言葉には、ロマンティックな意味も込められるからまたややこしい。異性愛者の男性にとって「憧れの女性」は恋愛対象や結婚相手の対象となるし、「憧れの君」というとやっぱり、「その人になりたい」の意味は薄まり、「強い思いを寄せる相手」という意味になる。「憧れ」という言葉はわたしにとって、ほんとに難しい。なんというか相性の悪い言葉である。

辞書で「憧れ」という言葉の意味を引いてみると、
あこがれ【憧れ/▽憬れ】
あこがれること。理想とする物事に強く心が引かれること。憧憬(どうけい・しょうけい)。「―をいだく」「未知への―」「―のまと」
(デジタル大辞泉の解説)
とある。一つ目の解説は、「あこがれること」…いまひとつまだ分からない。二つ目の解説は、「理想とする物事に強く心が引かれること」、これは分かる。でも「理想の女性」が自分にとって誰か、というと正直やっぱり答えるのが難しい。理想の自分は、他人でなくて、自分が今より成長した形でしかないからだ。「今の自分がこう変わって、こうなったら良いな」という像が理想の姿であって、誰かになりたいというのはないし、「憧れ」なんて、ない。でも「この人のこういうところに、強く感銘を受けて、明日の自分へ、未来の自分へ繋げていきたい」と思う人はいる。女性でも、女性じゃなくても。
もしかしたら質問する人は「憧れの女性」をそんな強制的な意味では捉えてなくて、ふんわりと捉えているか、もしくはわたしが今書いたように「この人のこういうところに感銘を受けている」という意味で捉えているのかもしれない。単に、わたしが言葉というものにこだわりすぎているのかもしれない。それでも、自分の中でしっくりこない言葉を使うわけにもいかないので、「考えることや生きることにおいて、良い影響を与えてくれた、これからもその時の感銘を忘れないでいたいと思うものを与えてくれた人」という表現の仕方を採用したいと思う。決して「その人になりたい」わけでも、「その人みたいになりたい」わけでもなくて。未来の自分が、もっと良い自分であるために。

Netflixの『Chef's Table』は世界のトップシェフが生み出す、息を飲むほど美しく独創性に溢れた料理とそれを味わうためのレストランの空間を、シェフの半生や哲学とともに美しい映像とクラシック音楽で紹介する大人気の番組だ。この番組が生まれたきっかけは2011年に公開された「すきやばし二郎」の店主、85歳の伝説の寿司職人を追った『二郎は鮨の夢を見る』が予想外の大ヒットとなり、監督のデヴィッド・ゲルブの目線と手法が一気に評価されたことから、同じテイストのドラマシリーズの実現へと至った。
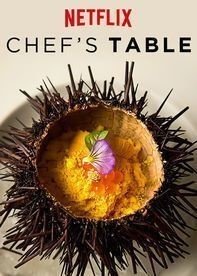
2013年、東京のフィンランド政府観光局で働いていた頃にフィンランドへの移住を決め、フィンランドで同じ職務を約束されていたにもかかわらず、結局仕事にあぶれてフリーランスとして翻訳やライターやウェブサイト管理や役者をやりながらキャリアパスを見直していたわたしが料理人を目指すことにしたのが2016年。料理が好きで好きでたまらなくて、『Chef's Table』を観てもっと料理の世界にのめり込んで、気がついたらフィンランドでシェフの道を目指していた。移民としてフィンランドで生きていくのは思った以上に大変だった。実際に、ちゃんとした労働許可証を得るまでに3年弱かかった。それにキッチンの世界は厳しい。昼夜問わず立ち仕事に力仕事、汗をかいて掃除をして。男ばかりの社会で乱暴な言葉遣いの人も多い。フィンランドだけではなく全世界で、暴力沙汰になって裁判になった例は後を絶たない。
2015年に始まった 『Chef's Table』は2018年現在、ボリューム5に突入。その最初のエピソードを飾るのはメキシコ出身の、アメリカはフィラデルフィアにバルバコアのお店を構えるクリスティーナ・マルティネスだ。彼女のエピソードを観たとき、わたしの中で何かが変わった。彼女は間違いなく、わたしにとっての「未来の自分に繋げたいものを与えてくれた女性」となった。

スペイン語でバーベキューを意味する、中南米のタイノ族に起源をもつ肉料理のバルバコア。穴の中に焼けた石炭を入れた上にマゲイの葉を敷き、オレンジと塩で味を付けた羊肉(脚や頭、胃などすべてを使う。ゼロ・ウェイストのホールフード)を乗せて8時間かけてゆっくりと焼く。クリスティーナはメキシコで、6歳の頃に家族代々伝わる調理法を教わり、現在もアメリカで古代からの作り方を踏襲してバルバコアを提供する。クリスティーナは、「食を通して、故郷に戻る」と言う。
幸せな家庭で育ったクリスティーナは17歳で結婚、夫の実家で暮らすことになるが、夫の家族による強制労働を強いられ、また夫からは執拗な暴力を受け続けた。一人娘が妙齢に達した時、夫とその家族は娘を嫁入りさせ、働かせようと言い出すが、クリスティーナは、娘には自分の二の舞を踏んで欲しくないと願い、娘もまた、寮制度のある学校への進学を志望する。娘の願いをかなえるため、クリスティーナは単独でアメリカへと不法入国し、不法労働をすることでメキシコでは稼げない学費を稼ぐことを決意。メキシコとアメリカの国境の砂漠を2週間歩き続け、国境につけられたレーダーに捕まらないようにと息も絶え絶え走り抜けた思い出を淡々と回想するシーンはこちらも息が詰まりそうになる。
キッチンでの仕事を見つけ、死に物狂いで働くクリスティーナは、ある日ベンという同じレストランで働く男性に出会い、恋に落ち、やがて結婚する。しかし、不法入国をしたためにグリーンカードが下りず、事情を話した勤め先の人々は誰も助けの手を差し伸べてはくれなかった。娘の送金の術も断たれ、絶望に陥るクリスティーナだが、それでも諦めず、自宅で秘密のレストランを開く。そこには、クリスティーナのような移民、食べること、そして故郷の味を求めてやまない人々が大量に押し寄せた。広がる輪はたちまち一つのコミュニティとなり、ついにクリスティーナとベンは自分たちのレストランを開くこととなる。彼女たちは愛情たっぷりのバルバコアを提供するだけにとどまらず、かき消されていく移民たちの声を届ける活動も行った。劣悪な環境で働かされる移民たちの声。耳を傾ける必要がないとされた人々の声。クリスティーナは言う。「わたしの料理以上に大事な戦いがあります。人間は平等です。移民ひとりひとりの声を聞いてください。すべての人生には重みがあるのです。」
2016年、米国の最大グルメ雑誌の一つ『Bon Appétit』が「アメリカの新しいレストランベスト10」を発表し、6位にクリスティーナたちのレストランが紹介されると、クリスティーナは瞬く間にメディアに引っ張りだこになった。そこでクリスティーナが一番伝えたいことは、移民の声だった。「移民たちは社会の陰に隠されています。移民たちは搾取されています。そこにあるシステムから目を背けないでください。わたしは真実を語り続けます。わたしのレストランに来る全ての人たちにそれぞれにストーリーがあります。」クリスティーナが料理を通して目指すことは、人々の心に自分の心を届けること。料理を通して人々がコミュニケーションをすること。レストランに来る人すべてを家族として見ること。愛情をたっぷり込めて用意した料理で、人々を元気にすること。


食べることは愛をもらうこと。料理は愛を込めて誰かを元気にすること。料理は食べ物を媒介にして、ひとりひとりとハートでコミュニケーションをとること。彼女のような人がいることを知ることができて本当に良かった。憧れじゃなくて、学んだこと、賛同したこと、心の奥まで届いたこと、忘れずに自分の一部にしていきたい。そしてわたしも料理を通してもっと多くのことを伝えていきた。できるだけ近い未来に。

たかが料理、とバカにする人もいる。
低賃金で肉体労働で、オフィスワークなどに比べて価値の低い職業だと言う人もいる。
でもわたしとって料理は文化で、哲学で、愛で、歴史で、芸術で、政治なのだ。胸を張って自分の味を、自分の生き方を模索していきたいし、できるだけ多くの人と愛を共有していきたい。シンプルで、おいしくて、わくわくして、涙してしまうほどの愛。わたしはわたしの物語をこれからも紡いでいく。
