
自分らしく過ごせる居場所づくりを通じて拡がる温かな気持ち / NPO法人京都コリアン生活センター・エルファ
南区情報ステーション「みなみなみなみオンライン」は,京都市南区役所が,南区に関わる誰もが南区をもっと知って・学んで・楽しんで・好きになってもらうことを目的に,南区の皆様によるまちづくり活動の紹介,区役所からのお知らせ等を,SNS等を用いて配信するWebサイトです。このnoteで,まちづくり活動に取り組む方々への深堀りインタビューを掲載していきます。
今回は,東九条を中心に活動をされ,令和2(2020)年に20周年を迎えた「NPO法人京都コリアン生活センター・エルファ」にお話を伺ってきました。
お話をきいた人
南珣賢(ナム スンヒョン)さん(NPO事務局長)
さとう大(さとう だい)さん(作業所職員)
当団体では,在日コリアン一世のための介護保険利用の支援からはじまりましたが,高齢者が地域で安心して過ごせるためのデイサービス事業や,多様な背景を持つ障害者が関わることができる共同作業所事業など,20年の間に地域福祉に関わる多彩な取組を増やし,現在は主に以下の事業を柱にされています。
・高齢者支援事業
・多文化共生事業
・障害者支援事業
・子育て支援事業
・その他地域活動事業
働き始めて20年,最初は聞き取り調査がきっかけ
今回お話をお伺いしたのは,事務局長の南 珣賢(ナム スンヒョン)さんと,
作業所職員のさとう 大さんのお二人。平日のお昼に,エルファが運営する「エルファカフェ」にお邪魔しました。
まずは,おふたりがエルファに関わられたきっかけを伺ってみると,南さんはエルファ発足の2年目,2001年頃に関わり始め,2002年から働かれているとのことでした。ちょうど在日コリアン一世の方々の聞き取り調査のサポートにエルファが関わり,言葉や文化や背景を知っている人の力が必要な時期だったため,調査の手伝いをしたのが最初だったそうです。
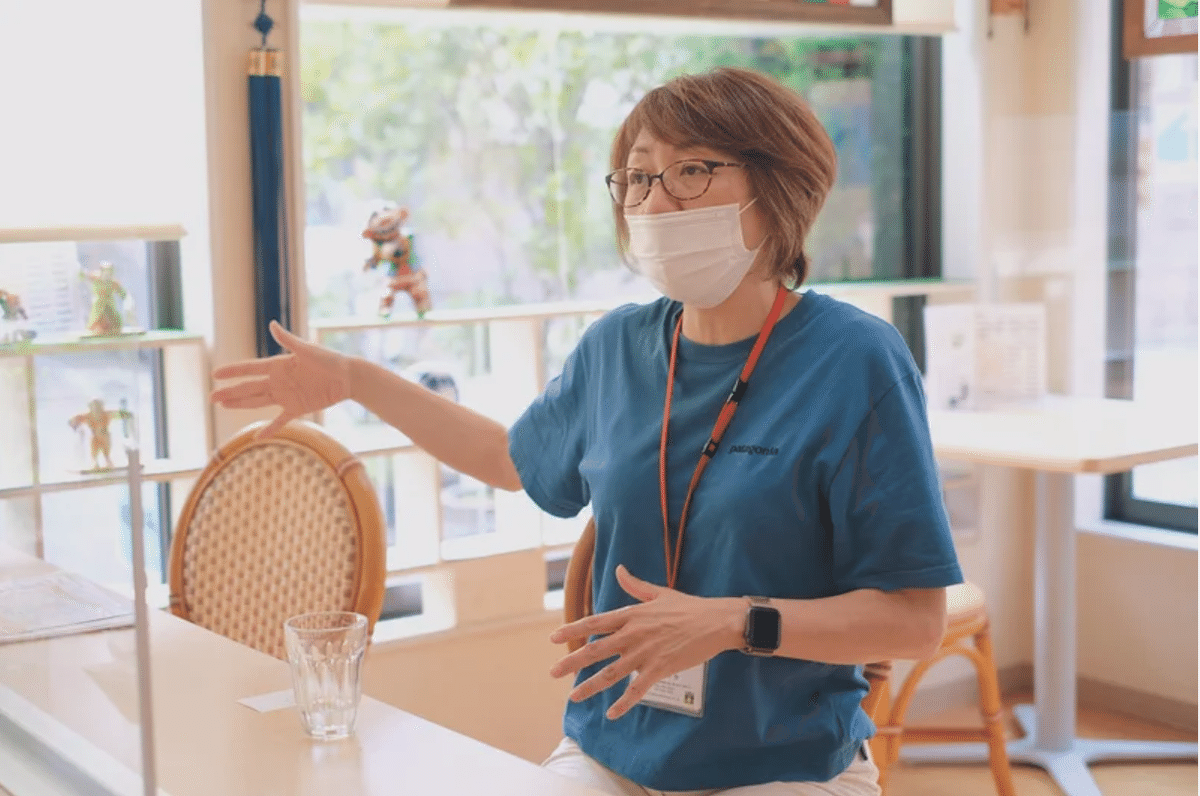
南さんは,その聞き取りを通じ,在日コリアンの方々が過ごしてきた人生の経験や出来事,その1つ1つを知るとともに人生に関わっていくことが,自分の財産にもなると感じ,エルファでお仕事を始められました。
また,さとうさんが働き始めたのは2014年頃になりますが,学生時代に歴史を学び,在日コリアンの方々の話を聞く機会があったことがきっかけでした。さらに,東アジアの様々な場所にも自ら足を運び多くの方々に話を聞いて過ごしていたところ,ご縁のあったエルファから声がかかったとのこと。
エルファで働く方々は,スタッフからの紹介でご縁ができ「エルファで働いてみたい」と思ってきてくれる方が多い職場なのだそうです。
エルファの原点にある,恩返ししたいという思い
そんなエルファの立ち上げ当時のお話を伺いました。
2000年4月から介護保険制度が始まりましたが,在日コリアン一世の方々は様々な理由で制度にアクセスしにくい状況にありました。そこで,制度利用の相談に寄り添うために在日コリアン二世が中心となり活動を始められたそうです。最初はコリアン高齢者のお宅を訪問し,日本人じゃなくても介護保険が利用できることを知らせていたものの,徐々に活動のことが口コミのネットワークで大きく広がっていき,数ヶ月もすると相談数が急増し事業を必要とする方がたくさんおられることを強く実感しました。

活動は広がり事業所も2,3箇所と増えていき,デイサービスの利用者の居住エリアも広がり,東九条だけではなく北区や左京区からもやってくるほどになりました。送迎をしたり,厨房に立ったりと事業を行いながら,新たな事業申請も行っていたので慌ただしい日々でしたが,二世の人たちに「苦労して生きてきた一世の人たちに恩返しをしたい」という気持ちが強く「この事業を絶対に成功させるぞ」という意気込みで,代償を求めずにボランタリーに活動が進んだことが,その後の健全経営に繋がっているとのことでした。
エルファでの経験が,社会に拡がっていく
次に伺ったのは,エルファの活動が拡がっていった背景についてです。南さんに伺ったお話の中に「当初,在日コリアンの方々向けの事業として始まっていたんですが,活動が進む中で“中国残留孤児”の方々から同じような相談を受けた」というお話がありました。中国残留孤児で日本に帰国した方々が,エルファの利用者が抱えてきた制度にアクセスしにくいという問題に直面していて,自分たちが取り組んできた経験が他の場面で活かされていくことを知ったのでした。
この経験から「日本での暮らしに困っている人,生きにくさを感じている人は在日コリアンに限らない」ということを学び,いろんなバックグラウンドを持った人たちがいて「自分らしく暮らしていくこと」に難しさを感じている人が多くいることを知ったのです。それから,エルファの取組では在日コリアンや外国籍にルーツを持つ人だけでなく,もっと様々な人に目を向けるようになったそうです。

また,さとうさんからも「外部との交流が活発になってきたように感じる」という話を伺いました。先日,THEATRE E9 KYOTOでエルファのNPO20周年の記念事業の一つとして開催をされた「えるふぁ展」では,アーティスト小澤亜梨子(ありす)さんとエルファ共同作業所の皆さんが作品を制作し,発表しました。
その他にも,エルファのある東九条自体にもいろんな人の行き来が生まれるなどの変化が起こっていて,施設の中だけでのケアではなく,様々な人が行き来することでこれまでに気付けなかった「福祉の世界以外」とのつながりも増えたように感じているとのことでした。
年間1000人との交流が行われる理由
そんな外部の方々との関わりの中で,積極的に取り組まれている印象があったのが「訪問者の受け入れ」でした。修学旅行生も含め年間1000人ほどの視察,見学や研修を受け入れる理由について伺いました。
訪問時には,施設の見学やヒアリングだけでなく,実際に長く日本に住んでこられた在日コリアン一世や二世の方とお話をするそうです。きっかけは,過去に子どもたちと人権学習の企画で話すことがあった際,自分たちの経験や想いが誰かの役に立てることや,子どもたちが話を聞き想像以上に想いを受け止めてくれたことが嬉しかったという経験から,話せる機会づくりが重要と感じ,受け入れを積極的に行うようになっていったとのことでした。

それ以降,赴任先が変わっても生徒を連れてきてくれる先生がいたり,ボランティアに参加してくれる方,全国各地から福祉,エスニシティ,人権,移民研究など様々な分野の研究者をしている人も足を運んでくれるようになり,これだけ多くの人が来るなら生きておかないといけないという気持ちになってくれているそうです。こういう機会を作れることが,エルファの強みにもなっていて福祉施設としてだけでなく教育施設としての役割も担えていると感じるとのことでした。
20周年を迎え,次に思い描いていることは?
今後の活動の展望について,伺いました。
「エルファは在日コリアンのための通所施設として立ち上がりましたが,今後は日本の高齢者も在日コリアンの高齢者も分け隔てなく利用する場になっていくことが大事だと感じている。でも実際には『誰もが自分らしくいられる場』とは何かを考える必要があって,そこでは何の歌を歌う?どんな遊びを取り入れる?など,参加者の自分らしさを踏まえて検討することはいくつもある。
それを,これからの5年,10年の間,民族や国といったルーツはもちろん,障害やその他の様々な違いを意識しながら“誰にとっても居やすい場" を目指し続けていきたい」とさとうさんは話されていました。

南さんは「何が本来のこの人らしさなのか,悩むことが多い。そして答えが出ないからこそ,悩み続けていきたい。悩み続けながら,いろんな人たちが『ここに来ると一番さらけ出せるわ』という場であり続けたい。今はそのためにスタッフ間でLGBTQのことや,様々な依存症についての勉強会をしたりと,この輪を広げていくような取組も積極的に実施し始めています」と想いを話していただきました。
エルファの取組を伺って
エルファの活動は「在日コリアンの方々のための支援」だけにとどまらずに,社会の中で生きづらさを感じる人たちが,自分らしく暮らしていくための幾つもの日々の積み重ねがあり,それを温かく育み続けていく営みがあるように感じました。
そして,ここで出会う人たちとの交流を通じて,周りにいる誰かを思いやることの大切さや,向き合い考え続けていくことの大事さを教えてもらったような気がしています。歴史的な背景を知るとともに,自分で足を運んで一緒におしゃべりしたいなと思った方は,誰でも歓迎の「エルファカフェ」や月に一度の「えるふぁ市」に足を運んでみてはいかがでしょうか?
NPO法人京都コリアンセンター「エルファ」
http://lfa-kyoto.org/
-
南区情報ステーション「みなみなみなみオンライン」
取材/文 まちとしごと総合研究所
